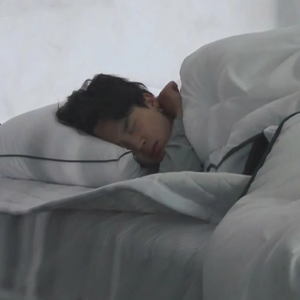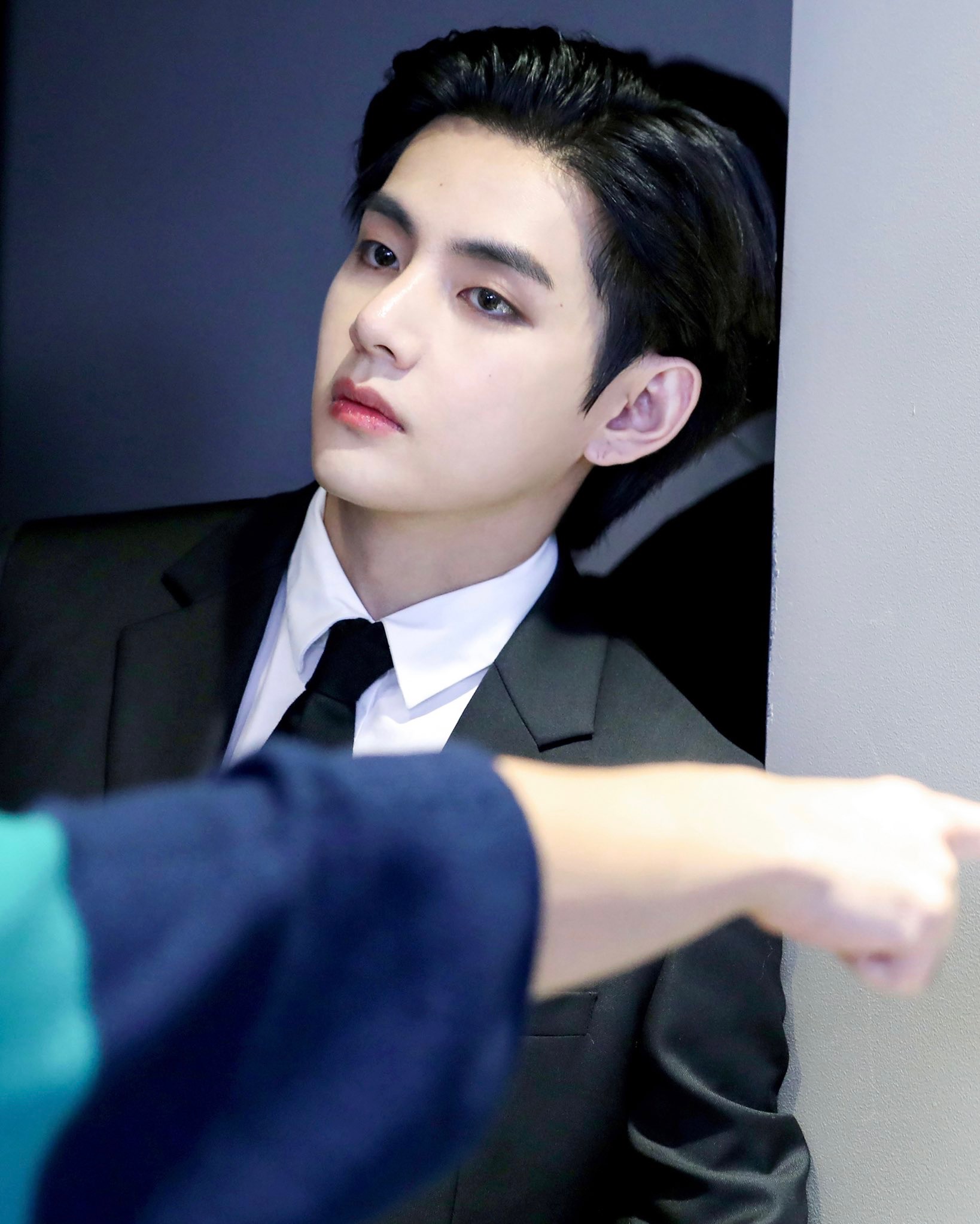
モングルモングル心理

「お前さっきから俺だけ見てる。わかる?」
キム・テヒョンにご飯を買うと言って、職場近くにある韓国料理の正式な家に入ってきた。歩いてくるずっと、さらっと怒って行かなかったような彼の卑猥な表情が気になったということだ。
だからティアンナゲ見つめたが、それを覗き込んだようだ。やっぱり、お茶じゃないのにあまりにも赤裸々に見たんだ。
「…大きい。何食べる?」
「私はこれ。一番高い」
「…とにかく。とてもキム・テヒョンらしい。」
たぶんそうな表情のキム・テヒョン。内部のスタッフを呼び、私たちが選んだメニューを同じように詠んだ。改めてメニューを確認した職員は分かるとし、注文書をテーブルの端に置いた後キッチンに向かった。
私が何も言わなくても私の前にスーザーから置いてくれるキム・テヒョン。左手を傷つけて使えないので、自分が自分の右手までウェットティッシュで拭いてくれる。やるべきことをしてくれて隠れないふりをする言葉がなぜこんなに面白いのか。 病気だからやってくれる。私は。
「…あるじゃないか」
「うん」
「…もしかして、まだ怒ってるんじゃない?」
私の手をティッシュで拭いたテヒョンは行動を止めたら、以内に頭を上げて私を見つめた。何も言わずにじっと見つめたら、内側のティッシュを縁に放っておいて口を開けるものがある。
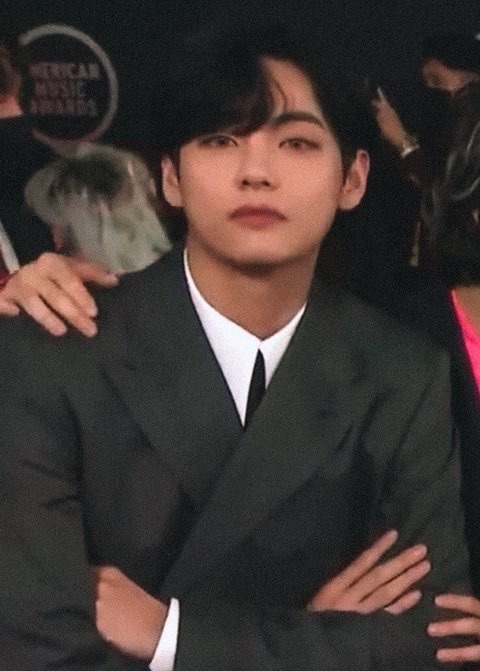
「…私はまだ分解死んでるのに」
その子があなたにしていたことが目の前に鮮やかです。警察が捕まっていく前に最初から息を切る直前まで押しつぶさなければならなかったが。それ以来も話から出てくる言葉は、一様に不気味なペアがなかった。さっきその目つきだけでも十分人ひとつ殺しても残ったようだが。
「…本当の私死んでもいいと思った?」
「…君が言ったじゃない。死ぬと思った」
「それは私が言ったことです。あなたはどうでしたか」。
「……」
怖かったの?怖かった?突然言葉がなくなるので、わざわざ馬に遊び心を混ぜて再度尋ねた。私は死ぬかと思って怖かったです、テヒョンは?いいえ、違うか私のいたずらを受けようとして起動することは彼。隠れて頭を前に突き出したら、内顎を壊して私を見た。

「説き主を心配したよ」
きっと冗談混ぜて取り出した言葉だろう。こんな言葉に変に…胸のひとつが盛り上がる感じがした。そう、友達だから気になる感情なら当然のことだ。そうではありませんか?ところで…これではダメなのに。何かおかしい。別れたばかりなので他人にこんな心…こんな感情は…ダメだよ。さらに、その相手が話したら… これはクレイジーだ。
その言葉一言でどれほど無数に多くの考えをすることになるのか。話はこんな私の混乱した頭の中を知ったのだろうか。 何して、食べないで。 その時、ついに出てきた食べ物に、私が遅れてスーザを聞いた。ああ、食べなければなりません。あなたも食べます。
「ウムここおかず大丈夫湯~」
「おいしい?」
「と本当…おかず食べに来なければならない」
「wwwwたくさん食べて」
「…ㅡㅡあなたがご飯を買う人のようだ?」
-🤍-

「お疲れ様でした」
昼食後、私とテヒョンは再び職場に向かった。働く部署が違って、しばらく顔が見えないまま離れているが、いつの間にかかっている退勤時間になったのかな。急いでスーツケースを持って1階に降りてみると、車を運転して建物の正門の前で待っていたテヒョンが私に挨拶を交わした。 どこに祀られればいいですか、ソルヨジュさん?
「ただ、家の前に近いそこに行こう」
「おい、すぐ出発するよ」
「すごい」
夕方に何を食べるか決めた?頼むから考えていたことがあるというキム・テヒョン。何かと聞くからそれはまた秘密だから。私にまた何すごい食事をもてなしてあげようとこうまで隠して、気になる。その時、ついに車の中を鳴らす着メロ。携帯電話をブルートゥース接続させているようなものなのか、ナビゲーション画面に浮かぶ発信者の名前は「キム・カンフン刑事」。仕事の電話のようで、ただ受け取るように手を振った。 はい、キム・テヒョンです。
「はい。キム・カンフンです。しばらくお話しできます。」
「言ってください。」
「相違ではなく、さっき面談取り消された人のことです」
じっと聞いてみると、相談予定だった前菓子二人のうち取り消された一人を指す言葉のようだった。テヒョンは刑事の言葉が落ちると、私にしばらく視線を移すと、以内にBluetoothを切って私の携帯電話に電話を受けた。仕上げ信号は赤い火。肩と顎の間に挟んだ携帯電話を再び手に握って耳に持ってくるのは彼だった。
なんでいくほど声も沈んで、表情もかなり深刻に見えるので何が起こるだろうからジレ推測は可能だった。何が起こるのか、気になるのにまずはキム・テヒョンが通貨に集中するのが優先だから、それから視線を集めて窓の外を見た。そんなに数分が流れたのだろうか。終了した通話。
「なぜ、どうしたの?」
「あまり仕事じゃない。ただ仕事に関連して」
「あまり仕事じゃないんじゃないみたいだけど…。」
私が知ってはいけないことなのか、より好きで、この頃から関心を収めることにした。まともに祝われただけのような雰囲気に、ダメになりたい話題を回した。あなたは最近会う人がいませんか? …私が言っても本当に浮かんでいなかった。

「必ずあることを望む気がする。」
「え、そういうわけではなく」
他の女性と同居する男を、ある女性が連れて行こう。 日針を飛ばすテヒョンだった。は、私みたいにもそんな男は会えない。それからそれは持ち上がる考え。私が今の話の前を止めているのかどうか… ?今度はただそれぞれ別々に生きなければなりません。
「…じゃあ私たち別に生きるかな?」
「…突然?」
「いや、ちょうどまあ、大丈夫、あなたが気になるじゃないか。」
妙にテヒョンの表情が凍った。織り、追い払う。いたずらしてみた言葉なのに。私たちが一緒に過ごした歳月がいくらですが、一瞬で私が家を出て行きます。 (もちろん私ももう君のいない家は想像するのも大変だから。)
「冗談、冗談」
「……」
「ただ今、」
同居する女性はあなたを取り戻すのですか?
どれくらい楽。他の女性に誤解することはまったくありません。
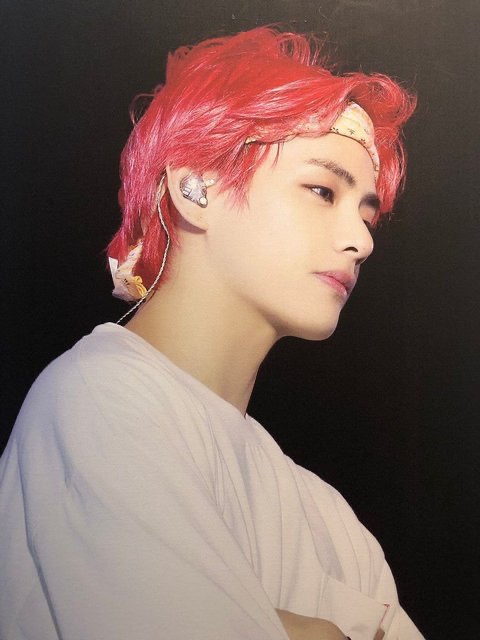
「…話また人勘違いしてるね」
まっすぐ女の雪。
そこにまた惚れたキム・テヒョン。