「は?ミン・ヨジュ、タバコでも吸ってんの?(笑)」
イェナは周囲を見渡し、誰もいないことを確認すると、ヨジュを見て嘲笑した。
刺々しい口調が少し気になったが……まぁ、この程度なら可愛いもんだ。
ヨジュは冷たい瞳でイェナを見下ろしながら言った。
「えぇ?私にはタバコが似合わないって?」
予想外の返答に、イェナの瞳が波打った。
当然だ。ヨジュがイェナの挑発に乗らなかったことなど、一度もないのだから。
でも、私はウ・ジェヒ。
お前なんか相手にならないよ、おチビちゃん。
ヨジュとイェナの間に緊張が走ったその時、誰かが階段を上ってくる音が聞こえた。
その音に気づいたイェナは突然恐怖に満ちた表情を作り、悲鳴を上げながら自分の頬を叩いた。
「きゃあーー!」
バンッ!
ヨジュが頬を押さえて倒れ込むタイミングで、ドアが勢いよく開いた。
かなり慌てていたのか、その足音には驚きがにじみ出ていた。
「イェナ…!」
倒れているキム・イェナ、その前に立つ私――ミン・ヨジュ。
誤解されるには十分すぎる状況だった。
そう…イェナの狙いはそれなんだろう。

「ミン・ヨジュ、お前何をしたんだ。」
しゃがんでイェナの様子を確認したソクジンは、赤く染まった彼女の頬をそっと包み込むように撫でると、顔を上げてヨジュを睨みつけた。
だが、ヨジュは微塵も動じず、薄く笑った。
「イェナ、待ち望んでた白馬の王子様が来たみたいね?それじゃあ、私はお邪魔虫だから失礼するわ。」
「お前のやったこと、しっかり見てたから。バレないように祈ることね。」
ヨジュの冷たい目線と不気味な言葉に、イェナはビクリと震え、ソクジンは怒りに満ちた声でヨジュに叫んでいた。
しかし、ヨジュはそれらを無視し、踵を返して歩き出した。
イェナが「ヨジュを許す」とでも言いたげな、優しいフリをした言葉を口にしている間に、ヨジュは屋上のドアの前で足を止め、シンプルな黒いケースをつけたスマホを取り出して振って見せた。
「イェナ、今日はすごく楽しかったよ。」
「……は!?」
ヨジュの言葉に、怒りで立ち上がるソクジン。

その腕を、か弱いフリをして必死に止めるイェナを見て、ヨジュはクスッと笑った。
そして、スマホの画面を彼らに見せつけた。
[録音中]
「ふふっ、話したいことがたくさんあるわね?」
ヨジュはイェナの顔が恐怖に歪むのを見て、口元を手で覆いながら笑った。
ああ、本当に面白い。キム・イェナ。
久しぶりに壊したくなってきた。
カリカリ、カリカリ。
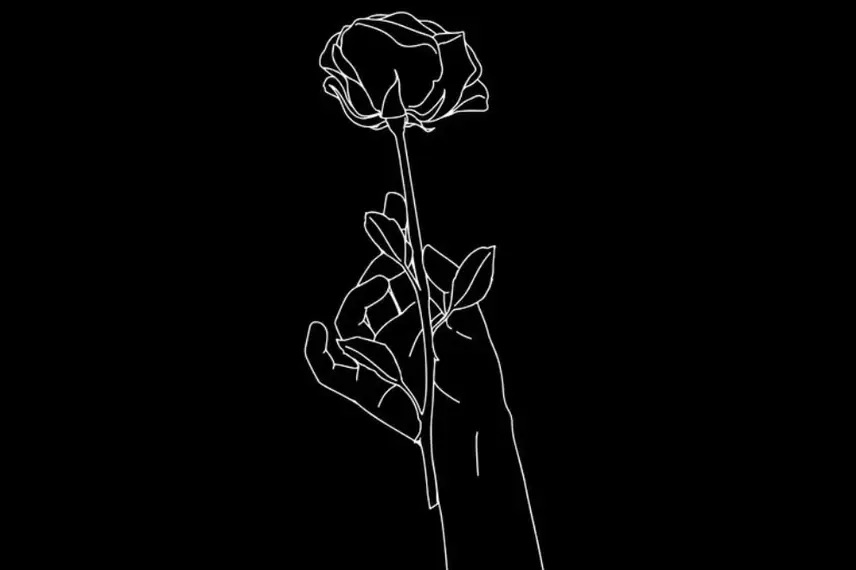
イェナが不安そうに爪を噛んでいるのを見て、隣の席のテヒョンが驚き、彼女の手をそっと握った。
「イェナ、大丈夫?さっきからずっと爪を噛んでるけど…。」

「え…?あ、ううん、何でもない…へへ。」
イェナはぎこちなく笑ってみせたが、テヒョンの心配は深まるばかりだった。
しかし、何かを考えたのか、彼はふと険しい表情になった。
「…ミン・ヨジュのせいか?」
「え…?」
「お前がこんな風になってるのって、ミン・ヨジュのせい?」
「ち、違…」
最初は否定しようとしたイェナだったが、ふと考えがよぎった。
テヒョンがヨジュを問い詰めるなら、その隙にスマホを奪えるのではないか?

そう思った彼女は、すぐに言葉を変え、涙をためながら俯いた。
「うん、テヒョン…私、すごく辛い…。」
ポロッと涙が落ちる。
それだけで十分だった。
テヒョンは即座に立ち上がり、ヨジュの元へと向かった。
その様子を見ながら、イェナは密かに笑った。
自分が誰かに見られているとは夢にも思わずに。
「…面白くなってきたな。」
バンッ!
教室のドアが、ガラスが割れそうなほどの勢いで開けられた。
ヨジュが静かに本を片付けていると、突然テヒョンが彼女の襟をつかんだ。
「お前、イェナに何を言った?」
「……何言ってんの?」
襟を掴まれても動じずに答えるヨジュに、テヒョンは呆れたように笑った。

「はーっ。」
「これもまた、注目を集めるための作戦か?裏では人をいじめて、表では何も関心がないフリをするなんて。」
「…何言ってんの?」
ヨジュの言葉を無視し、テヒョンは続けた。
「俺たちがそんなに好きなら、大人しくしてればいいのに。何で関係ないやつを巻き込むんだ?」
「…は?」
「はっ…お前、本当に図々しいな。最後まで否定するつもりか、クソ…」
「いや、黙れよ。」
「俺が、お前たちを好きだと?」
「…は?」
「学期の初めから、俺たちにくっついてきたのは、お前だろ?」
「は?何言ってんの?私はお前らなんて好きじゃないけど?」

感情が欠落したソシオパスにとって、誰かを「好きになる」という感覚は存在しない。
そして、ヨジュ――いや、ジェヒにとって、愛という感情は何の役にも立たないものだった。
そんな彼女に「お前は俺たちが好きなんだ」と言ってしまえば、納得どころか、殴られずに済めばラッキーなほどだろう。

しかし、そんなことを知らないテヒョンは、ヨジュがただ意地を張って認めたくないだけだと思った。
「この…!」
怒りで手を振り上げたテヒョン。
彼の手がヨジュの頬に近づいた瞬間――
ガシッ。
誰かがその手首を掴んだ。
「何やってんだ、キム・テヒョン。」
「…は?パク・ジミン?」

自分の腕を掴んだのがジミンだと気づいたテヒョンは、少し驚きながらも言った。
「ちょうどよかった。ミン・ヨジュがまたやらかして――」
「何やってんだって聞いてるんだよ、キム・テヒョン。」
ジミンは冷静な表情でテヒョンを見つめた。
「ヨジュはずっと俺と一緒にいたんだけど、どうやってイェナをいじめるんだ?」
「……は?」
動揺したテヒョンはヨジュを見た。
「…本当か、ミン・ヨジュ?」
意外だったが、味方をしてくれるなら拒む理由はない。

「うん。私はパク・ジミンと一緒にいたよ。」
満足そうに笑うジミンを見て、ヨジュは考えた。
こいつ、もしかして私よりヤバいんじゃない?
