「ええと…ベッド?」
きっと自分は公園の芝生に居なければならないのに、なぜここにいるのかと思う○○が数分の間、愚かなことがあったが、自分が昨日拉致(?)されたことを思い出した。そして自分の隣に横になっています...
「流れる……」
この人が誰なのかは分からなくても昨日自分を見て最も驚いた人だということも言葉だ。
日も暖かくてベッドも大きくてふんわりする。ただ人の姿でまた寝てしまった○○は男と一緒にベッドで資本的でなくて拒否感なくただ眠りについた。
もちろん起きて驚くのは相手だった。
「う…誰……うわーㅓㅓ!!!なんだ!」
スンチョルはすぐにベッドから出た。それにもかかわらず○○は眠りから割れなかった。
「あ…昨日…」
スンチョルは明らかに○○が昨日猫の姿で寝ていると覚えているのに、なぜ自分のベッドには人の姿で寝ているのかと思った...
..猫なので暑かったかと思うスンチョルは次からはカーテンを張って涼しくしておかなければならないと思った。
時々メンバーがスケジュールのために眠りから破った。
「お兄ちゃん、朝から何が…」
「…私は何もしなかった」

「何もしないのは…じゃあ、あの方がなぜ人の姿なんです!!!」
「いいえ!私は何も……」
スンチョルはミンギュに何もしなかったと無実ですが、それを信じるでしょう...
どんなに寝ているのは○○だが、音に敏感な猫であり、あんなに音を立てるのに安らかにしているはずがない。 ○○は
伸びを伸ばして音を立てる人間たちをぼんやりと眺めてあくびをした。

「朝からなぜ高艦質以来…もともと平凡な人間はそうなのか」

「と…」
「何」
「まだ不思議です…」
まだ不思議なスンヨン
不思議なことも多いと言って、一晩であれば、その程度は慣れると言って税収をしに行った。
「でも本当…可愛いですね…」
「猫じゃないか…王室の動物…」
「そうか…なんだか…」
3人は奇妙に頷いた。
税収をして出てきた○○が君たちがいない間、私はどこにいるのかと尋ねた。
当然、一緒にスケジュールを行くと思っていた子供たちは猫の姿で通ってはいけないかと尋ねた。
「嫌い。猫の姿が楽になっても人より弱い」
「…ただ静かにおられると…」
「私たちがいなければご飯もできません…」
「私と行きますか?」
上層でジフンが降りてきて話を聞いたのか、今日のスケジュールは作業室しかないと一緒に行こうとした。だが、スンチョルは最近記者たちがどれほど怖いのか、写真を一度撮れば終わりだと話した。

「それで、子供たちと撮影会場はもっと危険です。」
「……」
「行くのにろ過するのではなく、マネージャーの兄が連れてくる…兄に何を言わない」
いくら親しい兄たちだが、こういうまで言うことはできなかった。結局○○も自分の正体を隠すためにマネージャーが来て作業失踪までは猫に行くことで合意を見た。
「私も録音しないで終わったのに一緒に行こう!ㅎㅎ」
スンヨン島のように..
昨日からスンヨンが最も言葉が多くて騒々しいと感じた○○は、スンヨンがそれほど好きではなかった。
ドンドン
ドアが開く音が聞こえ、○○は素早く猫も変わった。
「ジフンああ〜今録音するつもりです…猫?」
「あはは……昨夜は歩き回るのに…とても人が好きだから」
「しかし…ジフンがあなたは動物が好きではありません」
「話は例外だから兄」。
「うーん…でも、お前らのスケジュールで、手に入れるのが大変だ」

「一緒に通えばいい!」
「?」
○○は猫の姿でどんな犬の声をするかという目つきを送った
「ニャアオン……」
「これを見て。
「本当に本当に時々泣く!」
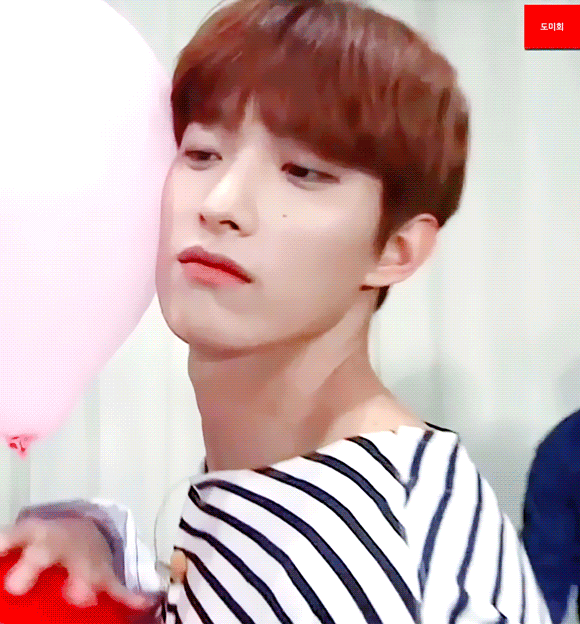
「お兄さんください…」
「それでもない…」
○○は自分を抱いて外に出ようとするマネージャーに長靴は猫の目つきを送った。
通じたのかマネージャーも可愛いという声をした。
その隙に乗ってメンバーたちも話が本当にスマートだとし、スケジュールの雨の日にはあまりにも退屈だといろいろな理由を増やした。
「でも…」
「やん……」
「……」
「ヤオオン……」
「わかりました、わかりました!…育てて……」
メンバーたちは歓声をあげて好きになった。
マネージャーも珍しくないと○○を下ろして撫でて録音室ガラエたちは出てきて用件だけ伝えていった。
しかし……
行く途中…うるさく知っていたスンヨンのせいで何度も○○これは何度も人に変わって殴るか悩んだ。
録音室に到着してからもチョルアルデは純英を避け、ジフンの品の中で安全に到着した。
「ここは人がよくわからない。人に変わってもいい」
帰ってきてもいいというジフンの言葉に○○が伸びを広げて人に戻ってきた。
スンヨンはいつ見ても不思議だと驚いた。
「しかし、いつからあなたに私に話しましたか?」
「お前の人の年齢も24歳だよ」
「…それはそう」
ジフンがスンヨンとレコーディングを開始し、全く真剣になった彼らが○○は少し見慣れないかもしれないが、それもしばらくだった…眠気に耐えてジフンの膝からいつのまにか猫に変わって眠りを楽しむ中だった。
少しずつ聞こえるスンヨンの歌声とジフンの興奮、すぐにエアコンで軽く涼しく真空空気のせいかたくさん寝たにもかかわらず、私の家だけで○○は寝ていた。
「…かわいいね」
「ジフンああ、これは分かった?」
「え?..えっ…次にしよう」
この味に猫執事されるのが好きなジフンだった。
