「あ・・・。もしかしたらちょっとそうですか?私は別の私の家に行くんだけど」
「すべてルン私の家?家がまたあるのか?なんだ、この人…お金が多いのか・・・。そう、家も別になのに、じゃあ、ちょっと待ってもいいだろう!」
「じゃあ、いいよ・・・!」
その男はトンネルの外に出ようとする手振りをしてからはトンボクトンネルの外に歩いた。突然明るくなると目が腫れた私は目をそっと覆い、その男を見つめた。その男は補助犬があったし、笑う時に奥に入るのが魅力だ。ああ、そうです。家も貸してくれるのに名前くらいは知らなければならない!
「彼……もしかして名前は何ですか?」
その男はフードティーの帽子を照らしてから頭を数回整理したところ、トンネルの中のように膝を曲げて目の高さを合わせた後、明るく笑いながら語った。

「イム・セジュンで二十五歳ですよー。ではそちらは?」
「あっ・・・、私はキム・ヨジュだ!二十二歳です」
「そうなんだー、お兄ちゃんと呼べばいいんだ!その町?」
「はは・・・。そうですか?私たち今日初めて見たのに…」
その男いや、セジュンさんは慌てたのか右手で後髪を整理して遠いところを眺めた。すると突然指で虚空を教えた。私はその指を目で追いかけた。セジュン氏が教えたのは丸くて明るく浮かんだ月だった。
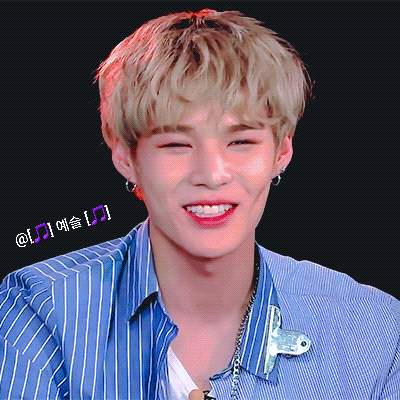
「月きれいですよね、私も後には月も買おうと思うよー」
「月を買って・・・?」
「あはー、知りませんでしたね!あの町。月も買えるなんて、不思議でしょ?」
「まあ、ちょうどそうですか?」
「ほっそり冷たいですね。ハハ…」
「ああ、申し訳ありません。元々初めて会った人はよく信じていません。長く見た人も信じていませんが、まあ..ㅎ」
この男は何と言うのか、私を少し悲しいと思って見ていた。やっぱり、私であってもこんな人がいれば哀れだと思ったようだ。しかし、私はそのような目つきを嫌い、同情する人が好きではないことに一言を言わなければならないと決心した。
「申し訳ありませんが、同情であればうまくやってはいけません。お金も多い人が・・・」
「同情心ですか?同情心じゃないのに」
「それでは、どんな心を持ってこそ私に家に連れて行ってくれますか?」
•
•
•

「まぁ・・・。ただ一目惚れたんですか?それでは可能じゃないですか。その町?」
