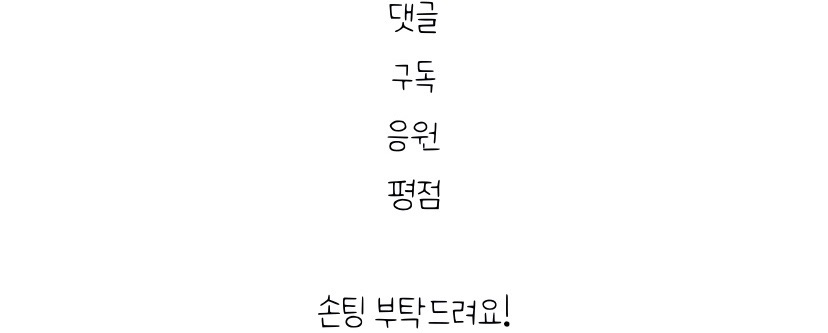ハンサムなクレイジー相手を相手にTALK

🍓
率直に言えば、完全に嘘だ。追い出された。それもとてもたくさん。女の子の多くが私の前に立って、とても怖い目つきで私を狙うのに誰が怖くないのだろうか?そんな人は絶対誰もいないと確信した。
「おい、あなたは何ですか?」
「え、え?」
「お前は何なのにテヒョンとついて食べるのか」
私も簡単に離せなかったキム・テヒョンの名前をあげたのはとても簡単に呼んだ。私はテヒョンと呼ぶまでも恥ずかしくてしばらくかかったようですが…。そんな思いもしばらく、ついて食べるという礼儀のない言葉に気持ちが少し傷ついた。ニードルの目に私がそんなにこっそりしてもそういうついて食べるという言葉はちょっとひどいじゃない。私は虫の子でもありません。
私の眉間がつぶされた。私が某に今気持ち悪いティーを出したらいわゆる屋上についてきてという言葉を聞くかと思ってしばらく我慢することに決めた。
「まあ…?」
「ハ?」
「しかし、私がキム・テヒョンと立ち往生していたのはあなたと何の関係ですか?」
「君は知らなかった? 俺がキム・テヒョン好きだと噂がずっと広がっていたから。
私の前の女の子にその言葉を聞く瞬間、悟った。話は今、私がキム・テヒョンの心を奪ったと思うのだ。私が挟まなければ、本人がキム・テヒョンと付き合うことができただろうというそんな妄想だと言うか。
「ふっ…すみません、私は知りませんでした」
「今、私は笑った?」
「いやー、あなたがどんどん変な言葉を言ってくれ」
その愛にはすみませんが、今私にはこの状況が笑うしかなかった。とにかくキム・テヒョンは今私と出会うのに、お前がそんなに強くしてみたら何の役だと。キム・テヒョンが来る前まではじっとしていてみようとしたが、迷惑が出てくれない。
「あなたがキム・テヒョン好きだと私は好きではない?
「これ、この狂った年が!」
ペア-!半分全体に擦れ音が広がった。私たちを見守っていた彼らは帰ってきた私の頭を見て水軍距離を始め、私の頬を下げた女の子は顔が真っ赤になってずっと飛んでいた。
頬があった。正しい部位が熱くなり、ウクシンウクシン通り始めた。ほっぺを当てた瞬間、私はあまりにも私が欲しいと思った。ああ、私はもともと学校で目立つスタイルではありません。これを見て狂った年だと噂は私ではない?
右の頬を手で包み、その女の子をまっすぐ見つめたとき、猫は私を勝ったような表情をしていた。私よりも本人が上というように、上手く体笑っていたんだろうか。
「そんなに適当に分けなければならない」
「うん、そういうことをした。ほっぺが遅くなって痛いね。異王こんなに当たったのはもう少し出てくれない?手に比べれば言葉は何もないから。」
「何?」
「お前、百日こんなにやってみるとキム・テヒョンがお会いできると思う?絶対に会わないのか?」
「…それをどうやって確信しているのか」
一台当たったと頭まで戻ってしまった模様だ。私がこれで学校で静かに過ごしたんだけど。その愛に当たると同時に手綱が解けてしまった私は口についたトリガーに始動をかけた。そして私は後で明らかに後悔する言葉を彼らに伝えます。
「それは私とキム・テヒョンと付き合うのですか?」
キム・テヒョンと私が付き合ったという言葉を私の口で直接吐き出した私はその言葉を吐き出していただき、身を傷つけた。みんなが私の口から飛び出した言葉に驚いたようで、その女の子は拳をしっかりと握りしめた。後悔しました。某君がやっても迷惑をかけてしまうから、稲妻に吐き出してしまった言葉だったのに…。こう知られてこんなに興味があった嫌だったんだよ!
「キム・テヒョンと寝ましたか?」
「…何?」
「そんなことでなければ理解できないじゃない。突然お前とテヒョンがどう…!」
その子は善を越えた。越えてもあまりにも明らかに、過度に超えた。その口でキム・テヒョンと私が不純な関係を持ったという言葉が出た瞬間から、私は全身が硬く固まって何もできなかった。ただ拳をしっかり握るしかない。爪が手のひらの内側を擦って血が出るほど。
その時だった。キム・テヒョンがそんな私の手をしっかりと握り、私を本人の後ろに隠したのは。その子の発言で全体が静的にたどり着いた時、全校を浮かべた張本人であるキム・テヒョンが現れた。それもとても怖い顔で言う。
私はキム・テヒョンの姿を確認するとすぐに安心になったのもしばらく、もしかしたらキム・テヒョンがその女の子が言ったことを聞いたか不安な目つきでキム・テヒョンを見上げた。
「キム・テヒョン…あなたも……」

「ヨジュヤ、私たちはしばらくやっている」
キム・テヒョンのその言葉を最後に私の耳には正確な音が聞こえなかった。キム・テヒョン手にある暖かいぬくもりだけが感じられただけ。キム・テヒョンとその女の子の間にどんな会話が行ったのか分からなかった。だがそのあの顔がかなり傷ついた表情だったのを見て、キム・テヒョンは私の側に立ったということを推測することができた。
🍓
キム・テヒョンが私の後ろから手を離した時はすべてが所定の位置に戻った後だった。彼女は私に申し訳ありませんでした。謝罪し、私たちを見ていた多くの人々は自分自身でやるべきことを探していました。そして私たちは…
「頬を注いだ」
「え?」
「え、ばかだ」
「馬鹿じゃない」
「愚かだよ」
保健室に二人が残されていた。保健室まで行かなくても良いという私の言葉を聞かずにクンギョンク役に連れてきたキム・テヒョンは私をベッドに座り、本人もその隣に座った。その後、女の子に当たった私の頬を指で指して試みた言葉遊びをした。
「イさん、バカじゃない!」
「あなたが愚かではないのはなぜではありません。
「彼、それは…!」
キム・テヒョンの言葉にどこか少し悔しかった私は唇をずっと突き出して反論をしようとした。しかし、赤く腫れた私の頬に本人の手をそっと持たせながら、心臓を殺す目つき攻撃をしてくるキム・テヒョンにはできなかった。
「私はあなたが病気になったのが一番嫌いです。」
ウクシンウクシン叩かれた頬がもう星の感覚がないと思った。むしろ心臓がとても早く走って心臓が痛いのかと思った。顔はますます真っ赤になり、私はキム・テヒョンと目が合った。
恥ずかしかった。ほっぺが腫れても、とにかく今は気にしないほど私はキム・テヒョンにときめきを感じていた。とても才能なく、キム・テヒョンはそのような私の変化をよく知っていました。キム・テヒョンはあまりないように笑いをする。
「私のガールフレンドはこの渦中にソルレナ見て?」
「…迷惑にならないで。そんな顔にときめかないのがもっと奇妙だから」

「お連れしますよー。ここと、氷蒸しやちょっと。」
「あ、嫌いなのに…」
「でもやって」
正直、ちょっと面倒なのに、それがキム・テヒョンの魅力だから仕方がなかった。私はそのようなキム・テヒョンを、今日の私たちがとても好きであったからだ。
10分。このトクビングの味は。見えない昔のギャンソン+土出るような呟きです。どうぞよろしくお願いします。私は。これを書きながら…指がなくなったのはもちろん。死んだ。悟り。