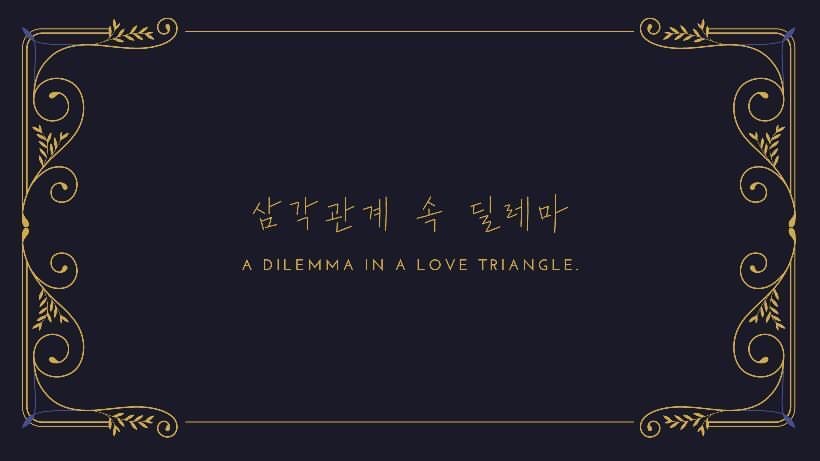
19. 嫌な思い出の中の香り
マランボール。
「スヨン、大丈夫?本当に病院に行かないの?」
「はい、大丈夫です。それよりも大丈夫私のために一杯捨ててどうですか…」
「なぜあなたのためだ。
病院は行かなくても大丈夫だというチョン・スヨンの言葉に、湖石は急いで救急箱を持ってきて止血してくれ、薬も塗ってくれた。それと共に罪悪感に陥ったふりをするチョン・スヨンを慰めてくれてテヒョンの過ちだと、前後状況も知らずにそう言った。チョン・スヨンは何も知らずにまともに慰めてくれる好石が本当に優襲期もした。すぐに目の前で行われた状況に精神が売れ、理性的な判断も下せないという。チョン・スヨンは彼が以前と変わらないと思った。
湖はまだバラの香りを濃く漂わせていた。チョン・スヨンの流血とナンジャハン生いちごジュースが混ざり、漂うフィビリン内を覆うほどだ。チョン・スヨンはむしろフィビリン内がバラの香を覆ってほしいと、フィビリン内の逆さがはるかに良いと考えた。バラの香りが鼻を通して全身に染み込むたびに忘れたかった過去の記憶がどんどん思い出され、吐き気が出てくるほど嫌で、それでチョン・スヨンはバラの香りを嫌っていた。
すべての治療を終えたホソクは救急箱を元の場所に戻した。そして、チョン・スヨンに近づき、膝は大丈夫か、立ち上がることができるかと心配な目つきを入れたまま聞いた。チョン・スヨンは当然歩くことができると話し、萎縮してあげる好石の手を拒否した。ホ・ソクは拒否された手を虚空にしばらくとどまらせる。その頃、チョン・スヨンは足を少しずつ突っ込んだとしても一人で分かってよく歩いて外に向かった。普段より濃いバラの香りがカフェの中で振動して外に出たかったようだった。ホソクはそんなチョン・スヨンを追って出た。どうやら絶頂する彼女が気になったようだった。
***
チョン・スヨンは外の空気をずっと吸い込んだ。濁った空気だったが、逆なバラの香よりはよく、さわやかだと勘違いして口の外に吐き出した。さわやかだと。しかしホソクは疑問な表情を浮かべて空気が今日のためにたくさん濁ったが、との中で考えた。口出して口の外に吐き出さなかった。ホ・ソクはあえてチョン・スヨンの言葉を否定し、彼女に無安を与えたくなかった。
「やん~」
突然どこかで猫の泣き声が聞こえてきた。チョン・スヨンとホソクは無意識に猫の泣き声を追って路地に入った。そこには、厳しい箱の中に捨てられた猫の一匹が寒さに揺れて泣いていた。本当に泣いているようだった。寒すぎると、捨てられて寂しいと、そう泣いているようだけだった。なんかチョン・スヨンは猫の目に涙が出ているような錯覚が聞こえた。
チョン・スヨンは、震えている猫を製品として抱いた。最初にチョン・スヨンの手に聞こえたとき、猫は足を叩くように見えたが、チョン・スヨンの品の中に入るとすぐに暖かく、彼女の懐にもっと抱きしめた。猫はチョン・スヨンの懐が温かく快適なように見えた。チョン・スヨンはそのような猫に視線を固定させて言った。
「とても哀れです。こんなに無責任に捨てられるなんて。」
「…そう。」
ホ・ソクが対装を打つとすぐにチョン・スヨンはホ・ソクに視線を向けて言った。
「この子も誰かの家族だったのにね。家族であればあるほどこれはダメだ。
ホ・ソクはその言葉にぎこちなく、もはや対戦を打つことができなかった。
「しかし、この子供はどうですか?」
「私はしばらく任せておきましょう。あなたは今たくさん傷つけたりして…さあ、家に帰ってみてください。
「わかりました。ありがとうございます、社長。ああ、猫に香水は有害であることをご存知ですか?」
「そうですか?それは知りませんでした。
「明日お願いします」
チョン・スヨンは抱いていた猫を箱に慎重に置いた。そうして猫を一度愚かに見つめて家に向かった。ホソクはバラの香りに乗って吹くシリン冬の風を迎え、チョン・スヨンの後ろ姿をただ見守った。
***
家に着いたチョン・スヨンは全身に力がほぐれ、ベッドにすっぽり座った。今日はチョン・スヨンの予想に外れることが多かったので疲れたようだった。そのようにベッドに座ってガラスの破片のせいで傷や包帯を巻いた私の手のひらを眺めた。
「これは傷跡に残らなかったらいいな」
チョン・スヨンはふわっとため息をつきながらそのままベッドに倒れるように横たわった。それで目を閉じた。今日はぐっすり眠れることを願っています。しかし天はチョン・スヨンに好意的でも寛大でもなかった。その日チョン・スヨンは自分が最も忘れたかった嫌な記憶に夢で会った。
