
「何をそんなに突き抜けてみて?」
「いや、何してるの?」
「目が悪くなるかと心配してくれるなぜ」
ミンユンギに言うか。でも返ってくる答えは狂ったかという言葉が明らかだった。当然この小説は全地的作家視点という、完璧にすべての人物の心を、感情をそのまま書き出した本だとだけ考えたから。
頭が複雑になる。じゃあここに小説が当たってるの?いや、作家が存在してるの?
「公認主」。
「……」
「頭が痛くなったら風に出て行きますか?」
「それを言い訳にしたデートじゃない?」
「あ、バレましたね」
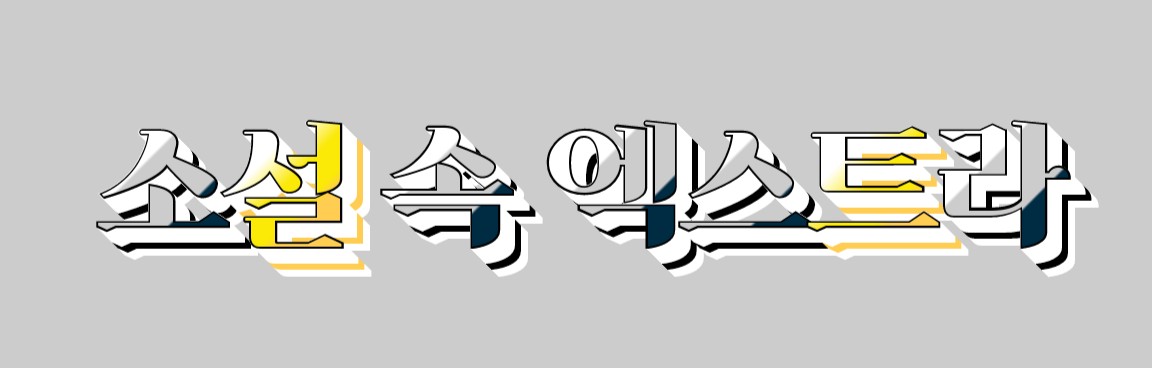
積極的な空間に響く肉を使う音が異質的に近づいてきた。赤い顔のゴン・ナムジュンの前にはキム・ジェニーがあり、キム・ジェニーはそれほど熟していてもしばらくは熟していないステーキを膣筋ジルグン切っていた。
本当に、
本当に、
あまりないことに気味が浮かぶ。

「お兄ちゃん。お願いがありますが」
「はい…!ジェニーさん何をお願いしますか?」
何でも入ってくれるように球はコンナムジュンにキム・ジェニの口尾はさらに上がる。
キム・ジェニーはこう考えるだろう。
愚かで、
愚かで、
また愚かな。
そんな馬鹿がかかったと。
「私はその時その女と会いたいのに」
「はい?どんな女ですか?」
「突然来てジミン兄に連れて行った女性です。知っているような雰囲気だったのに」
お願いします。
さあ、聞いたことがない。
さあ、吐き出してください。
一体その狂った女が誰なのか。
