「誰ですか…?」

「は…、そっちこそ誰なんです。」
「…あ、パク・ジミンじゃないの?」
「パク・ジミン…?誰か知らなくても謝罪します」
「あ、はは。すみません。友達と混乱してしまいました」
本人も慌てたのか瞳孔がひどく揺れるフィインだった。彼女の前にはまだまだ不十分だというような表情の男性が立っていた。片方の眉だけが上がって不快感を表わした。はぁ、地が消えて深いため息をついて何かを言おうと口を離した男性だったが、彼女の名前を世の中に浮かべて呼んでいるジミンの声に押された男性だった。答えがないように、ただ頭を切れ切って唇をぎゅっと噛んだ。
「本当に本当に申し訳ありません!私の友達と似たような服を着ておられて勘違いしました。本当にすみません…!」
無表情だからもっと怖く見える男性の旗から抜け出したかったフィインの心を知ることもするようにジミンが彼女の名前を大きく呼んだ。飲み物で興奮して濡れた男性の服を見ても、もしかしたらいいかな、という思いを胸の一点に置いても怖さが大きかったようだ。男性に軟膏りんごをして何度も腰を曲げた。そしてゴーストの家から逃げるように、後ろを振り返らずにフダダク自身を待っている三人に飛び込んだフィインだった。ギギ道に一人残された男性はハァッ、ちょっといないことを表現する笑いを流した。そして自分の服を見て再び首を切れ、彼女が行った場所の反対側にずっと歩き始めた。通り過ぎる人々は彼の飲み物で濡れた服をしっかりと見つめた。押されていないが、飲み物を飲んでいたので驚いた驚いたようだ。
「子供さん…家に入らなければならないね。いや、」
そう家に向かった男性だった。そして友達に飛び込んで彼らの中に入ったフィイン。二人が輝きを欺きながら背を一台ずつ殴る。いったいどこにあったのか今は来るのかと。
「おい、チョン・フィイン!あなたはなぜ今出るのですか?」
「私はトイレに行って来ましたが、あなたはいませんでした」
「トークを送ったのに確認しなかった?」
「あ…?」
携帯電話を取り出してアラームを確認するフィインとメッセージ確認しなかったかという星。フィインが画面をスクロールしてアラームを確認すると、怒りを始める。アラームウィンドウにはアプリの広告やゲームイベントアラームしかなかったからだ。速射砲ラップを吐きながら、星とジミンに問いかけるフィインに二人はしっかり笑って渡そうとした。
「ああ、これらは本当に死にたいですか?え?私が何分待っているのか知っていますか?」

「子供、ごめんなさい。あなたの飲み物でも一つ買ってあげる。早く行こう」
「イさん」
飲み物を買うというジミンの言葉に少しは怒りが解けたのか純粋に追いつくフィインだった。星はジミンに上手だったと自然スレフィインの肩に自分の腕を置いて先に進んだ。すぐにフィインの顔にも笑いが浮かんだ。それでも胸の一点には蒸し気がないと嘘だったようだ。気楽に笑えないフィインだったが、彼を気づかなかった二人はただ明るく笑って前に引きずっていった。それからジミンがちょっと変な感情に気づいたのか、フィインに質問を投げる。
「でも、お前はさっき何があったの? 隣にその人と。
「…それではなく、服もそうで全体的な体球がパク・ジミン、君と似ていて君だと思って押したんだ?」

「…クレイジー?よ、あなたは本当…クレイジーじゃない?」
「いや、黙って聞いてみて、ちょっと」
「……」
フィインの一言ですぐに死んだ星を見たジミンが一人で静かにゆっくりと笑った。彼の隣にあった星がジミンの背中を一台殴って、ジミンの笑いが止まった。フィインは先ほど言ったことを続けて付け続けていった。
「とにかく、それで彼の夏の夏の飲み物を飲んで服に恥ずかしがり屋…やってしまった…あまりにも大丈夫で申し訳ありません。
「エヒュ…、なんだか。すみませんが、もう会えない人だ」
「いいってこと、悪いってこと?」
それはジミン本人も考えられなかったのか、星の言葉にただ肩を浮かべて下げた。それに星は見当たらない表情でジミンを見つめた。星の目つきがジミンの気分を傷つけたのか、二人は話し合いを始めた。なぜそんな目で見つめているのかと爽やかなジミンとは、あなたは良く言ったのか悪く言ったのか一つだけしろという星。 そのように星とジミンがティカティカの間、フィインは一人で蒸し心に抑えられていた。さっきその男の服をどうでもしなければならなかったという後悔でいっぱいのフィインの中だった。二人は笑っているが、一人で真剣な表情で床に視線を固定したフィインが心配な星が彼女の肩を置いて回叩いた。それでもフィインのせいだからなんとシールド打つこともできないこのまあ同じ状況に少しぎこちない気流が流れた。しばらくの間、静的が流れていた三人の空間にジミンの声が出てきた。
「ごめんな気持ちがあるだろうけど、それでも今来て元に戻すことができないんじゃない。
すでにその男性は、フィインから遠く離れてから長く、ジミンの言葉が合う言葉だった。フィインが小さくうなずいた。それ以来、もう一度長ければ長く、短ければ短い静的ばかりが彼らのそばに走った。並んで肩を合わせて歩いていく三人。ジイイン - 誰かの携帯電話に電話がかかってきた。着メロが振動ではないというジミン、急に携帯電話を取り出して自分のものかどうかを確認するフィインと星だった。フィインは自分ではないという表示で携帯電話を入れ直した。星を除いた二人の視線が一斉に星に集まった。星は人差し指を口に持ってきて静かにしろと言った後、少し離れて通話を始めた。
「こんにちは?
星が通話を終えると、ジミンが尋ねた。
「誰?」
「お母さん、親戚の方々に来たと早く入ってくる」
「ハル、そう?それでは私たち全員に入ろう。どうせもうやることもないのに」
「ええ、私はすぐに飛び込んでみましょう!」
うん、おやすみなさい!二人が星に向かって手を振り、星はいつの間にかすかになった姿で彼らの瞳に照らされた。
「や、小ささ。よく行って。
「もう開学か…、ハイゴ」
ため息を吐きながら開学が嫌だとアンタルブリはジミンにフィインが自分が教育部でもないのになんだというのかとアンタルを切る。開学まで二日残ったと現実を注入してくれるフィインにジミンは地が消えてため息を吐いて帰った。
「おやすみなさい、チョンウィン」
「おお、お前も。二日後に見よう」
挨拶を最後に置く、いいえ3つの距離はより遠くなり、さらに狭くなった。いつも様々な対象の距離は操縦する人の心によって遠くなるか狭くなるが、そのような対象の心はお互いをしっかり握っているだろう。ジャロで絶対撮影できないそんな街。
________
いつのまにか、光の速度で週末が通り過ぎ、新しい一週間の始まりを知らせるひどい月曜日がやってきた。月曜日で開学日の今日、フィインの携帯電話で騒々しくアラーム音が鳴った。うーん… 、睡眠があまり壊れていないことを知らせるフィインの割れた声が部屋を埋め、フィインはアラームを消して再びプルッソ、ベッドの上に横たわった。再び眠りたいと思ったら立ち上がり、両腕を頭の上にずっと上げて伸ばした。副秘的 不備的-目をビビダが強く巻いた外れた。ジミン、星と一緒にいる時の目の大きさの約0.75倍の大きさの目をやっと浮かべたまま訪問を開いて洗うフィインだった。野蛮にヘアバンドを頭にかけて税収を始めた。その時、フィインの部屋でジイイング振動が鳴った。もちろん、トイレにあったフィインは気付かなかった。ピッタリの髪を巻いて出てタオルを頭に置いていたフィインが携帯電話を確認した。
「え?文別に電話してきた。一緒に行こうと電話したのか」
電話アプリをオフにするメッセージウィンドウに残っている星の言葉。
-ヤヤヤ
- 電話しない?
- エヒュ
-また寝ていますか?
-ああ作ってみよう
-見てない?
- いない証言
-ああ、早く見てください。
- そこですか?
- わからない
-今日の開学だよ
-あなたが出なければ知覚です。
-初日から稼ぐのではないでしょうか?
- このおばさんは本当に
-ああ、もう10分待って行く
星が送ったメッセージでいっぱいの画面だった。最後の文字を送った時刻は8時17分。そして現在時刻8時21分。残り時間はわずか6分です。服も着なければならず、朝も手に入れるには足りない時間だ。フィインはブリャブルヤン台所に走り、トーストに食パンを一つ入れては再び部屋に戻って制服に着替えた。笑みを浮かべて、スカートをほぼ全部着ていく刹那に部屋の外でヒュントーストが尽きたという声が響いた。ベッドの横に置かれたバッグを釣った後、背中にまたがって出てトーストを口に刺した靴に足を踏み込んだ。タクタク-つま先を明け、最後にぴったりフィット靴を履いて玄関のドアを開いた。外に出ると見える星。
「ああ、思ったより早く出たんだ。
「そうではない。今25分だから…、走らなければならないのに?」
星が小さくうなずいてエレベーターの方へ向かった二人だった。ちょうど上の階にあったのですぐに乗ることができた。 띵-エレベーターはいつの間にか1階に行き、二人は前に進み、ますます速度をつけた。アパートの玄関を出よう ああ! 彼らを待っていたジミンが突然私と驚かせた。

「ふふっ、驚いた?」
「ああ、びっくり。あなたも一緒に行こうと思っていましたか?」
「うん。当たり前じゃない。どうしてあるの?」
「じゃあ早く学校に出て行こう」
フィインの言葉を最後にいつもよりもう少し速く走る三人だった。一番前に走るジミンが二人に叫んだ。

「早く来て、カタツムリ!」
恥ずかしくて日当たりの良い、恥ずかしい表情でジミンを追う二人だった。ジミンはそのような彼らのために途中で止まって待っていた。すぐにジミンの隣に到着した二人で、少し前に校門がはっきりしているのではないように見えた。先ほどより早く学校に向かう三人は28分で校門を過ぎた。 30分になる2分前、ギリギリを免れたということだ。三人はすぐに学校の建物に飛び込んだ。ハルトクで3階まで上がって教室の中に入った三人は急いで席に座った。時針は30分が少し以上の時刻を指していた。大変だったか、フィインは机の上にこぼれた。残りの二人は来たらすぐに携帯電話を取り出してSNSを見回した。すぐに、先生が入ってきて携帯電話はポケットの中に入った。学校内部全体に響き渡る鐘が終わると授業が始まった。
授業内容が耳に入らないフィイン、スター、ジミン。ジミンはぼんやりしてただ黒板だけ見つめただけで、星は公策に落書きをしていた。フィインは首をすっかり下げて、眠りに落ちた。休む時間だけが切れるのを待っている3人には、授業中に時間がそんなに走ることができなかった。星の公策の一ページが落書きでいっぱいになった頃に紙がもう一度鳴った。チュウク-授業に集中だとは全くしなかったジミンと星が伸びを弾いた。すぐにフィインの席に走っていくことを確認しては、フウクのため息をつく星だ。

「これは寝ている。また寝るの?
右陰-目を飛びながら腕を後ろに伸ばしてずっと伸ばしてくれたフィインが時計を確認するとすぐに休む時間であることに気づいた。フィインの席の前に立って情けないという表情で眺めるジミンと星。フィインが席で起きるとすぐに肩に自分の腕を置いて教室の外に出て行く星だった。教室の扉を開き、三人が廊下の上を歩いた。その途中、頭を持って歩いていたフィインが何かを見ると、急いで頭を下げた。そして一人の男子生徒を過ぎた瞬間だった。
「やる?その飲み物」
特有の重低音が輝きを止めた。確信に満ちたような口調に、フィインが後ろに回った。アハハ、かっこいい笑いで頭を掻き取るフィインだった。

「…あ、あ…はは…こんにちは…?」
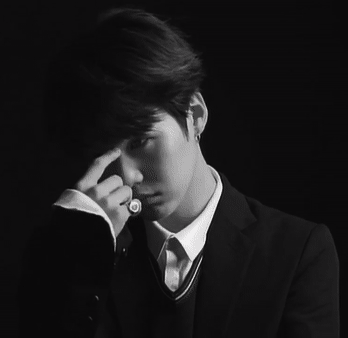
「今回は逃げると思わないの?」
_________________
尽きた作に冷たい水をかけます。台無しに。
