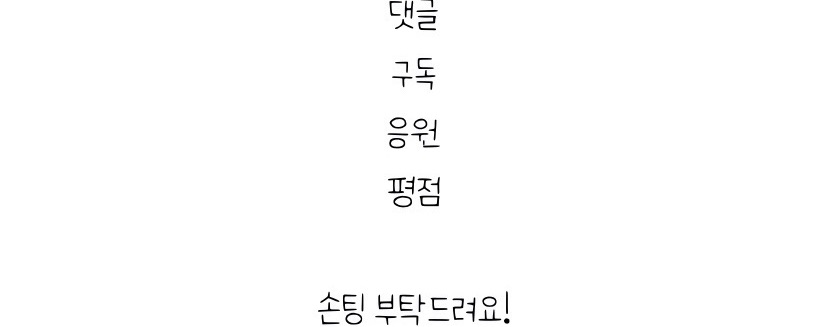レジリマンシー
相手の心を読む注文
私は幼い頃から他の人の心を読むことができる特別さを持っていました。まあ、それも相手と体が届かなければ読まれるのだったけど。生まれたばかりの時は誰も知らなかった。私が自分で考えることができる程度の年齢になると、ますます発現し始めた能力を、私のお母さんはぎゅっと隠すのに苦労した。 これひとつ隠すと私一人で何人も住んでいない叫び所まで送ったのを見れば。
やっと18だった。まだ高校も卒業していないのに…私は突然送られたこの場所が腐って気に入らなかった。すべてが不満であり、私に与えられた能力をもっと恨むしかなかった。それでも幸いなのは、こんな村の隅にも高校が存在するということだった。転校手続きを踏んで、聞こえてくる噂を見ると、その高校全校生がちょうど七つだけという。 …くそー。
人生がこうだから、一日も抜けず毎日考える。少なくとも私にこの能力は特別さというより呪いに近い、とても不気味で恐ろしいものだと。みんなの加食と偽りを読み出すのが特別さなら絶対に特別にしたくなかった。
「明日だったのか…」
遠く離れた場所で一人で過ごす娘が気になっているのか、学校の近くに小さな家を調べてくれた私たちのお母さん。トイレの1つに部屋の2つ、別々のキッチンとリビングルーム。一人暮らしにはちょっと大きな家だったがそれなりに居心地が良かった。まだ何もない家だから取り出してきたカップラーメンを煮て食べて厚い布団を敷いて横になった。

「体だけ届かないと…大丈夫だろ?」
望んでいなかった瞬間に相手の心を読むというのは、思ったよりかなり悲しく、悔しいことだということをよく知っていた。この能力は私が人を信じることができず、すべての心を疑わせました。 私に近づいてくる子供たちも、大丈夫にしたい子供たちも体に軽く触れれば彼らが私をどう思うか読んだから。そもそも他の人のように普通に友達を作って、誰かが好きなこと自体が私には許されていないわけだった。
カムカムな天井を望むより恐怖半分、ときめき半分で目をつぶした。私はあまり望んでいません。私も普通に人々の間で混ざって笑うことができれば、それらのうちの一人でも私を心から好きにしてくれればそれで十分だった。
🫧
新しい制服を着てカバンまで野蛮にした後、見知らぬところに向けた第一歩はあえて言葉で表現できないほどだった。校門に足が届くと見える 広い土場の運動場を越えてかなり大きな本館の建物にびっくりしたのもしばらく、教室の扉を開けて入ると先生に見える一人の男が笑って見えた。
「君がいるの?」
「あ、はい…」
「ソウルで暮らしてきて、ちょっと不便だろうけど、どんどん慣れていくんだ。もし私たちの学校については知ってる?
「全校生が七人だということだけ知っています。」
「それくらいなら全部ね!わかるように私たちは学生数が少なくて半分がちょうど一つだ。先生も何人もいない。私が担任だから今後何かあったらサムに来ればいい、わかるだろ?」
初めて見た担任サムの姿は親切なようだ以外は特に考えなかった。先生よりは今後一緒に過ごす友達がずっと気になったから。担任サムは簡単な紹介の後、私を連れて半分に向かったし、カンクン大は心臓をようやく付与し、半分に入成した。
追い出された。それもすごい。学生数が少なくてはいけない点が、彼ら同士がまとまっている可能性が大きいということだった。それなら私が割り込む席は当然ないだろうし。そうなると私は…自然にいじめ… ?!それだけは絶対にならないという考えだった。強制的に転校してきたのも、寂しく死ぬのにいじめだな。視線は床に下り、頭を通り抜けた。
傲慢な考えを尽くして不安に震えているとき、自己紹介をしてみるという担任の言葉と共に頭を上げて正面を眺めた。
「いや…」
言葉が顎詰まった。学生数が少ないのはとてもよく知っていたのに…。それがみんな男だとは誰も話しませんでした!二つの目が丸くなった私と同様に、彼らも慌てた気配を隠せなかった。転校生がやってきたことも、さらに女であるとは全く予想できなかったか。
「…キム・ヨジュよ。これからよろしくお願いします」
「ヨジュは…あの中央に座ればいいようで、今日の授業はお前らがヨジュ学校を見学してくれることで泣きましょう。
そうして半分には南政四七と転校生の私だけが残った。いや、どんなサムがやってるの?恥ずかしいほど自分勝手な担任サムに教託の隣に立って目だけひどいだけだ。心のようにはすぐにも逃げたい気持ちが煙突のようだったが、すっかり空いている席へと座った。
ハーピル席も中央だから七が私を包んでいるような感じだ。息が顎あふれるほどのぎこちないさにバッグを下ろして席で起きれば、みんなで合わせても同じように私を見る七つの視線だった。
「もし私に言うことでも…?」

「いいえ、私たちの学校に転校生が来たのは初めてです。ちょっと不思議です」
「私も不思議だ。女一人はいると思ったが…」

「まあ、どうしようか。こうなったことを元気にしよう」
「ええ、みんないいのにお前の名前は何?」
さすがにお茶したい形だった。私は転校生という名前を言いましたが、彼らは私に名前を教えてくれませんでした。彼らは一人ずつ帰り、名前を話し、私は頭をうなずいて、彼らに向かって笑った。彼らの名前はキム・ナムジュン、キム・ソクジン、ミン・ユンギ、チョン・ホソク、パク・ジミン、キム・テヒョン、チョン・ジョングク。一つのようなきれいな名前だった。
紹介を終え、私たちはみんな一緒に学校のあちこちを巡りました。彼らが説明してくれる学校の最大のシステムは、週に一日、それぞれ選んだサークルの授業を聞くこと、秋祭りだった。まもなく祭りシーズンだったのも同じで…。 ?
奇妙に私は彼らと友達になりたかった。理由はよく分からない。お互いいたずらしながら明るく笑う姿に僕もやはり彼らの間に挟みたいという考えだった。たぶん私はあなたがうらやましかったのかも。
🫧
10日頃、私は彼らと楽に話すことができるほどでした。見知らぬ人を多く選ぶ便と同時に乞食のような能力のために人々を恐れていた私が、彼らの前ではベシシ笑ってしまった。まさに彼らが好きで、良い子供たちのようで積み重ねた壁を壊した。しかし、私の心の奥深いところには依然として疑いと恐れがいっぱい入っていたことを自覚できずにいた。
しばらくだった。彼らに恐怖を取り出して見せて、たくさんの日を立てたのは。私がイヤホンを耳に挙げていてジョンジョングクの言葉を聞くことができなかったとき、ジョンジョングクは非常に少し私の肩に手を置いた。
「ヨジュ、ご飯を食べに行きます」
タック! 私の肩に触れた前庭の手を打ち、昼食メニューのテーマで騒々しかった周辺があっという間に静かになった。間違いだった。私は絶対前政局の手が嫌いでしたのではなかった。ただ…私が彼の心を読んでしまうのか怖くてそうだったのだ。私はあなたが気に入ったのですが、前政局の心はそうではないと言っているのではないかと恐れていました。前政局も以前彼らと違うことはないかと思う…。怖かった。

「なんだ。前庭、あなたは何をしたの?」

「…まあ、私は何をしましたか?」

「ヨジュヤ、なぜそう。大丈夫?」
イヤホンの列をずっと引き出した。私の両耳からイヤホンが抜けて、私は席から立ち上がり、集まっている彼らのそばで後ろに歩いた。今、私はすべてが怖かった。
「キム・ヨジュ、何が起こったのか。
私の顔が思索になったことを確認したキム・ナムジュンは表情を固め、声を出して私に近づいてきた。それも一歩だけ、本人が近づくにつれて私の体がひどく震えるということに気づいたキム・ナムジュンは眉間を突き刺して私に近づこうとする他の子供たちを防いだ。

「女主よ、保健室に行きますか?」
「おい、行かないで」
「愛の状態が良く見えないのに保健室でも連れて行かなければ…!」

「ああ、私たちが近づくにつれてもっと震えています。」
この中で最も気づいたキム・ナムジュンは、私に近づくようにするチョン・ホソクを片腕で止めたまま、私を注視した。キム・ナムジュンの言葉にみんながその場できつくなかったし、私は両目を閉じて息を大きく吸い込んだ。
「そ、私が人と体が届くとちょっと大変で…ごめん、本当にごめん……」
私はフロントドアを通してそのまま逃げるように半分を飛び出した。心のようにはすべてをすべて打ち明けたかった。だが誰がこんな言葉にならない話を信じようと思うかと思ったし、もしも私を魔女のように考えるなら…。あまりにも想像しそうだった。それから頭の中を通り過ぎる考えに走っていた足を止めた。 ああ…
「もう終わりましたね。」
かわいそうな笑いが私の口元にありました。私が彼らの前でこのような姿を見せてしまった以上、私は再び彼らと親しくなることができないようだった。猫が私をどう思うか明らかだったから。私は前庭の手を置いて打ち出したのも足りなくて彼らを恐れるまでした。しっかりとした説明もなく逃げたりしたし。
彼らは明らかに私をよく見ないでしょう。私に会ったみんながそうでした。彼らも変わらないと思っていた私は唇をきつく噛んでこうして生まれた自分を狂わせて憎んだ。
「なんと能力…必要ないんだ……平凡でない俺が嫌だ…」
涙が喉に落ちる。私は学校に声を出して泣くことができない私が心配するだけであり、渦中にもその7人が傷つかなかったのではないかと心配だった。今でも半分に戻るかという考えも聞いたが、彼らに直面する自信がなく、体が痛いという言い訳で助退症を書いた。
🫧
学校に行きたくなかった。明らかに数日前だけでもソウルよりも良いという考えだったが、今はまた心が変わった。 このまままた帰るのも悪くないかな…。 体をふとんで包んだまま、しばらく呟く携帯電話を聞いて担任に連絡を入れた。
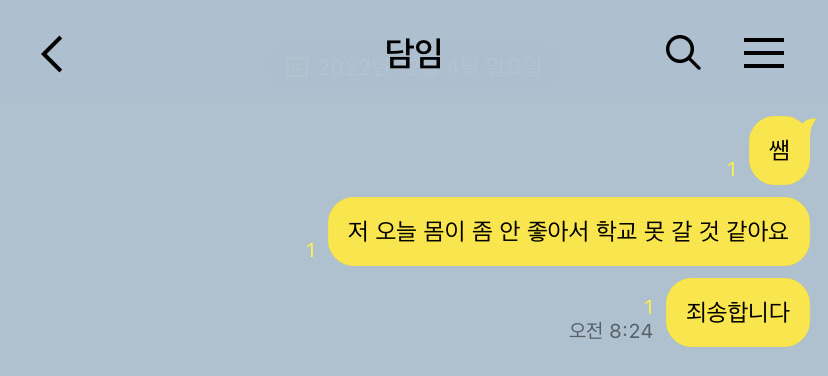
嘘だった。体が痛いこんにちはすごく乗っていた。昨日家に帰ってから何も食べずに横になってただけで体がチプドンした。外の口径でもするかと思って席で起きた私はフードティーをかけてスリッパを引いて外に出た。
「こんな村の隅にもならなければ私はもうどこに行かなければならない?」
家の前の庭を越えてこぼれた土道に沿って歩き始めると、いつの間にか学校の隣の精子に到着していた。ハピルに来てもいいのかという考えに拳で頭をパックした。それでもなんだか。まだ昼休みでもなかったし、この時に彼らに遭遇することはないから安心して精子に身を寄せた。
精子の木の柱に背中を当てて膝を引っ張った。澄んだ天気に涼しい風、ソルソル風のプルネムと耳をくすぐるスカラベ音まで。複雑だった髪が徐々に沈む感じだった。
「…一度読んでも見てみるよ」
頭が整理され、心が快適になると昨日のことがついに後悔した。前政局の手が届いたとそう私を日を立てるのではなく、少し恐れても、誰でも去っても一度読んでみることをそうだった。猫だと同じだろうという私の考えが興奮した状態ではあまりにもしっかりしていたようだ。
ため息をふくらませて彼らを打ち出したことを死ぬように後悔していた時、すぐ隣の学校が賑わい始めた。彼らであることが明らかだった。今日の授業に体育や野外活動があったか…。唇をずっと突き出してしばらく心配して精子で体を起こした。 … こっそり少しだけ見てくるよ、まあ。
地面に恥ずかしいスリッパでできるだけ音が出ないように慎重に歩いた。校門の後ろから頭だけを抜き差し出してみると、彼らは手にアイスクリームを一つずつ握り、運動場を漂っていた。一体どんな話をしているのか、あんな表情が出てくるのか気になって狂う地境だった。やがて彼らは校門側に向かって歩いてきて、私は機会だと思って体を校門の後ろに隠したまま、彼らの話をこっそり覗き込んだ。

「今日、女主はなぜ来なかったのか…」

「やっぱり私たちのせいで傷つけないのかな?」

「わかりません。しかし、昨日はとても震えましたが…心配です。」
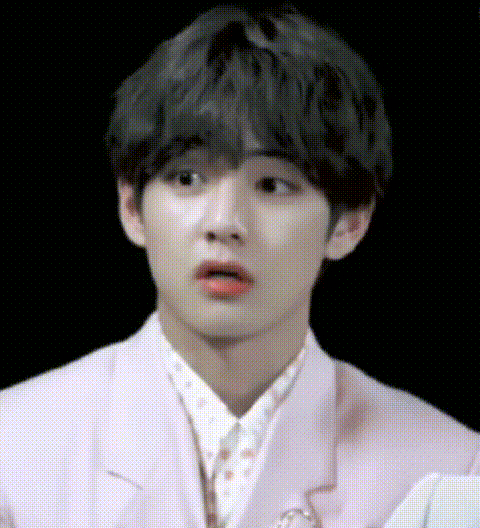
「おい、じゃあ、私たちはちょっとあなたに行きますか?」
「あ~キム・テヒョン~~」
「ハ、やったの?やったよ!」

「やめたもの。君はキム・ヨジュなんじゃない? できない電話番号は?
「…じゃあなんだ!キム・ヨジュ心配されて死ぬんだけど!!」
「あなただけが心配しているのか、私たちも心配してください」

「私たちはキム・ヨジュについて知ることがあまりない」

「本紙しばらくなったから当然のことだ。これから女主ともっと近づけばいいんだよ」
ハマターは音の中で泣いた。私がいなければ、彼らは知っていてよく過ごすと思いました。私が転校に来る前に戻り、彼ら同士ハハホ号を騒がせて過ごしそうだった。しかし、私の予想は正確に外れた。あの心配がたとえ偽りでも、一生友達の心配一度受けたことがなかった私だったから。両手で口をひっくり返して、叩きながら泣いた。
「ジン、チャ…イライラ、なぁ―」
すでに涙でいっぱい濡れたフードティーを手でしっかり握った。灰色だから涙跡がとても鮮明に見えたが、今私にそんなことは関係がなかった。腕で目元を一気に拭き取り、開いた目元で校門を越えて彼らの前に立った。
七は私がこのような姿で突然現れるとは思わなかったのか、私を発見するとすぐにウサギ目をしてウルル走ってきた。渦中に昨日私が体が届くと大変だったと言ったことを覚えているのか心配の言葉を渡すだけ、私に届かないように苦労した。
「みんな、私はあなた一回だけ抱きしめてもいい…?」
戸惑うのが私の目に見えるほどだった。やっぱり昨日まででも手一回触れたと怖くて逃げた子が突然抱きしめてもいいのか。俺みたいにもいやなく奇妙に感じただろう。しかし、私は彼らから確認したいことがあり、私の選択によって心臓にとげが刺さったとしても、完全に私が持っていく痛みでした。
まだ怖い。また相変わらず怖い。もし彼らが表にだけそんなふりをしているのなら、懐には違う心を持っているのなら私は…。不安な気持ちで、私は次々にそれらを引きつけました。ダルダル震える体で両目までしっかりと巻いたままだ。
…間違っています。私が間違っています。 七人みんなの本気を聞いた私は首をすっかり下げ、肩をすくめた。土底の運動場には、私の目から落ちた涙滴が丸い跡に残り、私はとんでもなく叫んだ。
「俺、ガ…俺、ガア…。ごめん、海愛―。俺が、お前、ネルを……」
「君が何がすみません、ヨジュヤ」
「ええ、あなたは私たちを何と言ったのですか?」
「俺、がお前の心、を…の、ひどかった。美、ごめん…」
彼らは私がなぜこんなに泣くのか分からないでしょう。彼らにはない能力であり、呪いを私が持っていたので、私が倒れるように泣く理由は私だけが分かった。
私が彼らをやった瞬間、私の耳元には他のような似たような心が読まれました。心配、恥ずかしい、そして小さな震え。生まれて初めて読んだ純粋な心に、私は限りなく心臓を走りました。私に彼らは捨てたかった能力を、呪いだけに感じられたこの能力を、初めて愛するようにさせてくれた人々だった。
上記の記事はCALLIOPEクミで書かれていることをお知らせします。