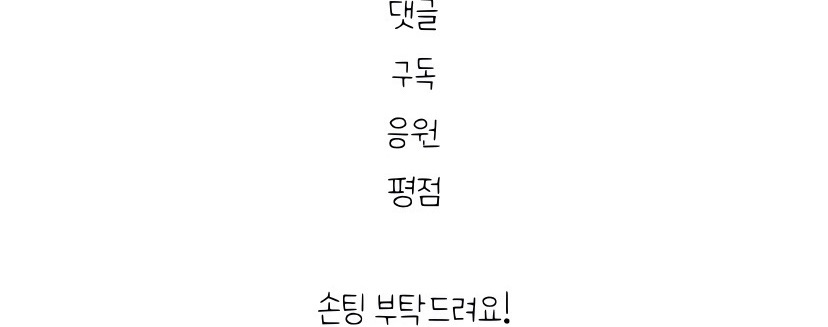奇妙で美しい
まだ生きている理由を知らない人には、話を聞かせたい。この物語は私の人生に一度しかなかった、何度も言っても誰も信じていなかった奇妙で美しい場所と私と他の存在についてのものです。
私はいつも人生の疑問がいっぱいの人でした。私はなぜこのように生きなければならないのか、私が存在する理由は何なのか、私がこのように生きていった後はどう描かれるのか。年齢に合わない疑問だった。このような考えをした時がわずか17であり、その疑問は1年の間はるかに大きくなった。
十八になった時、特に生きたくなかった。生きていく理由を知らず、生きていく方法を知らなかった。 1年前の疑問に追加された質問は私自身を苦しめ、私が見る他の人々の姿と私の姿がとても違って自分を嫌悪させた。
多分一日、毎日行った学校を初めて何も言わずに行かなかった。一日中携帯電話が泣き叫び、私を見つけた。家にいた家族たちは朝に制服を着て私を見たので子供がどこへ行ったのか心配されたし、学校では誠実だった学生の不在を親さえ知らなかったので変だっただろう。
しかし、私はすべての電話と連絡を取らなかった。私はそのまま携帯電話を切って、ちょっと肌寒い風が吹く街を出た。私の目には空虚さと寂しさだけ存在しただけで、まるで何も感じることができないロボットのようだった。
「あー、私は今何してるの?」
決まった目的もなく無頓着に歩いた。その一歩をしばらく止めたわたしは首を空に飛び込んで深いため息をつく。私が吐いた息と馬は、どんな言葉よりもずっしりとした。その中には様々な感情が混ざっていたから。 その時だった、私の人生に皆がびっくりすることが起き始めたのは。静かな道端に瞬間、体が押されるほどの激しい風が吹いてきたし、腕で目元を覆いながら風を頑張っていた私は真っ白な光を見た。

光を見た瞬間、体に力がどんどん落ちるのが感じられた。さらに眠くなるまで一体が軸増えて目を閉じたのが最後の記憶だ。
🏝️
眉間を刺して慎重に目を開いて見えるのは青い海だった。恥ずかしかった。きっと私は灰色の建物がいっぱいの街で目を閉じていたようです。私が夢を見ているのかと思ったが、鼻の先を叩く水の飛び出しと耳元を吠える波の音が鮮やかなのを見て夢は絶対ではないようだった。
席で体を起こして手の甲で目を浮かべ、ウサギ目で周りを見つめた。周辺は全海に砂や砂利がいっぱいの地、ずっと伸びたヤシの木まで。ここがどこか正確には分からなかった。ただ孤島のようだと思うだけ。

「誰が連れてきたの?」
「ジミンは兄です。」
「おい、お前まさかまた拉致してきたのか!!」
「うーん…ただ気絶させて連れてきたの?」
「それが誘拐だ、狂った子だ。」
事態把握のために精神をちょっと取り上げていた車、耳に刺さったのはウェン男たちの声だった。この島に一人ではなく幸いという考えと同時に、彼らはなぜここにいるのかと思ったし、何としばらくを去る彼らに席で身を起こした。好奇心に勝てて足音を殺して話を聞き始めた私だ。
「あー、パク・ジミンあの子はなぜ人を連れてくるのか」
「わかりません。今回も可哀想に連れてきたの?」
「もちろん人間を連れて来れば私たちが困るから」
「わかりました、私も。」

「知っている子が人間を連れてくるのか」
「いや…あの目がきっと……」
ネズミの子どもたちの物語を覗いていると、自然に眉間が鈍くなる。私を連れてきた男はパク・ジミンという男がはっきりしたのに…。話を聞くと聞くほど彼らは私とは違う存在のようだった。きっと私を人間だった。本人はそうでないことだけ。
私は通常、初めて見ている人を判断するとき、彼らが言うことを聞き、良い人なのか悪い人なのか、私に役立つ人なのかを区別します。しかし今は状況が少し違った。どんどん人間、人間するのがちょっと受賞した。私が彼らを怪しげに始めた瞬間、この島から出る方法は1つだけでした。彼らを気絶させて死んで走るか、それらを脅かすのか。ひとまず隣にある石を一つ拾った。石の大きさは私の手のひらにふさわしいほど。私は手に石をしっかりと握り、一足ずつそれらに向かって慎重に近づいた。
「目つきが何。私は人間のようにまた可哀想だった?」

「あ、お兄ちゃん!今回は違うんです。あの子は可哀想だより危ない?心だけ食べれば波に飛び込むかもしれないそんなことがあるでしょう。
「わ、それでここに引っ張ってきたの? 回ったの?
「テヒョンが兄、ちょっと待って」
なんてクレイジーな音かした。神の空間とは… ?彼らはすべて不審な言葉を送受信するだけでなく、人なら容易に信じられない言葉を術術吐き出した。何も理解できない状況に私はまだ石をしっかり握っていた。彼らが私を見ればいつでも投げる準備をしながら言葉だ。
だがすぐに誰かの手振りにさえも差し引いたし、私は席にすっぽり座ってしまう。

「あえて人間の話題に何をしているの?」
「も、石…!」
笑う姿とは全く見られない格好の表情で私を見下ろす明るいブルネットの男だった。その男の表情より不気味なのは、その男の手のひとときに私が持っていた石があっという間に彼の手に入ったということだ。私は席に力が落ちて砂の底に滑り落ちた。おかげでお尻を撮ったが、その痛みは全く感じられないほど私は震えていた。
「やっとこの小さな石一つで私たちを打つというのか…ええない。」
「おい、いや。ジョングク、表情を少し解いてください。
「ハァッ、どんな兄が私を育てて育てます。あの人間より兄がもっとええない、本当。」
悪魔が存在したなら、あんな顔だったかと思った男の視線が、私自身をアップして育てたという男に向かった。二人は騒々しくぶつかり始めた。レモン色の髪をしたパク・ジミンという男は私に手を差し出すまでしたが、私はその手を握ることができなかった。いいえ、正確にはキャッチしませんでした。現在、私の目には、すべての彼らに対する疑いと恐怖、そして境界がいっぱいだったから。
「大丈夫、握って起きてもいい」
「…そっちが私を傷つけたら、どうしようと手をつかむの?嫌いです。
「おい、人間。私たちはそんなに悪くないの?
「嫌いだと言ったでしょう。あなたたちが大丈夫な人なら、そもそも私をこんな所に連れて来てはいけないのではないか?」

「誰かが連れてきたくて連れてきたと思う。あなたを連れて来たのは私たちではなく、手を差し伸べているその子なのか?」
知っていた。すでに彼らがしていた話を十分に覗き込んだ状態だったし、私に連れて来たというパク・ジミンという男と私に性質を呼ぶキム・テヒョンという男の名前まで聞いた。私はそれで彼らの手を握ることができませんでした。知らない空間と知らない人、怪しい彼らの言葉まで。私が境界を遅らせることができない理由は十分で、下唇をぎゅっと噛み、視線を突き刺した私だ。
「ヒュー、キム・テヒョン、あなたは性質を殺してください」
「さん…私が何!」
「あなたは今、私に性質を呼ぶのではなく、あなたの友人の奴をジョンナ・パダンにしなければならないのです。

「そうだね。私が見た時、パク・ジミンさんは席を奪われてこそ精神になるようだ。
「お兄さん…私そのくらいじゃないですか?」
「いや、何はない。逃げる時間5秒与える。捕まったら死んで」
「キム・テヒョン、目が回ったのを見て…ツヤ、私を少し生かしてください!」
「うん、苦労」
パク・ジミンという男は悔しいように口を掻き出すキム・テヒョンという男が手で首を引くジェスチャーを取ると音を立てて走り始めた。そんな二人に馴染むように見守りながら、クッキュ隊は残りの人たち。彼らとは異なり、私の顔はまだ硬く固まっていました。私はこの状況でさえ、彼らが飾ったのかもしれないという考えに乾いた唾液を飲み込んだ。
それから、何の助けもなく自分で地をつかんで立ち上がり、空きスペースを通って走る私だ。目的地はどこかわからない。もともと、この島は私よりも彼らがよりよく知っていて、ここを離れることができなければ、彼らからも遠く離れなければ安全だという考えだった。
「お兄さん、あの女、そんなにしても大丈夫ですか?」

「まぁ、本人も考える時間が必要だろう。すぐにもともとあったところに戻すこともできない奴だから。
「うーん…24時間になるにはどれくらい残ったの?」
「まだ21時間も残りました。」
「ひとりちょっと置いてからなるまでしないと、その時能力を使ってみよう」
知りませんでした。彼らがどんな存在であり、どんな心で私を連れて来たのか。だからこそもっと必死に走ったのかもしれない。
🏝️
ハッハッとし、しばらく走っていたのはこの島でそれほど高い所だった。落ちると波が徹底する海に沈むようなそんなところ。崖まで走ってきて感じたのに、この島は彼らが言っていた神の空間?そんなことが合うようにしたかった。なぜそう思ったの?ここまで走っている間、動物はこんにちはギアを走る虫一匹見られなかった。草と木はこんなに壮大に育ったが、生きて動く生命体は私と彼らだけというのがパク笑った。
「…あ、涙がなぜ私」
私はちょうど面白いと言った?いいえ、それは実際には嘘だった。少し怖くなりました。生きて息づくのが植物たちと私、そして彼らだけなら…私がこの島で頼ることができるのは、私がそう恐れていた彼らだけだったから。
まだ彼らの存在でさえ疑わしくて恐ろしいです。どうすればいいのか、どこに行くべきかタイトな今。息が顎詰まってくる甲冑に拳で胸をパックパック殴りながら声を出して泣いた。
「ここで飛び降りれば帰れるか…?」
涙がもはや出ないほど泣いている場所で起きた私は、崖の下で海を焦点のない目で見つめた。その海に身を投げると帰ることができるという考えは、きっと本当に馬鹿だった。知りながらも、まさにそうしたらと思って口の外に投げ出した言葉だったが、一言で返事が戻ってきたのは私の予想外だった。
「人間はもともとそんなに愚かですか?」
「何?」
「いや、常識的にここで飛び降りると、あなたが住んでいた世界に戻ることができるはずがない」
後ろから聞こえてくる声にちょっと頭を回した。私に返事したのは、さっき私に性質をぶつけたその男だった。名前がキム・テヒョンだったか。前から感じたのだが、この男は妙に私の神経を傷つけた。私を可笑しく思うようなその表情と私を笑うような口調。中で泣く何かが上がった。

「そこで飛び降りると死んでいく。あのキラキラする波に巻き込まれて、ちょっとチイダ海の底まで沈むと。」
迷惑。迷惑。迷惑。彼を警戒し、恐れていたのもその時だけ。頭の中をいっぱい詰めたのは迷惑だけだった。私は現在、私の前で飛び散るようなキム・テヒョンという男が迷惑だった。中から上がってきた何かと彼に向かう不気味がつぶれて、私はやめられないように来るようにした。
「…ずっとこういうことになって、むしろ死ぬのが良い」
「おい、あなたは狂った?」
「才能のない子。私が出会った人の中で、あなたが一番最悪だ、人かもしれないが。」
私は被食して彼を笑った。そんなにどんどん後ろになって崖の端に身をかけ、結局そのまま体を後ろに濡らした。崖の下に落ちた瞬間、私は彼の表情をよく見ました。これをしっかりと噛んで両目をくすぐったその表情が海に向かって落ちた私の口元に好線を描くようにした。

その時、私がここに来る直前に見たその眩しい光が私の目の前にもう一度現れた。とてもキラキラし、目を開けてその光を眺め、同じように体に力が抜けて眠りが溢れてきた。体が軸が伸びる直前、私の体がある力に導かれ、崖の上まで一気に引き上げられ、そのような私の体を受け取ったのは愚かな男だった。その男の懐に抱かれたのを最後に、私の記憶はまた壊れた。
🏝️
同じです。初めて目を覚ました時のような水の飛び出しと波の音が唇をいっぱいに噛ませた。中央に浮かんでいた年が過ぎ、オレンジ色に染まった空を見ると時間はたくさん流れたようでした。空笑いが漏れてきた。時間はこんなに流れますが、私はなぜまだこの空間にとどまるのか…。力を与えていっぱい拳がぶらぶら震えた。
「壊した?」
レモンの髪の男だった。私をこの場所に導いた張本人であり、私に手を差し出したその男。パク・ジミンという男は私に近づいてきて、私は彼が近づくにつれて体を掴んだ。
私はまだ彼らを信じることができず、ただ恐れているだけです。その男はそれを知っているか分からないか近づいてきた足を止め、席にしゃがんで座った。彼がどんな考えなのか分からず、神経をたくさん急いで彼を狙ってみた。
「テヒョンが能力まで書いていって君を救った。 なぜそんな選択をしたの?
「…私はなぜ答えなければなりませんか?
「気になる?私たちは誰で、ここはどこで、いつ帰れるのか。
できるだけ体を丸めて彼を遠ざけていた私は私よりも下にしゃがんで座り、もう一度手を出した彼の手を握った。彼は私の手を軽く握り、みんなに行こうと導いた。

「ハル、ジミンが兄が本当に連れて来ましたね」
「ジャンの性格が人間たちが酷くていいじゃない。そうではない、人間?」
「…説明してくれると思います。無駄な音は拾い、早く説明をしてくれます。」
私はすぐに男の手を置き、彼らと少しは遠い距離を保ったまま座って体を丸めた。彼らはそのような私を見たとき、彼は笑顔を見せて、私はそのような彼らをもっと怪しいと思った。
「ああ、あまりにもそう見てはいけない。私たちは本当に悪いことはしないから」
「じゃあ一体何してる人たちがやって…!」

「私たちはあなたとまったく違う存在だ。うーん…人間がそのように信じる神々の一つだとすれば信じられるだろうか。」
「神…?」
「ここはあなたのような人間が触れてはいけない神の空間です。」
赤い髪をした男は自分たちを神と呼び、私が印象をつぶすと、再数のない男が怖い目で私をコック撮って口を開けた。その男の態度は少しばかりでした。私が来たくて来たわけでもなく、あのレモン色の髪が私を連れてきたのにこの男は私になぜこんなに敵対的なのか。
「私があってはいけない空間だと思いますが、なぜ私を連れてきたのでしょうか?元の場所に戻してください、今すぐ。」
「今はダメだ。人間は神の空間に足を踏み入れれば24時間が経つと元の世界に戻ることができる。」
「そうです、これは私たちも仕方ないルールのようなものです。」
「…乞食みたい。」
「何?」
「なんだかと。何の理由もなく私をこんな所に連れて行くのに誰が気持ちがいいんです。一体何故?
両目に涙が滴滴し始める。涙の意味は私もよく分からない。恨み?迷惑?怒り?自らもまったく知らない感情だった。二つの目がしっかりと開いたまま音を立てる私を見る彼らの目にはどんな感情が込められていたのだろうか。
実際、彼らが私をどのように見たかは関係ありませんでした。私が悪にさらされて彼らに叫ぶこと自体が大丈夫な花だったから。しばらくその誰も簡単に口を開けなかった。それから先ほどのようにパク・ジミンという男がしゃがんで座って出て目を合わせた。
「他の人間とは違った。人間は少しずつ輝く瞳を持って生きれば?
「それが何がどうで…」

「人間の瞳がキラキラしないというのは、買うのにあまり感興もなく理由もわからないということじゃない。いや?」
正確だった。パク・ジミンという男は私がここに来る前に私の心をそのまま読んでもらったように私に手を伸ばしてくる。神の空間に入る前、灰色の光でいっぱいの私が思い浮かび、涙が一滴落ちた。
「私があなたにここに連れてきた理由は、あなたが灰色の光の中に持って生きていなければならなければならない。
「クレイジー。パク・ジミン、あなたの口からそのような言葉が出てくる?」
「そういうことだ。思わず実実笑ってだけ通っていた奴が…」
「あの普段にもなってカッコいいのに」
「ジラル。」
今は認めをしなければならないのではないかと思う。私は明らかにそれらを恐れていた。たぶん彼らが私のような人間ではないというのは、本当知っていたかもしれない。それでも私が神という存在を警戒していたのは、おそらく私の灰色の光を気づいたかと思って、もしかして私の灰色の光に彼らの色が混ざってしまうのかと怖かったのではなかっただろうか。
普通の神だとはあえて見ることもできず、触れることもできず、形が不明なので人々が恐れている。私もそうでした。しかし、涙を流す私の前でお互いを見つめながら、たくさん笑って真っ白で、別に何もすることなく過ごす彼らを見ると、私は今こそ心を置く。私はそれらをそんなに警戒する必要はないでしょう。いっぱい急落した神経を抑え、体に与えていた力を解き放つと涙が顔を覆う。
「え、えっ…お兄さん、もっと泣いていますが…?」

「人間のなだめる方法を知っている人―」
「あるだろう」
「…やめなさい。息を切る」
恥ずかしかった男は淡いブルネット、なだめるような法律を聞かない男は濃いブルネット、ため息をついた男は水色の髪、そして最後はキム・テヒョンその男だった。彼は残りの6人に輝き手をかき混ぜて送り、私の前に片方の膝をつけた。その後、自分の手で私の目の下を撫で涙を拭き始めます。私はその男の手で両目を叩きながら体を呼んで震えた。
「あなたはまだ私が怖いですか?」
「……」
「それとも悔しいから馬を混ぜたくない?」
ピックして風抜けた笑い声が聞こえて目を開けて彼と目が合った。冷たくだけ見つめた目つきは、どこに行ったのか初めて見た穏やかな目と巻き上がった口尾がまったくぎこちなくて肩を押した。
「私はなぜ救ったの?能力まで書いたと言ったのに…」
「いや、じゃあ神が人間を死なせるの?
「… 生かしてくれて少しありがとう。

「ありがとうございました。ただありがとうございます。
「悪いね、神」
腕で膝を包んだまま私も彼に沿って口尾を軽く巻き上げた。私が笑って彼が笑ったとき、私たちの目はお互いを見ていました。
「あなたの世界に戻ると、さっきのように簡単に死にようとしないでください。すべてが灰色に変わっても、あなただけは捨てないでください。」
「…え、ぜひそんなこと。」
その一言に、全体的に灰色がかった私の世界は、どこからでも輝き始める。騙されている奇妙な感じと、なんだか分からなく涙が出るような妙さが私の瞳をキラキラさせた。
すぐに、私が殴られたこの島と私を捧げた彼らは、結局私の手をしっかりと握ってくれたものと変わらなかったことを私は元の世界に戻ってこそ悟る。
この記事はWORTH IT COMPANYクミで書かれていることをお知らせします