♪BGM:ジュールス・ブレイブ - Nothing To Talk About♪
矛盾した優しさを感じた。
その優しさに苦しんだ私は、その感覚を抱いて。
あなたに駆けつけた。
だからまだ泣かないでください。私のために。肩の上に重く上げられていた彼の手をゆっくりと打った。結局は俺、俺のせいで去ったんだね。辛く聞いて帰ってきたのはちょっとの沈黙。その中で、その短い沈黙にもツヤの口から肯定の答えが出るかと期待した。愚かなように。
「うん」
「…じゃあ、どうしてまた来たんだ。
「言ったじゃない。お前のせいで来たから」
「……」
「私はあなたをどれほどよく知っていますか?」
ツヤです。
もう口に入れるのも凄い名前。

私はそれではどうしますか。
私はその名前の所有者に私ができることを尋ねました。
かつて、いや多分今も愛している人に私が墜落できる道を尋ねた。落ちる準備も前に崖の位置を尋ねた。
あなたに捨てられるのは私が一人で崩れることです。君の力が聞こえない。私は一人でやります。うん?
「お前はヨジュヤ、本当。なんだろう」
「……」

「利己的だ」
「…何?」
「あなただけで崩れたら、私がその時まで積み重ねてきた計画は?」
「…じゃああなたは」
「……」
そう離れて利己的ではないと言えますか?
ジョヨジュ。
涙が恐ろしく止まった。初めて聞く声のトーンだった。低くも高くもない、それでも普段のトーンでもない。本当に利己的です。私がこのことをする理由も。
あなただから。
あなた。
あなたと締めてください。
彼の声で耳に響いた。うんざりしていじめた。その答え一度にすべてのことがすべて私のせいだと苦しむ。いいえ。いいえ。いいえ。首をしっかり掻いた。極度の不安を感じると無意識に飛び出した習慣。そしてあなたは無意識に打ち出した両手をまた私の肩を包んだ。フックに馴染むおなじみの香り、口調。
「けがをしてくれる」
「…やめて」
「軟膏を買うか?」
「どうぞ、ツヤだよ」
「これを見て、あなたはまだ過去に縛られているから」
「どうぞ!!!」
行きます!どうぞ、行ってください!ツヤを押しました。力なく押されていく彼の目に直面することもできないまま泣き叫んだ。ええ、私は過去に縛られています。その愛している言葉のせいで。その利己的な一言のせいで。いつもあなたと分かち合ったその言葉のせいで。君と一緒にして軽く感じられたその言葉のせいで。
何年も殺そうとした。
[大好きです。 ]
重くて恐ろしい言葉に変質されたのか、それとももとその意味だったのか分からない言葉が束縛になって、私は過去という刑務所に、思い出という独房に縛っておいた。
しかし、
今私はとても辛いです。
その考えが私を支配して、たぶんあなたが私を捨てても今のように頑張ればいいと思うという力のない自信ができて。
私は捨てると言った。
捨てると捨てる。
私は初めてあなたにナイフを差し出した。
「私も今、頑張って君を忘れるから」
「……」
「過去を忘れるから」
私たちはお互いに頑張りましょう。
誰が捨てられるのか、誰が捨てられるのか。
ついに向き合ったツヤの顔を見て表情を読む前に、私の言葉が終わるやいなや止まった。彼の印影が消えていくと、誰かが私の膝の後ろを打ったように、力なしにふわっと落ちた。そして私自身をなでた。よくやった。よくやった。よくやったよね。
壮大です。
壮大…。

...壮大です。
目が去った。同時に中が辛かった。昨日あまりにも憎まれていたのか、中のどこかが空っぽになった感じだった。鮮やかに浮かぶ昨夜のこと。ツヤは音なしで戻ってきて同時に宣伝布告した。私を捨てると。その言葉に私も、彼を捨てると言った時。
ああ。
君を捨てると言った。
酒気に蒸した体を起こしてリビングに歩いて出て、最初にしたことはミン・ユンギをクリアすることだった。毎回私を迎えてくれた壁に掛かっている額縁を開けて。死ぬように懐かしいたびに覗いていたアルバムはゴミ箱に処刑した。
片付ける中でも、君の声が私をいじめたが、絶えず私の心を掻き出したが。
「ヨジュ」
お互いのイニシャルが刻まれたブレスレットを壊す。
「愛してる」
ドライブに保存した写真や動画を消去します。
「見たかった」
「…え」
瞬間、頭の中を荒く過ぎた言葉の一言に、さてリビングの風景が目に入ってきた。ゆっくり、ゆっくり、一つ一つ見回した。そしてイライラして泣いた。
ミン・ユンギをクリアした私の空間は。
「……」
何も残っていないから。
ミン・ユンギ。
私全部だったのを自覚させてくれるみたいだから。
私はミン・ユンギ。

絶対抜けないと言ってくれるみたいだから。
午後の講義のために急いで心を振り、講義室に到着した。ドアを開けて入った講義室には、予想通りミン・ユンギがあった。私の側を見て、明るく笑って。そのおかげで後輩、動機、先輩に関係なく私に視線が突き刺さった。
「来た?」
「…え」

「昨日はよく入りましたか?たくさん酔ったようです。」
瞬間広い空間が水軍距離を始める。その騒音の間でも最後まで私に目を固定して執拗に答えを促すミン・ユンギ。自信を持って答えると信じたが、いざ彼の顔に直面したので、私の努力が無駄だったプライドに変質する感じだった。口がすっきりするのも難しく、すぐにも飛び出していきたい心情だった。
「まだ気にしないの?」
「……」
「やっぱり」
お酒を食べる前にはぜひ蜂蜜水を飲んだじゃないですか。
私はいないと飲んだ?
決定打が飛んできた。講義室の騒音はもう騒音ではありませんでした。みんなで出てきてミンユンギを置いて騒ぎ始めた。息が溺れて頭の中が混雑した。目の前がピントはその瞬間、フックを突く馴染みながら冷たい香り。その香の主人は私の肩をつかみ、体を支えるのを助けると同時に自分の方に引き寄せて、私の神経を彼の香に回した。
「先輩昨日私と入ったのに」
「……」
「蜂蜜も私が手に入れた」
「…ああ」
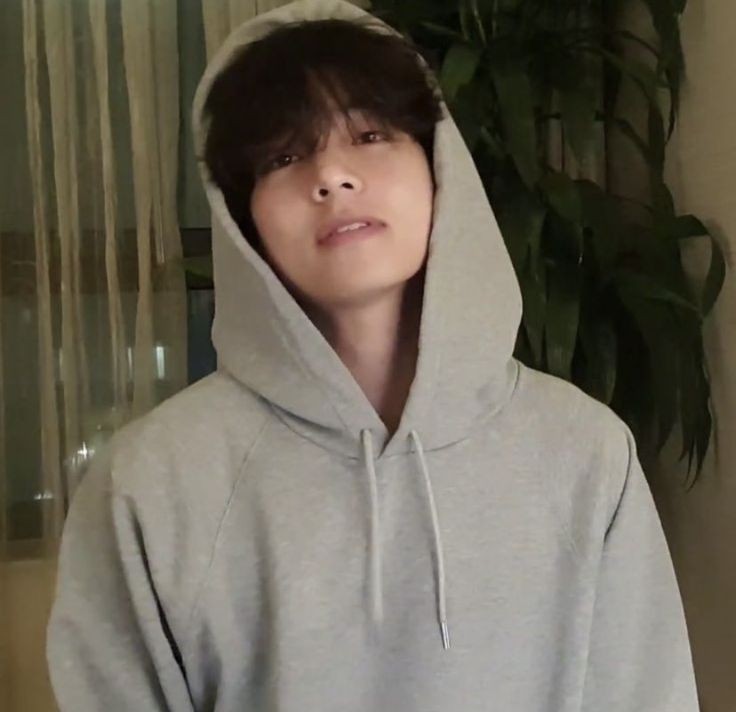
「そうですね先輩?」
声の持ち主が、その慣れながら冷たい香の飼い主がテヒョンということを体が感じると心拍数が安定して戻ってくるのが感じられた。先輩、ちょっと待ってください。誰も聞こえないように小さく叩かれた彼の言葉に私は薄く首をうなずいて背を向けた。
そのしばらくの間に向き合ったミン・ユンギの顔は、覚えていなかったが、口がぼやけていたのは、はっきりと覚えていた。
何と言った。

「…始発」
私が気にすることはありません。
矛盾した優しさを語った。
その優しさに苦しんだあなたは、その感覚を抱いて。
私に駆けつけた。
