「花が見たい」
「·····。」
「あなたと手をつないで」
いくら不思議な言葉でもいつも毎日のようにやっていた言葉だから、大変なことなく渡したのだったのだろうか。徐々に閉じ込められてくる目を頷いたまま、眠りに落ちた後はいつも君がいなかった。まるで最初からこの家に私一人でいたように。部屋に静的がまわった。依然としてマットレスでは湿気を食べたきつい香りがいっぱいだった。雨が降る朝、痩せる体をやっと起こし、何の考えもなく家を出た。今は顔すらきちんと覚えていない君が、私を去ってもすることは当然ないと思っていた私の傲慢から始まった私たちの愛がこんなに乗る縁を作り出したことを。

花雨の日にまた会いましょう © 𝐖𝐎𝐑𝐓𝐇 𝐈𝐓
昨年この頃の頃コンビニで買った透明傘の水気を図書館の入り口で打ち明けていた。一緒に図書館で働く仲間の司書が自然に私の隣に立って話しかけてきた。昨夜はどうだったかと、夜明けに打たれた雷を見たのかと言って、彼はいつも私に天気についての話を取り出した。彼はまるで自分がその日の気候のような心情をもっているかのように、雨が降る日には落ち着いていても日が晴れてくると、休むこともなくすっきり笑って図書館のあちこちを歩いた。残念ながら、または幸いにも今日は雨が降ったので彼の気持ちを私が全部買う必要はなかった。穏やかに敷かれた声が耳元に乗って入ってくると、硬くて柔らかい彼の低音が私たちの家のマットレスを連想させた。
「今日は新刊入ってきて整理しなければなりません。」
「いいですね」
「私も。雨が降る日には有毒紙の香りが強くなるんですよ。すでにからワクワクですね。
彼と会話するたびに感じるのは、彼は本当に世界をロマンチックに眺めているということだった。普通の人の思想とは異なり、彼はいつもこの世に友好的だった。誰は面倒だと思うかもしれない新刊整理を毎月指して待ち、人々があちこちに秩序なく置いて行った本たちもカートを引いて通って一つずつ集めて本と本の間、適当な席に差し込むのが好きだった。市立図書館であるにもかかわらず、窓辺のあちこちにサビで満たされた薄くて長い花瓶が数多く置かれている彼の感性。私でさえも愛さざるを得ない場所と人だった。彼は世界、そして自分のことを最善を尽くして愛する人だから。
「時々、テヒョンさんは文学のようです。」

「私も私の世界が文学だったらいいな」
フラッグは彼のコートで木の香りがした。鼻先がアリトした彼の香りが私の中を全部ひっくり返してからこそ精神を掴むことができた。彼は文学です。夏の終わり頃、私の一日を愛撫する鬱蒼とした文学。朝からあまりにも愚かな音だけしたかと、素敵に図書館に入る彼の後ろ姿を眺めて彼の世界を羨ましかった。私もキム・テヒョンの世界で生きてみたい。キム・テヒョンがそのように聞きたい言葉を中にだけ飲み込んで彼に従った。
図書館の扉を開くとすぐに引き受けてくる新しい本の香りとあちこちに置かれた草花のほのかな耐音。こんなに完璧な職場で、あちこちも珍しい人と働くということがまだまだ信じられない。もう3年はなるようなのに。あなたを忘れた後から見える彼が一気に私を捕らえて、思う存分彼のそばを止めさせている。優しいと思いましたが、私の心の中に住みながら月世一回を出さない、同じインターネットの主接が頭の中をブンブン浮かんだ頃、私の視線を満たした彼が私に手を振った。
「新刊です」
「ああ、新しい本のにおい。」
「とても良いです、一日中本の上に鼻を当てたいだけ。」
二人の男女が新しい本が収められたボックスに鼻を打ち込んでくるくる姿を誰が見てもしたら、一生の黒歴史として手に挙げられるほどだった。当時は香に酔って知らなかった私たちの姿が再び考えてみるとかなり面白い姿だったことを自覚すると、耳先が赤く染まるようだった。彼も今、状況が面白い状況であることに気づいたのか、少し笑った。彼の動き一つ一つで草花が育つようだった。
エアコンのおかげで冷たい空気が流れる図書館、彼は着ていたコートを指定された自分の椅子にかけた後、新刊をまとめた。彼が新刊をまとめる間、彼と私の机をまとめていた頃、彼のバッグから何かきらきら光った。ファンダントか。懐中時計かもしれませんか。その物に光が反射されて以来、ずっとその物の正体について悩んだ。こっそり取り出してみると聞いてみた方がいいと思ってまだ朝だから人がいない敵敵な図書館で彼を呼んで聞いた。
「テヒョンさんのバッグにあるものは何ですか?」
「バッグですか?」
「はい、そのどんなファンダントみたいな・・・」
「あ、お兄ちゃんのお品ですよ」
なぜだろうか。質問に審美的に答える声とは異なり、生き生きとした瞳が冷やすことが目に見えた。先ほどまででも楽しく本を整理していた彼が以後、動作が凄かった。よろしくお願いしたか。荷物も整理し、彼の隣で新刊数量を確認した。目は本にあったが頭の中は彼でいっぱいになるほど。しばらくして少しずつ入ってくる人にカウンターに座った。
さっき私の質問に対するキム・テヒョンさんの反応が気にならなかったら偽りだ。やっぱりまともに聞いたのがはっきり。キラキラと彼の動態を確認した。確かに以前よりも違う感じ。私のせいだと思って自責する用意だった。ハーフィルなら発見した物が親型遺品だとか。本当に運輸もいいね。とにかく奇妙なことに、物事はとても見慣れていました。私の知人の中に死んだ人がいたのか、ないようだが。それとも百貨店で見たのだろうか。パンダント一つのために頭の中が一体どれだけ壊れるのか。新刊整理を終えた彼がゆっくりと近づいてきた。謝らなければならない。本能的に挙げた考えだった。
「テヒョンさん、さっきファンダントの話を出したんだ・・・」
「はい」
「申し訳ありません。遺品なのか分からなくてよく聞いたようですから・・・」
「あ、大丈夫です。知らなかったから」
おまけに言っても指先がちょっと震えるのを見ると、おそらく本当に大丈夫だとは思わなかった。どうして、本当にすみません。まさに隣の席で安節不断できない私を見ていた彼が積極的な図書館の流れを壊さないために顔面筋肉を勝手に口にしながら笑いを我慢した。本当は大丈夫だと言って、手を打つのを見てからこそ心を置くことができた。
以後は別に無く時間を過ごした。仕事をして、貸出証を作って、図書館に来る人たちを見物し、本をまとめて・・・。ちょうど問題が一つあった。さっき彼が体を半分に折りながら息をして笑った後に彼と目だけ遭遇すると笑いが出てかなり高域だった。カートに置いた本を一つずつ差し込んで、しばらくカウンターで視線を向けるやいなや目が合ったときは本当にだし、笑わないようにしても笑うしかなかった。

「·····。」
「·····。」

「·····。」
「······!」
私は毎晩寝る前に未知の空虚感をよく感じた。この世に私一人残されたようで、私のそばに残った人が誰もいないように感じられる日々がほとんどだったから。だが彼に会った後は確かに違った。私がもし本当にこの世に一人残されたとしても、この人ひとつだけ私と一緒にしたら、何も恐れなかった。今も同じだった。まるでこの空間に私たちだけが残ったかのように深い瞳が当たった。これが愛だろうか。あなたと私は今愛しているのか。心臓が素早く跳ね返るせいで、胸パクに必ず抱いていた本が雄雄鳴った。私たちどうしても愛なのかな。しばらくを見つめたお互いの瞳が各自の視線に戻る頃にこそ精神をきちんと備えられた。
「愛・・・。」
小さく呟く言葉にも鼻先がシクンだった。なぜこれだ。私はただ愛という言葉だけ取り出しただけなのに。理由知らずに目元が赤くなるのを感じ、袖で顔を炒める。愛しているという事実が幸せで、そんなことだったらいいな。手にしっかり握っていた本をまた本棚に差し込んだ。幸せなのに笑いが出ない。まったく異質感が入って口元をやっと上げて歪んだ笑いを作った。何か間違っていた。
***

「この路地は正しいですか?」
「はい、少し狭いです」
「大丈夫です。長さが狭ければ、私が後ろから歩いていけばいいのです。」
空が暗くなり、時間帯が夕方に近づいた時点、仕事を終えた彼と私が図書館のドアをしっかりと歩いてロックした。朝から降っていた雨がまだ降っていた。本来季節が変わる時点にはしばらく雨が降るという。前の季節を忘れて次の季節を準備しようという意味だろうか。それでも夏が過ぎ去ったのか雨が降っても湿気よりは涼しい感じがした。家まで願うという彼の言葉に頭をうなずいた。私はもちろんいいので、楽なままにしてくださいという意味を込めて。
「一人で買いますか?」
「いや、一緒に暮らす男一つあります」
「男・・・と一緒に暮らすんですよ・・・?」
「はい、ちょうどいつのまにか一緒に住んでいました」
無駄に顔も上手く、笑いコードもよく合って、私が家に来るまで一人で家に残って待っていても朝に起きれば見られないその人。毎晩マットレスに横たわって誰にもできない中の物語をすべて打ち明けながらも、本名は知らないその人。それに対する説明を短く取り出したにもかかわらず、テヒョン氏は相変わらず慌てた気がした。バランカジン子供と見ているのではないかと心配になって。実は彼に言った言い訳もないのが、本当にその男が誰なのか分からない。
「不思議です。私のすべてを知っているように振り返って、私は彼を一つも知らないというのが・・・少し悔しいです」
「いいえ、一つも変ではありません。」
「なぜですか?」
「それじゃ・・・」
会話が途絶えた。彼との会話はこのような雰囲気を頻繁に維持する。誰よりも楽に会話をしても、私が何か質問をすると会話が止まる。まるで彼が何かを隠そうとしているように。あるいは、私が彼の考えを知らないか気づいていないかのように。本当に奇妙にも、この渦中に朝に見たファンダントがどんどん頭の中に残った。一体それが何をするのか私にこんなに長い余韻を与えるのか。
「あなたの兄弟の名前はどうなりますか?」
「はい?」
「いくら考えてもさっき見たファンダントが妙におなじみの感じがします。私の知人なのかと思って・・・」
彼の瞳が激しく揺れた。さっき私がパンダントのソースを聞いた時と同じ目つきだった。今は気づいた。彼が私から何かを隠しているという事実を。疑問いっぱいの表情で下唇を軽く噛むと、彼が私の唇に軽く触れて力をほぐした。
「後で話します、私たち」
「・・・・・・明日お会いしましょう。」
彼が未練いっぱいの目で私を見つめた。ただ、後で話そうというのも彼で、視線をあげて先に足を離したのも彼だった。きっと私は私たちが愛だと思いました。人の心の一つはこんなに難しいのに、何も持っていない私は愛がどれほど難しいのか。頭が複雑でゴールが鳴った。両目をしっかりと巻き、玄関のドアを開けると、その人が待っていたようにドアの前に立っていた。
「なんでこんなに遅れたんだ。もともと8時なら家にいる時間じゃない」
「ごめん。ちょっとテヒョンさんと話してちょっとやる…」
「その人と最近良くなる?」
「うまくいくようだが、先ほどは・・・。
狭い部屋のひとつに置かれたデスクにコンビニエンスストアの食べ物がいくつかあります。一体こんなのはどこから救ってくるのかも分からない珍しい形のおやつがいっぱいの袋までも。そしていつも欠かさないコーヒーキャンディまで。どうやって毎回ここラッパートリーが同じかそろそろ飽きようとした真だった。椅子を引いて机の前に座るとそのやはり椅子を引っ張って私の隣に座った。
「神様だ。全州ビビンバだから」
「三角キムバプに新式で旧式だがどこにいる。そして全州ビビンバは数年前に発売されたがどんな新賞・・・」
「あ、そうか。俺には神像だったけど」
おっぱい笑う笑いは樽に怒りを出すこともできないようだった。気軽に笑えばいいのか。ビニールを剥がした三角キムバプを大きくした口を尋ねた。全州ビビンバ三角金飯はそれでもできるように久しぶりに食べるようだ。私が以前に食べた・・・。食べましたか。不思議な記憶に噛む速度が遅くなると、彼が再び話を出した。
「でもテヒョンという人、どう?」
「うん?」
「君に元気にしてくれ?」
「よくやってくれ。家にも連れて行って、目だけ遭遇すれば笑って・・・。その人より見るとこれが愛かと思って。幸せだ」
「幸いです。」
「何が?」
「ただ色々と。君が愛されているようだから」
男が机にこぼれたまま私を眺めて言った。そんなことを言うと羨ましい目つきをしていたのか、そんな悲しい目で見てどんな幸いで寝て。一体、この男はどこから来たのか知る顎がない。一番奇妙なのは、なぜ私がこの男からなじみを感じて快適さを感じるようになるのか、私がなぜ初めて見たこの男が鈍くて家に入って座ったのに追い出されなかったのか。
「お前は誰だ?」
「うん?」
「名前も知らず、誰も知らない君が私の人生に突然訪れてきたのに、なぜ私は何の異質感も感じられないのか。毎回考えていたの。
「あえて今話すべき?」
まだ生き生きとした。ひとりでだけ売ろうとよく笑う姿を見ると薬が上がらなくてはならなかった。彼が手に入れたコーヒーキャンディーまで全部食べてから、よく準備を始めた。シャワーを浴びて、うがいをして、洗濯をして、ふとんを整理して。私がこれらすべてをやっている間、彼はまだ椅子に座っていました。どんなものにも触れず、ただそのように座っているだけ。
部屋が吹いて一つずつオフになるたびに、彼は私の隣に近づいて横になった。そしてその後はしばらく会話だけした。テヒョン氏に関する内容がほとんどだったが、図書館や今日の天気、そしてファンダントについても話を交わした。
「どんなファンダントかと聞くから兄の遺品だと言ったよ。大丈夫だと言われたのに私は指先震えるのもみんな見たから。どうやら私が言う間違えたのだろう・・・。」
「·····。」
「おい、今?」
「いや、ちょうど思う」
「どう思う」
「お前と手も握って口も合わせて、一般的なレストランも行ってみて、指輪も挟んで結婚もしてみる、そんな思い」
彼の言葉を聞くとすぐに、私の体が壊れたかのように指1本までも動けなかった。なんだ。まるでさっきその瞬間、テヒョンさんと目が合ったその瞬間に感じた卑劣な感情。彼がやっと泣きを我慢する目で笑いながら内側に回して横になった。
そして、その日は初めて彼の話を聞いた。彼が思う私、そして私の家。しばらく言っていた彼が私が眠っていると思ったかしばらく巻いた私の2つの目に触れた。実は触れたかもよく分からない。何の感覚も感じられないから。ただ、動きでは触れたことが確実だった。彼は私の目に触れながらまた昨日のような話をした。ただ昨日よりは少し長く。
「花が見たい」
「·····。」
「君と手も握って・・・」
「·····。」
「君を本当に長く、一緒に愛したいのに、いざ私は…
「·····。」
「嫉妬する」
言葉を続けるほど、彼の首が埋まってくるのを感じることができた。彼はそのように不明な言葉だけまた吐き出す言葉を止めた。彼が寝てから少し過ぎてから二人目を開いた。なぜこんなに狭く横たわっているのか。恥ずかしい心に私一人で覆っていた薄い布団を彼に覆った。すると残ったことは驚愕。それだけだった。彼は布団を覆わなかった。私が彼に向かってどんなに拳を吹き飛ばしても、彼は壊れなかった。私の手と布団がすべて彼の体を通過したから。
「や・・・。」
「······?」
「今出て。私今、今手震えて言葉も出てこない。すぐに私の家から出て。」
「なぜ、いや突然なぜ。」
「お前・・・人じゃないじゃ・・・」
彼のすべての体が私の言葉に動揺した。目は斜視のように揺れ、指先は震えていたが彼が背中に巻いた。慌てるだけで、いざ家の外に出てこない彼にすぐに出て行くとしばらくの私の持ち物をすべて彼に投げた。それさえ通る風に部屋の底に厄介に投げ込まれたものが壊れていた。してください、私はあなたがとても怖いです。戻ってくる言葉はなかった。彼は痩せた目元でドアを開けずにドアを通過して外に出た。
混乱板になった家の真ん中に座り、力がほぐれた足をぼんやりと眺める頃だった。それだけで分かった。彼は私が忙しく動いた時もどんなものにも触れなかったということも、毎晩扇風機の風が髪の毛をこすらなかった理由も。しばらくすべての夜を人でもないように過ごしたという考えに全身が震えた。眠りについた。結局、窓の隙間で日光が入るまで浮かぶ雪で夜を明かし出勤準備をした。
人でもなく、なぜ私の夕方を毎日手に入れてくれ、私の話も毎回聞いてくれ。まったく泣く心にまた下唇を噛んだ。そして静的。毎朝朝のように君のいない積極的な家が今日のように泣いていた。それで泣くしかなかった。彼が誰なのか分からず、なぜ私が泣くのかもしれないが、ただ本能だった。本当に、とても落ち込んだ朝だった。
***
敵の朝の空気が周りを回った。しばらくの間、あまりにも多くのことがあったので、正気をつけることができなかった。何の感情もなく図書館に歩いて行ったところ、テヒョンさんが見えた。素早く歩いてくる足とは異なり、顔には大丈夫な不安さとぎこちないさがいっぱい入った。ただそんな彼の変化を気にする隙がなかった私は遠くから頭を下げて挨拶して図書館に先に入った。これに慌てた彼が私を緊急に追いついて一緒に図書館に入った。
「今日は幸いには雨ではありません。」
「そうです。」
「顔を見るから眠る顔ではなく」
いつものように天気の話で軽く会話を続けている間、彼が私のモルゴルを気づいては言葉を止めた。昨夜の間に何が起こったのかと心配な目つきで私を眺めた。だがそんな彼に気づく隙もなかった。私の頭の中は一体その人でいっぱいで、彼の目にはまだ私だけが込められていたから。私が昨夜のことをこの人に言っても大丈夫だろうか。くまが考えてどうやらこの仕事を私一人で背負うにはあまりにも膨大なことだと思うと言うことに決めた。
「私が一緒に暮らすと言った男がいるでしょう」
「はい」
「人ではありませんでした」
前後の内容なしにすごく結論したと言うと、彼の顔に恥ずかしさがいっぱいだった。人じゃないなんて、じゃあ何してるの?でも私の言葉を信じていないようだった。だから私はすべてを説明しました。私と一緒に住んでいた、私と一緒に一日を過ごした彼が人ではなかったことを。多分愛だったかもしれない彼がやっと布団の1つ覆う存在だったことを。
絶対に散らばらない長い髪を持つその男は、名前も、生きるところも知らないが、不思議に追い出せない人だった。巧妙な鼻にナヌルの声まで持っていて、私と指先ひとつ打つことができない、そんな人。テヒョン氏はそのような彼を描いた私の言葉を一つずつ聞いたら、少し眉をゆがめた。非常に複雑な目で。そして彼が口を開けた。
「私たちの兄が俳優だったんです。そう演技が好きなのにも名前が知られておらず、ほぼ毎日を道で転戦しながら暮らしました。
「·····。」
「そして、とても長く、兄が笑う姿を見られませんでした。演じたいというその夢ひとつで命まで捧げる理由を理解できませんでした。しかしある日から兄が笑いという笑いは全部顔についているように生きているんです。」
「はい」
「率直に少し怒りました。兄が俳優になるために注いだお金と夢、そして希望の中に私のものが半分はあったから。それでしばらく兄を憎みました。」
長く続く彼の言葉に耳を傾け、首をうなずいた。彼はまるで自分がその当時のように少しずつ笑って言った。叩かれた残りの本人よりも上手な兄を時期にした彼の過去の中に成熟したまま残っているようだった。言うまでずっと手で拳を握った。彼の長い指が私の指と交差した。びっくりしたようにしたいと思っても、もっと固くつかみ、また話し続けた。
「だから私は気になりました。一体誰だから、あるいは何のために兄が幸せに見えるのか。だから一度は兄の家を私の足で訪れました。兄は当然好きでした。
「まるで私の家のようですか?」
「その家です。兄が住んでいた場所。あなたと兄が一緒にいた場所。」
彼の手を握っていた手から力が抜けた。私の家がテヒョンさんの兄の家だとか。それで私が昨日その路地に連れて行ったときに驚いた気づいたのか。彼が未知の目で私を見た。そして何も言わなかった。私が知っていて、その人が誰であるかを考えてみるように。しかし、私はその家で男と一緒に過ごしたことがない。そこで誰かと一緒に暮らした記憶は・・・その人だけなのに・・・。
「もしかしてテヒョンさんが言っている人、写真ありますか?」
「パンダントにいます。」
彼が自分のバッグから取り出したパンダントを私の両手に握った。私も知らない乾いた唾液を飲み込んだ後、慎重にパンダントを開いた。左は名前がわからない干し草が、右は出て・・・その人。テヒョンさんの兄、そして私が昨夜まで一緒にいた人。目元が赤くなった。彼の右頬と私の左頬が当たったままいたずらな表情をしている写真。私の恋人だったね。私が昨日埋没して送ったその人が、私の昔の愛だったんだ。習慣のように下唇をきつく噛んだ。奇妙なことに、私が唇を噛むとすぐに、何らかの記憶が盛り上がりました。まるでダムの一部分が崩れたかのように記憶があふれ出た。

「だからおそらく今回の作品に入ると、お金ができそうだ」
「そうですか?幸いです。そうではありません。
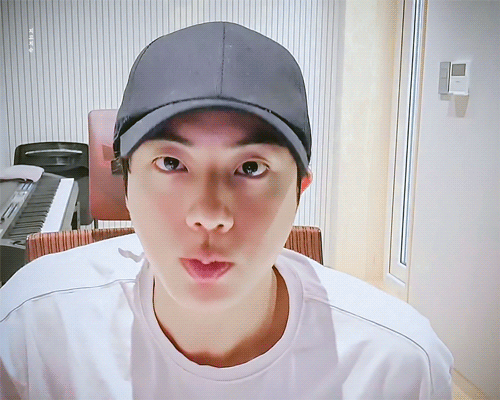
「しかし、あなたはまた唇を噛んでいましたか?それは本当に悪い習慣だからです。
「あ、そうだった。お前が言った後にずっと気にしてたけど・・・」
「無意識が怖いなぁ。とにかく、今回お金が入ってきたら、お前と花やちょっと見に行こうかと思って。
「桜見に行こう?本当?」
「おそらく撮影が終われば春中旬くらいになると思う。どう、いい?」
「当然じゃない。お前と一緒にするのは何でもいい」
「私も」
「·····。」
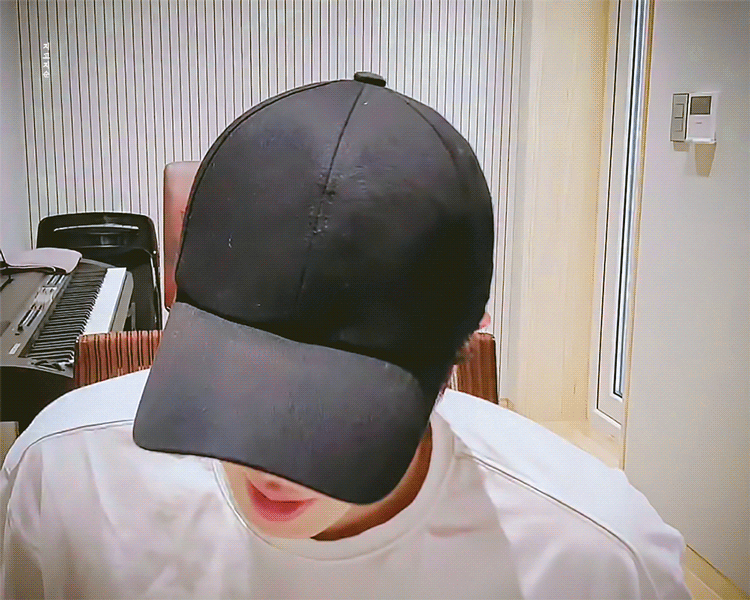
「私も好き。あなたとするのはすべて。」
キム・ソクジン。その人の名前。本当に私の頭の中のダムが崩れても一件か数多くの記憶があふれるようにいっぱい満たした。君と愛を語り、永遠を約束し、幸せを彩った日々がぴったり死ぬ直前のように押されてきた。私の心を捧げたように悲しく泣くと、テヒョンさんは私を抱きしめました。大丈夫でしょう。握っていた手は置いたかしばらくだった。彼は私の頭を包んだ。それでも彼のフードティーでウッドの香りが広がった。彼の胸元に顔を存分に打ち込んで泣いた。もう一度だけあなたを見ることができれば、本当にそうすることができれば私の残りの生をすべて捨てることができるのに。渦中に唇を噛んではいけないという言葉が考えも噂もできなかった。死にたい
「あなたと兄が旅行に行く前の日、私に兄が訪れてきました。今回の作品を撮って稼いだお金で、私にお金を一杯掴んでくれました。
「·····。」
「だからわかりました。あなたの顔。兄の葬儀にないのになぜないのか、したかったのに兄のサインが交通事故だったんですよ。あなたは病院にいました。
覚えてる?当然。キム・ソクジンの撮影がすべて終わり、お金稼いだとしながらきれいに笑って家に入ってきて私をぜひ抱きしめていたのも。まさに翌日桜を見にバスに乗ってお祭りが真っ只中に行く事故があったのも。右の窓から反対側から来たバスが激しく走ってきたのも。私はキム・ソクジンを見ているため、そのバスについて知らなかった。ただ私と外を眺めていた彼がそのバスを見たらすぐに私を抱きしめて自分と席を変えた。そして、私は窓を見ないように息が詰まるほど抱いた。
「よ、なぜ以来・・・ここ公共の場所・・・!」
「愛してる」
突然、なぜ愛告白なのか尋ねる前に大きな轟音が鳴り響いた。バスが転覆したのも、彼の背中に刺さったガラスのために彼を抱えていた私の手に血がたくさん埋まったのも全部覚えている。演技 私はバスの中でも、全身中に血がない場所がないにもかかわらず彼が私に話しかける。彼が私を確実に保護したせいで、私が傷つけたところとは額に軽く刺されたガラスの二点と打撲傷程度だった。
「ソクジン、ソクジンア。ソクジンア、あなたの血がとても・・・」
「お前と花見たかったのに・・・」
彼の目が巻き込まれた。どうぞこのまま死なないように、俺は捨てないでほしいと彼の頬をつかんで泣きながら叫んだが、声もなく笑うだけだった。彼の首をしっかりと抱きしめた。ふわふわの石鹸の香り。私が一番好きな四つの香りがビリッとした皮の香りと混ざり合って、逆味の香りを作った。私も君と桜見たかったのに。転覆したバスの外はまだ美しかった。桜が飛び散り、日差しは暖かい、ただそんな春の日だった。そしてこんなにきれいな日に、あなたを失った。
「あの家に行ってみてはいけないのでしょうか?もしかして、もしかしてわからないでしょう。もし石津があるかもしれません・・・」
「行ってみても大丈夫です。もともとあなたも、このパンダントも私のものではなかったから。」
「・・・・・・ごめんなさい」
「私はあなたのすべてを覚えていましたが、3年を通してあなたに言ったことはありませんでした。もともとこの愛は私のものではありませんでした。
「·····。」
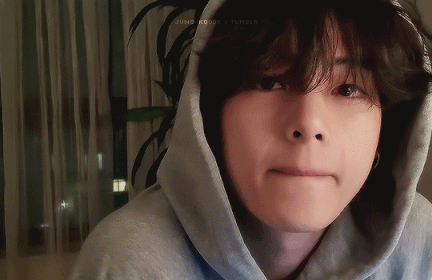
「早く行ってみましょう。遅くなる」
気にならないことができなかった。いつ私の習慣が移ったのか、彼が下唇を噛んでいることから、ウッドの香りがするフードとふわふわの髪が涼しい秋の風に少しずつ飛び散るのも。それでも私は今ここにはいられませんでした。私はキム・ソクジンを探さなければならない。それが私のアップレポート、私がしなければならないことです。まだ噛んでいる彼の下唇をジグシ押した。
「すぐに来ます」
「うん、待ってますよ」
その言葉を最後に彼を後ろにして無作為の前だけ見て走った。私の言葉はよく聞かなかったが、まさか私が出て行くという言葉にすでに消えただろう、という考えでいっぱい気になったテヒョンさんもいつのまにか私の頭の中の一足に遅れていた。それから背中を回した私を見る彼の心はどうだったか。しばらくかかる考えに足が遅れた。見なくても明らかだから。まさに後ろを眺めた。すぐに行きましょう。母をきつく噛んで再び君に向かって進んだ。
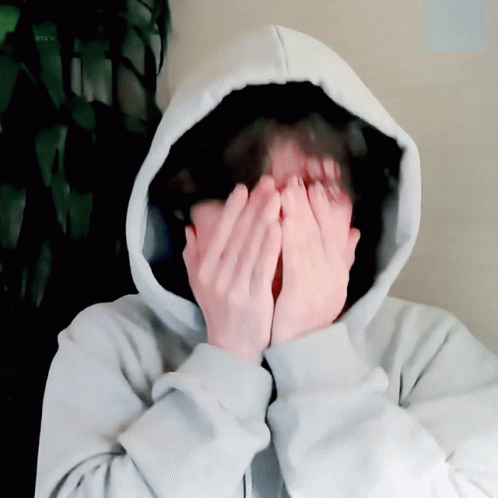
「やめるか、本当。」
彼が相変わらずその場に立って泣いているのも知らず。
***
その遠くに私たちの家に向かう狭い路地が見えた。あの路地に落書きもたくさんしたようだが。過去を自覚したら、普段はただ路地だったところがいつの間にか思い出になっている。急いで走る渦中にも路地の端に書かれた落書きを見つけようとした。 「私の人生の初めてで最後の俳優キム・ソクジン」という私の手書きで書かれた落書きと「私の愛、私の人生キム・ヨジュ」と書かれたあなたの手書き。目が乾いたかどれくらいになったと再びしっとりとなった。しゃがんで座って落書きを描いたその時。それまで私たちはきっと一緒だったが、今はなぜ私一人でこんなに座っているのか。君がとても見たかった。
パンツを脱脱して振り回した。今は過去に陥っている時ではない。現在に充実しなければならないから。いつのまにかドアの前まで到着し、取っ手をつかんだ。実はドアを開くのが怖い。ドアを開けたとしても、あなたがいなければ、私の世界が壊れると思います。両目をしっかりと巻き、唇もしっかり目覚めたまま玄関門に頭を傾けた。昨日の私はあまりにも憎しみ、まったく耐えられなかった。すでに握っていたハンドルに力を入れて強く扉を開いた。
「·····。」

「・・・ごめん。来ないように言ってたのに・・・」
「ソク・ジンア」
「うん?」
ドアを開けるとすぐに見えるのは部屋の中央にぼんやり立っている君。その姿を見ると、どれほど感謝して申し訳なかったのか分からない。ただあなたにはそれが重点ではないようだった。昨日、スッパクまで追い出して追いかけて恥ずかしい部屋に入ったのではないかと心配で申し訳ない表情だった。しかし、私があなたの名前を呼ぶとすぐに、あなたの表情が歪んだ。疑わしい表情とともに濡れてくる君の目がまるで先ほどの私を見るようだった。
「お前の名前・・・覚えてる?いつから・・・?」
「あなたは一体どれだけ・・・私がテヒョンさんの話をする時、怒っているのか、なぜあなたはそれをすべて聞いているだけだった。
「君まさか私・・・」
「覚えてる。覚えてるとクレイジーだよ。あなたは一人で行くのが好きですか?私はもうあなたがいなければ死にそうです。」
ぜひ目覚めの唇が出て似ていた。もう少し考えてみればみんな気づくことができるものだった。向き合う君と私はどれほど似た表情をしているのか。もっと私の心を軽く掘るのはあなたの装いだった。君はまだ事故当時その服にとどまっていたから。そして私はそれを疑ったり、奇妙に思ったりもしませんでした。君は私の人生に無頓着に入っても全く問題ない、私の愛だから。
「抱きしめたい」
「わかりました、できません。」
「しかし、あなたが泣いているでしょう、それも私の前で」
「お前も泣いてるじゃない。俺の前で」
お互いの格好が続想したり、う湿気もして軽く笑った。まだ私の部屋は冷たくて、人一つない部屋のように寂しいが、あなた一つだけで私の世界がいっぱいだった。あなたの香りが恋しい。あなたの温度、あなたの手、あなたの腕、あなたのすべてが欠場します。まともな心にお互いを眺めるだけだった。何も言えず、ただ眺めるだけ。そのようにしばらく積み重ね、彼が先に話した。
「花見に行きますか?」
「でも今は秋なのに・・・」
「もともと秋が春の次に花咲きの良い季節だ。コスモスもあり、菊もあって秋に咲く花がどれだけ多いのに。」
「菊は少し減らす?」

「とにかく本当です。今日が最後です。。」
「何が最後なのに」
「君を見ることができる日。だからさよなら挨拶でもして追い出そうとしたが、君が私を気づいてしまったから・・・。
今日しか知らなかったが、今日が最後だという事実は信じられなかった。まだ直すことができず、唇を悟ったまま涙だけを流した。君が慌てながら、なぜまたウニャと近づいて、私のボールに流れた涙を拭いた。いや、拭こうとした。彼の手が私を通ってしまって役に立たないことだったが。
「花見に行くんだ・・・?」
「行こう、どこに行こう」
玄関門を開けるとすぐに携帯電話で一番近いところにある花畑を検索した。よく分からないソルチェの花が一杯咲いているというところに向かってタクシーをとった。私はドアを開けて後部磁石に、あなたはドアを開けずに後部磁石に座った。窓に頭を傾けて手を四方に伸ばした。たとえ捕まえなかったけど、あなたの手は私の手と重なっていた。到着するまでそんなに握らない手をしばらく重ねておいた。手持ちの気持ちでも私に。
「私は君と桜を見たかったのに」
「じゃあ春まで俺といてくれればいいじゃないか」
「そうだ。
「·····。」
「それが難しいね・・・それが難しい」
ソルチェの花の間に青々と会話を交わした。テヒョン氏の物語、図書館の物語ではなく、私たちの物語。あなたが初めて愛するという話、その日少なかった落書きがまだ残っているというそんな小さくて小さな話。私があなたを少し早く知っていたならば、私たちの会話は一方的ではないかもしれません。まだ申し訳ありません。
「そして言葉がちょっとそうなのに、私は捨ててもいいし、女主よ。君が働かなければならない時間なのに私と一緒にいるというのは、おそらくテヒョンイにも全部言ったという意味だろう?
「うん。」
「そんな本当の心だ。
「·····。」
「それは愛だよ、ヨジュヤ。あなたとテヒョンが今愛しているの。
「でも…。」
「どういうことなのか分かる? 私も君を愛してる。でもここまでだけしよう。テヒョンイに言ったようにあなたにも伝えたい。
「·····。」

「私はあなたが本当に幸せになってほしい」
偽り一つない真実な言葉でいっぱいだったが、依然として私には拒否感のある内容だった。私も知っています。私とテヒョンさんが愛しているということ。ただ、テヒョンさんがあなたの弟だということを知らなかった瞬間からは、もはや以前のように愛することはできないようだった。漂う涙に二つの目を感知しようとしなかった。もう本当のやめたいと思った。花の口径を終えて帰ってくる道にも猿の心が続いた。君を捨てると。君は今日からこそ取り戻したのに捨てろと。利己的だと思っても君を捨てなければむしろ大変になるのはお前だからできないとも言えなかった。今は見えない私を心配するのがあなたには一番大変なことでしょうから。
タクシーから降りて家の前に到着したとき、私はあなたを呼んだ。図書館まで連れて行くと図書館に向かって足を合わせた。とにかく以前や今も一度決めれば終わりを見ようとするのが本当に変わらないと思った。私はまだあなたを送る準備ができていませんが、あなたはすでに終わっても残っているようです。
「お前は愛してない・・・?」
「当然じゃない」
「しかし、あなたはもう私には何の感情も残っていないかのように屈して・・・?
「わたしが毎日そうしたかった。むしろあなたの家で過ごしたのも、私はいつもあなたを愛したかった。私は知っている。
「私は君だけあればいいのに。君と一緒なら何でもいいのに・・・」
「私も」
「·····。」

「私も好き、女主よ。」
会話を分けるほど後悔だけいっぱいだった。以前の会話と重なる気分が聞こえ、さらに妙だった。早く知ったらよかったです。それなら君をこうして送る必要も、あなたの決断がここまで多ダをすることもなかっただろう。あなたの瞳に詰め込まれた深い深淵が私を押し出した。無理やり押し出す心だけいっぱいのまま。だから私は押された。不可抗力だから。
しばらくを静かに歩いていく図書館が見えるほどまで行った時だった。しばらく風で出てきたのか図書館のドアの前に置かれた小さな階段に座っているテヒョンさんが見えた。目を一度点滅するたびにため息を2回ずつ休むのを見るとまた気になった。そして心配な目でテヒョンさんを眺める私を眺めていた君は、むしろもっと悲しい目だった。多分体面が詰まった視線かもしれなかった。私が彼を愛しているということ、私を愛する立場から長く望んできたから。
「さっさと行ってください」
「今日は家に入るの?」
「いや、さっきも言ったじゃないか。ここまでだけしよう。
あなたの言葉が何を意味するのか知っています。だからこれ以上捕まえられなかった。君は終わりを見てこそ次の始まりをして、私たちは今終わりに近づいたから。再び目覚めた唇とあなたを見つめる哀れな目つきが未練を残した。キム・ソクジン。キム・ソクジンキム・ソクジンキム・ソクジン。あなたの名前を主張長槍の心の中で叫んでも、あなたはただ私を見つめるだけだった。非常に深く、非常に暖かく。
「その日私を生かしてくれてありがとう。」
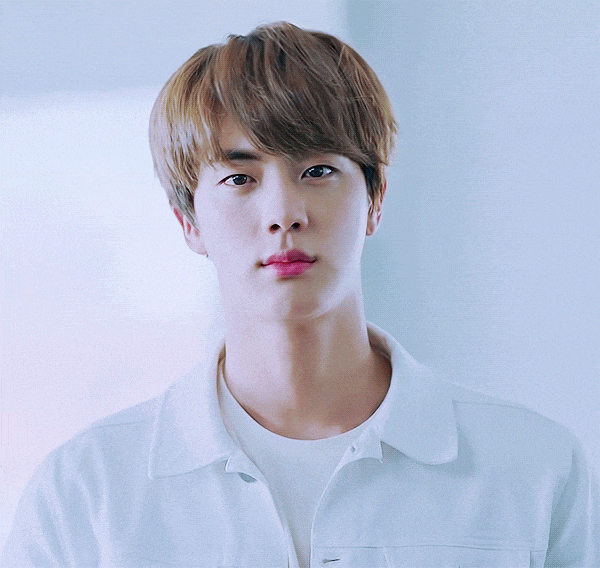
「君が先に私を生かしたから。
「私はあなたを?いつ?」
「最初に見た瞬間から今まで。
「テヒョンさんもお会いできたらよかったのに。お前にたくさんごめんなさい。こんなに幼いし、とても愚かでお前を憎んだ」
「私はあの子のあまりにも多くを持っていた。君まで持っていくには、空もテヒョンでも許さない。私は二人だけ幸せであれば何でもできる。」
笑顔の笑顔がまるで昨夜のようだった。はい、今はあなたを置く時が来たようです。もちろん今日は捕まえたが、今日置く必要があるから。どのように挨拶を渡すべきかもわからない。積幕が行った。複雑な頭の中をしばらく迷っていた頃、君が先に言葉を取り出した。毎晩聞いたその言葉、今は聞こえないその言葉。
「花が見たい」
「·····。」
「君と手をつないで、笑いながら、幸せに。」
「私も。私も・・・」
結局また泣いた。抱きしめられない懐に近づいて泣いてしまう風にまた再び慌てた君が私の涙を拭き取ろうとまた現実を直視した。私の肌一つ一つをすべて通過するあなたが一体どんな感情なのか想像すらされませんが、今ファンク泣かなければあなたが私の愛を気づいたようだった。ハド泣きは風に君まで泣き、ボールがすっぽり濡れたんだけど。
「じゃあ、私たちの桜を咲かせたらまた会いましょう。」
「いつ・・・?」
「いつでも。私は待つことができます。」
「·····。」

「君を愛していないことは一度もないから。」
君の身に抱きたい。お願いします。あなたの首も抱きしめたい、あなたの息吹、あなたの気温、あなたの香りすべてを感じたい。悲しげに泣きながらずっと呟いたが、君は何もできなかった。あなたはすでに死んで、私はまだ生きています。それ自体だけでも私の心を破って殺しても残る。私があなたのそばを去るつもりがないと、私はテヒョンさんに向かって始めました。本人も泣きながらずっとそっちに歩いた。
どんどん図書館に近づくと、階段に座ってぼんやりとした風景だけ見ていたテヒョンさんの視線に私が入ってきた。テヒョン氏は私を見るとすぐに階段を早く降りて、私の前に立って、泣き続ける私のボールを袖で拭いた。そしてその姿を見たあなたは本能的に後ろを打った。
「なぜ、なぜ何が起こったのですか。見つけられませんでしたか?なぜこんなに泣きます・・・」
「テヒョン、テヒョンさんあの本当・・・」
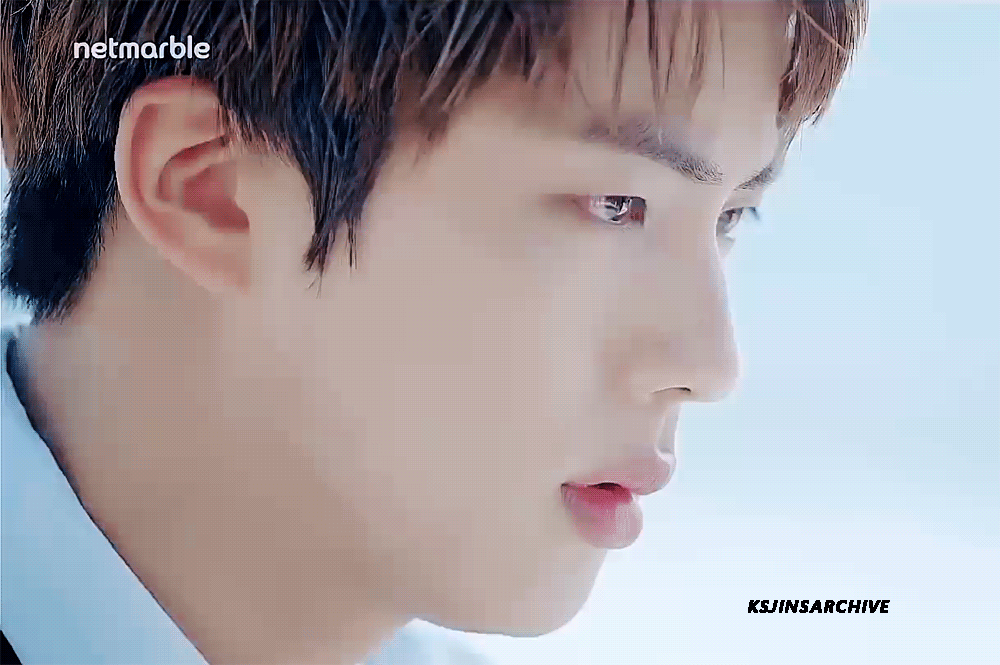
「·····。」
あなたの目は羨望と嫉妬、そして多くの感情が混ざっていました。キム・ヨジュが私の前で死ぬように泣いたとき、私は何もできなかった。涙を拭くのも、懐に抱かせるのも、頭を苦しめて慰めることも。そしてそのすべてが私の目の前で起こっている。少しでも残った未練も消えた。私が望むことをすべてすることができるテヒョンイに女主の未来を頼みたかった。本当に長い、一緒に愛してほしい。あなたと私ではなく、あなたとテヒョン。
「私に行きます、女主よ」
「ちょっと、ちょっと待って・・・!」
「愛してる。君と僕じゃなくてテヒョンと君が。二人で幸せに愛してる。それが私の風だ」
「私待ってくれるんだ・・・? 一緒に桜の眺めにしたこと・・・。」
「当然じゃない。だから君は続々と一人で残った人生最高に楽しく楽しんでくる。私もいいところで幸せに過ごしているんだ」
「愛して、ソクジンああ。本当にたくさん、本当にたくさん愛しています。」
「私も。」
「·····。」

「私もあなたを愛しています。」
多分テヒョンさんには私が狂った人のように見えるかもしれなかった。本当に多分、私は本当にクレイジーかもしれません。ただこれであなたと私の縁が美しい終わりを結ぶなら、私とテヒョンさんの愛打は縁も美しい始まりを成し遂げるから。だから私たちは皆幸せになるでしょう。みんなが美しく、みんなが始まりで終わりに到達し、何よりも爽やかな人生を生きることを願う。
「兄だったんですか?」
「はい?」
「さっき女主さんが虚空見ながら一言。兄だったんですか?」
「はい。その人でした。もう終わりました。」
「じゃあ始める事だけ残ったんですね」
しばらくの間、混乱した頭を耳の後ろに虐殺し、彼が言った。終わりがあれば始まりがあり、始まりがあれば終わりがあるので、今残ったのは始まりと終わりだけだ。まだウッド香いっぱいの彼の懐に慎重に抱かれた。愛するなら、あなたとやります。さっきソクジンイにしたかったことをすべてテヒョンさんにした。首を抱きしめ、向きを変えて温度を感じる事。彼は私の手を握り、図書館に導いた。私も彼の手をしっかりと握った。
そしてゆっくりと首を回して後ろを眺めた。空の通り。本当にあなたが私を去ったことを証明する積み重ね。もし私たちが本当にまた会うなら、桜の葉が飛び散る不思議で美しいどの春の日にまた会うか。やりたかったことをすべてしながら、口を合わせて愛を語ろう。お互いの手をつないできれいな花を眺めながら変で美しかった私たちの人生を振り返ってみるの。 賛美しなかった瞬間がないあなたと私の時間が重なるその日、私たちまた会いましょう。

花雨の日、また会いましょう。
𝑬𝒑𝒊𝒍𝒐𝒈𝒖𝒆

ソルチェ花:できない愛。
