「…おお、チェ・スンチョル」
「うん…」

「起きろよ~よ!チェ・スンチョル!」

「うぁ…え??お前なんだ!!」
「なんだって何…目覚めに来たんだ」
「いや…こんなに男の部屋にふわふわ…探してきたら」
「…まぁww」
「は…本物…」
ニーネがどこを見て男なのか、私の目にはまだ赤ちゃんだと朝から唱える○○に、すでに先日がカムカムというスンチョルは、もっと混乱するためにすぐに洗いに行った。
慣れなければなりません...
「..これからこんなに過ごすって…?」
静かにトイレで考えに浸っていたスンチョルは
それほど長く行かなかった。
「お兄さん!早く出てきて!」
「私は洗わなければならない!!」
「舌ああ…私たちに行かなければならない…」
このようにスンチョルと子供たちが時間に追われる間、○○は朝早くゆったりと準備を終えて外で久しぶりに会った友人と会話中だった。

「これまでどのように過ごしたの?」
「私は何…デビュー準備して…あなたも待って…」
「なぜ私を待っているの?」

「いつかは来るみたいだったから…。だから今来たじゃないか」
「確かに来てよかったと思うね~」
「でも…」
「…?」
「それは本当ですか?」
「何が?」
何を言ったか顔は真っ赤になって体をベベコソしながら言葉を叩くのかなと思う○○は自分の目を避ける指数の目をさらに向き合おうと努力していた。

「その…私が好きだったんだ」
「あ……それは本当だ」
「え……え…?
「あなたが初めて来たときに踊ると見て、何がこんなに多いのか…。
「……」
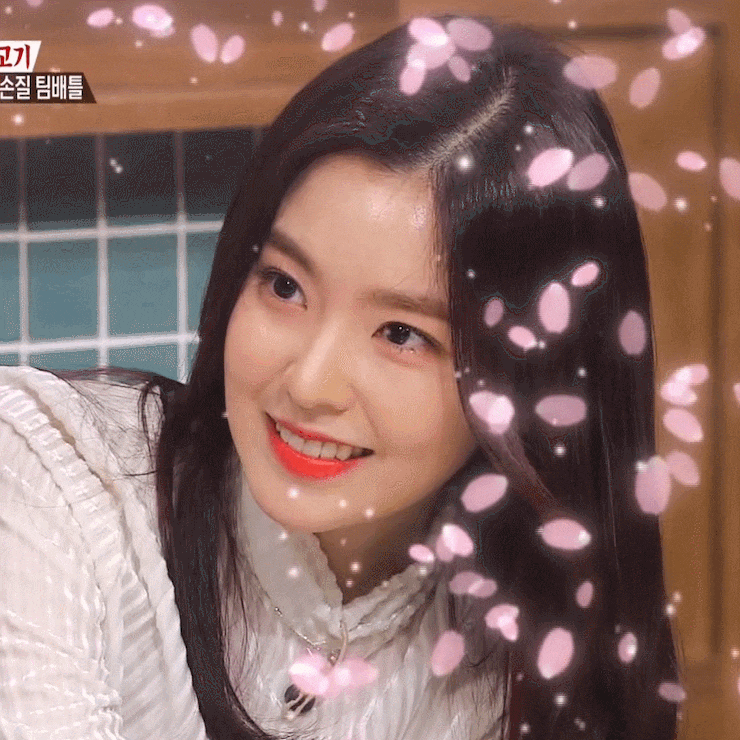
「まあそうだったんだ。だから今こんなに上手いんだから嬉しいな」
「…私はカット?」
「では~韓国で今一番ホットな新人になっていくの?」
「え~とても浮かぶ…」
「でも…私も浮かんだようだ」
「これは本当wwww」

「二人が何してる…?」
ハーピルならお互い遊び心があると指数が○○を抱くような姿勢になってしまった時、スンチョルが子供たちを連れて下ってきた。
誰が見ても誤解する状況だ。
かなり正真正銘中のスンチョルの姿に○○は慌てた。
「いや、これは…」
「あ~いたずらが足が絡んでそう。問題あり?」

「……」
「私たちは遅いのですか?早く行かないでください○○あ」
「ええと…うん。
ダンスユニットであるスルギに沿って○○はダンスユニット車両に乗った。子供たちの雰囲気が変になったということを○○はとても軽く感じた。
あの子たちは自分が以前に知っていた子供たちではないようだということだ。
そして指数は自分も知らずに出てきた欲に自分を見知らぬ人だった。
「は…私はこれすべきではないのに…」
スンチョルの状況も大きく変わらなかった。
ただ自分が指数に感じた感情がおかしく、二人の親近感がおかしかった。自分が鋭敏なのかと思い、また考えた。
「あ〜いたずらが足が絡まってそう。問題ありますか?」
あります。問題があります。理由なく気になるということ…長い間見て、今は気持ちよく終わりたかったんだけど、今来て以来捨てたらどうなのかな…
「うぁ……振り返るよ!…」
「お騒がせ……」
「私は昨日遅れて来たのを知っているでしょう..ㅜ」
「あ…すみません」
デビュー前からホットになったセブンティーンはそれだけ広告もたくさん入ってきた。
今日も朝早くから出て撮影を始めた。
しかし、17人を一度にケアすることができないため、控室はあまりにも複雑だった。
一方では服が問題、片方は頭が問題…一方では物事が消えることが多い。
「お姉ちゃん!…これ落ちるみたいですよね?」
「あ…あげてね。縛ってあげる」

「お姉ちゃん。
「あのショパで見たみたいだ」

「お姉ちゃん…これは服……」
「なぜ、また何ㄱ…これは服なの?」
短いスカートに肩はすっかり露出してしまい、腰がよくなったら全身が見えるような服だった……もう23歳の子供にはあまりにも
エッチな服だった。スタイリストという人が話の魅力を知らない?
本当に優しく、優しく、優しい○○が我慢できないことの一つ…ちょうど悲しみに対することだ。

「いや……下着は少しじゃないですか!」
「最近はみんなあんなに着るんですか?トレンドを知らない…ㅡㅡ」
「ハ、短くて露出が多いのが最近流行ですよね?
「もともと可愛いならば、私は知りません!??」
「あの衣装あなたや着てます!私たちは他のものを着るから」
「それが勝手になると思いますか?」
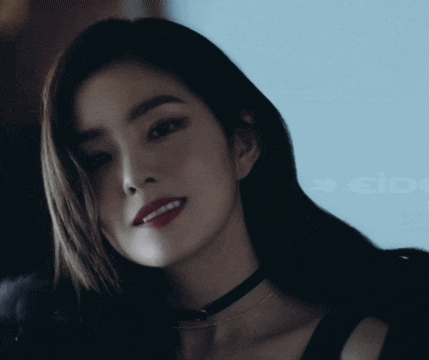
「いけないことは何ですか?
ホン・イル店!もともとスティーリストが忙しくて書いてくれました…」
「この女の子は本当!」
○○は緊急にスギが着る別の服を探した。スカートの代わりに男の子たちと自然にスラックスを着せてスタイリッシュなクロップシャツを着るとスルギのボイシな魅力が増えた。
○○が着た服を見て自分が着てくれた服よりよく似合って怒ったのかスタイリストは見逃せない。
「あの女なんだ…お前はこれが魅力なのに…」
「それでも毎回お姉さんがこんな気にしてくれるじゃないか~」
「ありがとう?」

「うん、本当にいい!ㅎㅎ」
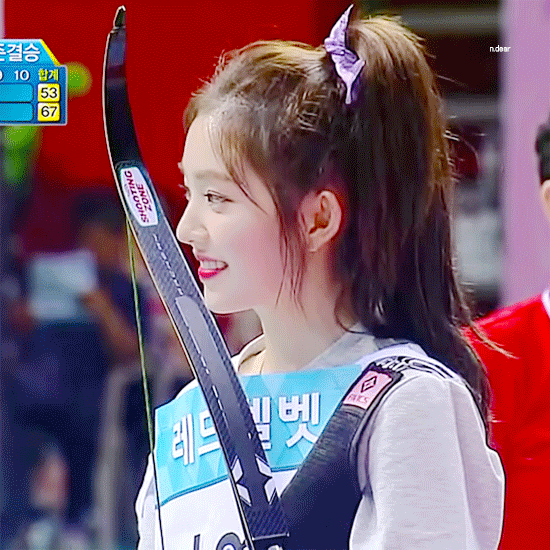
「う~~可愛くて死ぬわ私たちの悲しみ~」
その場面を見た他の子供たちは○○の迫力に一度打ち、弟を考える心に二度、弟の前ではきれいに笑う姿に三度を打った。

「と…」

「……」
そのうち2人は毎回心を整理しなければならない、整理しなければならないが..今日のような姿を見るたびに抜けていくのが事実だった。
絶対慣れていない自分の魅力を知っているか分からないのか、ただ会社ならスタイリストから切り取ってほしいと思う○○だった。
