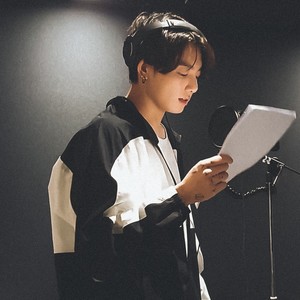- 作家が少し正気ではない状態で書いた。
- 一体何なのか作家も知りません。
- なぜ書いたのか作家も知らない。
- クリシェの塊。
- 軽く読んでください...とにかく、開拓性の犬がくれた混乱の文章です...
- 女主の元の名前が出てくる部分はわざと空にしました。読者の名前を入れて読んでください。
-TRIGGER WARNING! 2010年代初めに流行していたインターネット小説を背景にしているため、学校暴力を連想させる場面があるかもしれません。
-TRIGGER WARNING!流血主義
エクストラで生き残る方法
:ある日小説の中でエキストラになってしまいました。
W. はい
口を餅にしたら、バルリゴン私の前で鈍くするクォン・ヨンヒを窪んだ。失礼なことは分かったが、そんなしかなかった。彼もそうなのだ、私が知っていた人とは全く違う人だった。長く伸ばした黒い長い髪や、眉毛よりやや下の長さにしっかりと切った前髪や、きちんとした日付眉毛、彼と違って猫のように汗が上がり、すっきりとした模様をした目尾、賢い鼻、そしてコーラルライトが回る頬やきれいに赤い度
「…暗だけ見てもないの?」
「利益…!」
見た目だけ見ては全く分からない。私を知ることができないという事実が、これまで悔しいのではないか、今は足まで叩きながら悪を書く。私当たる!悔しがるペアがないという声を聞いていると、子どもがいないのだった。ああ、今は荒涼としたことを考えると、私はそれを追加しますか?私はもう一度クォンヨンヒを頭からつま先まで覗いてみたが、さっきとあまり気付かない結論だけが残った。 …本当ではないのに、私が知っていたクォンヨンヒ… 。ちょっと呟く言葉なのに、耳がどうして明るいのか分かるペアが無い表情で再び足をしゃっくり転がす。私が私に気付かなかったということで熱を出すことでした。それでも、アンマンでも、
「元の顔が一つもないのに…」 ?
だから、親しく過ごした友人なので、「XX高校1年4回クォンヨンヒ」については私も覚えていることがあった。なんと1年を同じ半分だったのに、しかも高校に入って一番親しく過ごした友人でもあるのに覚えていないリーが無理だった。それにもかかわらず、私が私の目の前にある「クォンヨンヒ」が「XX高校1年生4クラスクォンヨンヒ」と同じ人物であることを予想はどころか疑いすらしなかったのにはすべて理由があるという話だった。一応は、名前からがあまり一般的ではない名前ではないうえに、24歳の人生の間に「ヨンヒ」という名前をかなり多く入ってきた車にただ同名人なのだと言って渡ったというのがその第一の理由であり、第二の理由とはまさに私が先に説明したあの外観にある。
ここでしばらく、「XX高校1年4回クォンヨンヒ」に対する見た目を説明してみるとこうだ。巻き毛が回って整理されていない頭をいつも引き上げて、まろやかな印象に似合うアーチ型眉毛を持っていたし、目、鼻、口がすべてドングルドンハニ純粋なことなくできたのにボールサルが誤って痛い子だったと言えるだろう。そう、それこそ私の目の前にあるクォンヨンヒの正反対がまさに「XX高校1年4回クォンヨンヒ」だった。明らかにリスに似た顔だった。可愛いのが好きなせいで、その顔から好感を持っていたので、スマートに覚えていた。
私はまたクォンヨンヒの顔に直面しました。 …リスを一口に飲み込んだ猫なら分からないか、絶対私が知っていたクォンヨンヒの顔ではなかった。百回を開けても同じ人だという事実は決して信じられないようで、私は口を開いた。
「…そう、君がそのクォンヨンヒと打って…、」
「そんな打撃じゃなくて本当ですか?!」
「いや、分かりませんが、どうしてじゃあ…!」
私は少し悔しい。これくらいなら似た人でもなくちょうどまったく違う人なのに…。 !とにかく、私は私の前にあるクォンヨンヒが私の古い友人クォンヨンヒと同じ人物であるという事実を90%ほど受け入れることにした。どんなに見てもその熱が上がり、しっかりと上がった顔が嘘をついているようには思えなかったのでそうだった。
だからといって、私が持っていた疑問が完全に解消されたわけではなかった。なぜいくつかの疑問点がもっとできたら分からないだろうか。そうじゃない、久しぶりに見た同窓と嬉しい再会をすることはできない妄想ナプダ殺そうとするが、それも理由も言わず!常識的に理解できないことではない。さらには高校1年生、同じクラスの友人にもかなり親しく過ごした相手だった。アンマンの頭を転がしてみたところ、当チェクォンヨンヒが私を殺したくなるほどの恨みを持つようになった理由は全く分からなかったということだ。とにかくそうだし… 、
「…気になることがあって話をちょっとしようと呼んだが、君がそのヨンヒという言葉を聞くからもっと気になるね」
「……。」
「なぜそうだった?
数学旅行を皮切りにクォン・ヨニは絶えず細かい嫌がらせを続けた。迷惑が出なかったといえば嘘だろうが、とにかく何らかの理由があるだろうと思って我慢してきただけだった。それともこれも小説の展開とか。当然のような理由があると期待するものではなかったが、とにかくクォンヨンヒが私が知っていたクォンヨンヒなら、しかも私が知っていたクォンヨンヒとは全く違う行動を見せたらその理由を聞いてみたくなるのも無理ではないだろう。私はしばらく彼の答えを待った。かなり辛抱強く言う。
「…君がとてもイライラしてそうだった、なぜ!!」
辛抱強さの対価が成し遂げた答えなのは私の予想外だった。クォン・ヨニが抜け声を上げた。ずっとずっと私を死んで撃ってみるせいで、私はなかなか枯れた見知らぬ人を追い出すことができなかった。 …何?という素朴な答えを出したのもそれだった。私は何をしましたか?という悔しい心もないじゃないか聞いたことがあった。
しばらくの間近くなったクォンヨンヒが口を開いた。さっきの俺のように和田だー、整理されていない言葉を注ぎ出した。長くて長い話の始まりであり、その始点は現実での私が17歳になった年の春の日だった。
📘 📗 📕
十七になった年の3月2日は少し特別だった。 3年間うんざり着ていた制服の代わりに新しい制服を着たことからがそうだった。もちろん、これから繰り広げられる地獄のような3年と夜間の自律学習を考えればパク喜んだことではないかと思ったが、新しい学校がくれるときめきはそのような残念は全く忘れるようにするほど強烈なものだった。そんな学校での初友達がクォン・ヨニだった。クォンヨンヒも同じだった。どちらもかなり遠く離れた中学校から来たせいで親しく過ごしていた友人とは罪深く離れたままだったので、お互いの立場に共感できたせいに親しくなるのはあっという間だった。どちらもキム・ヨジュやイ・ユジンのように狂った親和力を持っていたわけではなかったが、親しくなる方法には親和力以外にも多くの方法があったので、特別な問題ではなかった。まぁそう、高校1年生、クォンヨンヒとは二人もいない友達になった。ちょうど半年だけ。
私が考えるには、私がそれほど良い友達の軸には属していないかどうか、だからといって悪い軸にはめることでもないという自信があった。ちょうど右の友人。暑くてぬるいかどうかかなり長く友人として残っていることができる適当な友人くらいにはならないかと思ったので、夏休みが終わった後、新たに始まった2学期からクォン・ヨンヒが私を避けて通うことを理解することができなかった。挨拶をしてもぎこちない答えだけ、昼休みには当然のように他の友達と一緒に給食室に行く姿を見てその時の私が何を考えたかは正確に覚えられなかった。かなり昔のことでもありますか?とにかく、私がクォンヨンヒと親しくなったというのが他の友達との友情戦線を締めくくってしまったという意味ではなかったので、私はすぐに他の友人と交わることができた。私が他の友人と交わり始めた後、パック快適に見えるクォンヨンヒを見て、ただ漠然と'ああ、私とよく合わない性格だったか?これまで参考のように通ったかも… '、という考えばかりだっただけだった。はい、私が覚えていたことはありませんでした。
ところがここにクォン・ヨニの話が入ると、私が知っていたものとは全く違う話になってしまうのだった。
例えばこんなものだった。私が渡した私とクォンヨンヒが遠ざかった理由についてクォンヨンヒはこう言った。 「あなたが私の友人だと思うようには思わなかった。さらに、見たように、他の友人ともっと親しくしていなかったのか」。これだけでなく、私は他の友人とより親しくなり始め、私が疎外感を感じた話まで。聞いてみると…私はそうでしたか?欲しいが、クォン・ヨンヒが吐き出す話を聞いてみると、どこか合わないパズルのピースを無理やり泣き込んだものだけで話が当てはまらない部分が一、二つではないのだった。いつの間にか私が私より他の友達とより親しく過ごし、私をいじめた主犯になっているだけでもそうだった。誓う私はそんなことがなかったから!そしてそれらの物語を掛けて、また掛けて、また…。掛けてみると、'…え?」と思うほど繰り返される文章が一つあるのだった。
「だから…、私が他の友達ともっと親しいのが苦手だった…?」
「…いや!全然違うじゃない!」
「私があなた以外の子どもたちともっと親しく過ごしたという話だけが今何回かったのに…、だから私があなたで遊んでいるように感じたって?」
「……。」
確かに二十四歳や食べた人の頭の中から出るような発想ではなかった。とても幼稚な発想だから…。 。クォン・ヨンヒもどんな感じだったのか、耳元を抜き色に染めては、私の唇だけがよく近づいている「とにかく!!」と音をすることだった。話が終わったような気はないので、私は聞いてみようという心情でクォンヨンヒに続けるように手を振った。その手振りにもう一度泣いたようだったが、とにかくクォン・ヨンヒは涼しくなった顔で続けて話を続けたが、その後の内容がもっと家官だった。
「私は…、私はそんな君がとても辛いから」
「おお、」
「…だから小説を一つ書いて、」
「…え?」
アンマンの気づきが薬に苦しんでいない人であるかどうか、今クォン・ヨンヒが言う'小説'と現状に対する相関関係をかなり気づかない人はいないと信じる。私はかなり悪い顔でクォンヨンヒを遠く見つめた。まさか… 、という表情で見つめていると、クォンヨンヒが続けて話を続けていった。高校2年生頃、親しく過ごしたある姉にクォン・ヨニは4人の男子高生たちの話を聞いた。 XX高校伝説の卒業生(この大木で私は裏目をつかんだ)… 。 4つすべてがうまくいって本当にF4というニックネームがついた(B4がどこでたくさん聞いたニックネームだったというのが私の妄想ではなかった。) 4人の男子高生たち。知っている姉のおかげで、あなたの男子高生の写真まで見たクォン・ヨンヒは文を書き始めた。粗雑なペアのない小説の中の主人公はきれいで優しくて4人の男主人公に愛されて、たまに嫉妬若い人たちの行動に傷つくかどうかまた4人の男主人公たちに交互に癒される…。 、どこでたくさん聞いた、いや、経験した話を言う。
'…実話?」
この小説がキム・ソクジンをはじめとする4人の男主人公に対するファンピックであることは知っていた(すでに狂ったように笑って濡れてキム・ソクジンに引き裂かれた戦績もある。)。ところで、そのファンピックを書いた張本人が私の友人だった。しかし、その友人は私を狂ったように嫌います。今回殺してしまうかという考えがあるほど言葉だ。 …これは言いますか?したい表情で私はクォンヨンヒを見つめたが、彼はしっかりと話を続けるだけだった。主人公に自分を代入させたまま妄想に陥った先日たちを。現実での4人の男子高生が原体の有名人だったため、クォン・ヨンヒの小説も流行に乗った、それが本人たちの手にまで入った事実はクォン・ヨンヒも知らないようだったが話だ。
しかし現実というのがそんなに緑緑ではないせいで、その妄想さえもいつか終わりを結んで、その小説がクォン・ヨニ、私自身の記憶の中でもかすかになったという話を…。 。しかし、そこで終わりだったら、そもそもクォン・ヨンヒと私がここでこう向いていたこともなかったから、私は寝てその裏話を待った。
ある平凡な日にクォン・ヨニは再びそのノートを広げた。発見したのはとても偶然だった。思い出の腕なら思い出の腕だった。久しぶりに小説を取り出して叩きながらその一人で小説を読んだその日に、信じられないことが起こった。目を覚ましたところが小説だますことを彼はすぐに気付くことができた。だよ、自分がこの小説の作家だから…。 !もし自分が主人公になったのだろうか?一度夢だと思ったクォンヨンヒはときめく心を抱いて背の高い道に上がった。そしてその前にキム・ヨジュが現れた。小説の本当の主人公だった。
クォン・ヨンヒは小説を切り直した。一度主人公になってみるのも悪くないようだが欲からだった。煩わしいアイデアがクォン・ヨニの頭の中を打ち、打って通り過ぎた。すでに完結近くにあった小説であるにもかかわらず、作家が直接手を待ち始めたので、一度完成に近かった世界さえも容易に変化し始めた。クォンヨンヒは、4人の男の主人公の愛をたっぷり受ける主人公のキム・ヨジュの隣に「クォンヨンヒ」という助演を立てた。そして分からないようにますます小説を変え始めた。女主人公の友人だった「クォンヨンヒ」から、ついに主人公の席まで占めるようになった「クォンヨンヒ」へ。すべてが順調に見えた。クォンヨンヒの目の前に慣れた人が入る前まではそうだった。ええ、それは私です。くそー。
クォンヨンヒはまた小説を開け直し始めた。作った「クォン・ヨンヒ」の席に「キム・ヨンジュ」を埋め込んだ(なんだかキム・ヨジュが狂ったように親しいふりをし始めたが…)。 「クォンヨンヒ」の役割は再び生まれた。今回は「キム・ヨンジュ」の席を奪おう。ところが勝手になっていなかった。シグンドゥクゴリョ私の恨みを見つめているクォンヨンヒだけ見ても彼が何を考えているのか簡単に分かった。 「あなたはすべて台無しだ!」
「あなたが持っていたことを私も持っていたかっただけだ」
「……。」
「そういえば小説の中だけだが、いや、小説の中でもお前より上手く見たかった。でも――」
「……。」
「でもあなたはなぜ小説の中でも、現実でも、どこでも!なぜ!私よりはるかにキラキラ光が出る!」
「ハァッ…。」
クォンヨンヒの目からチキンのような涙が鈍く落ちた。
「あなただけじゃなかったら、全部持てたよ!」
「あなただけ、あなただけがなければ、私はすべて持つことができます!」
いつか山で聞いたクォンヨンヒの声が重なりそうだった。なんだか曖昧な気持ちになって、私は頭を後ろに濡らして夕焼けがし始める空を見上げた。
「…一体前生に私が何の罪を犯したんだ……」
「…何?」
「物語よく聞いた」
真ん中から足に力が抜けて座っていた体を起こした。くしゃくしゃになった制服スカートをしっかりと打ち出した私は、涙を溜めているクォン・ヨニの顔に直面して口を開いた。
「それで、あなたはこのすべてが私のせいだと言いたいですか?」
クォンヨンヒは答えなかった。しかし、眉間を存分に掻いたまま私を死んで狙っているその顔だけを見ても、答えは聞いたり、同じだった。お前のせいじゃない、するその顔。
「でもこれは私のせいじゃない、正確に言えば君のせいじゃないか?」
「…ま、まぁ―」
「あなたが私をどう思うか分かると思います。それが良い感情ではないということも。でもそれ――」
どうせ全部劣等感じゃない?
もう赤くなることもないと思ったクォンヨンヒの顔がすっきりと盛り上がった。私が聞くにはそうだった。当崔理解が持てないクォン・ヨニの言葉はなぜかすべて私を責めていたということは即座に悟った。それが劣等感という感情であることを知るのは難しいことではなかった。クォンヨンヒが私の口で「小説の中でもあなたよりもよく見たかった」という話をしたのでもっとそうだった。
「あなたが小説を書いた理由が何でも、私をいじめる理由であれ、もう何とも関係なく……そう私のせいに回したいならそうして、私はもうお前に、クワク!」
「何?何?!あなたは言った?」
「ああ!おい、お前、狂った…!!」
…だからといってチョンゴクを刺したクォンヨンヒの行動が出る私の髪を掴むことだとは想像もできなかったが言葉だ。長くて細かい指に私の髪が巻きつけられました。頭皮が文字通り消えていく痛みに悲鳴を上げた。ジルセラ結構クォンヨンヒの髪をつかんだ。置くように!という私の言葉は聞こえないのか、相変わらずシグンドク大でクォンヨンヒは私の髪を握って掴んで言った。
「君が何を知っている! 君がー!! 君はみんな持ってたじゃない、ダ!! しかし、あなたを少し奪うのがなぜ悪い?
「悪!狂った年が…! そもそも私が何を持っていたのに!
「みんな持っているじゃない!キム・ソクジンも、パク・ジミンも、チョン・ジョングクも!さらにキム・テヒョンも!キム・ヨジュも!
「あー、人が物なのか、持つの?」
「私が持つのよ、キム・ソクジンも、パク・ジミンも、チョン・ジョングクも!あなたが持っているものすべて!
クォンヨンヒの言葉が壊れた。激しく私の頭をつかんで揺れた手も止まった。誰かがその手首をしっかりと握ったせいだった。クォンヨンヒの手から徐々に力が抜けて、私はクォンヨンヒの髪を内膨張して私の髪を包んだ。始発、本当の頭皮が引き裂かれると… !

「あなたがどれだけ話しているのか、いかに苦しんでも、私はあなたになることはありません」
いっぱい怒った表情のキム・ソクジンが私の肩を包んだ。もつれた髪をほぐす手は優しいが、硬く固い表情はそうできなかった。
「お前、お前!」
口を餅つけて恥ずかしさを表出するのが私だけではなかった。私が遠いのでキム・ソクジンの固い顔を見つめている間、クォンヨンヒはまっすぐに伸びた指で私を指して延伸その言葉を吐き出した。
「私、私が明らかに一人で来ると…!」
そうだったが、キム・ソクジンが私の後ろをこっそり踏んでくれた私も知らなかった。何も知らないかのように肩をすくめるとクォン・ヨンヒがシグンドク大ですぐにも駆け寄るように私を見つめた。熱がしっかりと伸びた模様だった。何か言葉を言おうとするように、つぶやく唇から漏れてくるのも荒い息吹しかなかったからだ。やがてその口からきちんとした単語が出る前に、キム・ソクジンが最初に口を開いた。先ほどのように冷淡な口調で吐き出すキム・ソクジンの言葉にクォン・ヨニの顔が淡白に飽き始めた。
「…やっとそんな理由で人を殺そうと聞く?正気なの?」
「主、殺そうとしたわけじゃない、ソク・ジンア、それ――」
「すでに君の口から出てきた言葉みんな聞いたよ、君がキム・ヨンジュにしたことももうみんな知っている。
「…殺そうとしたのではない!!」
クォン・ヨニの叫びがキム・ソクジンの話を断った。急いで切迫するまで聞こえる声だった。都合なく震える声でクォン・ヨニはたどり着いた。殺そうとしたのではない… 。
「…も、戻ろうとしただけだ、元の世界へ…」
「人を殺して?それが理由になると思いますか?」
「じゃ、本当だ!ここで死ぬと、現実から目覚めることができるから…!」
「確信していますか?どうですか?」
「それ……」
どのように確信するか、キム・ソクジンが尋ねた。低い声にクォン・ヨニが延伸体をつかんだ。それは、それは… 、明確な答えを出すことができず、唇だけをつぶやくクォンヨンヒをキム・ソクジンが冷たく見つめた。これまで怒ったキム・ソクジンに直面するのは初めてなのか、私も簡単に口を開いたりキム・ソクジンを捕まえるなどの行動ができなかった。クォン・ヨンヒが行った行動や、彼が吐き出した言葉がどれほど言葉にならない軌道なのか、誰よりもよく知っているから。でも、その後に続いたキム・ソクジンの行動に私は固まっていた体を動かすしかなかった。叫び声で。
腰をゆっくり曲げて何かを拾ったキム・ソクジンが私の手のひらを引く前までは私も遠いのでクォン・ヨンヒとキム・ソクジンの対峙を見ていただけだが、床に転がる鋭いガラス片を手に握ったキム・ソクジンがそれを手にした。割れた肉の隙間から鮮やかな赤色の血液滴がツードゥク、落ちた。
「…いや!狂った?!」
驚愕の悲鳴と共に、キム・ソクジンの手を握った。ガラス片を握っていた手を殴って彫刻を落とし、引き続きウルクプ、ウルクプ、ピットムルを吐き出す傷を袖口でしっかり押し止めようと苦労した。その間にもキム・ソクジンの視線は依然としてクォン・ヨニに向かっているだけだった。キム・ソクジンの行動に驚いたのか、さっきより一層青白な見知らぬクォン・ヨンヒはこうも、あまりもできないままキム・ソクジンの冷たい目つきを全身で受け取っているだけだった。

「…これがひとつ夢なんだろうな?これでも、死んだら元の世界に行けると確信できる?」
クォンヨンヒは何も言わなかった。キム・ソクジンは私の問いに答えもせず、貝のように口をぎゅっと多文クォンヨンヒをしばらく見つめるより、私の傷を包んでいた私の手を剥がした。行こう、という言葉に含まれている感情が決して軽くないので、私はクォン・ヨンヒにムアラもっと言葉を乗せることができず、キム・ソクジンに沿って歩きを移すしかなかった。
最悪の一日だった。
📘 📗 📕
小さなガラス彫刻でどれほど深く描いたのか、キム・ソクジンは手のひらを七針も縫わなければならなかった。病院の廊下の椅子に静かに座っている私の視野で包帯を巻いた手が入った。
「…行こう」
「……。」
ぎこちない沈黙だけが一緒だった。家に帰るずっとキム・ソクジンは何も言わなかったし、私はキム・ソクジンの包帯巻き手を見つめて歩くだけだった。単に「心配されて」という理由だけではなかった。偶然に聞こえるだろうが、先日キム・ソクジンが私にした言葉を今日このことが起きた後だけに完全に理解するようになったからだった。なぜそんなに私が怪我をするのに鋭敏に求めるのか、クォン・ヨニの行動を見守るだけで、どんな制裁もない私になぜそんなに怒ったのか、
頭の良い彼はすでに知っていただろう。この小説の中の世界が私たちが夜中に見る夢のように軽く逃れることができる世界ではないかもしれないという疑いを続けてきただろう。たぶん体育大会の日からかもしれなかった。桂州の大打に出て床を転がったせいでできた私の足の傷を妙な表情で見つめていたキム・ソクジンが今や思い出している。死んで終わるのか?しかし、この世界の私たちは現実での私たちと変わらず食べて、寝て、傷つければ血を流し、傷が出て、傷が何の時間は怖くなるように遅いだけなのに。小説の中で死んで目を閉じるとき、現実で目を開けるのではなく、現実の私も一緒に目を閉じてしまうのではないだろうか。安日に「これは夢に似て、死んだら壊すのと同じだろう」と思った私の考えがどれほど安日することができない考えだったのか。
キム・ソクジンは何も言わずに私を家の前まで連れて行った。入ります。特別な言葉なしでその言葉だけを吐き出したキム・ソクジンが体を回した。私はその背中に向かって、家に来るずっと考えた言葉を吐き出した。理解するという言葉も、申し訳ないという言葉でもなかった。
「危険だった」
「……。」
「次回はしないでください」
キム・ソクジンが歩みを止めた。だからとすぐ後ろを振り返らず、行っていた方向の正面だけを見つめていたキム・ソクジンが体を回した。声が大きく、その長い足ですぐに私の前に近づいたキム・ソクジンが私の肩を握った。傷ついた手が痛くなるのではないかと、私の視線がその手に戻るため、キム・ソクジンの顔が歪むのを見ていない。
「…危険?危険なのは知ってる?」
「……。」
「お願い、お願いしますからよくやって…!お前から危険な状況は少し避けてください。」
「……。」
「今日も、一人でクォンヨンヒに会っていると聞いて私が、どれだけ…」
キム・ソクジンが崩れた。自然に私も彼に沿って切って座るしかなかった。ギアがキム・ソクジンの目から涙が落ちる。あいごや、一言がこのような結果をもたらすと思ったらもう少し気をつけたことを。私はとんでもなくキム・ソクジンの肩をすくめていました。装着できなかったパズルの一枚が自然に合わせられる気分だった。

「好き…」
好きだからええ、好きだからもっと気にして泣き声と共に吐き出すキム・ソクジンの言葉に耳の末に熱が上がった。何も言わず、キム・ソクジンの肩をうなずくことを止めなかった。
友情してはとても重い気持ちだと思った。知らなかったにはあまりにもティーが出るものだった。答えるには確信のない心だった。ふくらんでいる音がさらに大きくなった。私は何も言わなかった。
📒