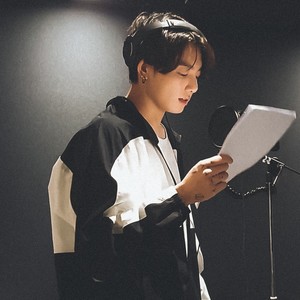- 作家が少し正気ではない状態で書いた。
- 一体何なのか作家も知りません。
- なぜ書いたのか作家も知らない。
- クリシェの塊。
- 軽く読んでください...とにかく、開拓性の犬がくれた混乱の文章です...
- 女主の元の名前が出てくる部分はわざと空にしました。読者の名前を入れて読んでください。
-TRIGGER WARNING! 2010年代初めに流行していたインターネット小説を背景にしているため、学校暴力を連想させる場面があるかもしれません。
エクストラで生き残る方法
: ある日小説の中でエキストラになってしまいました。
W. はい
「食べますか?」
これよりもあまりないことはないだろうと思う表情で私を見つめる相手に私はすっかり笑って見えて手に握っていたゼリー袋をダランダラン、振った。そういえば剥がれたゼリー袋の中に手が入る事はなかったが。喜んでゼリー袋に手を差し出す代わりに、本当に私に言ったことが正しいかと思うように延伸目を忘れていた相手が尋ねた。
「…私に言ってるの?」
まさかそんなに無い力力がいっぱいの言い方だった。しかし、私は本当にその子供にゼリーを許可することが正しいので、頭をうなずくことができない理由がなく、力強く頭をうなずいた。そうしたら今はハァッ!と笑いをすることだった。なぜ?という悪意のない反問に、彼は今、子供がいないという目つきを隠さずに淫らに出た。これは美味しいのに… 。なんだかゼリーでは視線も抱きしめるあの子にふわふわとした感情が押し寄せた。誰も手を触れていないゼリー袋に手を入れて、犬の中で最もおいしいもので選んだのも、そのような理由からだった。
「食べてみて、美味しいー、」
その子の口にランダムゼリーを入れるために。え、だから、
「…一体これが何をするの?」
クォンヨンヒの口の中にだ。
老婆にする言葉だが、決していじめる目的でそういうわけではない。アンマンクォンヨンヒが私を殺すために忙しい戦いがあったにもかかわらず。私は肩をすくめて言った。
「毒でも乗ったのかな? 心配しないで~、私はそんなことしない。君なら知らなくても」
「……。」
「それでも美味しくない?」
「…一体昨日からなぜこういうの?」
涼しくなった顔でゼリーを汚れ汚れ噛んだクォン・ヨニが尋ねた。特に言うことがなくなり次第、うんざりしていた。 '…友達はどうですか?」という私の言葉にクォン・ヨンヒは本当に、言葉を失ったように見えた。その表情が分通するという表情に変わるまでは、そんなに長い時間は必要なかった。まあ、言葉を間違って取り出しましたか?熱を受けた時はまた、ただ良くないし、そしてまたゼリー袋を後ろにしようとする私の後ろの首を急に掴んだ手ではなかったならば、おそらくクォンヨンヒはまた熱火が出るという表情でゼリーを噛むべきだっただろう。
とにかく、私はMacなしで膣を引っ張っていくしかできませんでした。最後にクォンヨンヒの手に桃の味甘酸っぱいを握ってくれただけを除けば言葉だ。
📘 📗 📕
分痛が起こるという表情をしたのは絹のクォン・ヨンヒだけではなかった。今回はパク・ジミンがピッタリ!クォンヨンヒが建てて見えたその表情そのまま私を見下ろしていたからだ。唇をつぶやくのに、いざ口の外に言葉を吐き出すには恥ずかしさに言葉がよく出ないようだった。それでパク・ジミンは、私の後ろをつかんで廊下その端の隅に到着してからこそきちんとした文章を吐き出すことができた。
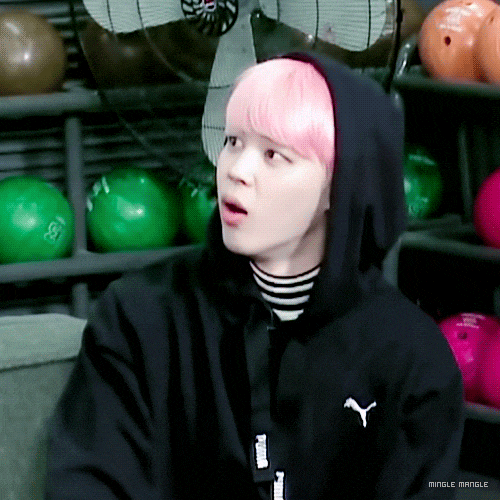
「お前一体何しよう……いや、なぜ突然そこで子どもを飼育してるの?」
飼育とは、それなりになろうと差し出した賄賂たちがそう見えたなんて痛々しく思わず、私は口を開いた。
「飼育って、友達にゼリーちょっとお勧めすることができるんだ」
「…君とクォン・ヨニが友達? むしろ猫とネズミが友達だというのがもっともっとそうだ。」
「それくらい?」
「そもそも親しくなる理由がないのにそこでなぜそうしているのか…。
クォン・ヨニに会った日の仕事をパク・ジミンと前政局にもすべて打ち明けたので、パク・ジミンがその日の仕事を運運するのはそれほど驚くべきことではなかった。クォン・ヨンヒがした言葉を土さん一つ欠かさず非常に細かく詠んだ。そのおかげで、それが人のやり方だと言って、すぐにクォン・ヨンヒを捕まえて殺さなければならない。小説の中で影響力のある家の自制で生きているのだろうか、子供たちが誰一つジョージするのに何の気持ちがなくなったようだ。そうでなければどんな解決策が罪だ クォン・ヨンヒをジョジョしてしまうことで結論が出るのか。
「いや?」
「何?」
「親しくなる理由がなぜない」
ガレージ溢れたらわからない、という私の言葉にパク・ジミンは印象を書いた。当催はどういう意味なのか分からないという表情で私はキックキック笑った。クォンヨンヒと親しくなる理由?ちょうど一つだけで十分だった。
「クォンヨンヒは作家じゃない」
「…それは何?」
「作家じゃない?」
この小説の作家ということ。それひとつならガレージ溢れる理由になるのだ。
「勝手に小説を開け直すことができるジョンじゃないのに、どうやって親しくなる理由がないと言えるだろう?」
見てみると、この世界で作家とは神や変わらぬ存在だった。クォンヨンヒの言葉だけでもそうだった。 「キム・ヨンジュ」という登場人物が生まれたのもそのような理由から働く。欲しいと思うように、やりたいとおり、この世界を導くことができる唯一の存在。パク・ジミンが口を開けたまま驚愕する姿を私は楽しく見物した。一気にその理由を納得しただけを見ても、クォン・ヨンヒが私たちにとってどんな影響を及ぼすことができるのか、その影響力が一気に立証されたわけだった。私はゼリーを噛んで咀嚼し、教室にゆっくり歩いた。
率直な心情では、その「作家」というすごい位置にクォン・ヨンヒがいるという事実ではなく、かなり複雑な理由が存在したが、それについてパク・ジミンに毎日説明する考えは追悼もなかった。 '昔考えてから'という思い出に濡れた理由を見てみたら、値段をかけると私は好口扱うことが明らかでした。

「じゃあその言葉みたいでもない計画を立てたのが…、」
とにかく、そんな様々な理由で、私はキム・ソクジンとパク・ジミン、そしてチョン・ジョングクがクォン・ヨニに無駄な敵意を持ってこれまで私に行った事柄に対する復讐をしようと出てしまうのを防いだ。小説の中に憑依するようになった庭に、作家を敵に回す愚か者がどこにいるの?だから私は、そのすべてを逆に考え始めた。
敵に回すのが嫌だったら、味方にすればいいのか?
…もちろん、私を除いた3つの憑依者たちが激しく反発したのだが、とにかく私はクォン・ヨニと親しくならなければならないという誓いを実践していた。名前によって、「友達を食べる大作戦」。幼稚なネーミングセンスはただ越えてほしい。どうやらクォンヨンヒを見ていたら17頃の黒歴史が真鍮に浮かぶ樽にそうだったから。
「それでもそう、やっと考えた方法が飼育か?」
「飼育ではないから。もともと食べてくれながら親しくなるのが定石なのかわからない?」
「…それだよ、普通の子どもなんだろう。お前とクォンヨンヒがマイチューン一つで親しい食べることが可能な状況だと思う?」
3人の激しい反対にもかかわらず、私は自分だけの作戦をとても着実に遂行していった。まさに昨日から。つまり、私がクォンヨンヒに「食べる?」と何かを出したのが今日が初めてではなかったという意味だ。クォンヨンヒから冷たい目銃を受けゴミ箱に詰まったチョコミルクを皮切りに、今日無理にクォンヨンヒの口に入るようになったゼリーまで。
「私の言葉を聞いているの?相手はクォンヨンヒだから!?食べるものとして左右される友情だったらそもそも君をそんなに嫌っていたのか、」
「食べるのに左右される友情か見て」
「…まぁ、食べない計画で時間を無駄にしないで、ただ私たち同士の解決策を探す方がはるかに良いようだ」
「いや、食べるの?」
「食べるって、これ?」
「…まあ、あなたの目にはちょっと違って見えるか?」
可能性がないように見える計画に首を結ぶように見えるかもしれませんが、私が本当に愚かではない限り、可能性にゼロに収束することに苦労しません。だから、私の目には見えた。クォンヨンヒの姿で肝臓が見える「XX高校クォンヨンヒ」の姿に私は可能性を掲げただろう。例えば、初日の内ミンチョコミルクに細かく震えた視線がそうで、無理やり入れたゼリーを吐き出す代わりに噛むことを選ぶ姿がそうで、手に握ってくれた桃味甘酸っぱいを突き抜けて見つめる。ええ、これまで私が出したものがすべて、私たちが17日ほど頻繁に食べていた主戦ブリーだったから。
もしクォン・ヨンヒが私が突き出ているすべてのものに対してシクンドン反応、インスピレーションがないという反応を見せたら私もこの計画を素早く諦めて他の解決策を探しに出たかもしれない。しかし、そうではありません。ちょっとした隙が見えたから、異王することすべてに良い結果が出せるように頑張ってみようー、これだ。もちろん、このような中の事情を知っているはずのないパク・ジミンは相変わらずとんでもない表情だったが、まあどうだ。

「…私はまだ君の頭の中がよく分からない。私を掴んで一度振り返らなければ直性が解けそうだ」
これからも分かればいいことだ。私はパク・ジミンの言葉にまたキックを笑って彼の口にゼリーを一杯入れてくれた。大人しくゼリーを受け取っていたパク・ジミンが言った。
「もしかして言ってるのに、危険な感じが少しでも見えたら…、」
「ちょっと関わりましょう。そのくらいは約束できますよー」
子指を差し出す日を見てパク・ジミンがピック笑った。私の子指をしっかり歩いて約束、塗装、コピー、最後のコーティングまで、誘致することができない一連の行動をした私たちは仲良く教室に入った。
「……。」
そしてキム・ソクジンと目が合った、
「……。」
私は遭遇した目を避けました。
「…私に聞きたいこともう一つある」
「……。」

「お前キム・ソクジンとまた戦った、いや、何があったのか…?」
…戦ったのではなく… 、馬の終わりをぼやける日を見てパク・ジミンが頭を傾けた。それでは何ですか?という表情に寝る不愉快な表情をかけてゼリーを一杯掴んだ。そしてそれをそのままパク・ジミンの口に選んで入れた。ただ、封弁されたパク・ジミンが恥ずかしさを全面で表出した。パク・ジミンの煩わしさを避けたり、彼の質問に回避したり、私は私の席で私に手を振っているイ・ユジンと無事退院を終えたキム・ヨジュに飛び込んで歩いた。遊ぶよ!週末に映画を見に行きますか?と歓迎してくれる人たちに言葉の笑顔を見せながら。
嘘ではなかった。戦ったのではない。たとえ前よりずっと厄介な仲になったのですが、やや喧嘩で人の間がこんなに遠ざけることはできない法だから。だから、私たちは戦ったのではありませんでした。
告白を撤回された。それだけだった。
📘 📗 📕
一体何をしたのか告白を撤回されるまでするか尋ねるなら、私は何もしなかったという答えを出す。本当に。比喩的な表現ではなく、何もしなかったと!始発!むしろ私がキム・ソクジンの好きな言葉を聞いて震えた気配を出したか、その後に彼を恥を与えたか、否定的な反応をしたりして、それに対する結果で告白を撤回されたとしたら、むしろ悔しいことでもない、いや、そんなことだったらむしろしかしそれではなかった。キム・ソクジンが告白を撤回した理由が私になかった。いいえ、私にありますか?
そう、考えを別にしてみると、むしろ何もしないのでそんなことかもしれない。こういう考えを頭に浮かべるようにしているということからがちょっといなかったが、薄くあったことを思い出してみると自動的に私の頭の中がその日の仕事でいっぱいになってしまうのだった。絹「告白撤回」という、人生において一度くらい経験するかなかの経験をした日という理由だけではなかった。実際、その理由が最も大きくなった。私はゆっくりとその日の仕事を一つ一つ振り返ってみた。だから、
私はちょうどぶら下がって泣いているキム・ソクジンの背中をあきらめた、
それからキム・ソクジンが好きだと言った。
そして、
'…私はただキム・ソクジンの背中をずっとしただけだ。
いくら考えても、私が何を言ったのか直視したキム・ソクジンが顔を淡く染めるまでして告白を撤回する理由がないように見えた。その後、キム・ソクジンが顔は白く飽きた主題に耳元だけ真っ赤に燃える、パックうっとりとした形鳥で立ち上がったせいで中心をとらえなかった私がお尻を突っ込んだが、すごいした。ええ、そうでしたが… 。その後に吐いたキム・ソクジンの言葉は好きだという言葉などではなく、先の告白に対する不燃説明はさらになかった。

「ごめん、失言だった」
「……。」
「ないことにしてください」
告白を聞いて、すぐ後ろになかったことにしてくれた言葉を聞いた。ここで私が取るべき行動は?百回を考えても荒涼とするだけだった。 …何?と言って印象をつぶして帰ってくる私の姿にキム・ソクジンが一体何の感情を感じたので顔をさらに青白く染めたかは分からないのか、それでも彼は引き続きごめんなさい言葉だけを繰り返すだけだった。答えを願った言葉ではなく、このように衝動的に吐き出して私を困らせるつもりはさらになかったと、都合なく震える声で言葉を吐き出すキム・ソクジンを見て私が一体何の反応を見せなければならなかったのかと…。 !恥ずかしさと恥ずかしさはもちろんだと、やがて私に好きだと言ったのが顔が淡くなるほど間違ったことだと思うようなキム・ソクジンの姿に俺は――、
「…熱くなる?」
プライドがワルル-、崩れ落ちてしまったのだった。くそー!
それでも、知って過ごした時間が決して短いとは言えなかっただけに、キム・ソクジンが本当に好きでもない私に告白する愚かなミスを犯したと思ったわけではなかった。むしろ私が知らない他の理由があるだろう-、と渡ることができるほど、短い時間の間キム・ソクジンと私をはじめとする憑依者4人に生じた信頼は厚い方だった。それでも告白撤回は話が違う。これをいっぱいに行って家に帰った私はベッドにこぼれたまま怪城を掴んだ。ああああ!というその声にママがうるさいと言い、背中をパクパク降りても私は苦しんでいる音を出すことを止めることができなかった。
好きなだけ言葉にハリルなく耳たぶや足元に染まってしまった私が迷惑してからだ!
キム・ソクジンが好きですか?という問いにはないと答えるが、それだと好感が非常にないかというとそれはまたなかった。このどんなゴミのような発言なのか、手に石を握る人たちにはそういうものではないから落ち着いてほしいと言ってあげたい。男周期に惜しくて、私が持つには嫌なそんなのは絶対じゃないから!言えば、確信がなかったと言えるだろう。キム・ソクジンが告白をしなかったことにしてくれなかったとしても、私がその場で出てくる彼に『ええ!私も好き!それでは私たちの邪悪な人!こういう言葉を吐き出すことはないだろうが、少なくとも考える時間を変えて―、程度の答えが出るほどの好感はある言葉だった。それでも、でも!それでも!あえて!告白を取り消してしまうその姿は熱が受けるしかないのではないか!なかったことにしようという言葉を聞いた瞬間、ただ、「この犬ごみの子が!」と言ってキム・ソクジンの頬を下げたいと思ったのがまさにだったと!
…まぁ、そうなったのだった。告白ビスムリハンが五間の間に昔のように壊れない間に過ごすことを期待するのは無理だろうが、キム・ソクジンと私の間に終わりが見えないほど広いぎこちないという川は、私たちの間に五行馬がやっと「告白ビスムリハン」ではなく、「告白撤回」というそれなりの大事件に。
そう、異王の打ち明けた金にもう少し率直な心情を伝えてみると、私は私の誇りがワジャンチャンムンギョしてしまった当事者であるキム・ソクジンを絶対に細かく見ることができなかった。キム・ソクジンだからその事を無かったことにしてほしいと頼んだ当事者だけに、私にすぐに厄介に屈するよりも平気な姿を見せるのが私になると判断したのだが、私はなかった。私はそうではありません。すぐに翌日から私はキム・ソクジンを安く無視するしかなかった。ちょっとした復讐なら復讐だったし、より正確に言えばキム・ソクジンとそんな距離を置く時間を持つことで、
団結したプライドを回復する時間が必要だった。
されていない言い訳を相手にキム・ソクジンを避けた。しばしば無視されたので、キム・ソクジンも熱が受けた草が死んだ私にこれ以上言うのが要員になったはずだった。そんなぎこちなく過ごし始めたのがやっと三日前だったし、たった三日ぶりに私たちは二人もなくぎこちない仲になってしまった。キム・ソクジンと私が内外する理由を知らないパク・ジミンと前政局はただ私がクォン・ヨニと一人で会って来たことのために戦っただろうなー、と渡った。先日キム・ソクジンが私一人で動くことにすごく鋭敏に反応したことがあったせいだった。まぁそう、世の中生きていくのになんら不要なのが自尊心という言葉には同意するが、今回だけはその言葉に反論する。少なくとも今、この状況では私のプライドを少し手に入れたいというのが私の本心だった。
「それでも生涯このように過ごすことができない法ではありません。」
だから少しだけ、私が束ねられたプライドをアリたわごとだけでも回復する時間を与えて。ちょうどその間だけぎこちなく過ごそう。キム・ソクジンは絶対に分からない理由を入れて中に退屈な謝罪の言葉を送った。利己的だからペアがないと思ったけど、あまりできなかった。まったくぎこちない演技をしながら仲を維持する パク・ジミンと前政局にバレて死ぬように煽られることよりも良いだろうし、ワジャンチャンギャングンジン私のプライドをそのままにしたくない。とにかく、私は適当な時間の間キム・ソクジンに心痛をちょっと呼んでみる予定だった。これまで出てくる理由とは、おそらく私が彼に好感があったという理由が最も大きく作用しただろう。時が来たら適当に誤解を解いて、キム・ソクジンと率直な話でも分かち合わなければならない。そう思った。思ったけど…
…それで、罪深いことになったのは断然私のせいではないだろう。絶対に!
「…う、髪だ…」
…いや、多分私のせいかも…。 ?ええ、私のせいが当たるようです。どうやら私が憤慨した、クォン・ヨンヒがお世話になったこの小説が私が予想したよりもずっと、多く、途方もなく幼稚な、言葉にならないことだけいっぱいだという事実を非常に真っ黒に忘れていた私のせいが合うようだ。
鼻を刺すクイクル ペアのない空気や、とてもしっかりと縛られた両腕と両足や、それに比べてぎこちなく被せられたまま私の視界を覆っているセカマン千や…。 。そう、数多くの小説を読んできてから、10年に氷の人生2ヶ月であれば、知らなくても大変なことが私に再び起こらなければならなかった。
「…また?本当に?」
どうやらまた!拉致されたようだ。くそー。
📒
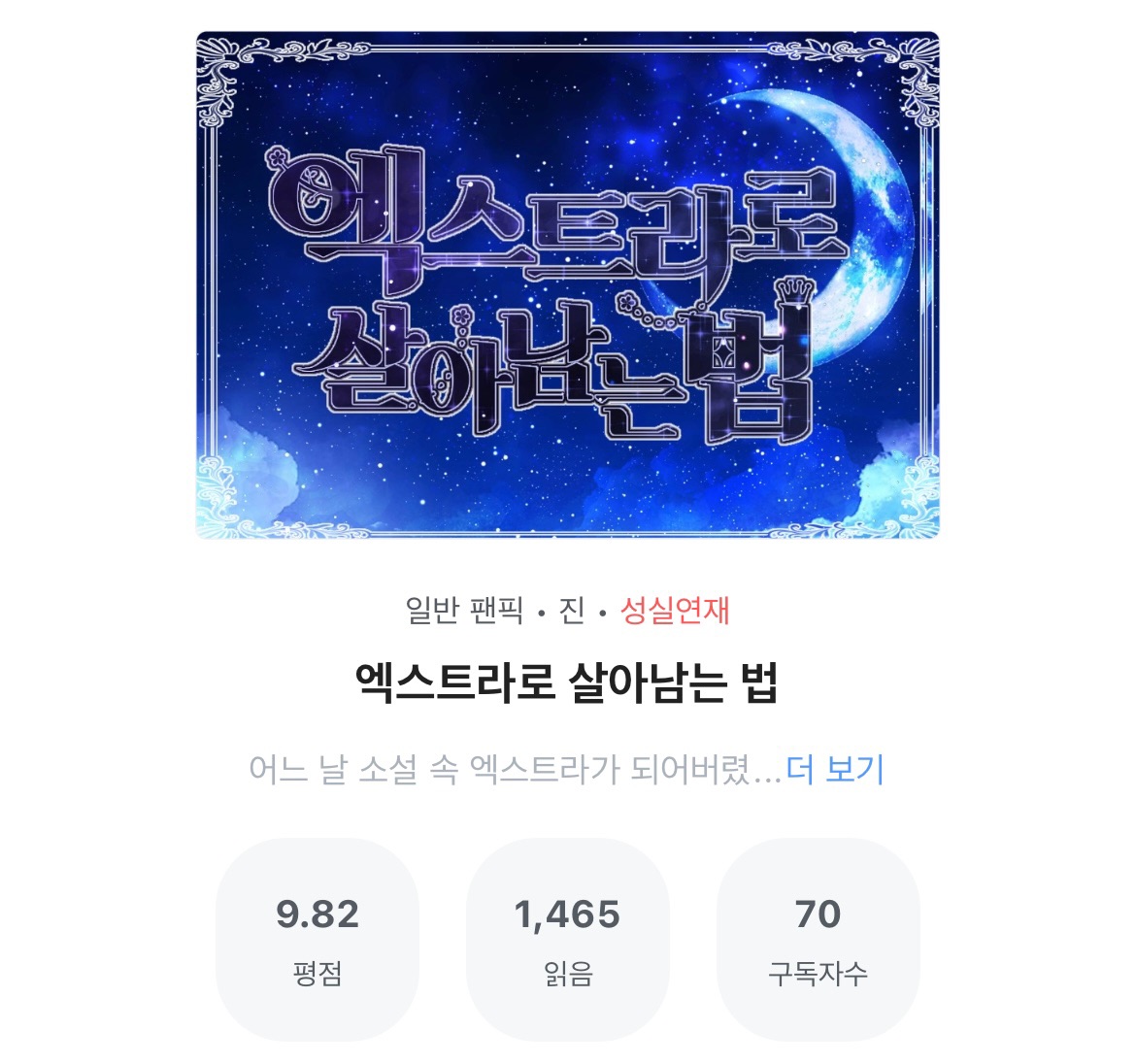
ハラン購読者70人ありがとうございますㅠㅠ