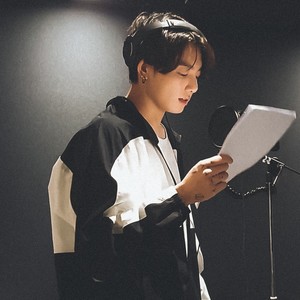- 作家が少し正気ではない状態で書いた。
- 一体何なのか作家も知りません。
- なぜ書いたのか作家も知らない。
- クリシェの塊。
- 軽く読んでください...とにかく、開拓性の犬がくれた混乱の文章です...
- 女主の元の名前が出てくる部分はわざと空にしました。読者の名前を入れて読んでください。
-TRIGGER WARNING! 2010年代初めに流行していたインターネット小説を背景にしているため、学校暴力を連想させる場面があるかもしれません。
エクストラで生き残る方法
:ある日小説の中でエキストラになってしまいました。
W. はい
おそらく私たちが拉致というひどい事にあったようだということをキム・ヨジュに伝えた後、今の状況について説明するのは簡単なことだった。まずキム・ヨジュがこの小説のヒロインという位置に位置しているということが最も多くの影響を与えたのではないかと思った。彼もそうだろうが、先日銀河別高校をとても騒々しくさせた「キム・ヨジュ拉致事件」の張本人ではないか。すでに拉致された経験が一度あるキム・ヨジュであるだけに(とても悲しいことだが)彼の状況把握もとても速かった。
「じゃあ演奏お前もここがどこか分からないってんだろ?
「え?うん…、罠の可能性もあるだろうけど?」
「うーん、いや。演奏の言葉を聞いてみると、その人たちはただ平凡な女子高生を拉致したという事実にすごく安心しているようだ。実は前回もそうだった。
「…いつ? 拉致された時?」
「うん! まぁそんなことで見た監視はうまく避ければ避けられるほどだと思う。ヨンヒを連れてくる気もしてるから見ては近所からそんなに落ちたところでもないようで。他の地域に移ってきたようではない。幸いだ、それ?」
「え、うん…。」
状況把握が… …早すぎた、うん… 。これは女主人公の悲哀なのか?なぜか涙が高そうで私は目をホップして頑張った。エキストララ幸いだ、なんかの思いをしながら。
とにかく、キム・ヨジュが拉致された時「꺄아아악, 살려주세요!!」なんだか愚かな痩せをする柳の女主人公ではない点は、本当に幸いだった。そうしたら私ができるのだとかやっと男主人公の力で女主人公を探してあげたいとまた望むしかなかったから。しかし、私たちのヒロイン、キム・ヨジュは違った。状況把握をすばやく終えて、あの幕屋だけの頭痛で、ここからの脱出角度を計るだけで見ても、卑猥さが目に見える地境だったが、これは新しい足の血に過ぎなかった。だから、ヒロインの能力値が私が思ったよりもはるかに詐欺だった。
「…どうすればいい?」
「よく見て、ここの結び目の先端をこんなにつかんで、反対側にこんなに…またこうして引っ張って再びこの隙間に押し込んで、次はこうした後に…、またこちらをつかんで強く引くと……解けた!」
腸の数十分という時間の間、汗が出るほど体になった私の意味のない行動がさらに意味なくなった。手首に赤い跡が残るほど強く結んだ結び目をこんなに手軽に解いてしまうキム・ヨジュのためだった。できますか?するその言葉で私は飽きた表情で首を振った。それはご飯おじさんが来てもいけない。そんな思いをして、私は大人しくキム・ヨジュに縛られた両手を差し出した。お願いしますが、私の言葉に頭をうなずいたキム・ヨジュは三分にもならず、足首と手首に縛られていたひもをすべて解放した。じゃあ、行こう!キム・ヨジュが笑って言った。拉致された状況だとは信じられないくらい笑顔のキム・ヨジュに私はずっと頭の中を振り回した質問を吐き出すしかなかった。
「こんなのはどうやって知ってるの?学んだ?」
「え?何?」
「これ、ロープ解くの。さっき拉致されたという声聞いた時も君になって落ち着いて見えて……」
「ああ、あまりないよ!前回拉致された後、テヒョンが教えてくれたら」
「…ロープ解く方法を?」
「うん!そして実は…、」
よく言っていたキム・ヨジュが恥ずかしいように両頬を赤く染めた。 …え?やむを得ず続いた言葉に、私は固い誓いをするしかなかった。
「前回と違って演奏お前が一緒にいて…私になって落ち着いていることができたよ!
何があってもこれからキム・ヨジュは私の友人だ。うん、そうじゃない。
もちろん、キム・ヨジュのキュートな発言だけが私の徳深爆発の原因ではなかった。だからキム・ヨジュは、なるほど何とか、なんでもふりをした。手足に結ばれたものもふりをして、コンテナを裏返して使えるものをすり抜けて見つけて(転がっていた鉄パイプをつかむ姿に私の二つの目を疑ったが)、入口の隙間新たに耳を傾けて人がいるかどうかを確認する鉄頭チョルミハムや、そう安心することができなかった。 …男主人公よりも良くないだろうか?そしてその姿をすぐ隣で見物していた私は思った。
「脱出…意外に簡単かも…?」
それだけキム・ヨジュは万能だった。やっぱり、ビングの初日からあまり親しくなりたい気持ちがなかったよ、うん。そしてこういう考えは、キム・ヨジュが近くにいたガード二人を叩いて敗れるのを見てさらに固まった。
「ふー、演奏よ!もういい、出てもいい!」
…一体この小説のジャンルは何ですか?私は頭の中に浮かび上がる人の顔を思い出さないようにしっかりと頑張り、キム・ヨジュの後を追いかける。
ジャランは絶対に戦わないでください。
📘 📗 📕
古いコンテナボックスが何十代も集まっている空場で人を避けて通うのは思ったより難しいことだった。特にここの地理をよく知らない私たちにはもっと。名前が分からない山の中に位置するだけでも足りなく、今はすべて遅い夜明けだった。日の出までそれほど長い時間がかかるようには思えなかったが、アンマン脱出だから一晩で山の中に入るのが正しい選択か苦労するのは当然だった。
「人質が逃げた!!」
「周辺を捜索しろ!女子校生二人!遠くは行けなかった!」
長く行かない悩みだった。人質が消えた!大規模なおじさんたちがクジラクジラの声をあげるのが、空き地と山の境界にあった私たちにも聞こえるほどだったから。人質が消えたという悲鳴に近い叫び声を聞いた私はキム・ヨジュを見つめた。キム・ヨジュは私を見た。目に出会った私たちは躊躇したことのないように山の中に歩き回った。がんばかり考えても人質で捉えられているのではなく、山の中で転がる方がはるかに良いと思われた。それでも名色が女主人公に女主人公親しいのに、山の中に閉じ込められても南主たちが救いに来てくれるだろう。
もともとヒロインには、このような苦難と逆境を乗り越える能力があるのだろうか?は、だから女主人公だろ。山を上手く乗り越えて行くキム・ヨジュの後を追いかけて追いかけて考えた。どんな一生生を山から出て育った人のように、あちこち山を乗り越えて前に進むように見えると、そんな気がするしかなかった。彼に比べると、泣くペアのない体脂肪を持つ私は?キム・ヨジュが簡単に一歩踏み出す距離をヘクヘクゴリョドゥセ三足だけに追いつくことがあった。疲れていくのは極めて当然の結果だった。
「演奏よ…大丈夫?」
「ほ、ほっぺ…、少し、ちょっと休んでいこう…、お願い…」
汗をかくことができず、涼しくなった顔をした私をキム・ヨジュが喜んで大きな岩に座らなかったならば、チャンダムは私がそのまま落ち込んでいた本当に山を転がっていただろう。咀嚼した息を追い払い、周りを見守った。短い時間にかなり遠くまで来たという事実は朗報だったが、山を後ろにするような人気のふりが依然として聞こえてくるというのは悲報だった。私は岩の上に座っていた体を岩の後ろに隠す側を選んだ。もしかして近くまで来た私を見つけたら犯されるのは私たちだから。
大丈夫ですか?と心配に聞くキム・ヨジュに私は大体首をうなずいた。休むからちょっと生きそうだった。喉の渇きが起き、足が泣いてしまったが、我慢しにくい。息だけを選んで行こうという私の言葉にキム・ヨジュは頭をうなずいた。岩の後ろに隠れた形が処分することはないので私はため息をついた。
「見つけた、これらのネズミたち、」
おやすみ、始発… 。ため息が節に出るしかなかった。誰がクリシェの塊の妄作小説じゃないかと思って本当のセリフ一つ一つがすべて陳腐することがなかった。束ねる目つきをしたり、やむを得ずひざまずいてこちらに近づく大型おじさんが見えた。私はキム・ヨジュを見つめました。アンマン女主人公だとしたら、このような状況ではパニックに陥る準備の法だと、キム・ヨジュの見知らぬ人がかなりパリに飽きていた。ああ、そうです。脱出させてくれた値はしなければならない、と思って私は息を何度も追いかけてキム・ヨジュを私の方に引いた。そして、
「クアああああ!この狂った年が!」
ナプダ土を振りかけた。命中だった。叫び声もあんなに陳腐することができるかという考えをしばらくして私は叫んだ。飛び出す!という私の言葉にキム・ヨジュはしばらく慌てたが、以内の後ろからバラクバラク音を立てているおじさんを一度見た後には迷うことなく飛び出した。捕まえれば殺してしまうよ!!と言って悪を使う音が山に響き渡ったせいか、いつの間にか後ろを追う人が船に増えていた。ああ、犯された。あごの終わりまで冷たい息を均等に吐き出して苦労して考えた。どうしよう、どうしよう、どうしよう、ただ捕まえばいいの?思考が尾に尾を噛んだ。状況を打開する妙獣が光って浮上することはなかった。アンマン小説の中で見たら私はエキストラだったから、そのような奇跡に希望をかけてバエヤ最悪と最悪を消していく方法を選んでいく方がもっと似合った。やはりここでは南主人公たちの登場に期待をしてみるしかないか、それとも、それとも…。 。頭の中が複雑だった。そしてそれが原因だった。
鉄パドク、と転倒することでも足りなく山道をくるくる転がりまでした。先日、クォン・ヨンヒが山から押したときと同じ類の痛みが全身に広がった。遊ぶよ!というキム・ヨジュの驚いた声も聞こえた。そう、この状況でクソ体脂肪は搾乳した力まで絞って逃げられない妄想っぽく倒れてしまっただけだった。おっさん、傷を確認する隙もなく体を広げた。膝で、肘がない病気の場所がなかったが、一度逃げるのが最初だった。しかし、すでに遅れているという事実は、私の視野に満ちたシーン一つでもとてもよく分かるものだった。絹の後ろから追いかけてくる厄介な粗暴なおじさんのためだけではなかった。
「…あ、めちゃくちゃ…」
絶えず走ったのも止まり、私が呟いた。キム・ヨジュの顔色がさらに青く飽きた。後ろだけでなく、前でもウェンサカマンスーツを着た群れが現れるとは知らなかったせいだった。そう、包囲されたという言葉が必ず似合う形だった。
アンマン目を転がしても脱出口はない。前後に出てキム・ヨジュを捕まえようとする人々が密かに壁をなしていたから。ああ、台無しに。一見で静かに貪りを噛んだ。ここで私ができることは何があるのか、何がありますか?最悪に最悪を消して残りの方法のうち可能なものだけを選び出す。できることは一つしかなかった。私はキム・ヨジュを私の後ろに隠した。隠すと何が解決されるのではないだろうが、まぁ倉庫でのその愚かな二人のおじさんたちの対話で見たときクォンヨンヒが狙うのは私一つだったので私だけ細かく捕まえればいいことだった。キム・ヨジュを返す条件で。それでは、キム・ヨジュが警察であれ南主人公であれ、助けを求めて私を救うことができるだろう。そう、足首も折れた庭にこれが正しかった。私は、異王ならスーツを着た側に握られていくのがあまり目立たなく見えるのではないかという心情でしっかりと前を眺めて立っていた。
「…エン?」
そして、虚しい音を出すしかなかった。だから、きっと私とキム・ヨジュをつかむために上がってきたと思っていた黒いスーツのおじさんたちが私たちを通り過ぎるのは私の予想範囲になかった状況だった。けれども傷ついたデンがないのか丁寧に尋ねるまでする彼らの姿に私は愚かな表情をするしかなかった。キム・ヨジュも同じだった。当催の状況を把握することができず、顔に疑問符だけ浮かせたまま固まっている私とキム・ヨジュの耳に慣れた声が聞こえるまではそうだった。

「おい、キム・ヨンジュ!キム・ヨジュ!大丈夫?!怪我をしていない?」

「キム・ヨンジュはすでに一風変わったのか見たが、足の犬が痛い…」
キム・ヨジュの体がすっかり折れた。ええと?と一緒に崩れようとしていた私とキム・ヨジュを前政局がしっかりと握った。大丈夫ですか?再び聞いてくるその言葉にキム・ヨジュはワアン、泣き声を上げた。緊張が解けたせいだった。私は目をひっくり返し、キム・ヨジュを一度、チョンジョングクとパク・ジミンを一度、あの後ろで鈍い音と叫び声を上げて、サムバクジルに熱を上げる黒いスーツのおじさんたちと私たちを追っていた朝暴の群れを一度見つめた。 …これは一体何だったの?ずっと立っていた私が口を開けたこともなく、私はそのまま誰かの胸にすっかり入って抱かなければならなかった。冷たい品だった。どれだけ飛び回ったのか風の香りが薄く残っている冷たい品、
「…幸い、無事で…、幸い……」
「…キム・ソクジン?」
彼の声が都合なく震えるまでして、私は驚いて手を挙げてその顔をたどった。湿った。なぜ泣く!彼の顔に直面するために苦しんだが、私の体をしっかりと包んだ腕は落ちる方法がなかった。やがてバルバドン打つと、バルバドンを打つほど、より固く罪が来ているため、私はその懐から抜け出すことを半分あきらめた。ふらっと音が大きくなった。私は手を伸ばして彼の背中をうんざりした。
「おい、いや、なぜ泣いてそう…」
それなりにやろうとした言葉なのに、今は私の肩に私の顔を埋めて非常に大声で通曲をするのだった。オタク死ぬが湿ったので濡れていったが不快ではなかった。なんとどうやってやるべきなのか、という心配だけが残っただけ。泣き声が飛び出したキム・ヨジュを慰めるパク・ジミンと、チョン・ジョングク、大成通曲するキム・ソクジンを何とかなだめるようにする私。他の世界である羊のあとでサムバクジルや行っている正体不明のおじさんたち。開版だが、そんな考えをして私は徐々に止まり始めたキム・ソクジンの泣きにまた彼に手を伸ばした。
「やめなさい?誰が見れば私は死んだと思う」
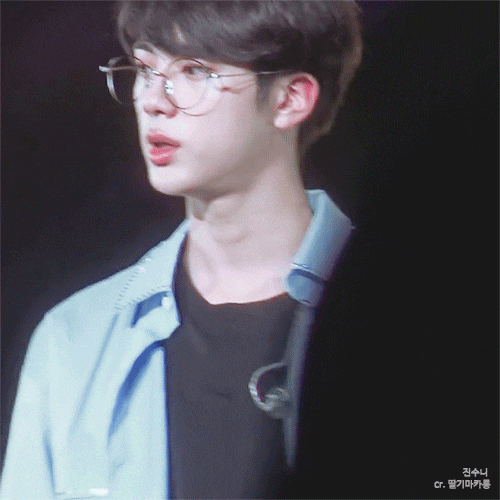
「…傷つけたのは?」
「足少し?倒れた」
キム・ソクジンの視線が下に下がった。チューリニングパンツの真ん中くらいに凶悪な穴新たにピットが湧いていた。穴の間に見える膝さえも傷で覆われているのを見たキム・ソクジンの瞳がまたすすくなるのを見て私はため息をついた。ここで足首も炒めそうだとしたら本当の泣くだろ?そんな思いをして、私は気をつけて手を上げた。両頬を湿らせた涙を慎重に拭き取った。
キム・ソクジンは簡単に落ち着かなかった。しゃっくりに近い曇りが止まるつもりがないのは、二番目に目が腫れていく渦中にも着実に涙を流す姿がそうだった。腕をほぐすと私が逃げてもいいか、私の腰を玉罪する腕をほぐさない姿さえもそうだった。その姿を見る私の気持ちは… …かなり妙だった。それは明らかに愛情だった。キム・ソクジンが惜しくも、好きでもない人に涙を見せるほどの偉人ではないということズムは、わずか数ヶ月を一緒に過ごした私も知るほどだった。それなら、それでも、こんなに泣きながらも、私に好きなだけ言葉を渡しても、一人で飽きてその言葉を再び隠してしまった理由は何か?ふと頭の中が澄んだ犬の気がした。たぶん私はすでに正解を知っていたかもしれません。キム・ソクジンの両ボールを捕まえた。湿ったボールが私の手の中に詰まった。
「…ハル、」
「…ひ끅、」
「……。」
告白撤回、私のプライドをすごい崩壊したその事件が結局キム・ソクジンが私を考えるために起こったことという事実をこれ以上は分からなかった。捕まったキム・ソクジンの顔に出る私の唇をぶつかったのもそれだった。ちょっと-、という男らしい音が聞こえ、曇りとしゃっくりが混ざっていたキム・ソクジンの泣き声がしゃっくり音に変わるのには10秒で十分だった。耳元からとても真っ赤に走り始めるその顔を見て私はカンルルー、という笑いを放った。キム・ソクジンの腕から力が抜け出した。泣き止めるには口当たりが最高だった。
「…お前、お前、ちょっと、な、」
「うん、私も好きだよー」
遅い答えにキム・ソクジンの顔が本当にぽんと鳴る直前まで赤くなった。後ろにはサムバク音が、四方では風が木にぶつかって出る先得な音が聞こえる山の中で、臀罪罪なモルゴルで膝から血や質の流れるように言う時遅い答えは雰囲気とムードで何もなかったがそれで十分だった。好きなだけ言えば十分だった。
「…なんでニードル?!キム・ヨンジュがキム・ソクジン好きだった?!」
「いつ告白したのか」
「なんだ、前政局君は知ってたの?なぜ私だけ知らないの?!」
「…うわあ、」
パク・ジミンとチョンジョングクがワクワク大は音とキム・ヨジュがナジマクが感心する音が聞こえた。まあ、一ヶ月かかりました誕生ですね。なんて考えをして、私はキム・ソクジンを見てベセット笑った。まだ赤くなっている顔が見えた。ふわふわの吐き出しは告白にとてもよく似合う答えだった。その真っ赤に染まった顔が言葉だ。
📘 📗 📕
小説のクリシェらしく、男主人公たちに救われる役割を非常に忠実にしてきた。いや、実はクリシェと言うにはちょっと違った状況ではあった。何が違うかというと、私とキム・ヨジュを救った人が男主人公ではない違うという点でそうだった。だから――
「お嬢様、制圧完了しました」
「お疲れ様でした」
私たちを救ってくれた張本人がまさにクォンヨンヒという点がそうだ。財閥の家娘だったら、お嬢様の声を聞く姿がパック自然に見えた。私は相変わらず顔が真っ赤なキム・ソクジンに手の片方をつかまえたまま'財閥集外東娘'の役割を非常に忠実にこなすクォン・ヨニの姿を見物した。
「女、ヨンヒのお嬢様!私がみんな申し上げます!これで、ああ、お嬢様のための…!」
「私のためだ?」
「はい、はい、当然-」
「これ?」
…ガンマン見ても私が覚えていたクォンヨンヒの姿ではなかった。外的な姿でも、内的な姿でも。少なくとも私が覚えているクォン・ヨンヒはあんな威圧感を吹き出すほどの人ではなかったから。まあ、それが何年も過ぎたという事実を振り返ってみると、たぶん今私の前で威圧感をふんだんに漂わせて、暴力おじさんたちをひざまずいて置いたクォンヨンヒの姿も私が知らなかったクォンヨンヒの姿かもしれないと思った。とにかく重要なことは、
「飼い主を噛む犬はいらない」
ジョンナクール。セカマンの頭をしっかり縛って話すクォンヨンヒを見て考えた。とにかく重要なのは、私の前にいるクォン・ヨンヒや私が覚えていたクォン・ヨンヒや両方とも同じ人という事実だった。犬は素敵です。
その後は一社天理だった。クォン・ヨンヒが連れてきたスーツのおじさんの群れが朝暴のおじさんの群れを捕まえて拉致事件は一段落した。遅れてニュースを聞いてハレバル餅走ってきたキム・テヒョンとキム・ヨジュ、この小説のナムジュとヨジュの再会も彼らの熱い抱擁で成功的に終わった(驚くべきことにまだ付き合う間ではない)。少し驚いただけで、他の外傷はないキム・ヨジュとは違ってまた格別に山道で転がった私はクォンヨンヒの車を借りて彼の家まで行ってクォンヨンヒの担当医師という方に山から倒れたせいでひざまずいて生きていた観子遊び付近の非常に浅い傷まで全部治療された。しかも十分な休息が必要だという意思の言葉とクォン・ヨニの父(なんとK企業の会長という…)の電話一通に翌日の登校まで芽吹いたまま休息を取ることができた。
「……。」
「……。」
クォンヨンヒの家で。
「…パックでもやる?」
「…ええ」
マスクパックを顔にしっかりと貼り付けた。クォンヨンヒが借りたチェック柄のパジャマを着て、並んでベッドに横たわって天井を眺めるずっとぎこちない空気だけが部屋の中をいっぱい埋めた。一日のうちに殺したいほど迷惑私は子供のようにパジャマパーティーをするほどの仲になれば十分に発生することがある厄介だった。 …キム・ヨジュやイ・ユジンでもあったら、このぎこちなさが少なかっただろうか? …ないかも?
「…すみません」
飛び回ったりんごに瞳だけがドリューグ、転がってクォンヨンヒを見つめた。私の側は見つめることなく天井だけを眺めてクォンヨンヒはもう一度言った。すみません。という言葉に私は首を回してクォンヨンヒを見つめた。何が?という私の問いにクォン・ヨンヒも首を回した。
「…これまでお前にやったこと全部。ちゃんと謝ったことないようだから」
「まぁ、君が野山で民挙、それとも横断歩道で倒したのか、それとも鉢を投げたのか、それとも消しゴムのたわごとを投げたの?」
「……。」
「冗談だよ。大丈夫」
チムリという言葉ではあるが、クォンヨンヒが本当に刺そうとしているから気分がおかしかった。口をぎゅっと多文クォンヨンヒを見て急いで冗談という言葉を付け加えると、クォンヨンヒはあえないという表情で私を見た。マスクパックの下にある表情がすべて現れるくらいなら、本当に凄くなかったかな。まったく雰囲気だけをもっと安く作ったようで、よく言ったという考えをして、私は続くクォン・ヨニの言葉を待った。
「…そう、それは全部だ。ごめんね。そして今日のことも。
「わかって、信じて。
「…どう?」
悩みました。コンテナに閉じ込められている間聞いた話をクォンヨンヒにすべきか。自分が誕生させたキャラクターたちがこんなに愚かだという事実に改めて衝撃を受けないのだろうか?そんな思いをした私は結局口を開けた。拉致後、コンテナで受賞した男二人が分けた物語をはじめとする私の考えすべて。
「…まぁ、だからあなたがさせたのではないことがわかった」
「……。」
話を聞く中、クォンヨンヒの表情は変わらず変わった。恥ずかしく見えた。話が終わって落ちた静的が当然だと感じられるほどだった。 …いい言ってたの?横から聞こえてくる笑い声じゃなかったら、まさに言ったという考えを百回ほどした。
クォンヨンヒはしばらく笑った。ぼんやりとしたあの笑い声を聞いていると、なんだか分からないように、私も笑いが血まみれになった。ずっと笑いが出ました。約10分ほどを笑うのにだけ使うほどだ。クォンヨンヒがベッドに横たわった体を起こした。マスクパックを外した彼が笑って目尾に苦しんだ涙を拭いた。私も顔に貼ったパックを外した。大体ゴミ箱があったような席にまとめられたパックを拾った。外れたのか鉄パック―、という声が聞こえた。クォン・ヨンヒがあまりないという表情で私を見た。だからといって私が体を起こすことはなかったが、馬だ。
ボールペンで描かれた落書きを消しゴムで消してしまうことができないように、すでに過ぎたことをなかったことにすることはできない。なかったことで打つかどうか、消しゴムで消してしまったところにも自国が残るように何とかその跡を残さなければならなかった。だからと言って落書きを一生甘く買う必要がないのだった。落書きの上に描かれた絵がはるかに美しいかもしれない法ではないか。本物の高校生たちのようにこぼれて激しく転がれなかったが、私たちはかなり多くの話を交わした。例えばこの小説に関するものとか、クォン・ヨニが知っていた元世界での南主人公の4人に対する話とかということを言う。
「現実には…小説が完結したら自然に戻ることはできないだろうか?おそらく」
「まぁ、やってみないと分からないことだな……でもこの小説完結も出たの?」
「……。」
「まあ、どうせ作家はお前だから気にしないけど」
「現実では何をしてたの?」
「私?ただ大学に通って、就職準備して…。
「意外だ。お前は何か…ちょっと格別なことをしそうだったけど」
「例えば?」
「…組織ボスとか?」
「…褒め言ってるよね?」
返事なしでキキッと笑うだけのクォンヨンヒの髪をずっと引き出した。悪!と手を辿っていたクォンヨンヒが私の髪を握ってジュウク、引っ張った。頭が折れた。頭が近づいた。
「どうやって過ごしたの?」
「…私は、まあ…」
「……。」
「普通に過ごしたような気もしたし、さまようと思ったりして」
「……。」
「わからない」
クォンヨンヒの髪を握っていた手を置いた。引き続き引き抜かれた髪が床に伸びた。私は何も言わなかった。それはクォンヨンヒも同じだった。部屋の中には沈黙だけがいっぱいだったが、さっきとは違ってぎこちないも、不便でもない沈黙だった。私たちはしばらくその静けさを楽しんだ。それぞれいろいろ考えに落ちたまま。
「あなたはここに残したいのですが。」
「…うん、そうかも?」
「うーん、悪くない。一応ここでは財閥屋娘でもあり、学校もそれなり面白くて、友達はいないけど。一応お前が換装するハンサムな人がいっぱいで…」
「よ」
「冗談。まぁ、悪くない選択だと思う。どうせ君の人生なんだけど。
「…あなたも小説の中に残るの?」
「いや?俺は帰るんだけど。異王なら完結ちょっと早く出せよ。100日を小説の中で迎えたい気がないから」
「……。」
クォンヨンヒが枕を振り回した。目を尖らせてはヤルミョ死ぬと叫ぶのも忘れなかった。ゾルジに枕に当てられた私が鼻を包んだ。うわー、犬が痛い。鼻を握って顔をしかめた私の姿を見てクォン・ヨンヒがギャルルル、笑いを放った。片手で枕を握って振り回した。パック、する鈍い音と共にクォン・ヨンヒが横に倒れた。ふわふわのベッドの上でしばらくのように子供たちのように遊んだ私たちは夜明けの遅い時間になってこそやっと眠ることができた。
📒