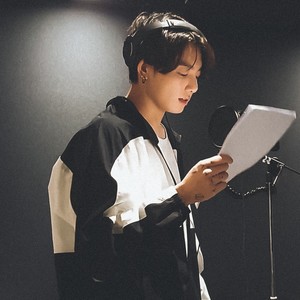- 作家が少し正気ではない状態で書いた。
- 一体何なのか作家も知りません。
- なぜ書いたのか作家も知らない。
- クリシェの塊。
- 軽く読んでください...とにかく、開拓性の犬がくれた混乱の文章です...
- 女主の元の名前が出てくる部分はわざと空にしました。読者の名前を入れて読んでください。
-TRIGGER WARNING! 2010年代初めに流行していたインターネット小説を背景にしているため、学校暴力を連想させる場面があるかもしれません。
エクストラで生き残る方法
:ある日小説の中でエキストラになってしまいました。
W. はい
時間は止める方法がない。たとえここが現実ではなく小説の中の世界であっても、その事実に変わりはなかった。やがてここでの時間は現実とは違うふわふわするまでして、ある日は一日の朝に二日が、ある日は一週間が、またある日は二ヶ月という時間が流れてしまったりもした。 1年生3クラスだった私が数日新しい2年生1クラスになり、また数日新しい3年生6クラスになる不可能なことが起こった。銀河別高校3年生6半のキム・ヨンジュ、2番目の高3というひどいことを経験し始めてから、1日目に、ついにキム・ヨジュが口を開いた。
「あるじゃない、俺、…テヒョンが好きだと思う…!」
眠気でいじめた目が点滅した。半分置いていたシャープをつかみ、私が目を呼んで叫んだ。何と言う?その勢いに押されたキム・ヨジュが殴りながら後ろに退くのを私のようにピッと立った目を呼んだクォン・ヨンヒが防いだ。何、何、何?あなたは何をしたの?と聞いている声は多級になるまでして、当최私たちがなぜこのような反応を見せるのか分からないという表情でキム・ヨジュはもう一度言った。私… 、
「テヒョンが…好きなようだな……」
新石よ、始発、いよいよ… !鼻先がゆがむ感じに急いで鼻水などをつかんだ。クォン・ヨンヒは首を濡らしたまま鼻をぶら下げた。途中に置いたキム・ヨジュだけがこの状況をとても理解できないように目だけが点滅するだけだった。そんなキム・ヨジュの隣にしっかりついてこのすべての状況をじっと見物していたイ・ユジンが割り込んだ。なんだ、なんだ、
「なぜこんなに過敏反応なの?
「何?!いや?!」
「嫌いになるだろう?」
「え…、じゃあ幸いなのに…」
…もしかしてあなたは泣いて… ?当初理解できないという表情でイ・ユジンが尋ねた。あなたは理解できないそのような事情があります… !私は泣く表情でクォンヨンヒを見ました。感激に濡れたクォン・ヨニの顔が見えた。私たちはお互いの手をしっかり握ったまま感激の涙を一滴流した。始発、いよいよ… !
だから、女子高生なら一度くらいのキム・ヨジュの「私の好きな人ができた」発言に私たちがこれまで過敏反応を見せるのには理由がある。高校、いやおそらく中学校時代からずっと続いてきたキム・テヒョンの純情が高校3年生になってこそ行われる可能性が少しでも生じたということから来る感動だけでなく、それよりはるかに複雑で、個人的な事情がいっぱい入った理由が存在するということだ。クォンヨンヒと私を涙にしたその理由についてじっくりと話してみると、時間は私とキム・ヨジュの拉致事件があった日のすぐ次の日、私がクォンヨンヒの家で束ねられた枕を顔に上げたまま目を覚ました日にさかのぼらなければならないだろう。
📘 📗 📕
その日が有毒特別だったかそういうことではなかった。
「それは終わりですか?何もありませんか?」
「…ないのに」
「それは本当にどこのウェブ小説サイトにも載せたら、なんでこんな虚しい結末が全部あるのかと貪欲だったような結末なのに」
「……。」
クォンヨンヒの口が突き出てきたのも同じだったが、私のアルバではなかった。氷が半分溶けたイチゴスムージーをしっとり、吸って飲んだ。ミンミンな味が気持ち悪く口の中を振り回した。いやいや、むしろいいかも… 。という私の言葉にクォン・ヨンヒが首をうなずいた。はい… 、
「代わりに完結までそんなに長くかからないからな…」
「だから。キム・ヨジュとキム・テヒョンと付き合って初デートしてキスぴったりすれば織った!完結です!これじゃないの?」
「…そうなんだけどなぜ気分が悪いの?」
「元の人はあまりにも合う言葉だけ聞いても気持ち悪くするじゃないか」
学校を抜いてほぼハンナー節をクォン・ヨンヒとついていた点において、あー、という感嘆師を吐き出すことができるだろうが、そのハンナーという時間の間に山に閉じ込められるとか、拉致されたりとか状況ではない高校生たちが時間を過ごす法的なもので満たされたことから。友人の家で寝て起きて朝を食べて、昼食までまた増えて横になっておしゃべりして、ハンバーガーを食べたい-、という私の言葉に食べに行く?クォンヨンヒに沿ってバーガー王でハンバーガーを食べ、その後、かき氷とティラミス、そしてスムージーまで完璧にジョジョガしておしゃべりをする日がそうだった。
「ただ、大体「キム・ヨジュとキム・テヒョンが付き合うことにした。完璧なデートをした」こう書いて片付けてはいけない?」
「なるの?それなりの開演性とプロットがあってこそ、この世界が私が書いたように流れることができる」
「本当に面倒……」
以前の話を取り出してみたら、良い雰囲気に流れていかない私たちの間に、会話のテーマが自然に小説の方に流れたのは当然のことだった。しかも昨夜の会話で小説の中で暮らしたいという考えが変わったりしたのか、小説から脱出することに積極的に出るクォン・ヨニのおかげで、さらに小説に関する話をするしかなかった。まあ、私も小説の中でもう一度入試地獄に陥るつもりは追悼もなかったので喜んでクォンヨンヒの長短に似合ってくれた。実際、この世界から出る方法を知らない私たちができることは、小説を完結させることではなかった。
だから私たちの立場では、一日早くこの小説を完結させることがかなり重要なことだった。そのためにはクォン・ヨニが小説の展開を少しでも早く作ることが重要だった。これまでやったように小説を開けて直していく。問題は、小説を開け直すのがかなり面倒だという点だった。キム・ソクジン、パク・ジミン、そしてチョン・ジョングクがこのファンピック… 、いや、小説について知っているほど、その時その時代の女子高生たちの間で流行していたこの小説はすでに完結に近い状態だった。すでにみな編まれた物語を切り直すためには、切り離された場面に対するそれなりの開放性が必要であり、小説の流れが自然でなければならず、元の小説から大きく抜け出さなければならないという条件が存在するだけに、話を切り直すのが面倒になったのだ。
「それらの条件を全て合わせても私を殺そうとしたの?
「ああ、ごめんなさい!!生涯懸念を食べるつもりだよ!!!」
「当然じゃない~」
クォンヨンヒのスパイシーな手のひらが私の右前腕を襲うため、私は悪!という悲鳴を上げなければならなかった。とにかく、そのような条件をすべて考慮して小説を解消しなければならないので、「完結」という状態に達するためにはかなり長い時間がかかるかもしれないとクォンヨンヒは言った。それは仕方ない。という私の言葉にクォン・ヨンヒが大体首を走り回って言った。それでは?だから意見を見てください。
「どんな意見?」
「キム・ヨジュとキム・テヒョンを続けてくれる名分。
「まぁ…、大体彼氏とやってみたことを入れても大丈夫じゃない?」
「……。」
「…まさかモソ?」
今回は左前腕だった。前腕にはっきりと熱が上がった。
「ああ、痛い。ちょうど大まかに書いて! クリシェを殴り込んで、まあ出版するわけじゃないのにそんなことを悩んでるんだ!私がここに来て見たシーンだけ数回、それをまた憂慮しても完結まですぐだ!」
「何!何を見たの?」
「売店で炎兵してたんだ!仲良くなったときに炎兵してたんだ!体育大会のときに炎兵してたんだ! そんなことうまく使っただけ! おかげで僕の目だけ辛かった!!」
テーブルにこぼれてきらめくように吐き出した言葉にクォンヨンヒは特に納得する気づかなかった。相変わらず猛烈にするだけで、このようなアイデアを出さない私が腐った役に立つとは思わないかと思ったし、消すとし、残りのプロットはゆっくり考えてみるという答えを出して席を立てるのだった。スムージーが込められていたカップを返却し、道具だった。助けても大騒ぎだ、という言葉に役に立たない、とクォンヨンヒが当たった。それにしてもカフェの前で別れる前に私の手に包んだティラミスを聞かせてくれる格好が結構可愛かった。ツンツン待ち。
文を少しずつ見てみようとクォン・ヨンヒがふらっと行ってしまったために時間が崩れた。下校時間に近いものを見ているので、多分私の時間が崩れたのがクォンヨンヒのためではなくクォンヨンヒのおかげかもしれないと思った。だから、キム・ソクジンや会って恋愛遊びやしろというそんな無言の配慮かもしれない…。 。政治なしに浮かび上がった足取りが決まった。学校が終わる時間に合わせて正門に到着し、途方もなく下校していたキム・ソクジンを捕まえた。どんな反射作用であるかのように私を見るとすぐに、ファールル燃える耳がかなり可愛かった。いつもフットプトなカップル劣らないデートをするずっと本物の高校生でもなく高校生のように求めるキム・ソクジンが笑ってしばらく笑った。
「高校生の時は制服を着て遊園地デートするのが願いだったのに」
「しなかった?」
「…お前はたくさんやったかより?」
「……。」
「よ」
「ああ冗談だよ、冗談」
熱が受け取った拳をキム・ソクジンが片手で包んだ。いたずら、いたずら、と言って手を挟む姿がそんなに憎むことができない。手の甲に短く口を合わせたキム・ソクジンが笑った。

「あなたとだけやるよ」
それがなんでも、口尾をそっと上げて言うその姿に、私は怒らずに彼の手を力づけて握るしかなかった。ワルマヤ、キツネが別にない!
こういう話をしようとしていたわけではなかったようだが、まぁ、私はその日、一日も憑依されたまま住んでいた他の日とは別のことがなかった日だったと言いたかった。連れて行くというキム・ソクジンをあえて断らずに家の前までつけてきたのもそうだった。そこで顔色がとても、真っ白く飽きたクォンヨンヒだけ向かわなかったなら、おそらく最後まで平和な日に残ることができたはずだ。
「なんだ、クォンヨンヒ?」
しばらく前に家に帰った子供が他人の家の前で顔色が真っ赤になったまま足だけを動動転がっているので心配にならないことができなかったのであった。声に謙虚さを込めて名前を呼んだら、なんでなのかすごくなった目をしては首を回す。家から追い出されたのですか?おまえですか?と水を鳥もなくクォンヨンヒは私とキム・ソクジンに向かって狂ったように走って来たら、ウェン工策一つとボールペン一つを握った手で私の手をダブソク捕まった。そして言うことだった。
「おい、台無しだ」
「何が?
「書かれていない」
「何?」
「文が書かないと……」
一体これがどんな大変なのかと思うが、少なくとも小説の中に閉じ込められた状態である私たちには本当の世界が滅びるかもしれない!級の大事だという事実をちょっと分かってほしい。めちゃくちゃ、お前が小さいけど書かないとどうしたら… !すぐにでも泣きそうなクォンヨンヒの顔が見えた。
どうやら脱出はとても遠い未来になるのではないか、という悲しい予感が聞こえた。こんなくそ… 。
📘 📗 📕
秋は日交差が激しい季節だった。昼間は汗をかき混ぜるほど暑い天気であったとしても、日差しになったら上着をちょっと手に入れよう…。 !という後悔が聞こえるようなそんな季節。だから私は半袖姿のクォンヨンヒが風邪をひく仏像死を防ぐためにも彼を私たちの家に持ち込むしかなかった。隣で私たちの対話を半絶も追いつけずに恥ずかしい表情だけ作っていたキム・ソクジンはおまけだった。
「今、水」。
パニック状態だったクォンヨンヒをソファに引き寄せておいて美的に近い水を与えた後にこそ、クォンヨンヒが言った「文が書かない」という言葉の意味が理解できた。
「だから、さっき言った通り完結を早めようとキム・ヨジュがキム・テヒョンに反する視点を早めたくて、」
「うん」
「原作から2~3年にわたって出てくる内容を半年以内に起こる事柄に変えたのに、」
「うん」
「…そうだったけど、キム・ヨジュがキム・テヒョンに惚れないって?」
「うん…」
正直に言う。半分は理解し、半分は分からなかった。惚れさせたのに惚れなかったのはなんだ?ただ「キム・ヨジュはキム・テヒョンにひどく惚れてしまった」こういう文だけ書けば終わるのではない?本当に幸いにも、この状況の簡単な説明を兼ねて聞いたキム・ソクジンさえもクォン・ヨニの言葉を完全に理解できなかったようだった。幸いだ、私だけが愚かではないから。有利な表情で頭だけかすかな私たちをよりできなかったクォンヨンヒがため息をつくように懇願に大切に抱いていた公策一冊を下ろした。久しぶりに使っていたように、どこか古いティーが出る公策だった。
「ええ、自分で見るのがもっと早いだろう…」
おなじみに公策を分けたクォン・ヨンヒが速い手のノリで紙の数枚をすっぽり渡した。目でいろいろな文章を盛り込んだが、内3分の2程度になる地点で止まったクォン・ヨンヒが指を伸ばしてノートの中を指した。ここから読んでみて、言葉に私はキム・ソクジンと頭を合わせて文字を読んだ。
「キム・テヒョンがキム・ヨジュの手首を握った。
「おい!誰が声を出して読んで?」
今回は背中だった。厄介!という声とともに背中で感じられる熱い感覚に、私こそ悲鳴が出る地経だった。恥ずかしい日に恥ずかしい表情で見たクォン・ヨンヒが公策を奪った。お馴染みの公策の一ページを繰り広げたクォン・ヨンヒがまだ空いている部分にボールペンを持ってきて言った。見て!もうキム・ヨジュがキム・テヒョンに反したという文章だけ書けばいいのに、それを書けば…
'キム・ヨジュは考えた。たぶん自分がキム・テヒョンが好きなのではないだろうか」
'… … ㅈは考え… … 。たぶん… ㅅこのキム… ㅎ良い… …あああ… … 、
「…なに?!」
文字が消えた。痕跡も残らず消えてしまった文章に出てきてキム・ソクジンが目をうんざりして公策を眺めた。そんな私たちの反応にため息をついて、私のチュンヨンヒが言った。だから… 、
「私が書かないと言ったじゃないか…」
いや、こんな物理的な状況を言うとは想像もできなかった。
クォン・ヨニの言葉によれば、このように文字が自ら消されるのは小説のプロットを変化させるにあたって条件を満たさなかった場合に起こる事だとした。
「例えばこんなのはよく書かれたんだよ」
クォン・ヨニがボールペンを持って公策にムアラ振り回した。 「キム・ヨンジュがキム・ソクジンのボールに口を合わせた」インクが紙に染み込んでそのまま文章を作った。文字は消えなかった。幼稚園生でもなく見ポッポラニ、という考えは私の大切な背中のために中に埋めておいた。
「流れ上、もっと自然な内容はキム・ヨジュがキム・テヒョンに反したという方だと思うが?
「それは…キャラクターごとにそれぞれ特徴があってそういうのに…、」
クォン・ヨンヒが返らないように呟き口を開いた。
「…こんなの、お前はここが小説の中の世界であることを知って、既にプロットが変わる経験もたくさんしてみた。だから無意識的に「ここでは何が起こってもおかしくない」と思っている。 「あ、小説の中だからこんなことも起きるんだな」と軽くめくるんだよ」
「でもキム・ヨジュじゃない?」
「うん。キム・ヨジュは憑依者ではない登場人物だから。 そっとはここが現実であり、現実で起きるようなことではないと判断すれば'そんなことない」と思うようになる。 「君はキム・テヒョンが好きだ」と言ってみたら、キム・ヨジュが「そんなことない」と思えば全く役に立たないのだ」
「ちょっと、どうせもともと小説ではキム・ヨジュとキム・テヒョンと続くじゃない。でもなぜそんなことないと思うようになるの?」
「要旨は続いて馬鹿の問題ではなく「いつ」続くのか……キム・ヨジュはすでにキム・テヒョンに好感がある。しかし好きだとは思わない。それは言えないことだから。
…この頃になるとキム・テヒョンが哀れになる地境だった。いや、いくらでもそうです、もうキム・テヒョンにすっかり抜けそうなことも何回あったって?私はクォンヨンヒの公策を裏付けた。キム・ソクジンとデートを楽しむわずか数時間、クォン・ヨンヒはすでに数十のときめき主義エピソードを書き留めた。一般的に「ああくらいならサムジ~」の間で起こる法的なことがかなり多かった。はい、それでは今作るだけです!という声が自然に出てくるほど、キム・ヨジュとキム・テヒョンのお互いに対する好感度は着実に積み重なっていたということだ。そして、そんな気がする恐ろしく私の頭の中で、ある仮定が一つ浮上した。
ガールストークの最も主なテーマというのはまさに恋愛ではないだろうか?そして、サムサムオオ集まってガールフレンド同士その「恋愛」について話すとき、必ずこの種の人がいる。
「…いや、や、もしかして尋ねるのに…、」
最悪の家庭が頭の中に浮上した。
「…キム・ヨジュモテソロじゃない?恋愛してみたの?それ?」
「……。」
「ああ、どうぞ」
自己感情を混乱させようとする子供たち。
恋愛は苦労して自分がその人を好きかどうかについての確信からない子供たち、必ず一つずつある。これが恋愛感情なのかもしれない子供たち。私は頭を握りたくなった。誰の頭を?キム・ヨジュの頭を… 。そう、私たちの無邪気なヒロインキム・ヨジュは、他のロマンス小説のヒロイン共に他人が経験しないような経験、例えば拉致とか、いじめとか鉢植えに頭を合わせる事とかすることはすべて体験しておき、一番重要なことの一つはできなかったことだ。
「…私たちの女性は天然だと…」
'恋愛'、ちょうどそれ一つだけできず見て私のように大変にする。涙が出そうです。くそー。
📒