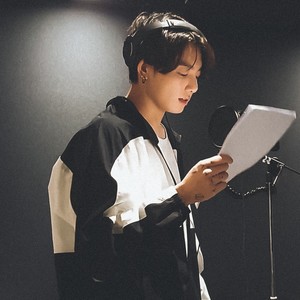- 作家が少し正気ではない状態で書いた。
- 一体何なのか作家も知りません。
- なぜ書いたのか作家も知らない。
- クリシェの塊。
- 軽く読んでください...とにかく、開拓性の犬がくれた混乱の文章です...
- 女主の元の名前が出てくる部分はわざと空にしました。読者の名前を入れて読んでください。
-TRIGGER WARNING! 2010年代初めに流行していたインターネット小説を背景にしているため、学校暴力を連想させる場面があるかもしれません。
エクストラで生き残る方法
:ある日、小説の中でエキストラになってしまいました。。
W. はい
なんでもみんな分かってふりをするキム・ヨジュが実は恋愛告者だった。今、キム・テヒョンとキム・ヨジュの恋愛を成し遂げなければならない私たちの立場ではこれよりも困難なことはないだろう。いろいろな方法をすべて試してみると、結局「時間が答えだ」という結論を下すまでにはそれほど長い時間は必要なかった。十日、やや十日だった。たった10日で、私たちはキム・ヨジュとキム・テヒョンの前に両手両足を持ったまま降伏を叫ばなければならなかった。
過去10日間本当に星をつくった。浮気の役割はもちろんであり、わざわざキム・テヒョンとキム・ヨジュの2人だけが残る状況を演出したり、キム・ヨジュにキム・テヒョンに対するあらゆる種類のティエムアイを注ぎ出し、キム・ヨジュの関心を思わせて赤ちゃんなどした。本当に涙のない努力ではないのに、私たちのヒロイン、キム・ヨジュは一様だった。一様にキム・テヒョンに異性としての関心を置かなかった。クォン・ヨニの言葉によれば、キム・ヨジュもキム・テヒョンにある程度の好感がたまっている状態だとは言うが、まあ、キム・ヨジュの姿だけ見れば、そんな感情は全く見えないせいでさらに目の前が暗くなった。とりわけ、いろいろな方法を悩んで笑うこともない事故一つを打った後にはさらにもっとそうだった。すぐにでも殴りたい気持ちが満満だった。台無しに。
だから、その「事故」とは、私が小説の中に落ちた後女主人公が経験するような拉致、監禁のような重犯罪なことを言うのではなかった。なぜそういうものよりも黒歴史にもっと近いことだったと言えるだろう。くそー、そのことを再び思い出すだけでも、首筋に熱が上がるようなのに、おしゃべるか。とにかく、そのことが起きた日も、いつもと変わらず非常に穏やかな日の一つであった。ランチを食べた後、運動場スタンドに飲み込んで売り場で打ち明けたスナックを食べる、とても平凡な一日。キム・ヨジュとキム・テヒョンを少しでも早く続けてくれるため、二人だけ捨てて走る試合であり、スタンドまでウダダ-、走って行ったことまでそうだった。私トイレ - と、イ・ユジンがしばらく席を開いたやいなや私を含む憑依者5人は遠くからドランドランの話を交わして歩いてくる予備カップルのペアを見て深いシルムにロックした。
「…何の方法がないの?」
「これもすでに4日間でしたが、どうしてそんなに進展がないのでしょうか?」
「私たちにも4日だから、ジャネにはもう2週間を超えたから…」
「じゃあもっと深刻なんじゃないのか…、あのサムだけ2年乗るんだけど、本当に」
「おい、黙れ。言葉が種になることがあるから。」
暗鬱なペアのない会話にため息だけをじっと出した。あんなによく似合うのに。つぶやきは私の言葉に誰もが頭をうなずいた。それほどキム・テヒョンとキム・ヨジュはよく似合う一組だった。ソンナム先生。だから今、私たちの中でちょっとやめて、これだけ付き合えばいいのです。いつのまにか前まで近づいてきた二人を見て考えた。
「演奏よ!これ新しく出たジェルㄹ、ええ、」
「え、え!キム・ヨジュ!」
キム・ヨジュの体が傾いているのを見て冷ややかな私が体を広げた。階段形式になっている運動場スタンドは、その傾斜がかなり高い方だった。だからこのままキム・ヨジュが転がれば大きく傷つくだろう。急いで手を伸ばしたが距離があったために私がキム・ヨジュを捕まえるのは逆不足だった。思わぬ事故にみんな瞳孔だけを育てていた車に倒れようとしていたキム・ヨジュを捕まえたのはキム・テヒョンだった。
'キム・テヒョンがキム・ヨジュの手首を握った。 꺅!キム・ヨジュが悲鳴を上げた。
やっと꺄악―、というキム・ヨジュの悲鳴が聞こえてきた。 …こんなに危険なシーンでしたか?頭の中を通り過ぎる文章一つに私はこうなると分かっていたように平気な表情をしているクォン・ヨニを見つめた。まあ、する口の形を作り出したクォンヨンヒが指でキム・テヒョンを指した。捕まえたので、いいじゃないか、そのようなその姿に私はため息をつくようになった。クォン・ヨニの言う通りキム・ヨジュはいつの間にかキム・テヒョンの品の中にとてもコオク、抱かれたままだった。
「こんな場面とは言わなかったじゃないか」
「きちんと読んだはずだ。そして、こんな場面が積もって積もらなければキム・ヨジュがキム・テヒョンをちょっと異なって見るきっかけになれば…」
「……。」
「…それとも付き合うのは選べない…」
…合う言葉で涙が出そうだ。とにかく、必ずしもこのような危険な要素ではなくてはならない言葉で、このような場面は少し自制してくれた私の言葉にクォンヨンヒは肩をすくめた。そうなんだ、という震えた答えと共に。ふわふわした表情でクォン・ヨンヒを見つめた。知らないふりのゼリーだけが、뇸뇸食べる姿がなんて不気味だった。それさえキム・テヒョンの萎縮を受けて私の隣の席に座るキム・ヨジュのおかげで視線をはずさなければならなかったが。けがをしていませんか?という私の言葉にびっくりしましたが、大丈夫だと言います。ああ、何かもっとあるようだが。何かを真っ黒に忘れて食べたような蒸し気分が聞こえた。突き刺された眉間にキム・ソクジンの長い指が触れた。
「なぜ印象を書いて」。
「いや…、何を食べたようなのに、それが何なのかわからない」
キム・ソクジンが首を傾けた。重要なのかと聞くその言葉には眉だけを刺した。わからない。わからないけど… 、なんだか食べてはいけないことを忘れたような感じなのだろうか。蒸しさが格別だった。それでも記憶もできないのを一日一日中捕まえて愚かなことはない法なのかなので、私はあまりないだろうな、という安日の考えで蒸しさを引き渡してしまった。それが問題だった。
昼休みが終わる頃になってからスタンドで体を起こした。それと同時に背中に不気味な気味が浮かんだ。あれ?やる気もなくすごく異質な気がした。久しぶりに感じてみるこの感じが一体何なのか気づいた鳥もなく私の体がぐるぐる―、返された。なんだ、なぜ以来?やる気もなく体が厄介に動いた。そして頭の中に通り過ぎる文章一つがあった。クォン・ヨンヒが大抵振り回した文章一つ。
「キム・ヨンジュがキム・ソクジンのボールに口を合わせた」
…これは少しではない!消したの?突然の私の行動にみんなが恥ずかしい表情で見つめながら、面白くて死ぬという顔をした人はクォン・ヨンヒしかなかった。イ、イ、お前みんな知りながら… !すぐに悪口が口の外に飛び出すようだったが、すでに私のコントロールから抜け出した体は私の意志とは関係なく、そのままキム・ソクジンに突進した。当惑した表情で私を見つめていたのはキム・ソクジンも同じだった。何か奇妙だと彼も気づいたようだったが、すでに遅れていた。遅くてもしばらく遅れた、めちゃくちゃ。すでに書かれた文章を抜ける方法はなかったので、
ちょっと、
-する男爵の音が聞こえた。
「…始発、」
キム・ソクジンの顔が真っ赤に盛り上がった。私も同じだった。体が再びきちんと動き始めるのが感じられた。みんな、私はキム・ソクジンだけを見ているようなものが負担で恥ずかしくてすぐにネズミの穴を見つけて迷い込んだ心情だったが、それよりは顔に面白くて死ぬと書いたまま笑いを押して我慢するクォン・ヨンヒを凝徴する。
「プハハク、」
「…いや、お前来て!!!」
「クッ……」
クォン・ヨンヒの笑い声を皮切りに前政局がぎっしり押し込んだ笑いを流した。ああ、台無しに。何と言う鳥もなく笑い板になってしまったせいで恥ずかしさはお腹になった。パク・ジミンが息をのむように笑った。私は何も言わなかったと言って、笑い声でいっぱいの声で叫ぶパク・ジミンの口に何でも選んで入れてみたくしたいという考えがいっぱいだったが、このすべての仕事の元凶であるクォン・ヨニを追い出すだけでも私の体脂肪は忙しかった。恥ずかしい、くそー。耳元がまっすぐに上がった。
📘 📗 📕
「そんなこともあった……」
ささやきの前のことだったのに、しばらく前のことを思い浮かべるようなパク・ジミンの言葉に笑いをかけた。冷淡な反応にも一杯で息を切る直前まで置いておびえて食べるというパク・ジミンの言葉には結局クッションを投げ出さなければならなかったが。作ってください。イライラが存分に込められた声でパク・ジミンに向かって警告を発したが、そのような言葉を聞いて処罰するパク・ジミンではなかった。くそー。
相変わらず思い浮かぶだけでも恥ずかしがりがなく、両ボールが熱く盛り上がるような錯覚を与える経験だったが、率直な心情ではこのことでキム・ヨジュが「恋愛」ということに少しでも関心を持たないかという期待はあった。なぜ、もともと他人の恋愛が一番面白い方法だと、誰かが恋愛する格好を見るだけでも恋愛細胞が生き返る場合も王王いないのか。して期待した。もしかしてキム・ヨジュが「恋愛」について一度でも考えてみたことがなかったのだろうか。まぁ、もちろんボルポポ一度やったってこんな思いをするのもちょっと面白かったんだけど…。 、
「…何を書いたの?」
「いや?全然?」
幼さもない音だった。公責と贅沢なクォン・ヨンヒが迷惑をいっぱい込んで吐き出した答えに、私はジュサムジュ島拾ってきたクッションに再び頭を打った。まだ書いたとすれば、隙間に消される「キム・ヨジュはキム・テヒョンが好きだ」という文章一つがそんなに憎むことができなかった。私の分に勝てず、公責を払って拾っていたクォン・ヨンヒが逮捕した。まあ、そもそもその文章を百度書いて作られる感情だったら真即キム・テヒョンとキム・ヨジュが付き合っても残ったのだろう。公策がボロボロになるまで書いた文章だったからだ。
「あお、なんでもちょっとやって!」
分痛がひどい表情でバラク悪を書くクォン・ヨニの姿にもリビングにいた彼らの反応はシクドンだった。 10日だった。なんと10日。それも私たちの時間で10日しかなかったし、キム・ヨジュの時間で考えると、ほぼ一ヶ月であっても2週間に近い時間が流れたわけだった。下服を脱いで春秋服を取り出して着て、すぐにあればパディングを取り出して着る季節が来るのにまだ!キム・ヨジュは鉄壁そのものだった。
「できません、しないでください。キム・ヨジュは自然ではありません。」
「猫が天然でなければ一体何だ」
「鉄壁だよ、鉄壁。オリハルコンで作られた鉄壁」
「は……。」
あふれずに飛び出したキム・テヒョンの愛情がそっくりキム・ヨジュに向かっていたという事実は通り過ぎていた猫も雪だらけだと舌を蹴って行くほどはっきりした。しかし、キム・ヨジュは知らない。いざその事実を最も知るべき人は知らない。最も重要な人は知らなかった。それが問題だった。
普通、このような場合には、隣にいる友人が「ええ、それくらいならあなたも好きなんだよ~」、というニュアンスだけが漂っても「え、そうなの?鋼鉄を越えてオリハルコン級の鉄壁でなければやり遂げられないことをオリハルコン鉄壁を持ったキム・ヨジュが作り出す。他人の目にはみんな見える愛情が私ではなく、断定するせいだった。当初からキム・テヒョンとキム・ヨジュ私の間に存在することができる感情は友情から流れ出る愛情だけだと断定建ててしまい、それ以上を見越すつもりもないのだった。おかげで欺かれるのは私たちだった。 「キム・ヨジュはキム・テヒョンが好き」その事実を少し悟らせてくれるために流したあらゆる言葉に対する反応が――
「ヨジュはキム・テヒョンはどうですか?」
「テヒョンは?いい友達ですか?」
友だちと線を引くだけでなく、
「ヨジュはキム・テヒョンを見ながら素敵だと思ったことがない?」
「うん?テヒョンがカッコイイー、」
「さて、素敵ですか?」
「うん!ハッ、もしかして演奏お前のテヒョンが好き?」
「…狂った?」
キム・ソクジンとずっと付き合っている渦中にあんな誤解を一度受けて出たら意欲がみなサグラドすることだった。できません。キム・ヨジュが私の感情を悟らせる。このクエスト完了報酬が現実世界に即座に帰還しても、私は別の方法を探して迷うだろう。絶対できないほど明確だから。ソファに伸びたままため息だけをふわっと出した。今はキム・ヨジュの鉄壁に団結することができず、たてがみを引き裂く直前のキム・テヒョンの純情が残念に泣かなければならないのか、高3という地獄のような1年をもう一度過ごすようになった日のために泣かなければならないか感も取られなかった。
厨房でダルグラクの声を出したキム・ソクジンがトレイを持って出た。キムがポールポール湧き上がるマグカップの一つを私に渡し、残りはテーブルの上に大体上げてしまう。甘い香りが漂った。マシュマロが丸みを帯びたハッツチョコに、自然にグジッとした表情がサルル解けた。ホロク、という声を出してホットチョコを一口留めた。甘さが口の中でいっぱいに広がった。
「どうせ続く子どもたちなら、私たちがあえて何をしようとする必要はないのでは?」
甘い香りに導かれ、ゾンビの群れのようにテーブルにスルムスルム近づいてきた彼らの目つきがキム・ソクジンに刺さった。ほとんどがどんな犬の声なのかというような表情なので、キム・ソクジンがすっかり体を震わせた。私も同じだった。 2番目の高3を落ち着かせたいかという言葉が喉まで飛び出した。
「だから何もしていないわけじゃない」
最も早く表情を唱えた前政局が語った。彼の言葉だけでなく、私たちの現実はここではありません。一日でも早く現実に戻るためには、一日も早くキム・テヒョンとキム・ヨジュを続けなければならない。そうしてこそ完結が現実に戻る方法かどうかを判断しない。もし小説が終わったのにまだまだ残っているなら、別の方法を探さなければならないし。チョンジョンククの言葉にキム・ソクジンが煌びやかな表情で首筋を触った。
「もちろん待ってみようという言葉ではなく…、時間を飛び越える方法もあるんじゃないから」
「…え?」
「なぜ、私たちの夏休みの時のように。」
誰かが聞いたらこれはとんでもない音なのか―、するが、今この席にいるこれらのうちキム・ソクジンの言葉を聞き取れなかった人はなかった。長い静的が流れた。それぞれの頭の中で様々な計算を終えた彼らがお互いの目に直面した。
これだ、正解を見つけた。
📘 📗 📕
結論から言えば、半ば成功した。クォン・ヨニに言うと、もともとキム・テヒョンとキム・ヨジュが続く日は韓国の高校卒業式の日だった。だから私たちの目標も自然に高校卒業式の日に時間をスキップすることに決まったが、いや違うかやはり「そんなに卒業式の日になった」という文章一つだけで2年半という時間を越えることは不可能だった。開演性をある程度気になるが、渡せる時間はパクパク渡してしまうのが最善だったという意味だった。そのように最初に、3ヶ月という時間を超えた。
「演奏よ!! 半割見た?
「ええ、見た、ヨンヒは?」
「あっ、ヨンヒは別の半分だよ…」
「これが致死に…!」
もはや面倒なことに編みたくない。これはクォンヨンヒと私がこの小説が展開されるずっと共通して持っていた考えでもあった。だから、異王の展開を飛び越えること、キム・ヨジュと南主人公たちだけが同じ半分に追い込まれ、私たちは他に反してはならないのか?と言ってクォン・ヨンヒを虐殺しただけは、致命的に私を含めて!キム・ヨジュとナム・ヒョンヒョンを2年生1半に追い込み、私は2年生7半に一人で落ちる蛮行を犯したクォン・ヨンヒのおかげで私はまた精神のない一年を送らなければならなかった。まあ、言葉がいい1年で、いざ私たちが銀河別高校の2年生として過ごした時間は数日余りだった。小説で時間があまりにもフックフック過ぎるのも悪いと言いながら肝幹が主となる事件が起きた日だけきちんと過ごした。
「今回英語がとても難しかった、それ…」
「…クォン・ヨンヒは実際には止まらない、私が」。
半割の翌日、まさに中間試験で飛び越えるせいで試験問題の半分を鉛筆を転がさなければならなかったのもこのためだった。クォンヨンヒこれ、バックプロわざわざそうだ。もちろん、もともと同じであっても勉強をそんなに頑張らなかったはずだが、ハーフィルなら中間試験の日でタイムワープをさせる靭性は一体何と言うのか。雨が降る試験紙を持って下校したが、お母さんに背を向けずに合わなければならなかったのもクォン・ヨンヒのためだ。台無しに!
夏休みは静かに通り過ぎた。先日の夏休みが瞬く間もなく消えたように、今回も特に変わらず休暇式のすぐ翌日が開学式になるでしょう。とにかく私たちの目的は早い完結だったので、2年生2学期といって前と大きく変わったことはなかった。ある学期が数日で終わった。修練会と第2のキム・ヨジュ拉致事件(キム・テヒョンに対するキム・ヨジュの好感度を上げなければならないため、必ず入れなければならない話だとクォン・ヨンヒがこだわった。)を除いた残りの日は私たちが直接経験できなかった日となった。ここまでかかった時間がわずか3週間だった。約20日という時間が経ってから、私たちは3年生になった。
「あるじゃない、俺、…テヒョンが好きだと思う…!」
この頃になるから1年も早くこの言葉を聞いたクォン・ヨンヒと私が泣いてコトザンなどを付与したのも無理ではないと思う。長くて長い戦いだった。
キム・ヨジュがキム・テヒョンを好み始めたからといって、私のエクストラ人生がすぐに終わるわけではなかった。小説の完結は二人が交際を始めることだったので、キム・ヨジュがキム・テヒョンが好きだという次の爆弾発言を聞いた後も私は-ではなくキム・ヨンジュとして残っていた。付き合うのにどれくらいかかるか、という心配が先に行ったが、いくら行かず洗ったように消える心配だった。なんだかキム・ヨジュの言葉を聞いた後からクォン・ヨンヒの顔で悔しさとは目を洗っても探すことができなかったが、これからは続転速決というクォン・ヨニの言葉を私はすぐに完全に理解できた。
もしこの小説の女主人公であるキム・ヨジュがサツマイモ百個をのどに選んで入れてサイダー一滴を与えるかと思うリュの女主人公だったら、おそらく私たちは高校3年生、受験生活を結局無理にしなければならなかっただろう。しかし、私たちのヒロインキム・ヨジュは自分の感情をきちんと悟った瞬間からブレーキが故障したスポーツカーのように転がった。ただ直進だけが答えだ-、するように無作為に押し込んだ。キム・ヨジュが私たちにキム・テヒョンを好んだという事実を打ち明けたか、わずか3日になった日に、二人が恋愛を始めた。それもキム・ヨジュ主導のもと。 「テヒョンがあなたと恋愛したい!」雰囲気とは何もない、ただ私の感情だけが先の告白だったが、キム・テヒョンの顔を真っ赤に染めるには十分で残る言葉だった。告白さえもあまりにもキム・ヨジュらしかったのでもっとそうだった。
そう、私達はこの小説の終章に達した。
📘 📗 📕
「…よくやってるだろ?また変なことに巻き込まれてデートパトナじゃないんだろ…?」
「お願いします。 釘をやめてください。あなたはキム・ヨジュのお母さんですか?」
「あなたの足をどうやって言うの?
最後はただ待つだけだった。よく行っていたカフェの隅に5人が集まってシシコールコールな話をしても「ヨジュはデートうまくやっているか」と何度の心配をする、待つ。
「帰ってきたら何してるんだ。スXイーザーマン4封切りしたのにもう開封したんだろ…?」
「私はドラマ…運転しなければならない…」
「私はビールを食べたい…」
パク・ジミンがテーブルにこぼれ、言葉に誰もが唾液を飲み込んだ。ハーピルならば憑依しても高校生で憑依したせいで、憑依した後には強制今週生活を続けていた車だった。ああ、人生児。これまで経験したことを考えてみると、アルコールを一滴もなくそのすべてを耐えたのが不思議になりたいと思っていても、ビールの一口がそんなに切実になったということだった。
「出て行っても集まってお酒を飲んでほしい」
「いいねー、あんたは本物のガレージ溢れるね」
「ここにあったことだけでも何本か」
「クォンヨンヒは私たちの酒席を持っているたびに布団キックする必要はありませんか?
「やあ!!」
「あ~さっき~、ここ作家様じゃないですか~!」
「ああ、イライラ!!」
「こんなに集まる必要もなく俺とキム・ヨジュだけ集まったら…、…あ…」
沈黙。誰も簡単に口を離せなかった。ああ、そうです。女主は、いない… 。改めて事もない事実なのに、いざ口の外に吐き出してみると気持ちがおかしかった。私たちの現実にキム・ヨジュはいない。加えて、理由進道。私の表情が暗くなるのを見たキム・ソクジンが私の手をそっと握ってきた。
「いや、キム・ヨジュは「全部過ぎたから大丈夫だよ~」そうだろう。
そうではありませんか?キム・ソクジンが遊び心いっぱいの声で話した。それながらもしっかりと掴んだ手に力を強める。まるで心配するもの一つないように、自分がここにいるから大丈夫だと言うように。沈んだ雰囲気は前庭の笑い声を皮切りに再び浮かぶ。クォン・ヨンヒをからかうのに誰よりも本気であるパク・ジミンがカンジョク通りを始めるからクォン・ヨンヒが忙しく性質を呼ぶ。私も笑い声を上げた。無理やり作り出す笑いは決してなかった。キム・ソクジンの肩に頭を散布する際に寄り添った。今は体まで立ち上がっていたずらする人々の姿を目にした。キム・ヨジュはないだろう、私たちの現実には。それでも大丈夫そうだという気がした。だよ、キム・ヨジュはここでも十分幸せだから。耳元にキム・ソクジンの騒々しい声がくっつく。
「大丈夫」
「……。」
「私はずっとあなたの隣にいるでしょう」
それで十分だった。
時遅い夕方のために場所を移しながらも、キム・ヨジュも、イ・ユジンも呼び取ると頑固なパク・ジミンに結局携帯を聞いた。夕食を一緒に食べたくない私の言葉に喜んですぐに来ると答えを出したキム・ヨジュと、話してから5分も経っていないので、チューリニングにスリッパだけの質を引いて出てきたイ・ユジンを連れて私たちは近くのゴジプジに入った。
「叔母!! ここサムギョプサル10人分と撃つㅈ、うふ、」
「サイダ!サイダよ!コラランよ!」
制服を着たまま堂々と焼酎を注文しようとしてクォンヨンヒに口が詰まったパク・ジミンを見て笑いを放った。癖が怖いと、現実でさえも気軽に飲酒を楽しむ合法的な年齢だが、ここではひとつ高校生なのだ。注文を受けた主人のポケットが私たちを飛行青少年見るような視線を無視したまま、私たちは一生懸命肉だけ焼いた。しばしば焼酎が懐かしいというパク・ジミンの口をつぶさなければならなかったが。贅沢な雰囲気は酒なしでも十分に上がった。
遅れて到着したキム・テヒョンとキム・ヨジュにデートは上手かったかと驚いて食べ始めた以後はもっとそうだった。顔が燃えるサツマイモだけ真っ赤に盛り上がるキム・テヒョンと、バシー時笑うキム・ヨジュの姿はあまりにもカップルのそれだった。初デートにキスはしたか尋ねるパク・ジミンの口が再びクォン・ヨニの手にひっくり返ったりもした。いつは私たちのところで主策バーガのようだったが、今度は自分がさらに酒を浮かべた。八人がみんな一緒に集まった席はそうだった。みんなが浮かんでいたし、みんなが騒々しく騒ぎます。これが最後かもしれないという事実は、5人の中の奥深くに埋めたまま。
呼んだ船をつかみ、暗くなった夜の街をみんなで歩く時もそうだった。自然に学校に行きたくないという言葉が堕落のない高校生の姿だった。普段と違って私は何も言わずに後ろから静かに歩いた。すごい。パク・ジミンとクォン・ヨニ、イ・ユジン、そしてチョン・ジョングクとキム・ソクジンの後ろにキム・テヒョンとキム・ヨジュが静かに追いつく。つかまえた手が見えて良かった。やはりよく似合う。キム・ヨジュがキム・テヒョンの腕を引っ張った。自然にキム・ヨジュの方に身を牽引したキム・テヒョンにキム・ヨジュがムアラ騒ぎました。キム・テヒョンが小さく笑ったキム・ヨジュの手を置いた。キム・ヨジュはしばらく停止したいと思ったら歩く速度を減らした。私を見て、笑い、演奏!しながら。自然に腕を組む姿が愛嬌だった。
「どう思う?」
「明日学校に行きたくない?」
「そういえば制服だね!」
「あ、うん。どうしようか。…明日まで肉臭が出ないんじゃないだろ?」
私の言葉にキム・ヨジュがギャルルー、笑う。そして、いつもと変わらず気をつけていろいろな話を吐き出す。開中には今日あったキム・テヒョンとのデートについての話もあったが、パク・ジミンの不気味ないたずらにも平気に転がった先ほどとは異なり、耳元が少し赤くなっていた。可愛い期は、小さく笑ってキム・ヨジュの言葉に立ち向かった。そうだった?しながら。その後、キム・ヨジュは首をうなずきながら続けて話を並べる。いつものようでした。
「女主よ」
「うん?」
「幸せですか?」
だからもっと衝動的だった。キム・ヨジュが目を丸くした。それもしばらくの間目尾をサルル折りながら笑って見えた。なんかその姿だけ見ても答えを聞いたような気がして安心だった。うん。とキム・ヨジュが言った。私は幸せです。それではなった。キム・ヨジュはここで幸せでしょう。今回は推測ではなく、確信だった。私は口尾を引き上げた。今回も無理笑いではなかった。
翌日目を覚ました時は、見知らぬ天井が見えた。
📒