ここ、数字ない限り青年がいる。
年齢は約19歳、名前はない。
いや、奪われた。
介護者にしかできない子どもたちに
私たちは家も名前も国も失った。

[フラグメント]成長バケツ
その始まりは予告なんてなかった。昼と昼のジャトガリはいつものように忙しく、ハーブバスケットを運んで運ぶアナクネたちと何がそんなに良いのかを叩いた子どもたち、ゴジドン一つを掲げては自分のものが一番良い泣いた社内たち。すべてが普通の風景だった。その日は明らかに普通の日になることができました。
空襲警報が鳴ったのは新市警のことだった。誰もが突然の銃声に驚いて頭を上げた瞬間、何人かは点滅する光の中に跡を隠した。誰かは手足の片側を、誰かは子供を、親を、また誰かは処子式を食べて生かす様式と財産を失った。
一瞬だったのですが、最近は最も惨めだったその日。私たちはまだその日にとどまっていました。
テロ以来数回の季節が過ぎ、数え切れないほどの深い夜が流れた。恐怖に飽きた村人たちは、一様に家の外に出るつもりはなかった。彼もそうだろう、空襲ひとつで終われば幸い。純死者がスルムスルムル都市全域を占領したという話が聞こえてくるせいで何も知らない私たちのような人々は漠然と外のニュースを待つしかなかった。
しかも隣人のおじさんたちが乙女式飢えて死ぬように見えないと出て行ったが、声噂なしに消えたのが数ヶ月だったので、村ではさらに不安に震えるほかのない器だった。やや12歳だった私の事件の前末も知らずに母に沿って家の中だけに留まり、幸いにやっと食べる食糧を備蓄しておいたので、私たちはそれなりに平坦な冬を過ごした。
しかし生存は生存であり、私はそれに反してまだ気になることが多かった。例えば、父が普段追求してきた正しい生活を捨てられたということだが、毎回夜中に出て朝になる前に息を喘ぎ、細く大門を歩いてロックし、また書斎にこぼれて朝も教えて何かを絶えず作った。それが何なのかとても気になったが、次々と聞くことができなかった。
訪問の隙を越えて見下ろした父の顔は今まで育ってきて見たどんな表情よりも真剣で、また深刻だった。私はそれが何であるか全くわかりませんでした。ただ外の状況が珍しくないということだけやっと類推しただけで、10代前半の子供が受け入れるのは大変だった。
そう疑問が深いだけ行っていた中、翌年の春、父が純死者に引きずられて、私の人生も180度逆転した。
「早くついてきて!!」
「蜂蜜!!!」
家に入り込んだ純死者たちは、あっという間に父親をオラトゥルに突っ込んでしまった。ウエストダンスに冷たい刀を振り回して私たちを脅かし、未知の言葉を乱発して父をまた殴った。母は悪にさらされて音を立てた私の口をふさぎ、通弾スレ泣いた。
惹かれるように家の外を出ていた父の目つき、母と私を眺めていたその偶然の目に、一生の間見たことがなかった涙が一滴落ちた。口の形で「すみません」と言うこともできなくなったので、結局は閉まってこそ大門の外に足音はますます遠ざかっていった。
その日以来、私は再び父を見ることができませんでした。

それから約7年後、京城。
"さく(사쿠)!!"
「そこで何してる!!」
「あ、てつや(テツヤ)。しばらく休んでいた」
「何の音だ。少しあればパトロール時間なのかわからない?」
「早く入ってこそ刑務所に引きずられていないと」
難しく入学した学校で出会った友人、テツヤ。僕とは違うぐるぐる性格によくも笑う姿がチョンが行く友達だ。サクと呼ばれる私を卒業して通って時間にいつも外を徘徊する癖を直して置くのにアダルが出たようだ。
「刑務所…そこはどんなところだろう?」
「そこに入った人は生き返らないと言った」
「爪を抜いてつま先を切って、いろいろな拷問をさせた」
「そうして死んだら悲惨に捨てられるんだ」
「…悲惨に、捨てられると…」
父が惹かれたその日以後、母は私をもっと厳しく育てた。そしてすぐにすべてを教えてくれた。父が毎晩出かけた夜明けに入るしかなかった理由、それほど書斎を秘密裏に隠しておくしかなかった理由を。
雨が追跡追跡下降しているのに、四方が暗まっていたある夏の日、私の目を隠して急に書斎に入った母親は少し激しい声で言われた。
「…ソクジンああ、あなたはあなたの父が誇りですか?」
「はい、当たり前です」
「…父が嬉しいですね」
「事実、あなたの父は-----と言う。」
「…はい?」
「どうぞ、お父さんの誇りを受け継いで
将来、胸が沸騰するそのようなことをしてほしい」
「お母さん、わかりますか?」
「……」
母の口から出た言葉は、むしろ衝撃的だった。今なんてそんなに驚かなくても、父の秘密を初めて聞いた当時は、言葉を失うほどだった。その時だけでもその日とは別に外の状況も私は知らなかったから。とにかく、うまくいくと13歳の子供がいます。 独立運動家について何を知ったのだろうか。
その時だったら子である私にまで隠されてこっそり独立運動をした父親が恥ずかしかっただろうが、今はその裏面の意味が何なのかよく知っている。おそらく自分の正体が分かれば家族である私と母まで報復されるかと思い、それが心配だったのだろう。どうしたのか父が捕まった後、純死者はまた私たちの家にやって来なかったが、目を閉じることが恐れて毎日浮かぶ雪で夜を買った彼
当時の記憶は数年が過ぎた今でも鮮やかだ。
父は…私よりはるかに痛く、恐れていただろう。
「…はぁ…」
「なんだ、泣く?」
「いや、泣いた。風のせいでほこりが入っただけだ」
「明日見て、てつや(テツヤ)」
「ええ、遅刻しないで!」
哲也を返した後、みんな崩れていく外観の扉をドゥルリュク-熱子クイクイカビ臭が漂ってきた。木がみじん切りに慎重に足を踏み込んでも、ギリギリの音がする床を通り、建物の内側の小さな部屋のドアに手を移した。
「さく(さく)、ちょうど入ってきたの?」
ちょうどドアを開こうとする刹那に遭遇した所有者のおばあちゃん。この家に住みながらずっと行き来してきたので親しい間だが、桜という名前はおなじみの声から聞いてもいつも見慣れない。
「友達としばらく会ってきました」
「とにかくおばあちゃん、私と二人がいるとき
その名前を呼ぶことにしました。」
「エグモニーや、ごめんなさい」
「私はもしかしたら殉士が聞こえるか…」

「とにかく私の本当の名前ではありません。」
「キム・ソクジンという名前がもっと楽です」
「そうそう。これからは気をつけて」
「しかし、仕事はうまくいっていますか?」
「おそらく一週間以内に計画が取れます。」
「そんなおばあさんに一番先にお知らせします」
心配半信仰半分の表情を浮かべて、おばあちゃんは言わず私を背負ってくださった。私もそんなおばあちゃんの手を叩いておらず、疲れていると部屋に私を思い出してくれた後にもバッグを置くことができた。
プーハ - ため息をつきながら小さなランタンをトク - とオンにしようと、古い部屋の姿と一緒に壁に現れたのはダクジドゥクジ埋められた赤、青の絵。誰が見ればこれがどんな落書きなのかと思うが、絶対に何の意味もない彩色質ではなかった。
木の板に描かれた円形の枠と四方に分かれた4つの茎の茎、そして中心を貫通する曲線一つがその上を刺繍していた。
誰かが窓から投げたようなしわくちゃの方も一緒に言葉だ。
「日付が取れました」
「3日後13日、中央刑務所で見ましょう。」
「…ふう…」
メモを読んだら、体が煮えた。すべての仕事の始点であり、意義になるこの結社が、たった3日後に幕をあげると思うので、しっかりと握った両手が知ってきた。彼とこの国にとって最も重要であり、すべての人々の念願が響き渡るようになるその日、未来を称えることもできるのか、今日の月明かりは非常に明るかった。
窓に降り注ぐ光を灯し、ペンを拾った手、微妙に震える両手に押し込んだ感情が紙に乗ってきちんと伝わった。
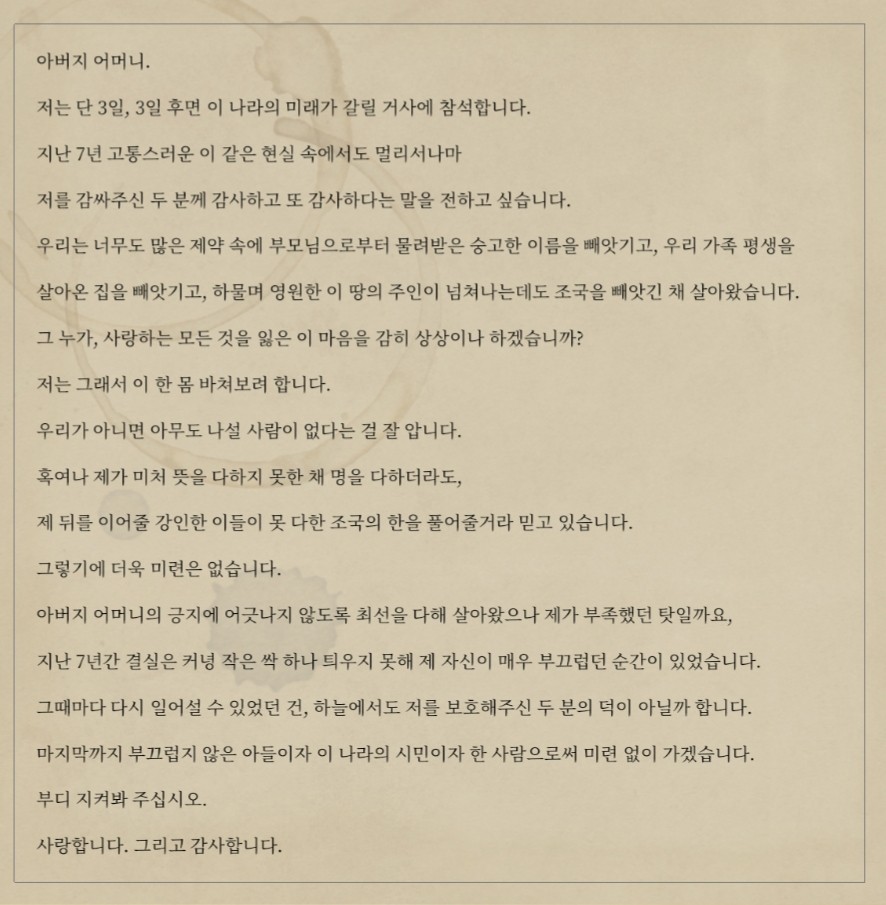
ペンの動きが止まり、汗に濡れた手が紙の上から落ちた。長い文を書いたわけでもないのに、まるでエッセイ一つを完成したかのようにジャリズリした。
少しずつワクワクは心臓が、拍動に追いつかない体を喘ぐようにしたが、気をつけなかった。私が生きていることを感じる瞬間が残っていなかったので。壁に付着していた紙の1つをブウク-剥がした私は初めて微笑んだ。赤、青、黒が調和して調和した小さな模様のひとつ。華やかではありませんが、強烈な色彩が目と心に満ちた。
その瞬間見た太極旗は、どれよりも美しかった。

2日間は学校に出ませんでした。先生が老朽化するのは明らかだったが、ほとんど死を控えている人にそのような叱られが何の役に立ったのか。すぐにモーレの生死さえ未知の状況で、私は一行と着実な出会いを持っていた。ただ13日のために一緒に走ってくれてありがとう、彼らの中には哲也もいた。
哲也は見れば見るほど不思議な子供なのに、朝鮮であること間違いなしに自分の本名を私に知らせたことがない。
去る前日の夜、哲也と私は刑務所近くの旅館で一緒に泊まった。いつものように笑って騒いでいたずらも打つようにしたが、なんかそうしたくなかった。おそらく哲也も私も、軽いがではない使命感のためだっただろう。
妙に厄介な沈黙が長くなって行くと、私は口を離した。
"てつや(테츠야)."
「うん? さく(さく)、どうしたの?」
「今回の仕事がうまくいけば…あなたの名前を教えてもらえますか?」
「…なんだww突然?」
「…ありがとう、そうだ」
「時間が経ってもつつじゃなくて
名前で覚えておきたい」
「……」
哲也はしばらく悩むようだった。おそらく私が一度もやってみたことのない質問だと思いますが、彼の答えを聞くまでには長い時間がかかりませんでした。
「いいね。教えてあげよう」
「…教えてもらえたらいいな」
「…不安になぜそうだ」
「でも、本当なんだ」
「私たちはいつ死んでも不思議ではない運命だ」
「……」
認めたくなかっただけで、哲也の言葉はほぼ全部合った。植民時代に住む植民地人の身分に過ぎない私たち。どれくらい綺麗なペアのない運命なのか。
いろいろな思いで眠りはもっと来ることなく、私たちは目を遠く離れたままほとんど浮かぶ目で夜をエビに至った。結局睡眠をほとんど眠らないまま夜明けが明るくなる頃、テツヤは一言を吐いた。
「ソクジンああ、今私たちは無限の暗闇の中だと思います」
「…それはどういう意味ですか?」
「周辺は暗く、
光が明るく見える兆しは見えるように、見えないように…」
「祖国を失ってしまったのがこんなに大変な日々のことは知らなかった」
「……」
「ところで…でもね」
「夜明けの中で光が明るくなるのは…
私たちのような人がいます」
「暗闇の中でもあきらめずに
自分で光を作る人たち」
哲也はしばらく息を選んだら、軽く泣く声を飲み込んで最後まで話をした。
「だから…私たちは必ず朝を連れて行こう」
「そして、最も明るく長い昼となるように、世界を照らしてみよう。」
「…そうしてくれるの?」
私の答えは、沈黙を模倣した堅い握手に取って代わられた。
タイトな両手。お互いの熱気が感じられる合った手から、私たちの意志のような赤い太陽が咲き誇るようだった。

翌日、通りはいつもと変わらなかった。
殉士たちは街を徘徊し、人々は彼らの気づきを見て厄介な日本語で呟くだけ。
ただ一つ違う点なら、ただ中央刑務所の裏側に立った見知らぬ人物だと言うか?
「……」
「……」
刑務所の裏側に位置する哲也が私を含む多くの人々に手を振りかける信号を送った。無電機一つない貧弱な環境だったが、みんな知ることができた。
「一、二、三に飛び出していく」
「一つ、二人…」
カウントが始まり、哲也の指3本が広がった瞬間。

「大韓独立万歳」

「大韓独立万歳」

「大韓独立万歳」

「のための独立万歳!!!!」
数多くの観客が飛び出して通りをいっぱい埋めた。
その広々とした空間があっという間に足のトレッドの隙間もないほどの人波で満たされ、また一度の響きが今回見る人の心までも熱く甘く掘り下げた。
みんなの口から出てきたただ一言。
「大韓独立万歳」
私たちはこれ一つのために、当然と考えられるべきこれのためにどれだけの日を披露した記憶の中で頑張ってきたのか。
予想したように、巡回社は無慈悲で攻撃を浴びせたが、退いてはこれは一人もいなかった。
祖国の先日と栄光を、私たちの子孫と未来を、恥ずかしくない朝鮮人の一人として崇高な信念を守るため。
我々は戦った。
周辺の何人かの人々が倒れた。純死者が勝手に発砲した銃のためだった。四方八方に血が飛び散って恐れた彼らが隊列を離脱して陣営が崩壊したが、それさえしばらくだけだった。みんなが一心一意に叫び続けた。私も一番前から彼らをリードして進んだ。
そんな瞬間、

湯 -

「カッ…黒…」
...ああ...
意識がぼやけた。
口から泣き出てくる血を見た瞬間、
私は床に倒れていた。
想像がつかない痛みが気持ち悪くも、漢気とともに腹部を選んだ。止めようとしても血が流れ続け、いつの間にか私の服は赤く染まった。渦中にも人々が移動するためにあちこちを踏むと、ふとこんな気がした。
「…こんなに死ぬな」
それでもこの程度なら、
「うんざりした人生だった」
「はぁ…」
目が閉じて、最後のため息を吐いた。
痛みまでますます遠くなっていき、頭の中が白紙化した。
本当に、終わりですね…
「いや!!!!」
「…テツヤ…」
「起きて!!起きろよ!!!!」
どこかで走ってきた哲也は人派を突き抜けて私を起こしてフィッシュした。傷が広がらないように気をつけて、私の疲れで自分の服が汚れても気にならないまま、私たちは近くの路地に入ることができた。
「うーん……ダメ…」
「いや、どうぞ…!!!起きてキム・ソクジン!!!」
「はぁ…テツヤ…」
「言わないで、何もしないで…」
哲也の目から一滴、二滴涙が落ちた。言葉の一言、吐き気すら大変だったが、その涙をとても無視できないので、無理やり気力を使って答えたら、傷がさらに潰れていった。
ああ…最後に言いたいことがありましたが。
「…テツヤ、ありがとう」
「…テヒョン」

「キム・テヒョン。私の名前...」
「……」
ありがとう、テヒョン。
それから約5年後、
青い雑草がいっぱい成長したある一人の墓、その先にサバク-サバク-音を出して誰かがゆっくりと近づいた。
彼は墓の前に小さな花を下ろしたところ、二度の寺院をしては一人だけの魂を並べた。
ああ、そうです。一人じゃない。
「…結局、私たちは今すべてが終わった」
「ハングルで会話をして、通金時間もない」
「強制徴用も何ももう消えたんだ」
「君がこの姿を見たらとても良かったのに…」
誰かが何度も言った。まるで会話をするような口調で。誰が見れば狂った人だと思うだろうが、実はそうではない。
彼の対話相手がまさにここに眠っていたから。

「…見たい。ソクジンア」
涙を留めて席から立ち上がったテヒョン。回想の目つきで石津の墓を眺めた彼は、内側の後ろを回った後、ナジマクが最後の言葉を跳ね上げた。
「私たちに明るく長い昼をプレゼントしてくれてありがとう」
