
夏だった。
私はなぜあえてこのような意味のない提案を受け入れなければならないのか分からないが、いたずらではないような真剣な表情をした彼を前に置き、さっぱりと言うのが難しく、結局私が勝って終わらなければならないと思った。
「わかりました」

「次の授業を始める前にこれを飲みましょう。私は先に行ってみましょう!
私の手を引いてリンゴソーダを握ってくれた後、彼は手を振って独特の爽やかな笑顔を再建し、ゆっくりと屋上を去った。屋上から降りて朝にもらったチョコミルクと私の手にあったリンゴソーダを交互に眺めながら妙に彼と似ているという考えをした。いなければ思い出したチョコの甘さと忘れたときに現れて、自分の存在を表す炭酸の存在。二つが調和した彼は人々が好きになるしかないそんな人だった。あるがなく、虚戦した彼の存在が少しずつ私の中で席を育てていくようだという考えをしてチョコミルクとリンゴソーダをバッグに慎重に入れた。
「あなたは最近何がありますか?もうすぐ終わりです」
「お母さん」
「最近重要なプロジェクトのために私が君を気にしないからといって、あなたまで解放されるとは思わない。
「気にしないようにします」
久しぶりに出張から帰ってきたお母さんがまた私を迎えに来始めた。前政局に遭遇しなかったので幸いなのだろうか。こんな息をのむ会話が慣れているのは、おそらく長い間経験してきたことだからだろう。私の1位が成功である理由は、これまで耐えてきたこの地獄をもう少し耐えれば独立できるから、その成功が誰よりも切実だった。私以外のお母さんの人形で、トロフィーで飾られたくなかった。
「お母さんすぐに会社に入ってみなければならないからご飯を食べてすぐに勉強して」
「はい」
家に入って、いつものようにご飯をお腹が呼べないほど、ご飯を食べて席に座った。横にあるバッグからチョコミルクとリンゴソーダを机に載せてじっと眺め始めた。屋上で露のリンゴソーダを握ってくれた苦い笑顔を作った彼の姿がずっと思い出した。最初から周辺人とそれほど遠く過ごしたわけではない。かなり活発な性格を持った私は遊ばなければならなかった幼い頃から与えられた過程に従い、生きてきたので親しい友人とはますます遠くなっていき、次第にこの人生に慣れていった。大変だが、誰にもティーを出せなかった私の子供時代を最後にすべての関係を断絶し、この状況をできるだけ早く終わらせたかった。
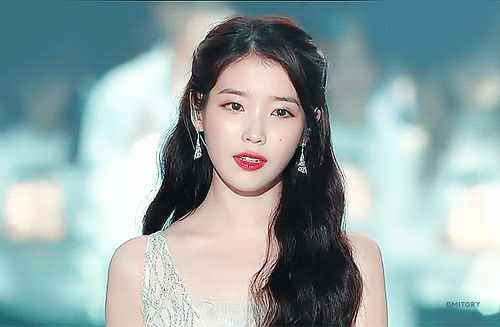
「たぶん、あなたが私に勝てばいいと思うこの考えは狂ったのだろうか」
/

ありがとうございます。
