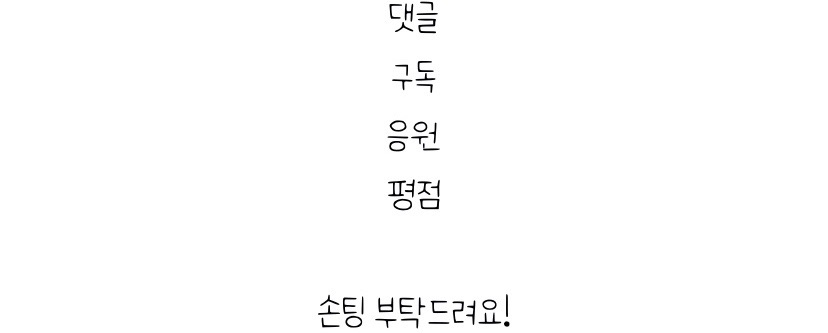私を台無しにしてきたヤンチの前庭
私は逃げるような場所を避けた。真っ赤に広がった顔を前政局に見せることができなかったので、ただ避けてしまった。急いでコインカラオケの建物の外に出たとき、さっきより多くの人で賑わう街で、私はその人たちの中に集まっていくことに決めた。
「あ、私のバッグ…」
人と混ざって素早く歩き始めた頃、私はカラオケに置いてきた私のバッグが思い出した。飲み物を選びに行くという言い訳で財布とフォンは私の手にあったのが幸いだった。
私はスーツケースが明日探しに行こうという気持ちでバス停に向かって歩いていった。私が停留所に到着するまで前庭に捕まらず幸いで、家の近くに行くバスをすばやく見つけて交通カードを撮った。
「…もうどうしよう」
ひとまずは前庭を避けるのが優先だという考えに避け続けたが、同じ学校、同じクラス、さらにはペアな前庭をいつまでも避けられない。明日いや、どちらも心を食べればすぐにも遭遇することができるのが私たちだったから。頭の中がきちんと複雑で、両目をしっかりと巻いてバスの窓に頭を傾けた。
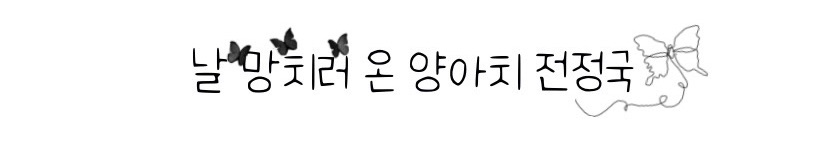
「学生、学生!」
ちょっと目だけ巻くというのがいつの間にか深く眠ったのか。私が眉間を刺して目を開けて見せたのは私の肩を振るバス騎士おじさんだった。
「うーん…おじさん、ここはどこですか…?」
「どこか、終点だよ!」
「はい?!」
終点という言葉に精神が点滅した私は目を丸くして周りを振り回した。窓の外は真っ暗になったようで、バスには出てバス騎士おじさんだけだった。
終わりました。前政局を避けようとしたのが問題だったのか、どこか分からない町内に一人でぶつかって残された私だった。私が持っているのは携帯電話と財布だけだった。ここでカードを書いた間、お母さんにバレるのが明らかで、現金は満員少し以上あった。
「台無しだ」
「学生、ここに座って少し待ちます。誰がすぐに迎えに来ると言ったのです。」
バスから降りるやいなや台無しだと頭を撫でた私に意味深い言葉を渡すバス騎士おじさんだった。終点駅にいる私を代替誰が迎えに来るということなのか…。まさか親ではないでしょう。私はバスの騎士のおじさんを捕まえて尋ねた。
「誰ですか?いや、私がここにいるのはどうやって知って…」
「私が生徒を目覚めさせようとしているのに、生徒の電話が鳴り続けると言われています。
「もしかして名前みたいなんですか?」
「あ、何と言ったのに…覚えがよくないな。とにかくここでちょっと待ってみてねー」
そんなにバスの騎士おじさんも待つという言葉を最後に私のそばを去り、私は近くのベンチに座って誰もが来るのを待った。静かに座って空を見上げて星を数えて見ていたとき、うるさいバイクの音が聞こえ始めた。びっくりして空を眺めた視線をそっちに回したら見えるのは、

「だからなぜ逃げるのか」
バイクヘルメットのために壊れた頭を手で振り、私に近づく前政局だった。また前政局だ。どのように毎回何が起こるたびに見えるのは前政局なのか。迷惑だったこれで私が前政局を避けたことが意味がなくなるのだ。
「…バイクも乗ってくれる知ってる?」
「えっ。前から乗ったんだけど、初めて見て?」
「君が見せなかったから」
「今見せてくれればいいな、何。」
高校生とバイクの組み合わせは考えたこともなかった。高校生が乗るには少し難しく見えるかな。道端にすっぽり通る配達のバイクのような感じかなと思ったが全くなかった。前政局が乗ってきたオールブラックのバイクは配達バイクと次元が異なるオーラを吐き出していた。
ところがそんなオーラを持ったバイクより私の目を先に捕らえたのは、前政局だった。ワイシャツボタンを全部解放したまま、片手にはヘルメットを持って、もう片方の手では髪の毛を振りながら盛り上がって歩いてきた前庭。
「素敵です。」
「ついにあなたの心にちょっとしたのか。」
「あなたじゃない、バイク」
気づいたかもしれないが、素敵だという言葉は前政局に向けたことだった。暗くてもっとそうだったようだ。周囲が暗く、前庭がより輝いて見えた。だから私も知らずカッコいいと言った。いつか一度はやりたかった言葉でもあったし。しかし、私は前庭ではなく彼のバイクに目を向けました。直接的な言葉はなぜかちょっと恥ずかしいからです。
「逃げたキム・ヨジュを捕まえようと乗ってきたんだけど、ただタクシーや乗り物だったんだ。
前政局が私の前に立った。私は前庭を見上げて、前庭はバイクに嫉妬する自分が面白いのか手で目元を隠して被式笑っていた。
今は前庭を見れば息がよく休まないほど良い。昨日より、先ほどより。時間が経つにつれて、前情国が良くなるのを見ると、私はすでに限界に達したのだ。少し遅れたが、今でも前政局に対する私の心を認めることにした。
私はその場でそのまま立ち上がり、両手で前庭の嘘をつかみ、そのまま唇を突き当たった。両目を呑み込んだまま、前庭の唇と一三秒ぐらい触れるとそのまま唇をはがし、前庭はそのような私を見下ろして上手く笑っていた。
「これはまたどういう意味なのか。」
「…あなたも勝手にやったじゃない。私も同じように返しただけだ」
知り知らないふりをする前政局のその笑いが嫌だった。ただその理由だった。私の心を認めることにしましたが、すぐに変わったのは。純粋に好きだと言う前に、私は前庭の確かな答えを聞きたかった。本人も私のような心という確かな答え。
「やがて私たちの女性は率直ではありません。」
依然として前政局の口尾は上がっていた。でも、私はもう一度二つの目を必ず巻くしかなかった。その言葉を最後に私の唇を噛む前庭国だったから。私は前庭のウエストダンスを握り、前庭は私の後ろを包んだ。
私たちは深い夜遅くまで同じ答えを言いました。それも非常に真剣に。