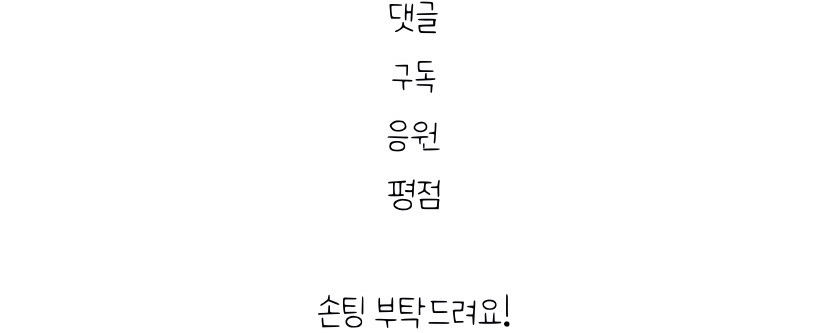私を台無しにしてきたヤンチの前庭
その後は正直よく覚えていない。前政局が私のような気持ちであることを確認したということと、ポポとは次元が違う口当たりをしたということに気持ちがいらっしゃった。チョン・ジョングクは真得だった口当たりを終えると手に持っていたヘルメットを私の頭にかぶせた。
チョンジョングクが私に書いてくれたヘルメットは前が黒くなっていて口当たりを終えたチョンジョンククの表情をきちんと見ることができなかった。薄暗い記憶では耳が赤くなり、本人の裏目をぶら下げていたようだ。
「た、連れて行ってあげよう」
「え、え…」
私たちはお互いに率直ではありません。これひとつだけは本当に似合った私たちだったので私もこっそり笑ってしまった。前庭が最初に自転車に乗り、私は遠くに立っていました。バイクは初めてなので、どうしたらいいかわからず、そうしたと言うべきか。
「手が本当に行くから」
遠くに立っている私を見たら、前政局は首を一度振り、バイクから降りた。その後、本人が着ていたワイシャツを脱いで私の腰に縛り付けては、ただガルタ座れば良いという式だった。
だから私は前庭の後ろに座っているように腰をかけて、両手で前庭の腰の近くに住んでいた。

「そんな見逃せば大変な日になるの?」
「そ、じゃあなんだ…!」
「こうして、ちょっとしっかり捕まえろよ」
チョンジョングクは本人服を握った私の手が不満だったかより。服だけ軽くつかんでいた私の手を直接本人の腰に持つダンを見たら。本意ではなく前政局の腰を包むようになると体を傷つけた。そうしたのもしばらく、口元に笑顔をいっぱい留めたまま前庭を抱きしめるようにした。
「…出発する。しっかり握って」
後ろから見る前庭の姿は私の心臓に触れるのに十分だった。餅が広がった肩、それに比べて薄いウエストまで。バイクに始動がかかり、私は前庭の腰を包んだ手にさらに力を与えた。それでも私は前庭の表情を正しく見ることができませんでした。
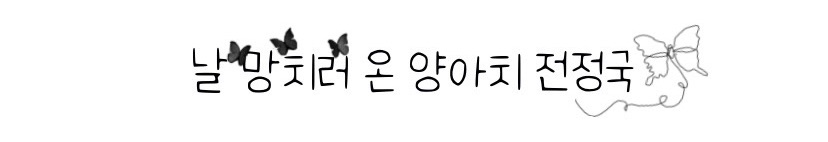
かなり遅い時間で道路の上を走っていたバイクが止まったのは、我が家の近くに行った時だった。バイクのスピードが徐々に減少し、内部始動がオフになったときには若干の物足りなさもあった。なぜすでに家に着いたのか。しかし、私はその物足りなさを折り、ヘルメットを脱いだ。
「前庭、これ。」
物足りなさが思ったより大きかったのか、バイクでは差し出せず、先に脱いだヘルメットを前庭に渡した。チョンジョングクは進んで降りて私をじっと見つめていたし、受けたヘルメットはバイクの頭に軽くかけておく。
徐々にまた体が熱くなり始めた。毎回いつも感じるんだけど、前政局が私をじっと見ている時は私は…何もできなくなる。私ができるのは、ただ顔を赤く染め、視線を避けること。ちょうどこれらだけだった。
「ヨジュヤ。」
「……」
「キム・ヨジュ」
「なぜ…」
「私は見ないの?」
前政局は必ずこういう。ただトゥクトゥク投げる優しさに人ときめく作っておいてはたまに狂って優しくする時があって。それがどれほど心臓を走らせるのか本人は絶対に知らない。
「見てるじゃないか」
「私の顔がそんなに下にあるのか―」
「…あなたは本当に嫌い」
きっとみんな知っている。チョンジョングクは怖いほど私を貫いている人であるだけでなく、やむをえず私よりも私をよく知っている人だから。今私が本人の目に直面できない理由が恥ずかしくてそうだということをよく知っている。笑い混じった口調で末尾まで伸ばすのが腐り気に入らなかった。前政局は依然として私をからかっているようだ。

「私は女主人がいいのに、どうしたの?」
瞬間だった。前政局が私のあご先端をつかんで目を合わせさせたのは。強制的に前政局と目が合った私は印象をパクチプした。
「…おめでとう、良い言葉にする時。」
「良くしないとどうしますか。」
「どんどんいたずらチル、」
不気味な混ざり合った私の声は、前庭の唇に食い込んだ。どうやら私だけが子供が乗っていく感じだ。前政局がこの前に恋愛をどれだけしてみたのか、キスは何回ずつしてみたのかよく分からないが、これ一つは明らかだった。チョン・ジョングクは私を自分の手の上で遊ばせるほど、すべてのものに上手だ。
なんだかわからなく前政局に負けているようだった。誰かに負けたことはない私だったから。自尊心が上海でもすごく傷ついた。私の口の中に入って絡み合っている前庭の舌を歯で噛み、前庭を押した後、そのまま逃げた。
「ふふっ…可愛いね、欲しいくらい。」
逃亡家は私の後ろ姿を見て手で顔を覆ったまま、肩を浮かべながらまで笑う前庭を知らないままだ。
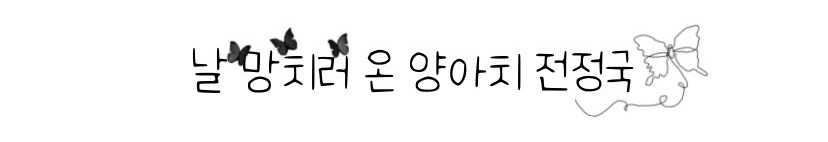
顔が真っ赤になって急なように番号キーを押した。無作為に押して何度も間違った玄関口のパスワードだったし、家に入ると両手で頬を包みながら深い息を吐き出した。
「ふ…これくらいなら大丈夫だろ?」
そうしばらく玄関で靴も脱がず深呼吸をした。相変わらずカンクン大は心臓を落ち着かせるためだった。そんなにある程度沈みたかった時、ぜひ巻いた目を開けると私の前には予想外の人物が立っていた。
「もう入りますか?」
ただ一言で言っても私を緊張させ、震えさせる存在。学校や学園のようにむやみにあげられない存在。現在私の首を最後まで締めている存在。まさにお母さんだった。
当然この時間にはうまくいくと思った。いつもの読書室でこの時間に入ると、私たちの家は誰も住んでいないのと同じくらい涼しく、静かだったから。しかし今日は違った。お母さんが目覚めているだけで、全身に力が入った。
「ちょっと遅かったな」
「その…科学遂行評価を少し準備していって来ます」
特有の鋭いように、ずっしりとしたママの声が私を刺す。私を見つめているお母さんの目つきさえ今は怖いだけで、お母さんは私に向き合いたくない人になっていた。そんな靴を脱いでお母さんに頭を一度熟した後、部屋に入ろうとする時。
「キム・ヨジュ、よくやっているの?」
「……」
「本当に昔のように気にしなくていいのか聞くんだ。」
体がつぶされた。それと同時に口がよく落ちない。私はいつも最善を尽くし、お母さんが望む結果を持って捧げました。そうしてやっと外れたお母さんの視線だったのに…。気を使うと言うママの束縛がとても嫌だった。今は恥が震えるほどだ。
「大丈夫です、前よりもっと頑張ってますから。」
「まあ…ええ、あなたはそうです。」
「……」
「無条件にうまくいけばいいよ、女主よ」
「…はい」
パルル震えるまぶたと手、そして足に素早く動いて部屋に入った。訪問を慎重に閉じて歩いてロックされた後でさえ、私は不安定な呼吸を吐き出す。何度も呼吸しても、月を震わせる手はまだ落ち着かなかった。
訪問を背もたれにして期待を躊躇した私はクマが考えた。私は果たしてこの空間から抜け出すことができますか?私は果たして両親の手から抜け出すことができますか?私は果たして…そんな力があるだろうか?頭がぎこちなくなり始めた。
「…前政局見たい。」
頭が痛くなり始めると、私の頭の中は前政局でいっぱいになった。私が頼ることができるところが精々前政局というのが、こういう時思い出すのが前政局だけというのが虚脱した。それにもかかわらず前政局といいという考えが本当に矛盾している。
一日中前政局とついていたにもかかわらず、前政局が見たい夜だった。