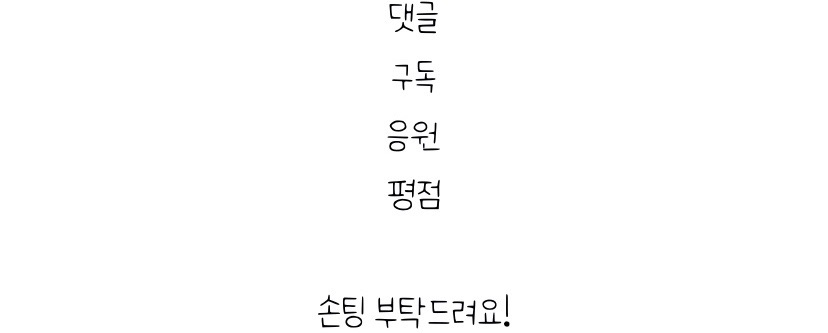私を台無しにしてきたヤンチの前庭
肝臓に登校を早めた。もともとお母さんの聖火に勝てず早い方だったが、それよりも早く家から出た。昨夜、お母さんにそんな話を聞いて息が詰まった。私に家は息を止める空間だったので学校といってもただ逃げたかった。
朝7時の学校はとても肌寒くて温もりが感じられない。私たちの学校だからもっとそうかもしれない。人気ふりが感じられない学校の正門を越えて、廊下を通り、半門をドゥルリョク開いた。半分も遠いが飛ぶだけ誰もなかった。やっぱり、この時間に人がいるのがおかしくない。私はバッグを置き、冷たい椅子に座った。お尻が涼しいほど冷たい椅子は、私を寂しくさせました。
「音楽や聞くか」
上着のポケットに常に座っているイヤホンを取り出した。フォンと接続した後、耳の奥深くにイヤホンを挙げた。その後、私のプレイリストに入り、お気に入りの音楽を選んだ。
「その時、もし私の肩を暖かく包んでくれたら、」
「これまで君を憎んでいなかったようだ」
「こんなに寂しくなかったらしい」
その歌のメロディー、雰囲気すべてのものを愛するが、最も愛するのは心臓をアリゲさせる作詞だった。私の世界は幼い頃からこの形だったので当然孤独だった。真実の友人も、家族もいないので、今の私は孤独だけいっぱいの子になっていた。
考えてみると、私が今やっていることも何の役に立たないかと思った。私がそんなに欲しかった自由を得た後は?その後の私は今よりも孤独な人になっているのではないだろうか?
「あ、俺なんでこんなに…」
私の目では涙が溢れていた。トゥク、トゥドゥク。机には私の目から落ちたいくつかの涙滴が残されました。その時、この時間には誰もいなくてはならない廊下に人気ふりが感じられた。うるさい音と一緒に私は後ろのドアに向かって首を回した。
「なぜ泣いてるの?」
前政局だ。片方の肩にバッグをかぶせるように結び、ワイシャツボタンは全部解けた。どのように登校する姿までこんなに一様なのか。私は前庭の登場に笑ってしまった。ちょっと前までだけでも涙をこぼした。
「泣くか、笑ったか二人のうちの一つだけしろ、ちょっと」
「あなたが突然来て、そうです」
「それではまた行きますか?」
「いや、ここにいる」
チョンジョングクは手で私の耳に差し込まれたイヤホンを引っ張って何と言った。そっと上がった彼の口尾に私もやはり口尾を上げた。ジョンジョングクは私の隣に座って、私の方に身を回し、人差し指で私の目の下を書いた。その後、独特の優しい目つきと笑顔で私をじっと見つめた。
「どうしたの?」
「わからない、ただ涙が出た」
嘘だ。私は積み重ねてきた孤独が爆発してしまったのだ。前政局の最後のターゲットになったのも、前政局と共にこうしているのも何ら役に立たないという考えに。私と前政局の目が虚空で当たった。前政局と目が合った瞬間、頭の中に思考一つが通り過ぎた。
前政局との交渉が終わる日には?以前に約束した通り、前政局の最後のターゲットになって完璧に自由を探した後には?前政局と私はその後も一緒にできるのか…。 ?

「私たちは女主の嘘が増えました。
前政局はまだ私を貫く。何らかの理由でかどうかはわかりませんが。私はまた考えた。この交渉が終わり、私が前政局と何もない関係になれば…。
「…前政局、何一つ聞いてみてもいい?」
「うん」
「私たちは交渉する前に戻ることができますか?」
むしろ私は自由を捨てる側を選ぶつもりです。前政局に何もない存在になるよりも、もともと何もない存在になる方がはるかに優れているから。私の質問に表情が固まるのは仕方ないかより。チョンジョングクは微細に表情が固まった再び口尾を上げて笑う。
「そんなことができるとしたら、あなたの答えが変わるのか?」
「…わからない」
「私もひとつだけ聞いてみよう。私にそんな質問はなぜするの?」
「やめたくなった」
そろそろ周囲が騒々しくなり始めた。登校する子どもたちができたというのは、すぐに多くの人派が迫るだろうというようだった。私は頭をすっかり下げた。
その時、廊下に跳ね上がった音が聞こえ、半扉が騒々しく開かれた。半分の子供たちが数人ずつ登校し、私の視線は自然に音がする方に向かった。
「ヨジュ、ハイー。今日も早く来たの?」
「え、え…お前もいない、」
前回半分で一気に破った後、私を嫌う子もいたが、むしろ私をよく見る子もいた。私に挨拶した子供はその一人であり、私も手を振っていた車に前政局が椅子を引いて席で起きた。それから、私の手首をしっかりと握ったところ、どこかに導いた。
「おい、前庭国!どこに行こう!」
「……」
「これを……」
私は前政局の力に導かれ、その後を追いかけ、前政局は声をあげる私は安堵にもいないように、後に一度振り返らずにどこかに私を連れて行った。
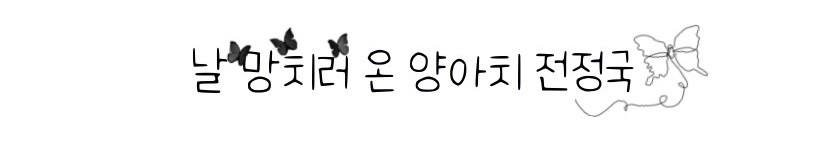
前政局が私を連れてきたところは学校の裏側だった。学生であり先生であり、人々が来るかどうかというような。私はまだ前政局が何を考えたのか分からなかったし、今前政権が私を引き付けた理由もわからなかった。
「痛い」
しばらく何も言わなかった私たちの間に私が口を開けた。前政局はおそらく知らなかっただろう。本人が無作為付与した細い私の手首が真っ赤に変わったことを。私が病気だと言うと、そんなにお茶が欲しかったのか私の手首を置く前政局だった。
「ごめん、たくさん痛い?」
「正直少したくさん?」
ただこの雰囲気がほしいと思う気持ちだった。こんな不思議な雰囲気の初めは私がはっきりしたが、前政局が私をランダムに引っ張ってきたおかげでもっとそんなこともあった。私はたくさん病気だと前政局に向かって笑ったし、前政局はそんな私の頭を一、二回撫でた。
前政局の手はいつも気持ちがいい。まるで私が一匹の犬になったことだけ前庭局が頻繁に撫でてくれることを望むというのもやはり奇妙だった。少し自らが変態のようだと感じられる頃、私の顔が漂う。
「こんなこと見れば私が嫌われたようではないのに…」
「え?」
「さっきそれ、嘘じゃない。」
前政局がそれと呼ぶのがどんな言葉なのかよく知っている。嘘というのはまたどうやって知ったのか…。前政局は色々と本当にすごいようだった。私はまた前庭の前で口を閉じた。
「私は何度も言うのがあまり好きではない、女主よ」
「……」
「最後に一度だけ聞いてみるし、嘘をついていた私はあなたが答えるようにする。」
「……」

「キム・ヨジュ、本当にやめたいですか?」
前政局は本当にあまりだった。本人がそう言うと、私が無条件に本気を語ると同時に涙を放つことを知っていたからだ。