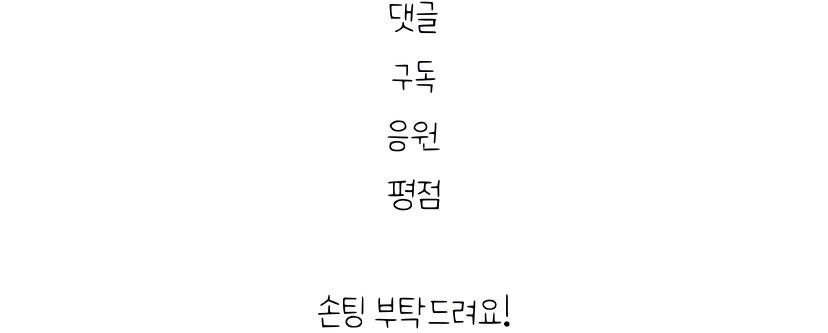私を台無しにしてきたヤンチの前庭
前政局と会い始めた後、初めて降る雨だった。不思議に思うほど雨が降り降り、太陽が中天日の時間にも暗くなるほど天気がめちゃくちゃだった。私は雨の日があまり好きではありません。こうして天気がめちゃくちゃの日はどんなことでもぜひ飛び出そうだったから。
「…やめてちょっと見つめてるの?」
一応は私の隣に座って顎を掛けて私を突き抜けて見つめる前政局が問題だ。登校した瞬間から授業時間、休み時間、ランチ時間まで全部あのように見つめているから。負担になるだけでなく、神経がきつく急いで何度も意識することになった。
いつの間にか鼻先に近づいてきた中間考査に解かれた問題集を覆い、前政局を倒してみた。一見見るのが何があるとあんなに見るのか…。理解できない。
「じゃあちょっときれいかな」
私を見つめるのは止まらないまま、口尾だけ生きて上げた前庭から似合わない言葉が飛び出した。似合わないけど僕はあんな言葉をかなり好きなのか。瞬間的に二つの頬が熱くなり、真っ赤な紅潮が広がった。
「私たち女主はいちご姫か見て。どうやって一日も抜けずに顔が真っ赤になる?」
「まぁ、なんだ!この上手な奴が…」
「好きながらなぜそう―」
反論できなかった。どのようにそのような言葉をさり気なくさせるのか。チョン・ジョングクはとても上手く、本当に変な奴だった。まあ、そんな前政局が好きな私も変だったけど。
「ジョンジョングク、あなたはなぜ私が気に入ったのですか?」
「幸せではないから」
突然頭の中をいっぱい詰めた質問だった。明らかに前政局は私に自分の最後のターゲットになることを提案すると同時に私を気に入ったと言った。しかし、その理由は聞かなかった。いいえ、正確には私が理解できませんでした。
幸せではなかったので、私が気に入ったというその言葉自体がちょっとアリソンした。実は私ではなく誰が聞いたとしても印象を醜めたはずだ。私が頭をかがめると、ジョンジョングクは私の目をまっすぐ見つめた。
「そんなに過ごしたら、一瞬で破ってしまいそうだったら、お前」
その言葉を聞いた瞬間、未知の妙な感情が冷え込んだ。私も知っていた。こんなに生きてきたら、私が確かに死んでしまってもおかしくないと私も思ったから。私はおそらく以前の私を誰にでも知ってもらいたいのではないかと思います。前政局のような人を願って、また望んだかも。
「これくらいなら答えになったか?」
「…すごい」
「幸いだ」
「どうやら私が君の考えよりも好きな気がする」
片手で私のヘアラインに沿ってスムーズに撫でる前庭に気持ちいいように両目を巻いた。私も知らずに外に飛び出した本気とともに、私の唇に暖かく渇いた肌触りが届いた。そして私は本能的にそれが前庭の唇であることを知った。

「ずっとそんなに好きになってくれ。逃げるつもりは追悼もしない。私が誰よりも綺麗にしてくれるから」
すっかり唇に惜しかったのもしばらく、巻いた目を開いた時、近くに見える前庭の顔と聞こえてくる甘い言葉に大笑いした。だが、依然として窓の外では雨が喉を落ちていた。不安を感じる。
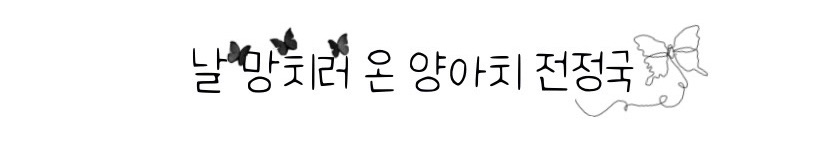
私の予感は間違ったことがほとんどありません。さらに雨がいっぱい降る日にはもっと。いつものように前政局と一日中時間を過ごし、夜遅くに玄関のパスワードを押した。 띡、띡、ティリリング-。ドアを開けて入るとすぐに息が詰まった。素早く靴を脱いで、カムカムで広々としたリビングルームを越えて私の部屋に入った。
「は…本当に嫌だ……」
私だけに聞こえるようなボリュームで呟いた。どんなところよりも楽で良くなければならないこの空間が嫌いなものを越えて逆さまに、突っ込んだ。私がバッグを机の上に投げるように下ろすと待っていたように鳴り始める電話ベルで、その主人公は前政局だった。
画面に浮かんでいる前政局の名前を見るだけでも気分が一層よくなった私が電話を受けようとしたとき、訪問が徹底的に開かれた。びっくりしてフォンを握っていた手に力が抜け、私の前には恐ろしいママという存在が立っていた。
「あ、ダメだったんですか…?」
思う存分握った二つの拳にぶらぶら震え、私の声もやや震えた。間もなく体全体が震えてきそうな感じに唇をぎゅっと噛んだ。
「すぐに試験なのに、なぜこんなに早く入ってきたの?こんな時ほど、もっと頑張らなければならないことを知っているじゃないか」。
「今日は雨が多すぎて…明日からは遅くなるでしょう」
「信じてもいいの?」
「…もちろんです。」
私にトゥクトゥク投げるママの言葉にとげが浮かんでいる感じだ。何か知りながら私を試したいようなそんな不気味な感じ。腕を組んでじっと立っていたお母さんはその手をほぐし、床にくるくる私の電話を拾って私に渡した。
「大切なことを守る方法は絶対に近づけないことだ。」
直接渡した携帯電話を握ったとき、お母さんは手に力を抜かなかった。むしろ力をもっとしっかりと与え、私と目を合わせ、少しの笑顔と共に私に意味深長な言葉を渡した。彼女の姿はまるで悪魔と重なって見えた。
「今日読んだ本に書かれていた文章なのにどう思いますか?」
「…まぁ。よく分からないよ、」
「人でも、物でも、あなたに大切なものを守るためには、あなたから遠ざけておかなければならないということに気づいた」
「……」
「そうでなければいつ壊れるのかわからない。」
一種の警告だった。ママは今、私が何をしているのかを知っているだけでなく、私の周りにどんな人がいるのかを知っています。お母さんが前庭の存在を知っているというのは…前政局が危険になったということ。ママは今私の善で前政局を整理する機会を与えているのだ。
口の中で血の味がする。唇と口の中をしっかりと噛んだのかは見えないが、真っ赤な血が流れるようだった。静的と一緒にママと目がもう一度出会った。彼女の目は私を吸うのと同じくらい魅力的でした。
私が発悪をしても完璧な自由を見つけることができなければ、死んでもここで逃げられなければ、前政局でもエクスポートしなければならなかった。私の人生に足を踏み入れた前政局を遠く離れておかなければならない。そうすれば前政局が安全だから。

「一日でいい、ちょうど明日一日だけ」
私は私の人生から前庭をエクスポートすることにしました。狂気の痛い涙が溜まっているのを頑張って手のひらでこすりながら言葉だ。