3年前、刑事だった私の父が殺されました。
何かを明らかにする機会を得る前に、彼は多数の暗殺者を操るボスに射殺された。
もし彼が他の刑事たちと協力していたら、もし彼が単独行動ではなく正式な捜査を行っていたら、彼はあんなにむなしい死を迎えることはなかっただろう。
しかし、私が知っているのはこれだけです。
ボスが本当は誰なのか、なぜ父がボスを見つけることにそれほど執着していたのか、なぜ父が秘密裏に一人で事件を調査することを選んだのか、私には全く分かりません。
父の死は自殺とされ、何人の刑事に捜査を依頼したが、誰も父の事件をきちんと引き受けようとしなかった。
彼ら全員の言い訳は同じでした。忙しすぎたのです。
— 刑事さん、3年前…
— その事件はもう解決済みだ。今さら持ち出す意味はない。
— でも彼はあなたの同僚だったのに。どうしてそんなに無関心でいられるの?もう一度だけ…
— 出て行ってください。周りを見てください。私たちは忙しいです。今すぐ行ってください。
— 父の事件も重要なのに。刑事たちはどうしてそんなに冷酷になれるの?
— …ちょっと私と一緒に外へ出てみましょう。
刑事が突然私を外に呼びました。
何か言いたそうな雰囲気だったので、不安を感じながらも、一縷の望みを抱きながら彼の後をついて行きました。
— もう来ないでください。私たちもこんな形で終わらせたくなかったんです。気にしていないわけではありませんが、ハ刑事は一人で捜査していました。情報も何もなく、私たちにできることは何もありません。
――結局、父の死の真相をきちんと解明できる人はいないのですね。
――……そうだね。ごめんね。
— 分かりました。お時間をいただきありがとうございました。
その日、私は決心しました。
私は自ら真実を明らかにするつもりです。
私はもう十分理解できる年齢になっていたので、自分でこの問題を解決するのは当然のことでした。
私は父の死が自殺ではなく殺人であったことを証明します。
あまりにも多くの時間が経過していましたが、亡くなった父と病院のベッドに横たわる母のために、私にできるのはこれしかありませんでした。
- はぁ…
しかし、どこから始めればいいのでしょうか?
情報はありませんでした。
私が知っていたのは、ボスとその暗殺者の2つだけだった。
もし誰かが私がなぜ警察に通報しなかったのかと尋ねたら、答えは簡単だ。どうせ警察は捜査しないだろうから。
彼らは忙しすぎて、すでに5年も前の事件を調査する人は誰もいなかったのです。
チン!
突然、知らない番号から私の携帯にメッセージが届きました。
💬 何も調べようとしないで。何もしないで。傷つきたくないなら。
メッセージは非通知から来たものではなかったが、それは奇妙だった。
それはボスが言うようなことではない気がした。
すると…それは彼の暗殺者の一人に違いない。
しかし、さらに混乱を招いたのは、そのメッセージの背後にある意図でした。
「傷つきたくなかったら何もしないでください。」
この人は私に警告していたのでしょうか?
それとも脅迫だったのでしょうか?
わからなかった。
しかし、さらに詳しい情報を知りたければ、この人に連絡する必要がありました。
私はすでに決心していたので、恐れるものは何も残っていませんでした。
返信を入力しました。
💬 あなたは誰ですか?
すぐに返事が来ました。
💬 これも調べようとしないほうがいいわ。今すぐ家に帰りなさい。
そのメッセージに私の目は釘付けになった。
その時私は気づいたのです
この人は私を見ていた。今この瞬間に。
私はすぐにその番号にダイヤルしました。
ルルル……ルルル……
電話がつながるまで呼び出し音が2回鳴り続けました。
心臓が少しドキドキしていたけれど、私は決心しました。
これはすでに始まっていたが、私はそれを最後までやり遂げるつもりだった。
📞 今、私を見てるよね?もしそうなら、直接会って話しましょう。
📞 本当にそんなに自信満々なの?私が誰だか知ってるの?
📞 まあ…君はボスじゃないのは確かだ。たぶんただの暗殺者だろう。もう話はやめて、俺に会ってくれ。
📞 もし私が本当に暗殺者なら、これがあなたにとってどれほど危険であるか分かっていますか?
📞 わかってるけど…
📞 住所を送りました。本当に会いたいなら、一人で来てください。
通話が終了しました。
私は住所を確認し、すぐに慎重にそこへ向かいました。
ボスの隠れ家にまっすぐ歩いていくのか、それとも到着した瞬間に殺されるのか、私には全く分かりませんでした。
しかし、そんなことは問題ではなかった。

「なんだ……?普通の家だよ」
その住所に辿り着くと、通りにある他の家と何ら変わらない、ごく普通の家があった。
私がドアの前に立つと、ドアは自動的に開きました。
私は慎重に中に入ったが、別のドア、エレベーターも自動的に開いた。
エレベーターで地下へ降りると、まったく違う空間が現れました。
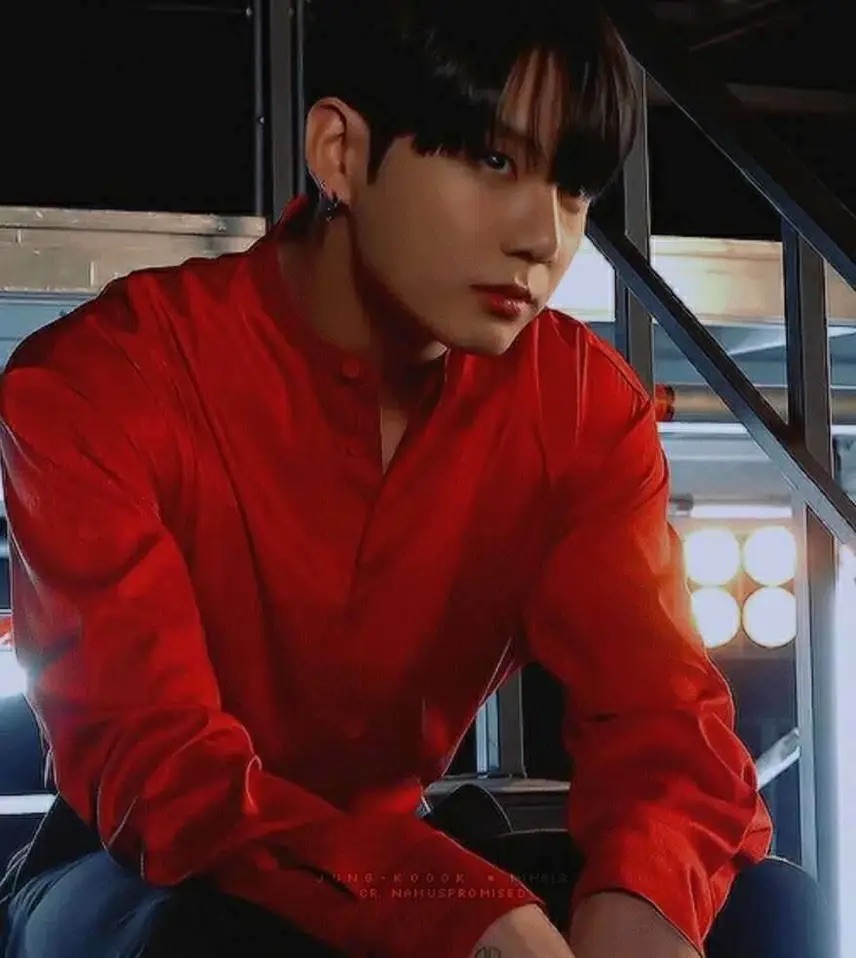
「ここへ来たんだね?」
「あなた…私にメールを送ったのはあなたですか?」
「ああ、私だよ。何、怖いの?」
「何だって?もちろん違うよ。」
「それで、なぜ私に会いたいと思ったのですか?」
「私…を殺すつもりですか?」
"知るか。"
「あなたは本当に暗殺者ですか?」
"うん。"
「それなら…ボスのところに連れて行って」
「はぁ……ヘイジュ、君って本当に何も怖くないんだね?5年も経って、なんで急にこんなに情熱的になったの?」
「もう、この事件を解決できる年齢になったんだ。真実を暴く。だからボスのところへ連れて行って」

「死んでしまうよ」
「じゃあ、まずは殺してやるよ」
「…正気じゃない。誰も――俺も、誰も――ボスに勝てない。なのに、お前は殺せると思ってるのか?」
「つまり…あなたは私を助けてくれない人なんですね。」
振り返ってエレベーターのボタンを押しましたが、ドアは開きませんでした。
すると、後ろから別の声が聞こえてきました。
「あのドアは君が決して開けることはできないだろう。」
この人物は暗殺者と違って、丁寧かつ親切に話した。
私は、予想外の新参者に少し驚いて振り返った。

「こんにちは、Jです。ちなみにハッカーです。あのドア?Kと私だけが開けられます。指紋認証ロックなんです。」
「なんで全部説明するの? とにかく、諦めるならドアを開けてあげるよ」
「諦める?自分で別の方法を見つけるよ」
「具体的にはどうやってそれをやるつもりですか?」
「…」
答えがありませんでした。
何の計画もなかった。
「ドアを開けてください。」
それでも、私はこのKという男に自分のフラストレーションを見せたくなかった。
その後-

「ボスを見つけたいんでしょう? だったらあなたも暗殺者になってみたら?」
彼の誘惑的な言葉は私のプライドをすり抜けて、私を引き込んだ。
