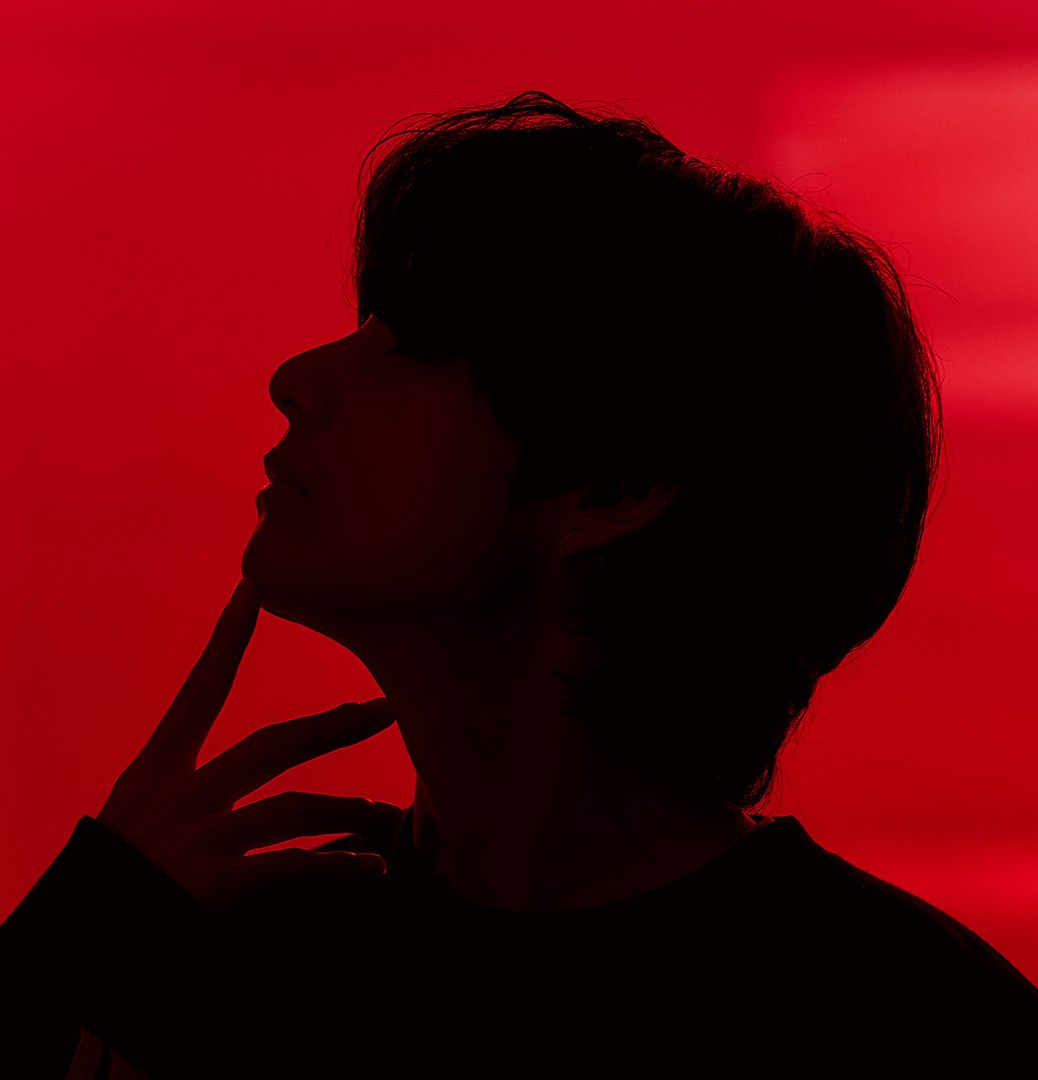「あと一日」ピンクのシーツを脱ぎながら私は思う。
ドアの向こうから姉のジウの声が聞こえる
- ミスク、起きて、学校に行かなきゃ。朝食を食べに来て!
「行ってきます!」と私は言いながら立ち上がり、ピンクのスリッパを履きます。そう、私はピンクが大好きなのです。
部屋を出ると、まず目に飛び込んできたのは妹が朝食を作っている姿でした。
「こんにちは、ジウ」私はダイニングテーブルに座り、左側にあるピッチャーから水を一口飲みながら言った。
「やあ、妹ちゃん、よく寝たよ。絶対起きないと思って、部屋に入ってコップ一杯の水を顔にぶっかけるところだったよ」と彼は言いながら、私の方を振り返り、手に持ったひしゃくで何かの合図をした。
「すごく眠かったの。昨日はお母さんを待とうとしたんだけど、結局来なかったの」私はカウンターまで行って皿とスプーンを取りながら言った。
- お母さんは決まった時間に帰って来ないのに、どうして待っているのかわからない - 彼女はフライパンを掴み、ベーコンと卵を数個私の皿に載せました。
「ええ、正直、どうしてそうするのか分からないわ」私は皿を見て微笑んだ。「私の好きな朝食を作ってくれると嬉しいの」私は自分の部屋へ歩いて行き、食べ始めた。
「妹よ、いつも心配してるわ」と彼女は言い、私の頭に近づいて触れた。「さあ、私がシャワーを浴びて学校に連れて行く間に、早く朝食を食べなさい」と言い、自分の部屋へ向かった。
「はい、奥様」私はベーコンを一切れ取って口に入れながら言いました。
ジウは私にとって一番の母親のような存在です。私の面倒を見てくれて、毎日学校に連れて行ってくれて、卵とベーコンは体に悪いと言うので、時々私の好きな朝食を作ってくれます。私にとっては、そんなのは馬鹿げています。死ぬなら、好きなものを食べて死にたい。
朝食を終えて、部屋へお風呂に入る。お風呂に入りながら、人生で起こっているあらゆる出来事に思いを馳せることほど、リラックスできることはない。バスルームから出て、服を取り出す。膝丈の可愛らしい青いドレスで、スカートの一部には花柄があしらわれている。白いスニーカーを履き、鏡で自分の姿を見て、肩まで伸びた髪を梳かし始める。
「わかった、準備できた」彼女は微笑んだ。「ああ、そうだ、歯だ」私は洗面台に向かい、歯を磨き始めた。
遠くで、妹が母と話しているのが聞こえる。昨夜はどうだったか、どうしてあんなに遅く帰ってきたのか、話し合っている…でも、本当のところ、どうでもいい。もううんざりだ。妹が私に構ってくれないこと、妹だけが存在していることに。妹だけが…
妹がドアをノックする音が、私の考えを中断させてくれました。
「妹さん、急いで。ドユンが迎えに来て一緒に学校に連れて行くから、私は外で待ってるよ。」
「行くわよ!」口をすすいで乾かしながら言う。最後にもう一度、鏡を見て自分に微笑む。
家を出て、ドユンの車に向かいました。ドユンは妹の彼氏で、付き合って2年になります。正直に言うと、私は彼を憎んでいます。彼はいつも妹を汚物のように扱い、殴り、虐待し続けています。実は、私も幼い頃に同じことをされたんです。
(…)
私は車まで歩いて行き、車に乗り込みます。
「おはよう、ドユン」私は無理やり笑顔を作った。本当は、彼の顔を殴りたいくらいだ。
「やあ、坊や」と彼は言い、バックミラー越しに私を見ながら車を始動させて学校へ向かった。
顔を殴ってやればいいのに、どうして「ちびっ子」呼ばわりできるんだ。妹のそばにいる彼を見るのは嫌だけど、どうすることもできない。妹は彼を愛していると言うし、彼女の人生を壊したくない。少なくとも、彼女は幸せそうに見えた。でも、心の奥底では彼を恐れていることは分かっている。彼が妹に与えてくれるささやかな幸せなんて、妹が彼と共に耐え忍んできた苦しみに比べれば取るに足らないもの。
学校へ行く途中、私は携帯電話を見ていましたが、生徒たちはその日に何をするかを話していました。私は彼らの話に注意を払っていませんでした... 学校に着くと、私はできるだけ早く車から降りました。
「連れて来てくれてありがとう、ドユン。またね、ジウ。愛してるよ」私はそう言って、振り返って学校に入っていった。
「さようなら、妹よ、僕も愛しているよ!」遠くからジウの声が聞こえ、振り返ると二人が歩いて去っていくのが見えた。
深呼吸をして教室へ向かう。そこには友達のファサ、ホビ、ジンがいる。彼らがいなかったら、どうなっていたか分からない。ドユンがどれほど嫌いなのか、彼らは知らない。彼らに言うのが怖い。もう友達でいてくれなくなるんじゃないかと思う。いつかは言うけど、今はまだだ。
歩いていると、とてもゆったりとした服を着た、青い髪と、ほとんど完璧すぎるほど美しい目をした少年が目に入った。彼が少し気を取られたように辺りを見回しているのがわかった。思わず微笑んでしまうと、彼が振り返り、なんとも言えない視線が合った。頬が熱くなるのを感じた。これが困ったものだ。私の肌はあまりにも青白いので、少しでも触れるとすぐにわかる。
「こんにちは、ここに来たばかりです。ソウルに来たばかりで、この学校もよくわからないんです。B6号室はどこにあるか教えてもらえますか?」 ああ、なんてことだ、彼が私に話しかけているんだ、と私は思った。彼の完璧な顔立ちを見つめながら。その整った完璧な顔立ちは、まるで神々によって彫り出されたかのようだった。
「ええ、もちろんです。さあ、私もそこで授業を受けているんです。」私は歩き始め、彼女に続いて来るように合図しました。
彼は時間を無駄にせず、私についてきた。廊下に着くとすぐに、私は彼に中に入るように言った。
「もう、どこか別の場所に行かなきゃ。じゃあ、また後でね」と、私は笑顔で振り返りながら言った。
ああ、もちろん!じゃあまたね。彼の声は本当に男らしくて、聞いただけで胸が締め付けられる思いがする。
これは私にとってまったく新しい感覚です。17年間、誰にも恋愛感情を持ったことがなかったのです。
私はトイレに行って用を足し、出て教室に着くと、先生が指示を出しているのが見えます。
「新しい先生はもう紹介されたみたいで、私はそこにいなかったのに」と思いながらドアをノックした。「先生、おはようございます。入ってもいいですか?」先生が私に手振りで示してくれたので、私はファサとジンのすぐ後ろの席に向かった。二人が手を振り返してくれて、私はただ微笑んだ。
授業中、ついあの男の子に目が釘付けになってしまう。彼の笑顔に心を奪われ、美しい横顔に時間を忘れてしまう。どうしてこんな気持ちになるのか、自分でもわからない。好きだと言ってもいいのに…
時間が経つのは早い。実のところ、私は授業中まったく注意を払っていなかった。ただ彼を見つめて、彼にキスしたいと願うことしかできなかった。彼の唇は、イチゴの味がするほどふっくらとしたピンク色をしていたからだ。
(…)
-ミスクへ地球- 考え事を止めて前を見るとファサとジンがじっと見つめているのが見える
「どうしたんだい、みんな?」彼は微笑んだ
「君が新しい男をじっと見つめているのをすでに見たよ。彼のことが好きなのかい?」ジンは唇に笑みを浮かべて私に言った。
-ジン、何を言っているの? -私は振り返って水筒を取り、それを飲みました。私が関係を持つことに興味がないことは、あなたもよく知っています。
「分かってるわ、バカ。でも、彼は全然悪くないわ。それに、あなたと彼が一緒に来たのを見たわ。もしかしたら知り合いかも」と彼女は口に手を当てながら言った。
「もちろん違います。入り口で彼にばったり会ったんです。彼は道に迷っていて、私に助けを求めてきたんです」と彼女は微笑んだ。そして本能的に私はその美しい少年を探したが、どこにも見つけられなかった。
「心配しないでください。彼女は出かけてしまいましたが、あなたの愛はすぐに戻ってきます」とファサは満面の笑みで言った。
「何を言っているの!私は彼を探しているのではなく、ただ…先生を探しているだけよ」彼女は微笑んで、次の授業用のノートを探した。
「君の言うことは何でも聞いてくれ、スク」二人が振り向きながら彼は私に言った。
「ああ、男の子を見ると自分がこんなにも目立つなんて信じられない。自分をコントロールしなくちゃ」と私は思う。
しばらくして先生が入ってきた。一緒にいたのは、私が大好きなギリシャ風の顔立ちをしたあの少年だった。彼は先生に話しかけながら、自己紹介をするように言った。
彼女はついに微笑んだ。私がこんなに好きなあの男性が誰なのか、きっと分かるだろう…