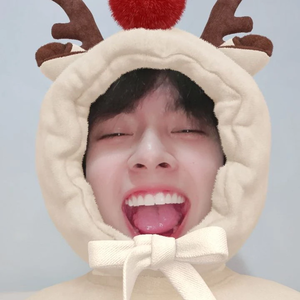2020年8月31日午前1時6分
「アティンさん、起きてくれてよかったです。」
アティンは微笑んで、部屋に入ってきた二人の男に敬意を表して頭を下げた。
「ダンテ兄弟、久しぶりですね。フェリックス博士、どうしてここにいらっしゃるんですか?」アティンは困惑した表情で尋ねた。
「エラ博士、あなたなら誰でも驚かないでしょうか? 心理学部の私たち全員が、ネイス卿があなたたち二人をここに急き立てた時には衝撃を受けましたよ。」
アティンは無理やり笑顔を返しただけだった。フェリックス医師は母親の弟子の一人だったので、心理学科の研修医3年目とはいえ、彼女のことを心配していた。
「え、待って、パウロ?彼に何があったの?彼は大丈夫?」A'tin の質問は間違っていません。
「容態は安定しています、アティンさん。ただ彼が目を覚ますのを待っているところです」ダンテが答えると、アティンはただうなずいただけだった。
「何が起こったのか調べられますか?」アティンが事件を語りながら、フェリックス博士は尋ねた。
「先生、どうしてパウロは自分がセジュンだということを忘れないようにと私に言うのか、理解できません。セジュンって誰ですか?」アティンは二人を驚かせながら尋ねた。
「え、待って…本当ですか?セジュン本人が紹介したんですか?」ダンテは尋ねた。
「パウロなんだけど、セジュンって言ってる。理解できない。どうしてセジュンって覚えてほしいの?」
ダンテの唯一の反応は深いため息だった。
「ダンテ、彼女に真実を話すべきだと思う。セジュンはアティンと深い繋がりがあると思う。アティンは彼の人生の恋人だって、君も言ってたよね?」フェリックス博士は言った。
ダンテは考え込んでしまったが、アティンに真実を知られないようにしても何も得られないだろうと思った。
「てか…あこぽ?私が彼の最愛の人?先生、私たちはもう何年も前に別れたじゃない。ありえないわ。」アティンは尋ね、自分自身を指さした。
「それはあり得る、アティン。特に、パウロの別人格であるセジュンが君に恋をしたのならね。」
「アルター?それはつまり……」フェリックス博士が邪魔をしたため、アティンは考えを続けることができませんでした。
「確かに、あなたも同じように考えているでしょうが、そうです、パウロは解離性同一性障害を患っています、アティン。」
「えっと、いつからですか、先生?」アティンは不安そうに尋ねた。
「もう10年以上経ったんだ、アティン」
アティンの心は真っ白になった。感情を抑えきれなくなり、目から涙が流れ落ちた。
「それは、私たちが付き合っていた頃から、彼はすでにその症状に悩まされていたということでしょうか?」
「はぁ…付き合って3年目で急に変わったのも無理はない。あ、そういう理由だったのか」アティンは言った。
「なんで気づかなかったんだろう? 僕は精神科医なのに!」アティンは思った。
「な、なんで教えてくれなかったんだよ、クヤ・ダンテ。彼がどれだけ苦しんでいたか知らないまま、別れてしまったんだから」
二人の男はアティンに答えることができなかった。ただ、涙を流して悲しむ女性を見つめ、彼女の痛みを感じていた。
「あの頃は、彼に文句ばかり言っていた。彼がどうしてあんなに豹変したのか理由も分からず、何人もの女を抱いたことを疑っていた。もしかしたら、私と別れたのはパウロではなく、彼の別人格だったのかもしれない」
アティンの心は後悔でいっぱいだった。パウロの気持ちについて無知で愚かだった自分に、彼女はひどく腹を立てていた。
「自分を責めるのはやめなさい、アティン。あなたと別れたのはパウロの決断よ。彼はあなたが自分のような男と関わることを望んでいないの。あなたのためよ、アティン。」ダンテは女性を慰めるように言った。
しかし、これによってアティンはさらに泣き崩れた。
「私の人生の愛は誰? 私の心を傷つけたのは誰? パウロ? それともセジュン?」アティンは絶望と混乱の中で考えました。