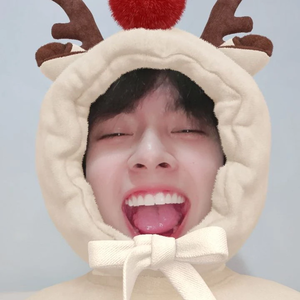(注:この先に自殺を誘発する内容が含まれています)
「フェリックス博士!!!」
ドアがバタンと開き、息を切らした看護師が部屋に入ってきた。
「お、申し訳ありません、フェリックス先生。緊急事態が発生しました。ネイス卿が行方不明です!」
"何?!"三人はほぼ同時に尋ねた。
「うわぁー!防犯カメラの映像を確認して、見かけたら電話してね。」ダンテはすぐにそう言って部屋を出て行きました。
「さあ、ここにいなさい。休む必要があるわ。」フェリックス医師はそう言って看護師と一緒に駆け出しました。
「ここでただ座って何もしないなんてできないよ!」アティンはイライラしながらそう言うと、手からブドウ糖を取り除いた。
彼は病院内を歩いていると、ある部屋を通り過ぎた。
「もう、いやだ!死にたい!薬代にもうそんなにお金かけたじゃない!」室内にいた男性患者は泣きながら言った。
アティンはこれらの言葉を聞いて何かを悟り、歩みを止めた。
「死にたい?もしも――」
アティンは考え続けることができず、病院のエレベーターへと駆け出した。14階を押し、不安そうに待った。
「いや…パウロはそんなことしない。また自殺したりしないよね?」
しかし、アティンさんは5年前に自分とパウロに起こった出来事を思い出して衝撃を受けた。
彼女は、自宅のリビングルームの床で意識を失っているパウロを見つけた日のことを決して忘れないだろう。彼のそばには薬瓶が置かれ、周囲には薬が散乱していた。
パウロが自殺を図ったのを初めて見た時だった。幸いにも事態は収拾し、パウロは一命を取り留めた。
「でも、彼は完全に忘れていた。自殺したことも忘れていた。もし…もし、以前彼の命を奪ったのが別人格だったら?」
エレベーターのドアが開いた瞬間、アティンの考えは中断された。彼女は急いで階段へと駆け出した。
彼女は屋上のドアを開ける前に深呼吸をした。震える手でドアノブを回し、ドアを押し開けた。するとそこに、ずっと探していた男の姿があった。

「ポール…」アティンは考えながらゆっくりと彼の方へ歩いていったが、男はまだ彼女に気づいていなかった。
「命は終わるからこそ大切。だからパブロはここにいる。」
パブロは屋上の端に一歩足を踏み入れ、身を乗り出して下をちらりと見た。


「人生には終わりがある。だからこそ、私たちは生き、一瞬一瞬を大切に生きるべきなんだ、パブロ。だから、アティンはここにいるんだ。」
パブロはゆっくりと視線を後ろに向け、眉をぴくぴくさせながら言った…
「それで、私に電話したのはあなたね。パウロが今死にたがっているのは、あなたのせいなの」

アティンは涙目でその事件を目撃し、一言も発することができなかった。
「私は精神科医ですが、なぜあなたの病状に気づかなかったのでしょう、パウロ?」アティンは思った。
「あ、本当にパウロは死にたいと思っているの?」アティンはどもりながら尋ねた。
パブロは目の前の女性に話しかけたいという衝動に駆られた。そのため、彼は崖から飛び降り、アティンの方へ歩み寄り、彼女のそばに立った。
「彼女は私の最後の言葉を運んでくれるだろう。」パブロは思った。

「私、パブロは自殺願望を持つ別人格です。パウロが問題から逃れるために死にたいと思ったら、私に助けを求めます。だって、パウロは臆病者なんです。セジュンが言った通りですから。」
アティンは怒りに震え、拳を握りしめた。しかしパブロはただ無表情な視線を彼女に返した。
「セジュンはどうした?もう死にたいかって聞いたの?」
この質問はパブロに強い衝撃を与え、彼は唖然としました。
「わがままはやめなさい、パブロ。そして、彼らの代わりに決めつけるのはやめなさい。パウロが今衝動的に行動しているだけだと分かっている。君を召喚したわけじゃない。彼は死にたくないんだ!」アティンは男に向かって叫んだ。
しかし、パブロは弱々しい笑みを浮かべただけだった。
「あなたは私たちの何を知っているの?何でも知っているかのようにうるさく言うのはやめなさいよ、女。」パブロは無感情にそう言って、アティンを怒らせた。
「俺には名前があるんだ、バカ!アティンだ、女じゃない。そしてもちろん、お前も知ってる!お前は俺の元カレだ!5年間も付き合っていたんだぞ、この野郎!お前の病状なんて何も知らない!」アティンは叫んだ。
「何も知らないことより悪いことって何だと思いますか?」パブロはアティンに向かって歩きながら尋ねました。
「え、何?」パブロが彼女を威嚇すると、アティンは緊張して言った。
「全てを知っていると思い込むのは間違っている。アティン、君は全てを知っているわけではない。だから、干渉するのはやめなさい。」パブロはそう言ってアティンから背を向けた。
パブロが再び屋上の端に登ろうとすると、アティンは目を見開いた。彼女はパブロのジャケットを掴んで止めた。
「そんなことはできない!死ぬことはできないよ、パブロ!」アティンはきっぱりと言った後、すぐに彼の前に進み出た。
アティンは涙目でパブロの目を見つめて叫んだ。
「ファッキュー、ジョン・パウロ・ネース!そこから出て行け!」アティンは激怒して叫んだ。
しかしパブロは無表情のまま、微動だにしなかった。少しもひるまなかった。そこでアティンは彼の肩を掴み、二人の距離を縮めた。
「パウロ、聞こえてるでしょ。きっと今、怖いだろうね。ごめんね。あなたが一番私を必要としていた時に、一人ぼっちにしてしまって。気づかなくてごめんね。パウロ…ただ…」アティンは涙を流し、自分の気持ちを言い終えることができなかった。
「パウロ、私から離れないで。わからないの?私たちの関係を元に戻したいの。お願い…私から離れないで。」アティンは嘆願した。
女性は圧倒的な感情のせいで膝が震え、ついには地面に倒れ込み、どうしようもなく泣きじゃくりました。
パブロは、見知らぬ女性が泣いているのを見て、なぜ彼女が傷ついているのか理解できなかった。だから、深く考えずに地面にひざまずき、女性の涙を拭った。

しかし、パブロは頭に痛みを感じた。それは別人格が外に出たがっている兆候だった。
「あなたは、男??パブロはアティンを困惑させて尋ねた。
"はぁ?"
「誰かのドアをノックするときは、こう言わなければならないと言われています男あなたが神話上の生き物ではなく、人間であることを示すためです。」
「しかし、私たちの場合は違います。もし誰かが男ドアをノックすると、私たちの一人がパウロを守るために出てきました。」パブロは頭痛に耐えながら、息を切らして苦しんだ。
"理解できない。" アティンは泣きながら言った。
「私もだよ、アティン。あ、あなたの名前は男、それにあなたも神話上の生き物じゃない。でも、どうして私たち全員をトリガーできるの?」パブロはどもりながら尋ねた。痛みに呻き声を上げずにはいられず、頭を抱えた。そのことでアティンはすぐに警戒した。
「え、ちょっと、どうしたの?」
パブロはアティンの質問にただ微笑んだ。
「あなたは治療師ですか、アティン?」パブロは思った。
「初めまして、アーティン。」パブロは意識を失う前にそう言った。
「パブロ!!!」アティンはパニックになって叫んだ。