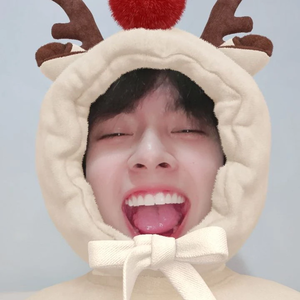2020年8月31日午前7時05分
「ポール、彼も出てきたの?」
「はい、パウロ卿。アティンさんがいなかったら、あなたは自殺するところでしたよ。」
「アティンはポールを止めたのか?」
パウロはダンテとの会話を思い出して落ち着かなかった。アティンが自分の人格をどう呼び起こすかを考え、ほとんど何も食べられなかった。
しばらくして、誰かが彼のアパートのドアベルを鳴らした。
彼はドアベルのカメラをオンにし、アティンの姿を見て目を見開いた。
「あ、どうだ、パウロ。君はアティンだ。」彼は彼女がこう言うのを聞いた。
「チッ!もう行っちゃった!私がオーラムでない限りは!私の名前はアティン。A、アポストロフィ、T、I、N。アティン!」
「ハッ!さらにヤバイぞ!」
この幻覚を見たパウロは、頭に鋭い痛みを感じた。この記憶がどこから来たのか、彼には理解できなかった。
「な、何……」
頭痛が悪化し、人格が変容しつつある兆候が表れたため、パウロは思考を続けることができなかった。
「セジュン?」パウロは意識を失う前に心の中で尋ねました。
ほんの数秒後、彼の目は再び開きましたが、今度は彼はもはやパウロではありませんでした。
彼はゆっくりと立ち上がり、ドアベルのカメラの方を向いた。アティンの姿を見ると、彼の笑顔は大きく広がった。
「もう二度と会えないと思っていたよ、アティン。」若者は心の中で言った。
「ウポだよ」
「ありがとう、ポール」
若者はそれを聞いて耳をそばだてた。
「私はパウロじゃないって、何度言ったら分かるの、アティン?この表情を覚えておいてって言ったでしょ!」若い男はイライラしながら言った。
「セジュン?!」アティンは目を大きく見開いて鼻を鳴らした。セジュンは絶望に陥った。
「え、待って。どうして――どうして教えてくれなかったの!?」
「私はあなたを試していたのです!しかし、あなたは失敗したのです、アティン。どう罰したらいいでしょうか?」セジュンはそう尋ね、彼の方へ歩いていった。
「お、お仕置きしてよ!セジュンとふざけるために来たんじゃないわよ!パウロを出て行け!」アティンはイライラしながら言った。
「チッ。出たくないのはあいつだ」
「そして、なぜ?」アティンはすぐに尋ねると、セジュンはため息をついた。
「10年前のことを思い出したから」セジュンは答え、アティンは眉をひそめた。
「どういう意味ですか?何を思い出したんですか?」
「シーッ、あなたはもうそこにはいない。あなたも覚えていないでしょう。」
「覚えていると言ったらどうなるの?」
「ありえない。パウロとの5年間の交際中、あなたは一度もそんなことを口にしなかった。」
「セジュンのことは忘れたけど、今は覚えている。10年前に起こったこと全部。」
周囲は静寂に包まれ、誰も彼らに話しかけることはできなかった。
「セジュン、私は全部覚えているよ。義兄が亡くなった日のことを。」
「どうしてそんなことを覚えていたんだ、アティン?そんな辛い記憶を、君に思い出させたくなかったんだ。」
「セジュン、全部覚えてるよね?でも、どうしてパウロは覚えてないの?」アティンは尋ねた。
「彼は臆病者だったから。あの日起こったことに向き合えなかった。いとこたちに裏切られ、自殺を目撃した。パウロは自分を守るために、あの記憶を背負わせるために私とパブロを作ったんだ。」セジュンは言った。
その言葉を聞いて、アティンは悲しさのあまり泣き出しました。セジュンは慌てて彼女の涙を拭い、ぎゅっと抱きしめました。

「あなたを忘れてしまってごめんなさい。この何年もの間、一人で苦しみに耐えてきてごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。」
セジュンは、これがアティンの罪悪感を和らげる唯一の方法だと知っていたので、彼女の度重なる謝罪をただ聞いていた。
「大丈夫。私はその方がいいのよ、アティン。あの恐ろしい記憶を、あなたに思い出させたくないの。」
アティンは抱擁を解き、セジュンの暗い瞳をじっと見つめた。その瞬間、アティンはセジュンが以前よりも少し温かく感じられたのを感じた。
「あ、はぁ……」
"ふーむ?"
「あ、その思い出をパウロと共有できないの?」アティンが尋ねると、セジュンの表情はすぐに暗くなった。
「一体全体、どうしてそんなことをするんだ?アティン、彼は耐えられない。あんな記憶を抱えたままでは生きていけない。」セジュンは言った。
「でもセジュンは――」
「本当に私を死なせたいのか、アティン?」セジュンは激怒して尋ねたので、アティンは言葉を失った。
「パウロがあの記憶を思い出し、どう対処すればいいのかを学ぶ時…それが私たちの最後の日になるかもしれないわ、アティン。だって、パウロはもう私たちを必要としなくなるから。」