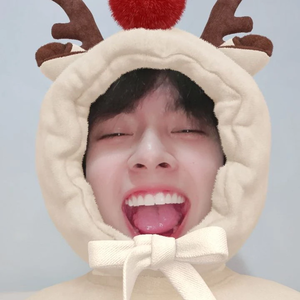「パウロがあの記憶を思い出し、どう対処すればいいのかを学ぶ時…それが私たちの最後の日になるかもしれないわ、アティン。だって、パウロはもう私たちを必要としなくなるから。」
「あの卑怯者は、苦しむたびに隠れるばかりだった。私たちの飼い主になる資格はない。弱すぎる」セジュンは言った。
アティンはセジュンをじっと見つめたが、彼が激怒しているのがわかった。
「セジュン、パウロがあんな風になったことを責めることはできない。私もあの日のことでトラウマを抱えている。暴力を目撃するたびに、あの日のことを思い出す。恐怖で震え、気を失いそうになる」アティンは言った。
「だからこそ、アティンを守ってくれる人が必要なんだ。でもパウロにはそれができない。自分の身を守ることすらできない。でも私にはできる。アティン、私が守る。10年前と同じように。」セジュンは言った。
「え、10年前ってどういう意味ですか?」アティンは尋ねた。
「あの男が自殺した朝は、私にとっても初めての日でした。ただ、手のひらから血が流れて目が覚めただけでした。その時は、痛みも恐怖も感じませんでした。」セジュンが説明した。
「あの頃、君のことさえ知らなかったのに、頭に浮かんだのは君を守ることだけだった。そして、君を救えて本当に良かった、アティン」セジュンはそう言って笑顔を見せた。
アティンはセジュンの笑顔をただ見つめることしかできなかった。パウロの笑顔と似ているのに、なぜ違うのか説明できない。
セジュンはアティンの手を握り、じっと彼女の目を見つめた。

「あなたは精神科医ですよね? パウロを始末するのを手伝ってくれませんか、アティン? そうすれば、あなたを永遠に守ることができます。彼を永遠に眠らせてあげましょう」セジュンが尋ねると、アティンは非常にショックを受けた。
アティンが怒りに任せてセジュンの頬を叩くと、リビングに大きな音が響き渡った。セジュンはすぐに立ち上がり、一歩後ずさりした。一方、セジュンはアティンの反応に驚いた。
「アティン。
「あなたはパウロだから、パウロを捨てることはできない。パウロはセジュン、パウロはパブロ、パブロはセジュン、そしてパブロはパウロ!セジュン、たとえ世界がひっくり返っても、あなたたち3人は一つ!それ以上でもそれ以下でもない。」アティンは叫んだ。
「いや!アティン、俺はもう何回――」アティンの次の言葉に言葉を失ったため、セジュンは続けることができなかった。
「愛した、愛した、そしてこれからも愛し続ける。たとえあなたがパウロでも、セジュンでも、パブロでも、構わない。私の目には、あなたは10年前に私を救ってくれた、私が愛する唯一の人だ」アティンは心からそう言った。
「でも、アティン、君は私のものであってほしい。私だけのものだよ!」セジュンは叫びながらアティンを壁に押し付けた。
一瞬のうちに、セジュンはアティンの唇に自分の唇を乱暴に押し付けた。
「でも、アティン、そんなことは起こらないって分かってる。あなたを独り占めするなんて、私にはできない。でも、感謝してる。あなたがいるからこそ、私は笑顔になり、これまで以上に夢を描ける。奇跡をありがとう。あなたはいつまでも、私の人生の愛よ。」セジュンはそう思って目を閉じ、涙を流した。
次の瞬間、パウロはアティンとキスを交わしながら目を覚ました。彼は目を見開き、衝動的にキスを中断した。
「な、何……」パウロはそう言って唇を覆った。
「パウロ!息子よ…」アティンは唇を噛みながらパニックに陥って考えた。
「は、は?えっと…だって、えっと…セジュンだから。」アティンはだんだんと声を柔らかくしながら言った。
「セジュンがキスしたの?!」パウロは大きな声で尋ねた。
アティンはただため息をつき、イライラしながらうなずくことしかできなかった。
「彼はあなたを強制しましたか?傷つけましたか?」パウロは再び尋ねたが、アティンはただ首を横に振っただけだった。
「ごめん、パウロ。私も驚いた。だから――」パウロが再びアティンを抱きしめたため、アティンは話し続けることができなかった。
「セジュンはよくやった。アティン、今どれだけ君にキスしたいか、君には分からないだろうね」パウロは心からそう言った。
「チッ。さっき押したでしょ」アティンはヒス音を立てた。
「さっきはセジュンがあなたを無理やり迫ったんじゃないかと怖かっただけ。無意識のうちにまたあなたを傷つけてしまったんじゃないかと、すごく怖かったの」パウロはそう言うと、抱擁を解く前に安堵のため息をついた。
「だが今回は、アティン、君を拒絶したりしないよ」パウロはそう言うと、アティンの顔を包み、もう一度キスをした。
長い間、お互いに想い合い、欲望を抑えてきた二人は、ついに一瞬でもそれを解放しようと決意した。
「パウロ、私たちに何が起ころうと、どうでもいい。でも、同じ過ちは二度と繰り返さない。私はあなたを選ぶ。そして、何度でも、迷うことなく、一瞬の内に、あなたを選び続ける。」