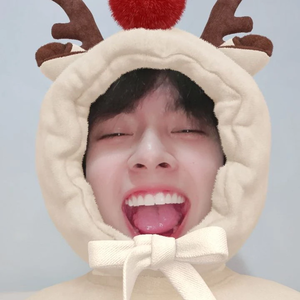2024年
「セジュン。どうして僕と話したいの?」パウロは尋ねた。
「パウロ、良くなってきているんだね?潜在意識の中で私に話しかけられるようになったよ。」セジュンは言った。
「ええ。10年前の思い出を全部覚えているわけではないのに、教えてくれてありがとう。」パウロは言った。
「それは私の記憶じゃない、パウロ。あなたの記憶だった。ああ、違う、私たちの記憶だった。アティンは私に言った。私はあなたであり、あなたは私であり、私たちは二人ともセイゼミックだ。私たちは一つだ。」セジュンは笑顔で言った。
「もう…行かないよね?」パウロは心配そうに尋ねた。
「もちろんだめよ!アティンを一人にしないでほしいのよ!」セジュンがそう言うと、パウロはただ笑った。
皆様、ニノイ・アキノ国際空港へようこそ。現地時間は午前10時24分、気温は29度です。
「ほら、セックスするわよ。アティン、起きて。」セジュンは言った。
「ああそうだ。ありがとう、セジュン」パウロは言った。
「まあ、ナセにしてよかったね。」セジュンは英雄だ。
その音とともにパウロは目を開け、飛行機の天井が彼を出迎えた。
「機内に持ち込んだ私物がないか、座席の周囲をご確認ください。また、重い荷物は飛行中に動いてしまう可能性がありますので、頭上の荷物入れを開ける際はご注意ください。」
SB19航空と乗務員一同を代表し、今回のご旅行にご参加いただき誠にありがとうございます。近い将来、またご搭乗いただけることを楽しみにしております。良い一日をお過ごしください!
「アティン、起きて。」パウロはそう言ってアティンの頬を軽く叩いた。
アティンは目を開けてパウロの顔を見つめた。
「へへ。君はパウロだね。」アティンはぼんやりしてそう言うと、パウロは微笑んだ。
アティンがどうやって自分の別人格を見分けられたのか、彼には未だに謎だ。もしかしたら、彼女が精神科医の資格を取ったからかもしれない。でも、それが本当に助けになっていると彼は認めている。
「誰か迎えに来てくれるの、パウ?」アティンは荷物を押しながら尋ねた。
パウロはただ頷き、誰かを指差した。アティンはその方向をちらりと見た。すると、黒いマスクをかぶった四人の紳士が集合写真を撮っているのが見えて、彼女はすぐに目を見開いた。

4人の男たちはパウロとアティンを見ると、すぐに次のような言葉が書かれた旗を掲げた。ようこそ、NASEさん。
「それはパウロさんに関することですか?あぁ、それはとても恥ずかしい。」アティンはそう言って、手で顔を隠しました。
パウロはアティンのほうに寄りかかってささやきました...
「忘れたのか? あなたも今はナース族だ、アティン・エラ・ナース夫人。」パウロはアティンをからかって顔を赤らめた。
「それは何のフォームですか?目立ちすぎますよ。」パウロは4人に尋ねた。
「文句はやめてください。ダンテが顔を覆うように言ったんです。記者に邪魔されたくないんです。」ジョシュは言った。
「おじいちゃんが無理やり迎えに来たんだ。チッ。予定をキャンセルしてやったんだから文句言わないで。」ケンは言った。
「念のため言っておくが、アティン。まだ撤退できるか?」ジャスティンがそう言うと、パウロは鋭い視線を向けた。一方、アティンは末っ子のいたずらっ子ぶりに微笑んでいた。
「行きましょう。このあと写真撮影があるんです。」ステルはうめいた。
5人のいとこたちは、パウロの病状を知るや否や、すぐに和解しました。アティンが本気で懇願してきたので、パウロは彼らに告げざるを得ませんでした。
後悔の念が彼らを襲ったが、時が経つにつれて、その感情は徐々に薄れていった。信じられないかもしれないが、アティンは5人の従兄弟たちとの仲裁に苦労した。しかし、精神科医である彼女は、彼らはいずれ和解するだろうと確信していた。結局のところ、彼らはナセ家、つまり家族なのだから。
パウロは、治療に集中したいという思いから、ナセ・コーポレーションの会長職をジョシュに譲りました。一方、ジャスティンはプロゲーマーになり、ステルはソロアイドルとしてパフォーマンスへの情熱を追い求め、ケンはアーティストとなり、最終的には自身の美術館を設立しました。
パウロに起こった良い出来事のおかげで、彼の状態は改善しました。彼は人格の切り替えを制御する方法を学びました。特にアティンがそばにいることで、以前よりもはるかにうまく自分のシステムを管理できるようになりました。
「パウロ、最近はもうセイゼミックに電話しなくなったね。」アティンはパウロと一緒にベッドに横たわりながらそう言った。
「ふーん。多分、前より自殺願望が減ったからかな?バキット?彼と話してみる?」パウロが尋ねると、アティンはただ首を横に振った。
「いや、ただ心配なだけだよ。また自分を抑えつけてないよね?」アティンは言った。
「はは!いや。あなたは何者?私の夫は精神科医だし、他に何を隠せばいいの?」パウロは尋ねた。
「あなたとセジュンがこれまでに何人の女性と関係を持ったか、まだ話してないじゃないですか!」アティンはイライラしながらそう言ってベッドから出た。
「あ、待て、行こう。俺のせいじゃない。セジュンのせいだ!」ポールは答えた。
「そうしたいって?セジュンと君が思い出を共有していたなんて、私が知らないと思ったの?君もきっと、自分があんなに女々しかった頃のことを覚えてるよ!」アティンはヒス音を立てた。
まあ、完璧な関係なんてないんです。特にパウロとアティンの場合は。彼らはほぼ毎日口論しているけれど、一日の終わりには抱き合っているんです。
恋人たちの喧嘩は、誰かが家のドアをノックしたことにより中断された。
"男!"
その言葉を聞いて、パウロは再び恐怖に襲われた。アティンはすぐにパウロの手を握り、微笑みながら呟いた。"大丈夫。"
アティンさんは、パウロさんがトラウマを乗り越えられるように、自宅のドアベルを取り外すことを決意したが、それは簡単なことではなかった。
「ドアを開けて、パウロ。心配しないで、私はここにいるよ。」アティンはそう言ってパウロの手を離した。
パウロは大きくため息をつき、ゆっくりとドアに向かって歩いた。
「いいえ、パウロ。彼じゃない。怖がらないで。アティンはここにいる。」パウロは何度も自分に言い聞かせた。
彼はドアノブをひねってドアを開けた。
「彼はそれをやった。」アティンは微笑みながら考えた。