
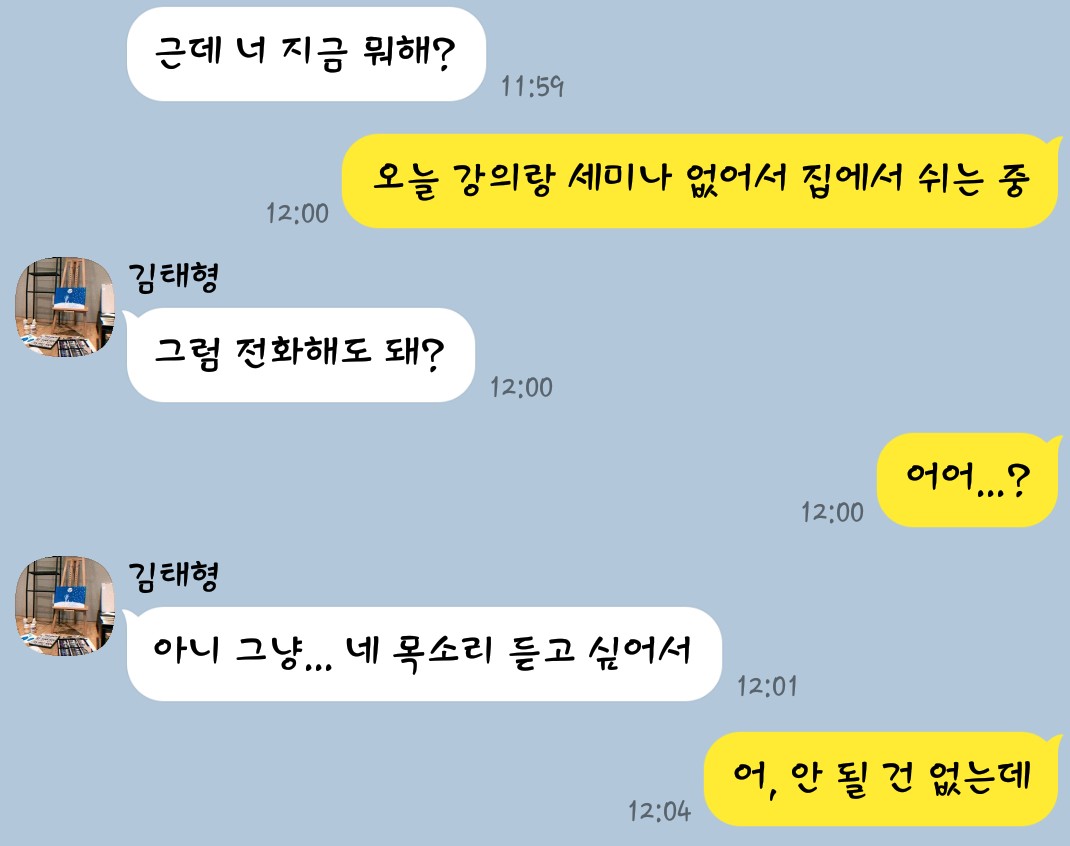
突然、フックに入って心臓発作で低世界に行きました。
しかし、なぜ私の声が聞きたいのですか…?
「あああ、大きい!理由はわからないけど、
声を聞きたいなら聞かせてくれ」
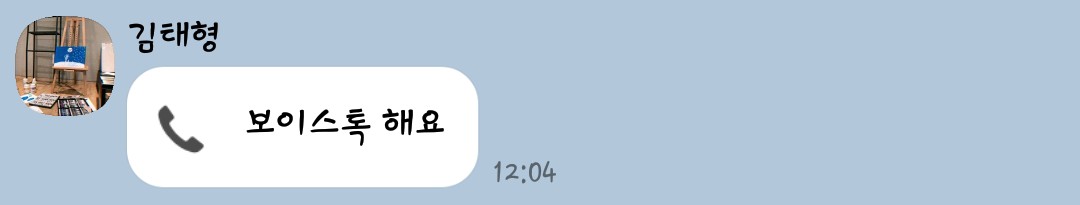
「ヒュー…震えないで。ソ・ヨジュ…!」
「テヒョンは私の友達だと思っています。
一人であまり浮かんではいけない」
きつい。
「こんにちは…?」

「トークでしか会話してこんなに声が聞こえるから、
気持ち変だ」
「私もそうです」
「私はあなたに疑問がありました」
「何?」
「幼稚園の時に私は本当に好きだった?」
「ㅇ、うーん…それは突然なぜ…?」

「私はあなたが本当に好きだった」
「あなたも知ってるよ。
「あ…///そうでした…」
「だからあなたの答えは?」
「私もあなたが好きだった……」((声が小さくなる
「うん?何って?」 ((すべて聞いたが、わざわざ聞かなかったふり
「私もあなたが好きだったと…!」
「今も私が好きですか?」
「好きではない…ファンとして」

「ファンとしてではなく、ただ私のキム・テヒョンは好きではない?」
もちろん、テヒョンが嫌いではなかった。しかし、テヒョンリーに感じるこの感情をただファンとして好きだと断定することも、それでも歌手ではないテヒョンリーが好きだと断定することも大変だった。私の心を私もよく分からない。
「それはなぜだろう?」
「まさか…あなたが好きですか?」
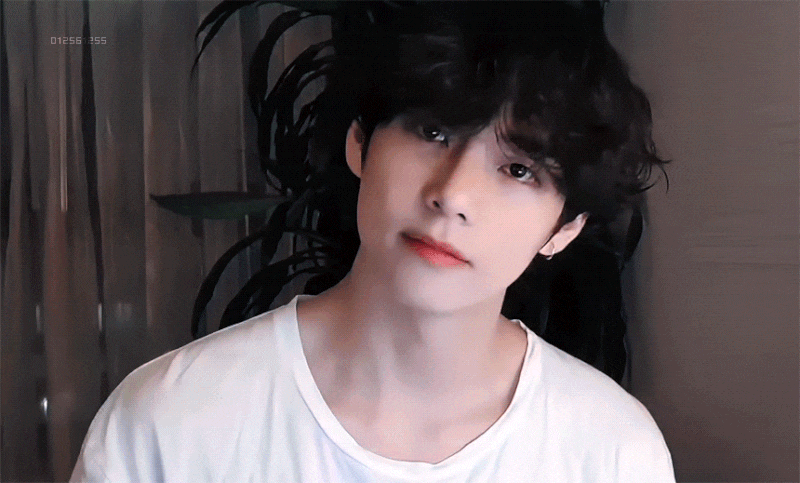
「え、私は好きです」
「え…?」
「私はあなたが好きだとこのばか」
「私が好きではない人にコンサートチケットを
救ってくれる?」
今私は告白された。それも私の最愛で、元彼氏であり、大韓民国最高のグループの歌手であるキム・テヒョンに。夢じゃないのはもう確認したから、現実だね。
「ソヨジュ、あなたは今私を聞いていますか?」
「ㅇ、えっ…聞いてる」

「今すぐ答えてくれなくてもいい」
「コンサートの日、終わって行かないで、その場で待ってください。
それから私に答えてください」
「じゃあコンサートをしてみよう」
「えええ…」
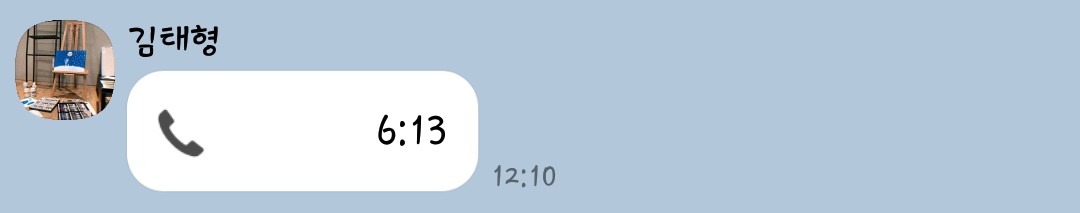
短い通話が終わって女主は半精神が出た状態で座っていた。どうやら衝撃が大きかったようだ。女主以外の人であっても、明らかに同じ状況だったはずだ。
そう気づかず時間は流れてまた流れて待望のコンサートの日の朝が明るかった。
