第1章 新入生歓迎会
程よいハイヒールをカチカチと鳴らしながら、レストランの前に立った。深呼吸をしてから、ドアを開けて中に入った。
賑やかなレストランと「♡♡大学、入学おめでとう!」の垂れ幕が出迎えてくれた。
ちょうどその時、部署の代表者らしき人が近づいてきた。
"あなたの名前は何ですか?"
「イ・ジウン」と私は答えた。
「あ、ジウン!好きなところに座ってください。」
私は彼の言葉に頷き、できるだけ目立たない席を選んだ。
席に着くとすぐに、目の前にお酒の入ったグラスが置かれました。
驚いてぼんやりと見ていると、可愛い女の子が明るく微笑んで私を見ていた。
「こんにちは!キム・ヘジンです。」
彼女はとても陽気で、すぐに笑う人でした。
彼女の明るいエネルギーのおかげで、私は自然と彼女に惹かれ、気づかないうちに自分の名前が出てきました。
「私はイ・ジウンです。」
「ジウンさんですね!プロフィール写真は白いプードルですよね?」
"うん。"
「気軽に話しましょう。私たち同い年だし!」

"わかった。"
ディンドン
「ジミンお兄ちゃん!来たよ!」
楽しくおしゃべりしていると、ジミンという男性が入ってきて、レストラン全体が彼に注目しました。
皆が彼に挨拶するために駆け寄った。
ヘジンは身を乗り出してささやいた。
「やあやあ。うちの学校には伝説のイケメン4人組がいるんだけど、その中の一人があの先輩のパク・ジミン。私たちより一つ年上だって聞いたよ。」
「本当ですか?」と私は答えた。
「彼は本当にハンサムですよね?」と彼女は言った。
「そうでもないよ」と私は答えた。
「あなたは目が見えませんか?」

「いいえ、視力はまったく問題ありません。」
私たちが話していると、ヘジンの目と口が突然幽霊を見たかのように大きく見開かれた。
「やあ、どうしたの?」
「こっちに向かって来ているよ!!」
"誰が?"
「あなたの後ろにいます。」
彼女の言葉に従って頭を回すと、パク・ジミンが私たちの方へ歩いてくるのが見えた。

彼の顔を見て、私は無意識に眉をひそめてしまった。
私の反応を見たのか、彼は一瞬笑顔を消したが、すぐに表情を正し、かすかな笑みを浮かべて歩き続けた。
彼が近づいてくると、あれは何だろうと思いました。
ジャケットを脱いでヘジンの隣に座ると、彼の腕に小さなタトゥーがあるのに気づいた。目立つが、それほど目立たない。
彼は私たちに丁寧に挨拶した。
ヘジンは呆然とした様子で返事をするのにもたつきましたが、私はかろうじてうなずいて飲み物を飲み続けました。
それまで静かだった私たちのテーブルは、たちまち注目の中心になりました。
他のテーブルの女の子たちが羨ましそうに私たちを見つめていました。
ヘジンがパク・ジミンと熱心に話している間、私は彼らを一度ちらっと見てから携帯電話に集中した。

見上げると、私たちの目が合った。
パク・ジミンは顎を手に乗せて私を見つめていた。

彼の視線は、獲物を狙う捕食動物のように冷酷だった。
私は一口飲んだ途端凍りつき、アルコールが唇から流れ落ちた。
「おいおい、飲んでるのか、それともこぼしてるのか?」とヘジンがからかった。
驚いて現実に戻り、私は急いで口を拭きながら、「しまった、口紅がついていた」と思いました。
「トイレに行ってきます」と私は言った。
「わかった!」ヘジンは答えた。
急いで外に出ると、痛みで額を押さえながら誰かにぶつかりました。
「ああ、しまった……ごめん」と私は呟いた。
見上げると—
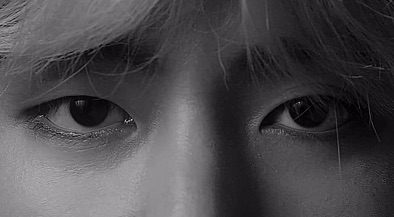
「大丈夫ですよ」
その声。
思っていたより怖かったです。
私はすぐに口紅がにじんでいたことに気づき、急いでバスルーム。

"はぁ..."
第2章 アイスクリーム
バスルームで身支度を整え、化粧を直した後、レストランの入り口で躊躇しました。
今さら戻るのは気まずい。
ヘジンはきっとまだパク・ジミンとおしゃべりを続けていたのだろう。
私は時間をつぶすためにドアの近くにしゃがみ込み、髪をいじっていました。
するとパク・ジミンが手でドアを押さえながらドアを開けた。
「コンビニに行くよ。誰かアイスクリーム食べたい人いる?」と彼は呼びかけた。
「はいっ〜!!」と中から声が返ってきた。
彼がドアを開けると、騒々しいおしゃべりは少し静まった。
彼は私がそこにしゃがんでいることに気づき、一瞬驚いたものの、すぐに落ち着きを取り戻した。
「なぜここにいるんだ?」と彼は尋ねた。
彼が私に話しかけていると分かっていたにもかかわらず、私の体は思わず固くなってしまいました。
「……ただ、」私は答えた。
「退屈してる?一緒にアイスクリームを食べに来ないか」と彼は提案した。
正直に言うと、中に戻らない言い訳ができて嬉しかったです。
私はうなずいて彼の後ろを歩いた。
コンビニは思ったより遠く、私たちの間には深い沈黙が漂っていた。
ついに彼は口を開いた。
"あなたの名前は何ですか?"
「イ・ジウン」
「ジウン…僕はジミン・パクです。新入生ですか?」
"はい。"
「気軽に話してもいいですか?」
"もちろん。"
彼は質問し続け、私は短い答えをし続けました。
たぶん彼は何とか会話を続けようとしていたのでしょう。
私たちは店に到着しました。
「どんなアイスクリームが欲しいですか?」
「何でもいいよ」
「ここで待ってて。何か取ってきます。」
"わかった。"
彼が中に入って行く間、私は外のベンチに座ってぼんやりしていました。
振り返ってみると、あることに気づきました。
私は先ほどの彼の冷たい表情だけを見て、彼をあまりにも早く判断しすぎていた。
実際のところ、彼は…驚くほど優しかったようです。
私は独り言を言った。
突然、頬に冷たいものが押し付けられるのを感じました。
彼は笑顔で私にアイスクリームバーを手渡した。
「念のため買っておきました。」
ポッポ酒場でした。
私はすぐに包みを開けて、底を一口かじりながら、こうつぶやいた。
"ありがとう。"
私たちが歩いて帰る間も、彼は満面の笑みを浮かべ続けました。
一方、私はアイスクリームだけに集中しました。
レストランに戻ると、すぐにみんなの視線が私たちに向けられました。
私は彼らの視線を素早くかわし、自分の席へと急いで戻りました。
「おお~何が起こっているの?」とヘジンがからかった。
「何もないよ」と私は答えた。
「トイレに行って、30分後にパク・ジミンと一緒に戻ってきた。怪しいわね!」と彼女は笑いながら言った。
どうやら私が不在の間、テヒョンというもう一人の先輩がやって来て、テーブルが広くなっていたようです。
ヘジンは興奮しながらそのことについて語った。
彼女がテヒョンについて熱く語っている間、ジミンは私たちのテーブルに戻ってきて、みんなにアイスクリームを配りました。
「ヘジン君は食べないの?」
「もし私にくれるなら、喜んで!」
彼女の忠誠心の変化に目を回しながら、
退屈しながら、さらにお酒を飲みました。
だんだんと酔っ払ってきた気がして、顔が熱くなってカーディガンを脱ぎました。
「ジウン、顔が赤いよ。大丈夫?」とヘジンが尋ねた。
「大丈夫だよ〜」と私はろれつが回らないまま言った。
すぐに、私の頭はテーブルの上に落ちました。
