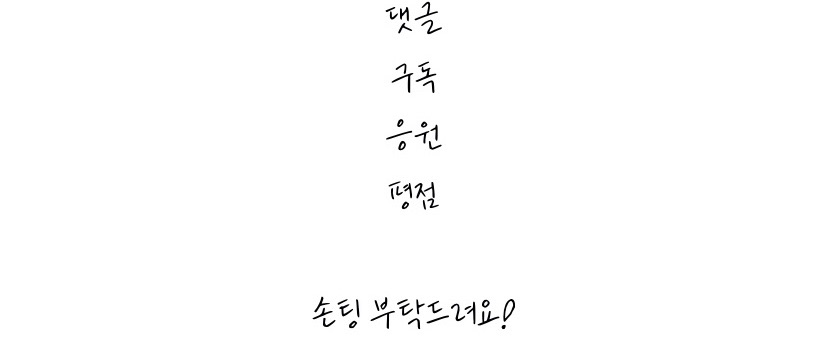私たちの別れ猶予期間は
火のような愛という言葉を聞いたことがありますか?ある瞬間に花婿燃え上がったが、またある瞬間簡単に消えるそんな愛を言う。ほんの数ヶ月前までしか私はそんなことを愛といえるかという疑問を持った。どうやって人の心が一度に盛り上がった冷えることができるのか…。正直、ちょっとちょっとしたくらいだった。
私の人生に一人の男が登場するまで、いや、登場してからも同じ考えで、彼とそんな愛をした後に私は悟った。いくら火のようでも一度来て行った心は仕方がないということを。
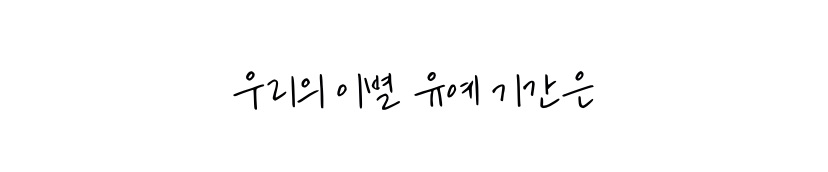
最初の出会いは単純だった。フリーランサーで仕事があった時だけ外を歩き回った私は家の近くのバス停もよく分からなかった。 20歳の時から今までソウルに住んでいたのに、私にはまだ難しいソウルだったから。その日もやはりバス停を訪れ、道を迷っていた。
「ここは一体どこだ…」
その日のために奇妙にしたいほど道を見つけるのは難しかった。いくら吉祥でもこの程度迷ったら道を訪れたのに…。何でもあるかのように同じところをバンバン回るだけだった。
結局自分で道を探すのはあきらめた。近くの路地の壁に背中を傾けてしゃがんで座った後、人が通り過ぎるのを待って、私がどんどん疲れていたときに現れた人がまさに彼だった。

「私…どうしたの?」
同様に、この近くに住んでいるように灰色のフードティーにチュリニングパンツ、スリッパを惜しむ最初の出会いだった。私は彼に向かって頭を持ち上げ、彼は心配な目で私に手を伸ばした。
「起きて、服を汚す」
「…ありがとう」
私は初めて見た男の手を引っ張って彼の力を借りて席で立ち上がり、私を起こしてくれた彼の手はとても暖かかった。それで私も知らないように力を与えて彼の手をしっかりと握り、その男はすっかり体を震わせた。
「あの…私の手ちゃん……」
「あ…!すみません、私も知らないでやめて」
彼も私もお互いに驚いて握っていた手を置いた。初めてだった。誰かの手を置くのにこんなに残念なのは。私がその人に惜しいという気がしたというだけでも私には驚くべきことだったと言う。
私は顔を赤くし、彼は恥ずかしがり屋の後ろを握った。そんなくすぐった雰囲気もしばらく、私の電話で約束時間がほぼ終わったというアラームが鳴り、壊れた。私は緊急に警報を切ると同時に彼に道を尋ねた。
「もしこの辺にバス停がどこにありますか?」
「向こうにずっと行けばあるのに、一緒に行きます!」
「一緒に行ってもらうにはすみません…」
「え、まさに前ですが、何。」
申し訳ありませんが、私はその男と一緒に行くことを選びました。ここで近いというバス停一つ探すためにしばらく回ったが、すぐに見つけることができるという保証がなかったから。男は綺麗な笑顔を見せて前に立って、私は彼に従った。
「近くに住んでいますか?」
「はい、向こうの住宅団地に住んでいます。そちらは?」
「私は00アパートを生きています!」
「なるほど近い」
バス停まで行く途中で少し話をした。その間、私たちはお互いが近くに住んでいることを知り、一緒にバス停に着いたとき、私は彼に向かって手を振った。
「今日はありがとうございました、こんにちは!」
「ちょっと…その……もしかしたらナンバー与えることができますよ…?」
彼の耳が真っ赤に染まったのを見た以上の番号を与えられなかった。まあ、実は私も少しは彼が気に入ったのかも。緊張でもいいようにしばらく躊躇する慎重に番号を聞く彼がかわいいと思った。私に向かって携帯電話を出した彼の手が気にしないように携帯電話を受け入れては被食笑った。
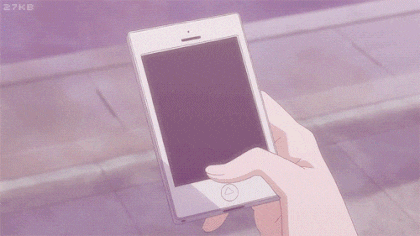
「番号を差し上げたので必ず連絡しなければなりませんか?」
「…やるよ、ぜひ」
「あ、そうだ。名前は何ですか?番号も交換したのですが、本名はわかりません。」
「パク・ジミン」
「私はキム・ヨジュ!連絡します、ジミンさん!」
彼の名前はパク・ジミン。瞬間燃える愛を信じなかった私をそう信じるようにした張本人だった。彼に番号を与えた後、バスに乗った私はまだバス停に立っているパク・ジミンを窓越しに眺めた。
多くの席のうち、わざわざパク・ジミンが見える席に座った。どんな心だったのかよく分からないが、全然全身がくすぐった。パク・ジミンは私に向かって手を振った。
「ジミン…パク・ジミン……う、くすぐる」

「また会えばいい…女主さん。」
たぶん私たちはその日知っていたかもしれません。お互いをたくさん愛することになるということ。私はガタガタバスの中で、パク・ジミンは家に帰った途中で、私たちの口にはお互いの名前がありました。