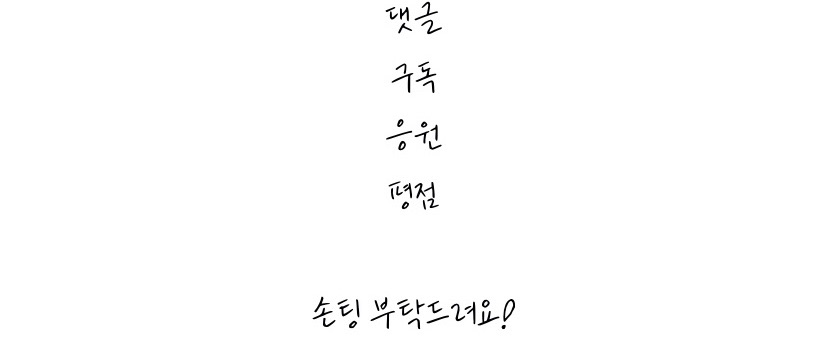私たちの別れ猶予期間は
すごくくすぐった初めての出会いを皮切りにパク・ジミンと私はよくぶつかった。本当に奇妙だった。その前には一度も惜しまなかった私たちがその日以後、家の近くの路地、マート、公園、カフェなど様々な場所でパク・ジミンに遭遇した。お互いの小指に真っ赤な糸が結ばれたように。
「これくらいなら…運命というのが本当にあるのか?」
私はいつも運命という言葉自体を信じなかった。生きることも迫力ある世界に運命なんて信じて、その運命を待つには…。自分にとってとても過酷だという考えだった。しかし、その考えさえますます変わり始めた。パク・ジミンを何度も遭遇した後は馬だ。
パク・ジミンは私にそのような存在に近づいてきた。何に惹かれたかのように、私は彼が私の運命であったかった。

「ジミンさんもそうしたらいいな」
誰かに見せた恥ずかしい顔で枕を必ず抱きしめた。恥ずかしがり屋のように丁寧に口、ベベのねじれの体、そして赤くなった二つの頬まで。永遠に恋に落ちたような私の姿がぎこちなかったが嫌ではなかった。なんだかそのやはり私と同じ状況だと思った。
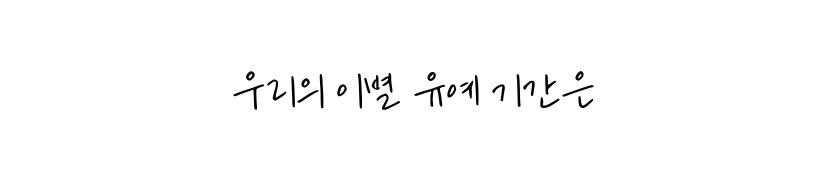
一日が経つにつれて、パク・ジミンと私はますます近づいた。会う回数も、連絡が行き来する回数も増えたが、関係に対する変化はなかった。ただお互いの年齢を知り、好きなものを知り、言葉を楽にするほど。ちょうどそれほどだった。
曖昧な関係が持続したか1ヶ月ごろ、性格急な私がパク・ジミンを浮かべることにした。気づかなかった私だったので、パク・ジミンの心がある程度見える時点で、パク・ジミンは明らかに私と同じ状態だった。よく死ぬが、いざ告白するのは怖い。
「ジミンああ、私は悩んでいます。」
「何?」
「好きな人ができたのに…その人が私をどう思うかよく分からないと言わなければならないのか?」
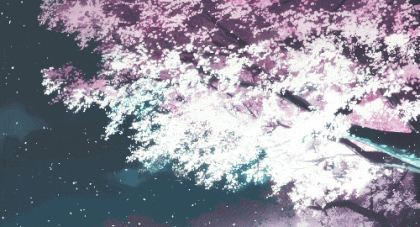
春の終わり、天から桜が注がれ、桜の葉よりも濃いピンク色を帯びた私たちがいた。優秀に落ちる桜の間を歩いた私の足が止まり、足を止めた私を後ろにしたまま先に行ったパク・ジミンの足もやっと止まった。
「…どんな人なんですけど」
私は少しずつ漏れてくる笑いをやっと越えて、パク・ジミンの姿を後ろから見守った。こんなことを見れば私は実は彼の心を既に知っていたのかもしれない。好きな人ができたという私の言葉に先に行った体がそびえ立つパク・ジミンであり、私は数歩離れたところで答えた。
「うーん…見るだけでも笑いが出てくる人?」
「……」
「とりあえず可愛いのに、カッコいい。そしてハンサムだよ!」
「…そうだね」
「私より若いのに成熟して、すごく優しく、また…もっと教えてくれるか?」
これくらいならほぼ全部教えてくれたわけだ。私の好きな人がパク・ジミン君だと。だが、気がつかないパク・ジミンは全く気付かなかったようだった。まだ私を背負っているのを見たら。
「いいえ、しないでください。」
本人に対する説明であることも知らず、もはや本人について話してはいけないという言葉とともに、全身を回したパク・ジミンだ。表情はいっぱい固まったのも足りなくて、すぐにでも涙を落としそうだった。
恥ずかしかった。私たちの間を確実にしたかっただけで、しばらくからかっていただけだった。絶対パク・ジミンを鳴らす心はなかったが…。パク・ジミンは長い足で盛んに私に近づいてきた。私の前に立ったパク・ジミンは真っ赤な目元を一度見たら頭をすっかり下げて私の襟を軽く引っ張った。
「私も見てください、姉。」
「え…?」
「おそらくその人よりも私がはるかに好きだ」
パク・ジミンは知らない。その言葉を聞く瞬間、笑いが出るのをようやく我慢した僕を。もしかしたら私が本人を置いて行ってしまうか私の服袖を握った手にはさらに力が入った。

「だから…その人好きじゃないと……」
可愛い投情でしか聞こえなかった。襟をぎゅっと握った手で、すっぽりと堕ち、少しずつ震える声で。その人ではなく、本人を愛してほしいというパク・ジミンのすべての言葉と行動がただ可愛いだけだった。唇をきつく噛んで、二人の目を引き締めて笑いを我慢しようと努力したが、結局我慢できずに笑いを破った私だった。
「ふっ…ふふ…!」
私が笑いを放つと、パク・ジミンはふくらんでいた頭を持ち上げた。本気を話した本人の言葉をいたずらに渡すと思っただろう。
唇は飛び出してきたが、依然として私の服の袖は置かないパク・ジミンに存分に笑って見た後、笑って結ばれた涙を指で書いた。その後、袖を握っていたパク・ジミンの手を握って両目を合わせた。
「パク・ジミン、あなたになるのはかわいいことを知っていますか?」
「かわいいですよ。」
「あなたが私を毎回笑わせるのは?」
「え?」
「あなたじゃない、バカだ」
向かい合っていたパク・ジミンの目が丸くなった。私はもう一度彼を見て被食笑ったし、パク・ジミンの目元がどんどん赤くなるようにしたかった。私はそのようなパク・ジミンの顔に私の両手を置き、パク・ジミンは私の手の上に自分の手を乗せてそのままつかんだ。
「好きだ。私と付き合った人、ジミンああ。」
笑いながら伝えた私の告白にそのまま私を懇願してしまったパク・ジミンだ。パク・ジミンはしばらく自分の胸から私を放してくれなかったし、少し息が詰まっているような感じさえ好きに口を伸ばした。
春の最後の桜の花びらが吹き飛ばされた日、私たちはすぐに熱く燃える炎の中で愛を始めました。