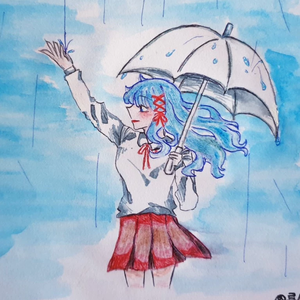「あ、席がない」
彼氏と言ったのは気にしないのか席がない状況を嘆くだけだ。
「隣にいてもいい?」
「兄はいつから私にこんなに親切だったと?
いくらでも隣にいてください~」
細く折れる彼女の目笑いがきれいだ。恋に落ちた少年に女の子のどんなものがきれいではないかだけは。
「ミングちょっと素敵だった」
「…大丈夫?」
「何が?大人と誤解されたの?」
「いいえ。私があなたの彼氏だと言ったことです」
大丈夫かと尋ねたとき何が、 と答えたのを見れば最初から傷も受けなかったという話だ。幸いながらも幸いではない。
「それなんだ…でもそういう言ってもいい?それなりのアイドルじゃないか」
私よりずっと小さい彼女の頭をなでる。再び黒色に染色したが、髪の毛が悪いのは相変わらずだ。
「これほど仕事は起こりません。」
頭をふさぐ彼女は頭をうなずく。
「助けてくれて…たくさんありがとうございました」
オグル通りは言葉をよくしながら今日はかなり恥ずかしいようだ。頭まで熟したまま言うのを見たら。
「うん」
私の答えにはやっと頭を聞いた。そして私に向かって笑ってくれた。私も彼女に沿って笑ってくれる。
「スカート…減った?」
心が今着ている服は私と違って制服だ。制服への愛着が違うのでそうだっただろう。とにかく初めて着てきたその日よりスカートがちょっと…いいえ、短かった。藍色に近い黒のスカートはA型だった。そのスカートは思ったより多く上がっていた。膝上にした15cmは軽く上がっていた。
「うん…おかしい?」
変じゃない。むしろきれいなこと。この状況で綺麗だと言っていいかもしれないけど。隣の男たちの視線がさかのぼる。なぜ彼氏が彼女に短いスカートを着てはいけないのか知っているようだ。しかし、私はあなたの本当の彼氏ではないので、明るいふりをしてみてください。
「ええ、私はあなたの彼氏ではなく、なぜスカートの長さを
心配してくれます。しかし、試してみると少し
不便かもしれませんか?」
「体操服も持ってきたよ」
「ただ制服を着たかったんだ」
「制服は私にとって特別な意味ですか。
修能はぜひ制服着て行きたかった」
特別な意味とは「平凡」を意味することだろう。現在心の願いもそれであり。とにかく私たちと結びついた以上、もはや普通に生きることはできないでしょう。大丈夫かな。
「あ…すごく緊張する。黒告示のせいで私の身がないから定時を上手にしなければならない」
彼女の言葉を聞いていなかったのではない。ただ私の神経は彼女の短いスカートに行っていただけ。少し気づいてより彼女の後ろに行って立った。それだけで安心になった。
「うぐ、どうせ来年も打つことができるじゃないか」
後ろから彼女の頭をなでる。私が席を変えたのを知っている気がしたが、なぜそうなのか分からない気がした。そのようなときめきは過程を経て中央高に到着した。学校の建物の正面、私は言葉を取り出した。
「私…2番で打つのに」
「私は4番。」
一緒にランチ食べるか、と聞いてみようとするのに心が先に選ぶ。
「ただランチ食べに来ると言ってもいいのに」
「ヘン、バレた。
どうやら試練に当たる私が行くほうがいいだろう?
心のある踵を最大限に聞き、私の頭をなでる。腕が長いほうだからかといって、それに対する難しさはないようだ。
「うん、そうしてほしい。思いやりありがとう」
彼女の手をやさしくつかんだ後、目の高さを合わせる。
「うん、これからもそうします」
私はこのようなことを言っていますが、なぜ私がときめくのですか。それでも不幸中幸いか彼女の顔もたくさん赤くなっている。

数科目を打った後、ついに昼休みだった。水能だからランチタイムの時も移動が不可能だと思ったのに十分可能だという。嬉しくて浮かんだ心を隠し、思いもなく心が受能を打つ4班に向かう。
「え、ミンギュ兄さん!」
窓際に最も近い席、そして一番後ろの座。一番隅に座って私に向かって手を挙げてみる。彼女は彼女の席の隣に所有者のいない椅子を引いて私に座るように勧めました。この椅子の所有者は私のように別の半分に昼食を食べに行きました。
「うまく打った?」
「一応は。でも残ったのが問題だ…」
自尊心が高いと自負できる彼女にも不安な部分が勉強のようだ。どんな結果にも満足していません。だから勉強成績がとても高いのだろう。
「残りは英語ですか?」
「うん。英語と、第2外国語」
「ほとんどのネイティブレベルで英語だった。
私が見たときは本当にうまくいく」
気になる口に入れたご飯を呑みながら答える。
「普段全く書かない言葉が出てくるからそうです。
私は通常韓国語を話しながら頭の中で
英語に翻訳中ですが…これは大変です。
おそらく、シュアの兄弟も解けませんか?」
「その…くらい難しい?」
「私たちのミング兄はどうしますか?」
「は…むしろ日本語だったら」
私の言葉に心のキックキックで笑う。
「あ、日本語は上手い?少し日本の現地投入ではあったけど」
「じゃあ、もちろんその前にも頑張ってたんだけど、
やはり現場投入が直方だ」
彼女は頭をうなずく。バケツを求める信号に彼女の手にバケツを握ってくれる。化粧のせいかバケツには彼女の唇が最小限に届く。
「それでも頑張ってください。ああ、SEVENTEEN、
今日のスケジュールがあっても終わる時間を最大限に合わせてみた。
メンバーが遅れば兄と僕と一緒にいればいいな」
「うん、一緒にいればいい。前にカフェもあって、
あなたが好きなブックカフェもありました。
たくさん遅れたらそんなに行こう」
「本当?本物のブックカフェもありますか?
と、メンバーたち遅れてほしい… 」
被食の笑いが漏れてきた。彼女に遊ぶのは読書だ。もちろんそれを乾かしたり、そんな考えは全くなかった。むしろそのような趣味は好ましい。しかし、私にもう少し気を使ってほしいと思った。
「できた。終わればお腹がすいたじゃない。心が君もファイティング!」
心が今着ているのは名札のない制服だ。名札は普通学校で一括して分けてくれるもので、それにないのが当然だった。だが普通の人生を望む彼女に名札一つが持つ意味は大きくないだろうか。高校の担任に連絡してみなければならない。もしかして可能かもしれないから。
「うん、ありがとう!」
明るく笑う彼女の顔が綺麗だった。彼女の笑顔をもう少し守りたかった。春のように華やかな彼女の笑顔に外の目が溶けているような錯覚を受けた。