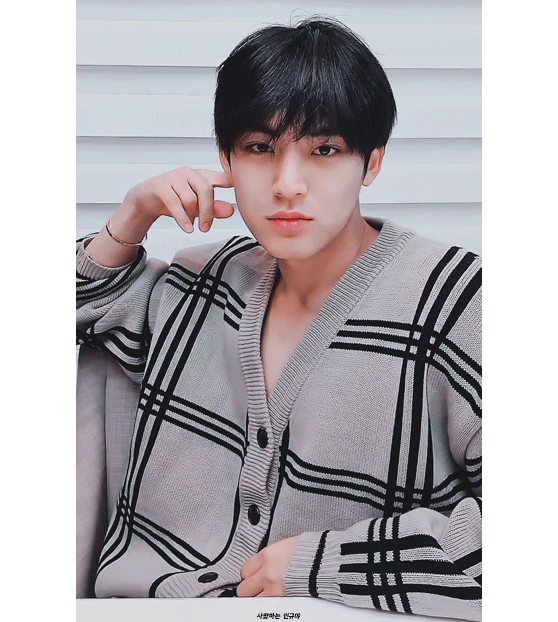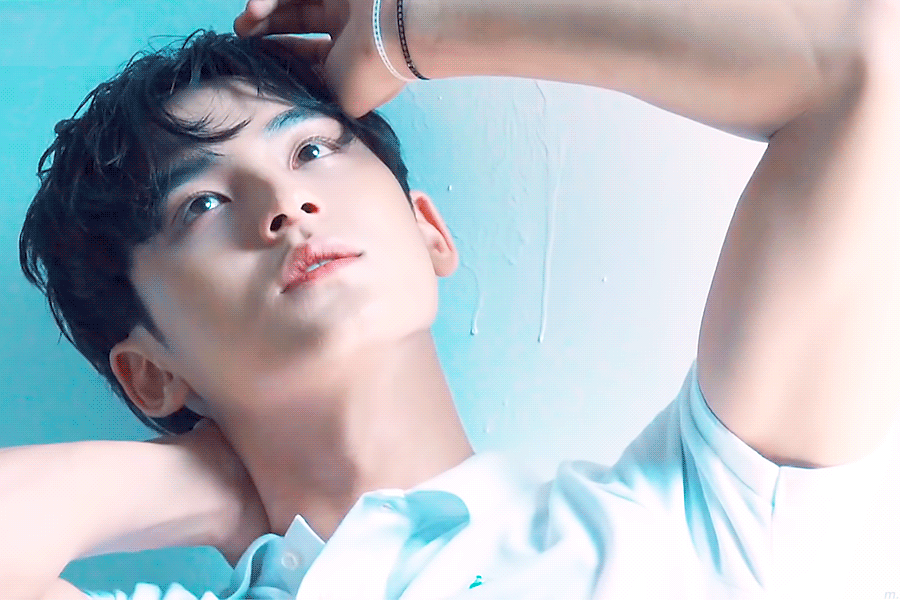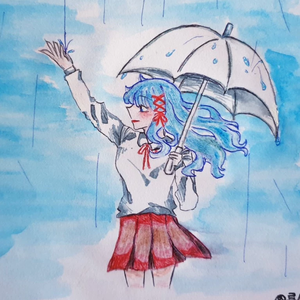肩に濡れた水を落とした。ああ、そうです。白いシャツを着ていることを忘れてただ走ってきた。まだ映っていないので幸いだと思って傘コーナーを見回した。
「これは一つしか残っていませんか?」
アルバ生のかなりきれいな声が一つしか残っていないと答える。もちろん私たちの心は声がもっときれいだったが。少し弟バカになった気分だが、こんな気持ちが悪くなかった。
「学生の方がかなりたくさん買ってくれました…」
再びその声が聞こえ、そちらに首を回す。女性の方でしたが、芸能人を一生懸命見て生きる私にもかなりきれいな方に属する顔だった。猫のように上がった目元、鮮やかで高い鼻。そしてきれいに曲がった笑顔の口。そしてピンク色が回るパアルガン唇色。このように表現することに対するものにオーバーはない。現実そのままを形容するのだ。しかし、ちょうどそれくらいだった。客観的にきれいだが主観的な視点では、私たちの心がもっときれいだった。猫さんよりも子犬の像が好きで、あんなにシャープにできたことよりも可愛くできたのが好きだった。
「大丈夫です。いくらですか?」
財布を開けて尋ねた。
「3500ウォンです」
反応の代わりに財布から4000ウォンを取り出す。彼女に与えると、彼女は500ウォンをさかのぼって言う。
「私…私の理想のタイプですが、電話番号をお願いします」
芸能人だと明らかにするのをあまり好むほうではなかった。芸能人だと明らかにした瞬間、あまり関心のない人々もまず駆け寄ってみて。それで、私の心を言うことにしました。
「すみません。好きな人がいます」
名前がわからないコンビニアルバは優しく笑って言う。
「大丈夫です。元気になってほしい」
「ありがとうございます。」
ここでうまくいってほしいと応援を受けることはない。うまくいって欲しいのに、争いのライバルが多すぎます。口の外では絶対に取り出さないと言ってコンビニを出た。
ミント色の傘を広げて広げる。遠くから心のシルエットが見えた。チルパクパク、水が故人の水たまりのおかげで、水がズボンまですべて飛び散っている。彼女に到着するとすぐに、彼女は私を心配しています。
「ハル…お兄さん全部濡れたの?」
「こんなに全部濡れるとは知らなかった」
「そんなに愚かな時じゃない。今みな親友だよ…」
「顔はなぜ赤くなるのですか、心の量」
「ㅇ、いや…」
最近の運動を一生懸命やろうとうまくいったようだ。ハ、この渦中にこんな思いもしているなんて。
「体がいい」
「いや…そうなのに。それを本人の口で…」
「なぜ、わくわく?」
心は赤くなった顔を隠すために頭を下げてうなずいた。そんな姿さえ可愛く見えた。
「すごく素直なタイプですね」
心は私の言葉に再び頭を持ち上げて私をじっと見つめた。
「なぜ?」
「率直なタイプであることが判明したキムに」
心は自分のマイを脱いで私の肩に囲んだ。身長差のために大きな差がありますが、小さなマイがかわいいです。
「小さすぎるの?効果があるかな~」
「小さいことを知っているのに…映るのは嫌だ」
彼女の頭をなでてくれた。肩からは私のサイズよりも数段階は小さいマイが落ちそうだった。もう一方の手で肩に戻します。
「後で笑うまで死ぬと言うの?」
「セブンティーン笑わないのは本当幸い…」
「しかし、あなたはいつも見ますか?」
これは事実だった。メンバーの中に気をつけないメンバーもかなりあった。スンチョルが兄、ジュンヒ、ウォン、ジフン、そして私。残った本当の気をつけようとしているようだが、たまに心が笑うことを見せた。
もちろん故意ではなかっただろうが、心は初めてその姿を見て目一つ驚かなかった。むしろ体がいいと感心するまで。理由を聞いてみると男の子たちもたまにそうだったと。うわー、本当にあなたの男の子たちは何ですか。
「お兄ちゃん!あえてそんなに覚醒すべき?」
「いいえ…ただ見たことがあります。
これまでする理由が何かしたかったんだ、私は」
「他の人が見るのは嫌だ。
とにかく、私は本当に小さな行ってください」
結局落ちたマイを心が拾った。私にまた与えたが、それはなかった。
「20cm差だから小さいしか。
心がそんなにかたまりのある方でもないのでもっとそうだ」
「ただ服屋に行って何でも一つ買うか?私が買ってあげる!」
「ええと、この子。
私があなたに何を買うのを受けるのを見ましたか。
「それじゃないけど、私の書くにはとても笑うと思うから」
「最大限に照らすよ。心配しないで」
「わかりました。しかし、傘はなぜですか?
私と一緒に使いたくて〜?」
「そんな私心満載の理由ではありません。
傘が一つしかなかった。生徒がたくさん買った。」
死心いっぱいの理由が全くないとは言えない。彼女とした傘の下にあるのが望んでいたから。しかし、心が不快になれば、いくらでも私心をしばらく排除することができた。彼女のためにできないことはなかったから。
「あ、そうだ。じゃあ一緒に書いていこう。大きさも大きいね」
彼女はさりげなく吐き出した。私は彼女の兄弟よりも友人であり、男の子の友人でもなくただの友人でした。男では1度見ない存在。それが彼女が私を見る時だった。
しかし、私はなかった。あなたが感情なしに言うすべてが私にはときめきに近づきます。普段は気にしなかった心臓が狂ったように動いて、ときめきでいっぱい生きていることを感じて。あなたは私の人生の理由であり、人生を続ける原動力です。
「ブックカフェはどこですか?早く行こう!」
あなたの言葉にやっと気をつけて君の考えば、現実からどんどん抜け出す傾向がある。
やっと考えを唱えて傘を開ける。
「つけなければならない…だろ?雨に合うには」
「うん、わかった。腕を組むか?」
それが一番良い方法ですが、私の腕が私の腕に触れる瞬間、私の心拍があなたに聞こえないかもしれないか。それを大胆にすることはできません。
私は右手で傘を聞き、左腕は心の右腕が届いていた。ここで重要なのは彼女は何気なくなかったということだ。
「今回の能力はどうだった?」
「私…いつも難しいよ」
私の答えでは、彼女は彼女のユニークな笑いでハハ笑う。ああ、本当に笑うのを見るだけでも幸せになる。
「そう言ったらどうしよう。
私は今回の能力が不可能なのか、水の能力なのか
区別がない簡単なことだ。
ああ…不可能だったらいいな私になるのが好きだと思います。
腕が彼女の腕によって束縛されたがなかったら、彼女のボールをつまんでくれただろうと思って答える。
「おぐ、よく打ちましたか?」
「ええ、私は簡単でした。しかし、周りの人は難しいです。
するようだった。しかし、これを少し置いてはいけませんか」
私も知らない鳥に彼女の手を握っていた。腕を組んだ状態で手を握るとかなり不便だった模様だ。
「嫌いなのに」
「いや、なぜ!」
私は私も知らない鳥に彼女の方に傘をもう少し傾けていた。気をつけて左肩がたくさん濡れていた。心が確認したら心は少しも濡れていないようだった。幸いだった。