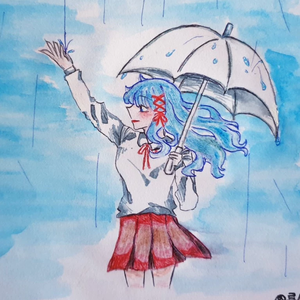ほぼ全部来たというスンチョルが兄の連絡を受け、北カフェから出てカフェに入った。ただ飲み物を飲んできた状態で、ちょうどイチゴのかき氷を一つさせた。
「受験票割引になりますが、もしかしたら受験生ですか?」
「あ、はい。しばらくしてください」
バッグを後ろに受験票を提示した。定価でなんと5000ウォンも割引してくれる。と、受験票ちゃんなのに。
「10000ウォンです。」
そして計算はミンギュ兄さんがした。一体何故私が買おうとするのは全部防ぐのだ。私は兄に感謝を返す必要がありますが、彼らは私に機会を与えませんでした。彼ら別では配慮と言うだろうが、間もなく気に入らない配慮が出た。
「はい、しばらくお待ちください。」
振動ベルと一緒に領収書を受けて席をとって座る。まさに振動ベルを転がしていたずらを打つ。そんな日見ていたミンギュ兄さんは尋ねる。
「受験票が割引される場所がたくさんありますが、遊びに行きませんか?
俺はスケジュールだなんて忙しいけど君はいないじゃないか」
「あまり。勉強にそんなに酷かったわけでもなく、
次も修能しなければならないようだから。
元気なのはただ感じだから。
決定的に私は一般の友人がたくさんいない」
「私が見たときはとてもよく打ったと思いますか?
心が欲しい大学につけることができるんだ」
彼の応援に気分がくすぐる。胸の中の深いところで何かうずく。
「言葉でもありがたい、お兄さん」
意図しない方言が流れてきた。ヘヘン、方言をこんなに置いて書いたことはないようだが。手に握っていた振動ベルのためにミンギュ兄の反応をすぐには見られなかった。ミンギュ兄弟カウンターに行き、かき氷を持ってくるまで時間のタムがあったから。
「あなたは時々ウォンウ兄弟、ジフン兄弟と
似たような方言を書いているようだ。故郷はどこですか?」
「ウォン兄と同じだ」
そう答えてスプーンを聞いた。イチゴのかき氷が思ったより美味しかった。プレーティングもゴクイルだったが、写真を撮ったりすることはしなかった。寝て食べ物はまっすぐ口で食べなければならない。
「ワンウ型故郷が…」
「昌原」
「あ…遅れ…あ、気持ち悪い」
ピンク色のかき氷を食べながら煩わしい。
「一体兄弟がなぜ気分が悪いのか。」
かき氷だけを叱りながら一人でなく一人で言う。予想価格は答えがある。なぜか彼の答えが待つ

「嫉妬韓隊」
いつ現れたのかウォン兄弟特有の重低音のボイスが私の耳のすぐ隣で聞こえた。ミンギュ兄に望んだ答えは、ワンウ兄から出た。すごくびっくりして声を上げた。
「びっくり!」
ワンウの兄は私の音に驚きました。ウォン兄はミンギュ兄と同じくらい顔を隠していた。黒い帽子の黒いマスク。調べるのが不思議だった。私もウォンの兄であることに気づいたのは声のためだったから。
「私たちは何をしているのか、どうやって知りましたか?」
ミンギュ兄さんが尋ねる。私も気になったことだった。
「中央郷で一番近いカフェに行って…
なくて次に行ってからまた来た。どうでしたか?」
私たちがブックカフェにいる間、ここに来たようだ。さて、私たちがここに来たのはしばらくしていませんでした。
「ブックカフェ。女主が行きたくて」
時々その兄が不思議になる時がある。二人がいる時は、気軽に心と呼んでメンバーたちだけ現れたら、間違えずに女主と呼ぶのが。芸能界で働くには、この程度は必要な能力なのか
「ヨ・ジュウウー!
チョンハンが兄も同じだ。一度くらいは間違いをする時もあるのに。
「それなり?」
「ああ、やっぱりウル姉さん」
「お姉さんじゃないからそう…」
ウォン兄はいつまで姉という表現を書こうとするんだ。
「よく打ったらしい。俺は全滅したんだけど」
スングァンが兄は滅びたという事実を楽しんでいる感じだった。
「私、これ食べてもいい?」
この渦中に気付かない純英が兄のかき氷を見て尋ねる。私は頭をうなずく。それを買ったのはミンギュ兄だったが意思決定はなぜまた私がするのか。このオニャオニャはいつまで続くだろうか。
「言わなくてもわかります、副承官さん」
「ヘヘン」
「賞賛ではありません。」
「それもわかりました」
「クレイジー…なんて愛嬌…」
ハンソルが兄が極嫌なように言った。ではないふりをしても他のメンバーたちも同様のようだ。
「ちょっと頑張ってはいけない。
スンチョルは兄が尋ねる。
「見ても見えない。団体で聞いて寝なかっただろう」
「おお…チェ・ハンソルどうやって分かった…」
スングァンが兄はこの状況さえシンナ見える。ええ、むしろ楽しいのが良いです。
「スンヨンはどうですか?よく打った?」
「仮採点結果300点?ちょっと越えたのに」
「なんだ…思ったより上手だったのに。兄が…?」
「あなたは一体何をしているのかわからない」
スンヨンが兄の言葉に横からミンギュ兄が変わる。
「何で見たもので見て。勉強できないお兄さんだろ」
正解という意味で薄く笑って見える。
「さあ、やめて、ご飯や食べに行くか?」
シュアの兄が状況を整理した。そうだ、そうしようと出会ったんだ。
「そう。じっと置いておけば本当の戦いになるね」
「戦うのは日常じゃない?」
その日常は激しい戦いではありませんが、
「がん、日常だ」
チャンイの言葉にスンチョルが兄は額をつかむ。戦いが起こったら、通常仲裁は乗組員が兄だから
「じゃあ戦ったのか…」
「それはまた違う、兄。」
ソクミンが兄の言葉はすでにスンチョルが兄も知っていたはずだ。スンチョルが兄もセブンティーンで、こういう言葉がいたずらであることを既に知っているから。
「早く行こう!私の兄たちを待っていた!」
私はスンチョルが兄の腕に腕を組んで話す。なぜしたのかはわからない。ただそうしたい気がした。そして心をただ追っただけだった。ああ、兄弟という表現はチャンちゃんまで含めれば兄たちという表現を書くには合わなかったがなぜか彼らはメンバーたちという代名詞を特に好む気はなかった。おかげで住んでいたのに、幸せだったのにこれくらい何もなかった。
「何を食べたい?」
スンチョルが兄が別の手で私の頭を撫でてくれる。まったく気分が良くなる。
「まあ。何を食べるの?何を食べなければよく食べたと噂が出るのか?」
「うん、うわさは絶対にないよ~」
かき氷はいつ食べたのかボウルはいつの間にか空いていた
「ち、悪かった」
結局14人が食べたいすべてを食べることができなかった。今日の主人公たちは受能した人だったので、スンヨンが兄とスングァンが兄、私とミンギュ兄が相談して決めることにした。
「チャジャンミョン!チャジャンミョン!」
スンヨンが兄は恥ずかしくないか少し声を上げた。は、お兄ちゃんほど官種も見られなかったけど…。大きい、おめでとうございます。
「ジャジャンミョンは何…私たちのカルジルに行こう!」
カルジルに行こうというのはステーキを食べに行こうという意味だった。もともとステーキ高価なのに14人で食べると、いくら出るのか。 1人当たり10万ウォンで握っても140万…考えないようにしましょう。ステーキハウスは個人別に行くことにしよう。
「ヨジュ君は何を食べたい?」
ミンギュ兄の突然の優しい言葉。もともとこの兄がこんなに優しいのか。
「え?私は何でもいいの?」
ステーキを除いて。そんなに高価なのは食べるのも負担になりそうだ。
「え、それはなんだ。食べたいことはあるんじゃない」
ウォン兄が私を心配してくれた。私は本当に何でも大丈夫だった。修能を打つことができるとは思わなかったし、水能を打つとしても美味しいものを食べに行くことができると夢でも想像できなかった。私はそう生きてきたので、このような好意に適応できませんでした。
「大丈夫、長女。何でも買うから言うだけ」
ジュンフィ兄さんが私をぐっと見下ろす。瞬間お兄さんに貪欲だった。まあそんな感じに見つめるかと。いつの間にときめくのではなく、貪るレベルになった。それだけ私がそれらを楽に考えているだろう。
「大丈夫、教えてください」
ハンソルが兄の言葉にその頃食べたかったのが思い出した。心の片隅に編みこんだ涙でも洗い流されていなかったその味がついに思い出した。
「本当…なんでも大丈夫? オシャレじゃないけど…」
「世の中に素敵な食べ物はないのに」
食べるのをとても好きなミンギュ兄さんが言った。私を安心させようとする目的はなかったでしょう。私は安心して私が食べたかった食べ物を口から出した。