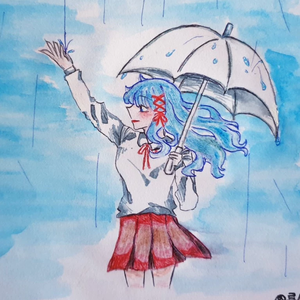「女主の言葉を聞くと私たちに一体何故聞いたのか」
ソン・グァンが兄の言葉の内容とは異なり、彼のイントネーションは非常に穏やかだった。何の不満がないように、むしろ満足しているように笑って見えた。
「礼儀上聞いたことがある」
ジフンが兄が硬く答える。隣でスンヨンが兄が道具を踊る。
「そうしたら聞いてみようか…」
私が食べたいと言ったのは庶民の食べ物だった。まさに「カルグクス」。しかし、私がここに来る前に私は庶民でもなかったので、私にとっては特別な食べ物でした。箸をまともに触れる。イェナ姉の顔がまだ良い。
「もともとこんなこと好きだった?」
ミンギュ兄弟が私に尋ねる。今日のコンセプトを何で捉えたのかは分からないが、兄の性格とまったく反するものではないという気がした。有毒に似合ったから。
「子供同士がとてもおいしく食べた記憶があります。
ああ、もちろん孤児院の子供たち。
その時…小学校5年生だったんだ」
「そうだった。おいしかった?」
「うん、すごくおいしかった。イェナ姉さんだったのに、
そのお姉さん高校卒業式の日にお金を集めてきた」
今ジョンナという表現を書くのが合うようだが、このようなことには悪口を書きたくなかった。
「おいしいお店だったみたい」
ハンソルが兄の言葉に小さく首をうなずく。ひとつで非常に縛られた黒い髪が私の首を少しずつ打つ。その日もこの頭をしていたのに。
「それもあったのに…」
何の感情が聞こえないのかと尋ねたら、私の答えはNOだった。しかし、それで難しいのかと尋ねたら、私の答えはやはりNOだった。完全に大丈夫なことだった。顔と名前しか知らないその姉が今どこに住んでいるのか、どのように生きるのか分からず、特に親しい姉ではなかった。
だがメンバーたちが私を心配するか言いたくなかった。私が言うのはただ私が克服した少し不運な過去に過ぎないということを知ってほしいと思った。
「うん、言い続けてもいい」
チョンハンが兄だった。私をその地獄から取り出した人、私を無限に考えてくれるどんな形容詞でも形容できない優しい人。
「…高校卒業が意味するところをとてもよく知っていた。私の友達は知らなかったが…」
高校卒業は大人という意味で、
もうお姉ちゃんに会えないと思って泣いた。
ただ…泣き叫んだ」
「続想した…そのお姉さんとたくさん親しい?」
ちゃんが尋ねた。友だちだけど友達以前に私の人だったし、彼は他のメンバーと違って友達の観点から心配してくれた
「いや、特に親しくなかったけど…好きだったんだ。
唯一の高校生の姉だったから。
今考えるとなぜ唯一だったのか分かるけど」
集団的に暴行が行われたから。どうやって彼女は耐えられないのか分からない。どのように大人になるまで、その地獄のような場所で生き残ることができたのだろうか。おそらく生涯答えることができない答えだった。私としては不可能なことだから。
「どこに行ったらそんなに美味しかった?」
やはりチョンハンが兄だ。もう話したくないことを、いや正確にはメンバーたちが私を心配するのが嫌だということに気づいた。私は今笑って話すことができますが、あえて同情を得る必要はないから。
「どこに行ったの?」
続いてシュア兄さんが自然に雰囲気をさらに回す。私はありがとうの意味で笑って見えると言う。
「ここ。」
「ああ、それではここはとてもおいしいです」
チャンイが唾液を飲み込んだ。芸能人だからこんなこと食べないと思ったのに偏見だけだった。メンバーの中のチャンイは本当に特に好きだった。
「うん、だからここに来ようとしたんだ。
道の複雑な台にもかかわらず… 」
「期待してもいい。長女酒が美味しいとした家なら…」
「うーん…얜ちょうどみんな美味しいって言ったの?」
ソン・グァンが兄とハンソルが兄の言葉だ。私はクッククック笑った。私の口当たりがそれほど高い方ではない。ところで、お兄さんたちが私を連れて行ったところは美味しいので噂のグルメだったので、みんな美味しかった。
注文した14ボウルの刀麺が出て、私たちの前に置かれたキムがモラッカッとした刀麺が美味しく見えた。私はすでにこれがおいしい食べ物であることを知っていました。
「よく食べます」
今日は涙濡れたカルグクスではなく、とても嬉しいです。もう少し悪くなったこの瞬間が食べ物に関係なく幸せですね。
「うん、女主がもっと食べたいものがあればさせて。
わかりましたか?食べないからゆっくり食べます」
「はい~!」
今日の計算者であるスンチョルが兄が言う。私はただ彼に感謝していました。
「お兄ちゃん~」
ジフンが兄がいたずらして尋ねる。スンチョルが兄は断固としている。
「ダメ」
「はい」
「ㅇ、なぜこんなにクールだ。欲しいなら買おうとしたんだけど」
「私のお金で買えばいい。
おそらく私の兄よりもお金がたくさんあるでしょう」
中に認めながらカルグクスを吸入するミンギュ兄に話しかける。
「ミンギュ、味はどう?」
中では兄と言うが、馬は兄という言葉が簡単に出ていない。
「とても半末が慣れているの?私は嬉しかった」
「セブンティーンもそうな雰囲気もっと。気にしてる?」
「うん、気にして。
私は他の子供たちにも呼びかけを省略しています。
あなたも呼んではいけませんか?」
「お兄ちゃん…はお兄ちゃんより友達感が強くて。
中で考える時は兄と言うのに…。 」
彼を考えると、心強くて嬉しい存在だと、兄という感じが強かったが現実ではなかった。現実は友人の感じが強く、おかげでミンギュ兄弟という呼称よりミンギュという呼称が良かった。ミンギュ兄さんがお兄ちゃんでもいいけど、友だちもよかった。
「年下、同甲、連想中に何が一番好き?」
突然フックに入った理想的な質問。数ヶ月前だけでも孤児であり、未来とは存在しなかったのに。そんな私にもう理想型を聞いてみる人までできた。そして私はそれを考えることができる余裕ができました。そんなのんびりした人になった。理想型を聞く人のおかげで。
「年下抜け…少しお姉さんの声聞きたくない」
最後に少し笑う。メンバーの中に年下がなくて姉の声を聞かなかった。私が姉の呼称を嫌う理由は、幼い頃の話に上がる。私の下ではみんな弟だったので、私の世話をしなければならなかった人々が私の姉と呼ばれたからです。決定的に私は赤ちゃんをあまり好きではなかった。なぜなのか分からない。赤ちゃんのせいで私の人生が消えてしまうと予想するだけ。
「ツンデレはどうなの?」
ウォン兄が尋ねた。本人がツンデレラそんなことを聞いてみるのか。
「優しい人がいいよ。表現上手くやってくれる人が好き。
私は…そんなに住めなかったから」
「嫌い…という言葉か」
ウォン兄はかなり心配な目つきだった。その心配は私をどのように見て出てくる心配なのか区別できなかった。
「いや、好きなんだけど…」
どうやって話を終わらせるのか分からず、ただ末端をぼかすのにシュア兄さんが手伝ってくれた。
「前回制服買いに行った日、録音もしたじゃないか」
「うん、その時歌うことがよくあるってことも分かったよね」
ウォン兄さんが答える。続いてジフンが兄が会話を続ける。
「その時私は女主側を少し聞いてくれたが、ときめきだった」
さりげなくときめくという表現を書くというのがジフンが兄が私と違って見えた。私はときめきという表現を本物のときめきの時だけ書くんだ。
「うーん…そうだった。そうだったのに、私の理想の話なぜなの?」
ミンギュ兄が私を見つめた。そしてなぜか彼の心の声が聞こえた。気づいて汚れないと。もちろん彼が本当にそう思っているのかは知らなかった。ただ気づいて気づいたんだ。
「ただ言うのではないか?
あなたも大学に行き、それから彼氏を作ったのではないでしょうか?」
「まあ…私が彼氏を作ることができるか?」
馬の終わりに兄弟のために、飲み込んだ。家族がいなくて反対する人がいないと思ったんだけど。ああ、その前に彼氏を考えなかったけど。だが今は違った。 13人にもなる人々が私の兄弟のようで、私の両親のようでした。したがって、反対する人が13人にもなった。
愛されるという考えに幸せだったがジュンフィ兄の言葉に心配され始めた。私は本当に彼氏を作ることができますか?その彼氏は大丈夫だろうか。
「100%付き合うみたいなの?」
なぜスングァンが兄があんな話をするのか分からない。私がきれいだったり、魅力的だったりしているのではないようです。
「うーん…そう?」
「え、私も付き合えると思いますか?」
「その前にお兄さんたちが私の彼氏を許してほしいと思うけど」
ハンソルが兄の言葉に反論した。するとスンチョルが兄はプハハ笑った。
「あなたの彼氏が大丈夫な子なら受け取ってくれ」
残りのナイフ麺を食べながら中に考えました。
「果たして。どんな人でも嫌いだと思います。」