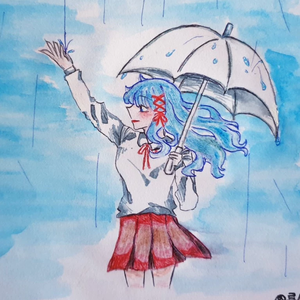「カット、OK!お疲れ様でした、心の量」
私は少し気分が良くなったので、少し気分が良くなりました。
「いや…私のせいで本当に申し訳ありません」

「演技一度も学んだことがない」
「はい…だからか今日のNGもたくさん出して…」
「いいえ、叱るつもりはありません。
オーディション、なぜ心を選んだのか教えてあげたいです」
なぜあえて私でなければならなかったのか、被害だけにしたのに何が良かったのか。
「なんだかどうか見たかったのに…」

「もちろん演技力がそんなに優れていませんでした。」
「しかし…情熱があり、潜在力もありました。
そして、頑張ったのが見えました。
演技とは一度も学んだことがない
部屋PDさんの言葉に事実期待、ほとんどなかったのに
思ったより良くなったんですよ」
どうせ新人のために作られた配役。演技実力よりは情熱と初心、努力する誰かに与えたかったのだろう。
「初めてだったのに3日しかできなかったのに
一ヶ月は練習したようで、
しかもあまりにやりたくなる目でした。
そんな目が、簡単に忘れることはありません」
「ありがとうございました。本当に…本当にありがとうございます」

「あ、製作陣にも申し訳ないようだったけど、
それも心配しないでください。みんな直感した」
「はい…」
「お誕生日おめでとうございます〜お誕生日おめでとうございます〜
愛する梅雨。誕生日おめでとうございます〜」
セブンティーンと同じくらい感動的な誕生日のお祝いの歌だった。さらに主演俳優のパク・ソジュン先輩はケーキまで持っておられた。
「そ、これ…」
「お誕生日おめでとう、心の量」

誕生日を祝ってくれる人がセブンティーンだけでも十分だろうと思っていたのに、こんなに多くの人が祝ってくれたら、体の両方を知らなかった。
私が生まれたことを祝う人がいませんでした。彼らは大きな意味がなかったでしょうが、私にとってはとても大きな感動でした。
「心が涙が多すぎる。来て」

「お姉ちゃん…」
「次に見ると、私たちは泣かないことにします」
涙は依然として流れており、凄惨で可憐な女主人公のように見えたかもしれない。しかし、私はそのシーン一つ一つがとても大切でした。
「なんだ、サポートがお姉さんと呼ぶんですか?」

「支援が姉がそう言って、ハユンが姉」。
「お姉さんという呼称は変ではないのに、
兄はちょっとおかしいでしょう?」

「どうせ劇中親兄なのに、兄と呼んでもいいですか?」
「じゃあ!」
「ㅎ、ハユンと私と一緒に…」
「あ、ジェホンが兄と呼ぶよ!」

「もともと未成年者は10時になれば退勤なのに、ごめんなさい…」
「私ができなかったからです。大丈夫です。
あ、じゃあ先に行ってもいいですか?」
そして家に帰れるように、ソク兄に電話をかけた。
「うん、心よ」
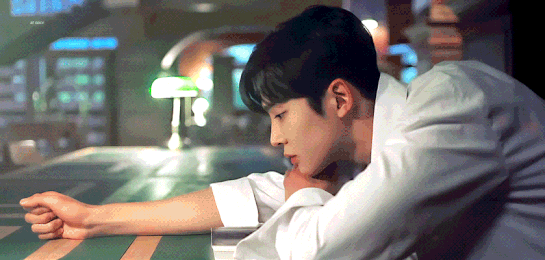
「お兄さん寝た?声がロックされてる」
「ちょっと眠くなった。すぐに行くよ。しばらく待ってる」
「私は一人で行きます。
「私代表にホンナ」

「私は頼んだと言うでしょう。
マネージャーが待っているのが初めてなので、適応できません。」
「は…それでは今日だけですか?
私はあなたを待つのが仕事です。わかりますか?」
「じゃあ明日見よう、心よ」

「うん、休んで」
タクシーに乗って行けばいいが、タクシーが来る大きな通りやタクシー乗り場までは出なければならなかった。
そこまで行くのに傘を貸してくれる人がいるだろうか。だが、すでに撮影場を出た状態で、一番近いコンビニも近い方ではなかった。
「…ただジャンプしなければならない」

「…なに?」

「お兄さん!」
突然抱かれてきた心があるので少し戸惑ったが、すぐに傘を持っていない左腕で彼女を暖かく抱いてくれた。
「心よ…」

「キム・ソクさんに聞きました。なぜ来ないでください」
気になってきた。大丈夫?」
「すみませんでした。私は完全に大丈夫だから」
この時まで待ったところなかった彼女に休むことができる人になってあげたかった。人間対人間ではなく、男性対女性として。
静かに小さな心を眺めた。夜空の月明かりに輝く彼女の瞳が私をじっと見つめていた。
負担もないのか目を絶対に避けなかった。
「…とりあえず傘を聞いてみる?」

「うん?あ、うん」
「ああ、センス」
「雨だったじゃない。寒かった?」

「寒い感が少しあったんだけど…」
「あなたは寒くてすごいです。
風邪もほとんど甘く生きて体を温めてくれなければならない」
「寒いならカーディガンの中に腕を入れてもいい」

「すごく大きくないかな?」
身長差もたくさん出るうえ、体格差もたくさん私はほうだからなおそんなそうだった。
彼女は私の手を過ぎて残りの袖が不思議になったかちょっと愚かだった。大きな服にすっぽり埋まっていて、必ずパパ服を取り出して着た子供のようだった。
「兄の服は本当に大きい…」
「おかげで、私たちの心はもっとしっかり見えますね。

「私はじきじゃないんですよ…」
「私より小さいじゃないですか?」
「いや…それを兄と比較してはいけない。
男女の平均身長が違う。」
ピーシック笑顔の後ろに彼女の手に聞こえていた傘をやさしく再び握った。
そんな瞬間、気持ちと私の手が少し擦れた。するとただ幸せな子供の顔を維持していた心の顔が花婿燃え上がった。
「なんだ、心よ。お前顔すごく赤くなったよ」

まともな希望顧問であることが分かった。恋愛は単純遊戯ではなく自分が成長する足場になったり、あるいは生涯一緒にする誰かを探し回る事だったから。
「何もない…」
「…うん、早く家に帰ろう」
それほど遠くないわけではなかったが、その間、狭い傘のために肩に雨を迎える彼女が心配された。
私も知らない鳥に何の感情もなく、どんな思心もなく彼女の肩を握って奥、だから内側に引き寄せた。
正直に言えば私も驚いた。好きな感情とは別に、彼女が雨に合うのが嫌だという事実で見て、異性として見る以前、ただ人の長心が好きであることに気づいたようで。
心の顔をやはり赤くなった。彼女が恋愛についてどう考えているかはよく分からないが、彼女は今19歳になった少女だった。
恋愛感情とは別に、ただ自分によくしてくれたり、優しくしてくれる行動一つ一つにときめいているようだった。
そしてその感情をどうすべきかわからず、そのまま顔に入った。
「傘が…一つだった?」
「もしかしたら不便だ、気に?」

「あ、いや。そんなことではないのに…気分がちょっと夢中だ」
「モングルモングルだという言葉は、わくわくという言葉ですか?」