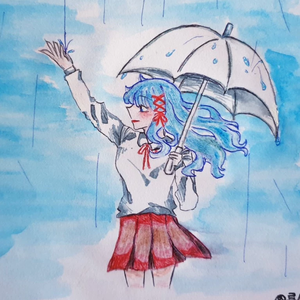「わ、気にしてお前は本当に久しぶりに見る…」

「それじゃない?
連絡したほか、連絡もほとんどしなかったし… 」
「ああ、前回あなたのオーディションを見るとき
私は予告転校に行くと言うから
その時いじめられるのではないかと
疑って電話してきましたか?」

まあ、一人で怒って一人で結論を出して一人で合理化し、今これが何をしているのか。
「本当に?
スンシク、スビン、チョンヨン、そしてスンウ…チョン・ヨンリーと私のナムサチンたちはもちろん方法も違って、時期も違ったが結局私を今この席にさせてくれた大切な友達だった。
これらのどれもなかったとすれば、私がこんなに耐えることができたのだろうかと思い、大丈夫に鼻先がシックになった。
「とにかく、その時以来
電話は一度やってもらえませんか。
あなたのニュースを必ず記事で見なければなりません!」

「ええ、それでも私は心配しませんでした。
無知が朗報だとも言うじゃないか。
仲良くしてくれると信じて、
実際に、記事で少なくとも4つの外面的な外観
仲良くしているみたいだからすごく安心した。
君の心配はすごかった。」
「あのスンウ。
馬が始まる時と馬が終わる時と
言葉は少し反対のようではありませんか?」
「心配しなかったという言葉から始めます。
心配すごいという言葉で終わったら
言葉に信憑性と説得力が一度に落ちるじゃないか、僧侶だ」
「あ、本当にそうなの? わからなかった」

「それでも、あなたはとても感謝しています、スンウ。
あなたが本当の友達です。イ・チャンその子は… 」
「それでも少し仲良くしてください。
どうせ生涯見る友達じゃない?」

そして実際に私に打ついたずらは、深い愛情と愛が込められていることを知るために彼を憎むことはなかった。
「あなたの受講申請は何時ですか?」

「馬は本当によく回ります、カン・スンシク。
9時だ」
「ハル!よ、あなたは10分しか残っていません!」
「私も目あるんですよ、ユン・ジョンヨンさん」
「やはり、あなたは女の子と遊ぶ必要があります。
あまりにも男の子とだけ通わないで」

「あなたはどんな講義を申し込みましたか?」
「専攻で東西洋書士芸術、
イメージとストーリー創作基礎1と2、
文章文体実習、韓国文学セミナー。
教養で著作権授業、現代美術の理解と鑑賞。
「お前…スケジュールしながらできる?」

「空強をよく見なければならない。
これはクレジット銀行制度にならない分野ですか。」
「ええ、あなたは24時間1秒単位で
壊すことも分かる奴じゃないか、お前」

「褒め言うよね、僧侶?」
「おい、気持ち。しばらく残った。準備して!」
そして始まった鉱山。コンサート票もこんなにしなかったのに受講申請のせいだなんて。
「ハル、大ヒット。私はオルキルだ!」
「オール~梅雨~初学期に幸運なのに~?」
たぶん、内省的な私にはこんなに外向的な友達がいるのがとても良かった。私ができないことを彼女はできます。
「ああ、でも飲みますか?
大学入学すると鼻が曲がって飲むと思う」

「いいえ、もう19歳です。
法的に飲んではいけないうえ、食べたくない」
「よく考えた。体に良くない、それ」
「あなたはこういうふわふわに住んでいました、
私の誇りに思う友達」
「はい、私はここで住んでいました、私はこれがとても好きです〜」
あ、これはたとえ話ではなく本当か。今ここに集まったすべての人が私の幸せのために与えていたから。
「ああ、ゲームしようとしているのではないですか?
私は来た意味がないのに… 」

「カン・スンシク!
梅雨顔見たことで意味が十分にある!
あなたは何年も会えませんでした!」
チョン・ヨンリーがスンシクより体格が小さくてもしばらく小さく、小学生がお兄さん一代殴る感じだったが、それでもそう言ってくれたチョン・ヨンリーがありがとう。
もちろん、スンシクが言葉が本気ではないことを知っているので可能なことだったが。
「何をするの?
ああ、どんなゲームでも私はできません」
「教えてあげるよ。しながら増やせばいい」

「おい、気持ちよ。お前…」
「ただ地雷探しやせよ」
「わ、スビンア。私の地雷探すこともできない」
「梅雨深刻だね…」


「ああ、私は少し前に大学の面接を見に行ったとき、
その時親母に会った?
「ファック、どんな見栄えで現れるのか」
怒っている人が怒るのが一番怖いと、彼女の怒りの対象が私でなかったにも正直少し追い出した。
「良心のある子なのか、それが」
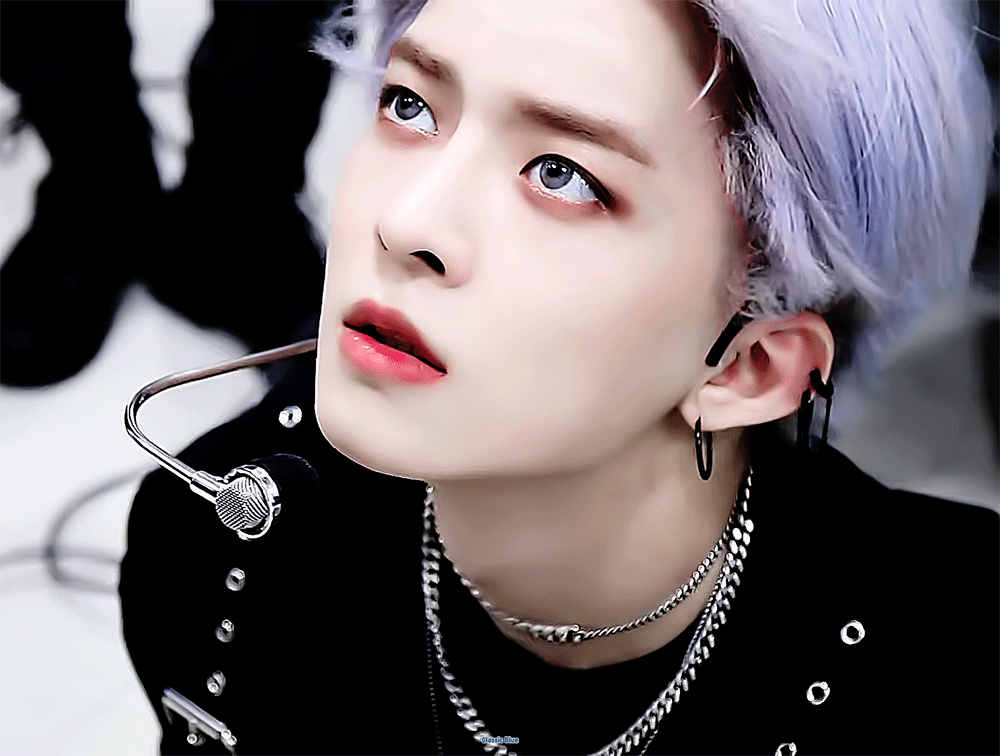
「いや、良心で寝て、ただの獣じゃないかな」
「ええ、それは獣にもあまりにも言っていませんか?
たまに獣たちも養育の義務を果たしたが」
わたしができなかった貪欲を彼らがしてくれ、私が出せない怒りを彼らが与えた。
「いったん落ち着いてから。
落ち着かなければ私の話も聞かない」
「…今真にできたよ、気に?
その子たちのせいで
どんなに難しい人生を生きてきたのか
私は知っている… 」

「そうではない…」
実はほとんど何も否定することはなかったが。結局私は幼い頃から大人であり、自分で生きていくのが大変な年齢で一人で生き残った。
「…どんな人だったの?」
「SG企業代表理事だ」
「そんなにうまくいけば心なのになぜ捨てたのか」

「私が曲がっているときは
死んでも現れなかったら、
よく暮らすと、なぜ突然現れたのか分からない」
「お金を狙ってきたと思いましたが、
引っ越しというからそれじゃないみたいで… 」

私はあなたたちに率直になりたいのですが、実際にはまだ私には率直ではないので、どうすればいいのかわかりませんでした。
「…多分本当の私が恋しいかもしれない。
本当に心から私を探したかったかもしれないことで…。 」
お母さんはそうだったのかもしれませんが、父はそうではなかったかもしれません。
「まあ、あなたがその人に何と言ったのか気になる」

「私は私の本当の家族を持っている、
行きたくないと言った。しかし… 」
だが、答えをしたくないと言えば、越えてくれる人たちであることを知るのではなく、言葉が出た。
「私の両親は本当に私の家族の役割をしています
やりたくて訪ねてくれたら?
それから私は…どうすればいいですか… ?」
「まあ、今来て何をしようとしています。
セブンティーン、血は混ざらなかったが、あなたに家族じゃないか」

スンウは知っていた。今セブンティーンは私に家族のような人ではなく、ただ家族であることを。
「そうです…セブンティーンのおかげで、あなたはまた名前を取り戻しました。
家族の役割をやろうとしたら、百回譲って。
仕方ない16年の隙はどうするの?」
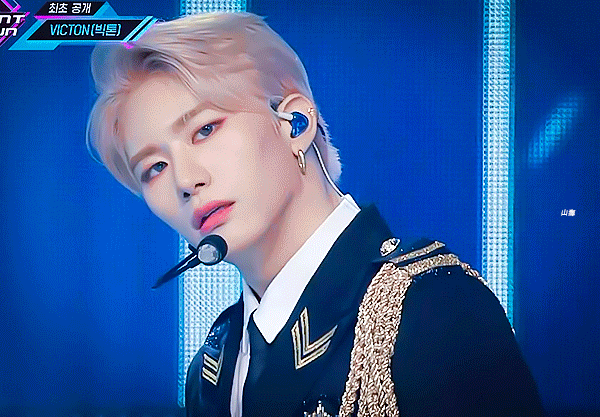
「あなたはどうですか?その16年の隙を壊したいですか?
結局これはあなたの選択だから…
私の兄弟はすべて理解しています。
もちろん、連絡を取り続けるという
家庭の下で可能でしょうが」
彼らが追求したい究極の目標は私の幸せだったからです。
私はチョン・ヨンリーの質問に首を振った。 16年の隙間をあえて破っただけ彼らは私に切ない存在ではなかったから。
セブンティーンを捨てるほど、これからの発展の可能性がある人ではなかったから。
「それではこのまま生きてください。
もし電話番号教えてくれたらそれも変えて。
会社に来る電話も受けないでください。
「ありがとう、私の友達」
「ありがとう。ただ私はあなたの心を客観化させてくれただけだ」

申し訳ありません。