
センチネル恐怖症
うーん…どこから言えばいいの?すでにセンター長も知っていて、これが広がっていてもそこ7人のうちの一つだからなんとか捕まえることができるからです。 ソクジンがつかむと、まず傍らに言う女主だった。
私の家族は、父はセンチネルであり、母はガイドされました。とても..和解しました。ソクジン兄弟は隣人でした。いつものようによく従いましたし、お兄さんも私をよく手渡してくれました。本当に..平和で幸せな日々だけ続いた。
「暴走です!」
タブー - ある男性が飛び込もうとしていた女性を捕まえた。どちらも年齢がかなり見え、女性を見る目には心配がいっぱいに見えた。それにもかかわらず、女性は男性の手を打つしかなかった。センチネルにはガイドである自分が必要であることを知り、暴走中のセンチネルに助けを与えることが自分の仕事であることを明らかに知ったので。
彼女の母親はなんとS級のすごいガイドだったが暴走したセンチネルはSS級でその差がかなり大きかった。それでもガイドは珍しかっただけであっても低級がほとんどだったのでS級ガイディングは一般的ではなかった。だからなのか、初めて感じるS級の恍惚なガイディングに、近くでガイディングをしてくれた他のガイドをささげて彼女にしがみついてガイディングを吸収した。
いや、吸い込んだが正しいか。本当に吸血鬼のように一滴も残さないようにセンチネルの体が彼女のガイディングを狂ったように吸収されていた。むしろS級だがS級に次ぐほどガイディングを上手にしていた彼女も、SS級の前では別ではなかった。
無理を感じたガイドがセンチネルを押し下ろそうとしたが、すでに目が戻ってしまった彼が彼女を置くことになった。そのように女主は10歳という若い年齢でセンチネル暴走に巻き込まれた母を失った。彼女は無謀だった。世の中にも数少ないS級ガイドであり、他の低いガイドを熱名で2000年に失っても、カプセルや錠剤を使っても暴走に巻き込まれて怖いなら行かなかった。 S等級だけの特権だった。しかし、他人を犠牲にしたくないと私の墓を自ら掘り出した。
そして、そんな彼女の選択がひとつだけの娘を地獄に追い込んだら、そしてその事実も彼女が分かったら。彼女はそこに入ったのだろうか?そうだったらこの結末が変わったのだろうか?
。
。
。
私の妻を失った後、彼は徐々に壊れた。死んだ私の母親のために狂った父が呼び起こした被害は、ひたすらその娘だけに向かってその娘にそっと下がった。お父さんはいつもお酒を飲んで彼女に暴力を置き、彼女はそれをその小さな体に耐えるしかなかった。そしてそんな女主に力になったのは、隣の兄のソクジンの小さく大切な慰めだけだった。
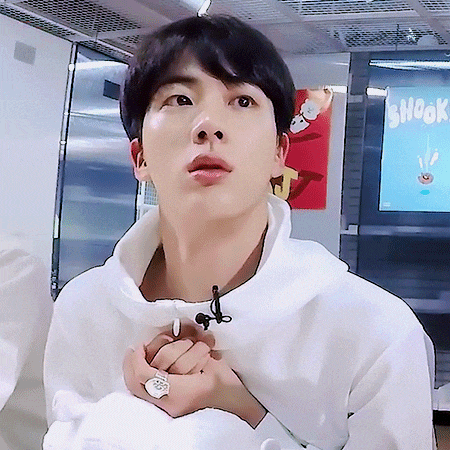
「あなたは大丈夫ですか?」
ちょっとよく言ってみようか? プソス-笑いが飛び込んで出た。この状況にはあなたはスピードなしでそんなに笑いが出るかというソクジンの叱責にも気持ちがよかった。私はいくらお父さんが暴力を行使したのに、もはやお母さんを見ていないにもかかわらずソクジンの小さな心配一つが私が生きていることを悟らせてくれた。お母さんが死ぬしばらく前に発現されたリカバリー能力が合い、また当たっても自分を生かすという絶望的な事実も、お父さんがそんな自分を知る上でもっとひどく殴ると信じられない事実も。石津の小さな心配と慰めがあり、少しずつ克服していった。
たまに私が死なないように、どんどん生き返るリカバリーが嫌いで人生が無力だと感じられた時は、たまにわざわざ訓練でけがをして治療してほしいというソクジンの生涯をなくして感謝された。ある瞬間、ソクジンは自分自身にパパになっていた。親パパよりも従うパパ。それがソクジンだった。
そんなソクジンが去るという話を聞いた時は、本当に全世界が崩れるようだった。唯一の私の側が消えたら、自分はまたどのように生きていかなければならないのだろうか。という否定的な考えだけを聞いた。石津が去った後一週間ほど経ったか、女主の能力がもう一度発現された。それがまさにエグノエルだった。
おかげでパパの能力で痛くなくてもいいが、女主はさらに苦痛だった。毎晩、高い能力に比べて足りないガイディングで喘ぎました。毎晩鋭敏になった感覚と悪夢に苦しんで、ますます初めてなって行った。パパが能力で攻撃する時はエグノエルが飛び出し、それに迷惑や武力で攻撃する時はリカバリーが飛び出した。望まなくても寺に飛び出す能力に、たまに苦しむほどであれば、パパの暴力が終わった。
そのように苦しんで13歳になった春頃、狂ったように病気だった。数日を恐ろしい目覚めた後、向き合ったのは、 体から流れるガイディングのオーラ。ガイドで表現した瞬間だった。
しかし、女主はただ新鮮な高級ガイド。ずっと漏れるガイディングを防ぐことも、調節することもできなかった。結局、家の中でいっぱいのガイディングが満たされ、センチネルの彼女の父親がそれを感じることができなかった。
つま先からチリチリと上がる恍惚なガイディング。体にあった疲労が芽生えて鋭敏だった感覚すら静かに眠るようだった。あまりにも恍惚だった。肌全体に浸透するようなガイド。これはきっと放射ガイディングだった。ああ、放射ガイディングがこんなに良ければコンタクトガイディングはどれくらいいいのだろうか?
放射ガイディングよりも接触ガイディングが良い理由は、放射ガイディングは全肌が吸収してもあちこち抜けていくガイディングも多いだけで少しずつしか吸収できないが、接触ガイディングは届く面積が狭くて抜けていくガイディングもいくらでもない。隅々を通り抜けて疲れた体を心地よく満たしてくれるためだった。
場合によっては、低グレードのセンチネルが高いグレードのガイディングを受けると、そのガイディングに中毒され、他のガイディングは受けられません。いいえ、受け取ることができますが、他のガイドのガイディングは消耗がひどく、吸収もうまくいかず、高いグレードのガイディングを受けなければ生きることができません。それさえも恍惚するよりも無理に何かを選んで入れるという感じがして生きにくくなる。
だがこんなガイディングなら中毒されてもいいようだった。むしろガイディング中毒を言い訳し、私の隣に必ず貼っておきたかった。チリチリハンガイディングに合わせてつま先もつまんで持ち上げた。何かぎこちないながらもおなじみの気持ち。このガイディングが私の娘のものであることを知るまでにはしばらくかかりませんでした。
男の目が明るく輝いた。最近ガイディングも足りなかった車に、これがどんな横制かと思った。はい。女主の母親であり、彼のワイプだった彼女が死んだ後、彼は女主をハンサコの娘として見たことがなかった。もちろんその前まで愛して惜しむ娘だった。だが、彼女が死んだ後から女主はただ酷い存在だけだった。

ダルコプ - 訪問が開かれ、視界に入って冷たいのは、手首には100%で輝く時計を冷たい野望でいっぱいの目で自分を眺める私の父だった。とても嫌で吐き気がするようだった。普段はユリや投げて武力を行使していた私の父はどこに行ったのか。一様に気に入らなかった。自分を守り続けるリカバリーも、役に立たないエグノエルも、もう暴走もできないようにしたガイディングさえ。そんなに気に入らなかった。
ひどかった。ただ嫌だった。その間、そのように殴って憎みながらガイドで表現したこの時点でこそ、怒りが和らげられた私の父を見て、今私の体から流れるそのような血も嫌だった。 ただこのまま全部やめたい。 ただ、私の父がそのような欲望の塊だということ自体も信じられず、これまで幸せだった過去が一握りの蜃気楼になって飛んでいくようだった。全く嫌だった。とても疲れました。
お父さんがゆっくりと近づいてきた。来ないで。私は。ガランだよ中に狂ったように叫んだが、口の外に音が漏れてこなかった。嫌いです。嫌だと… いくら叫んでもパパは聞けなかった。実際の口から出てきた音はなかったので…いや、そもそも大声で叫んだとしても…お父さんが聞いたのだろうか?あのように目を覆っているお父さんが?
表情がますます絶望的に変わっていった。ガイディングによる脅威が感じられると、自分も知らないようにガイディングをかけてロックした。するとパパが口を振りながら惜しいような表情をした。だが、これまで惜しいようなその表情また消し、欲がいっぱいの表情でますます近づいてきた。
本能的に避けた。手を後ろに出して退いた。嫌いです。こうして純潔を奪うことはできない。ゆっくりと後ろに向かう渦中にも見えるあの貪欲な表情に、全身がくっついているように動くのも大変だった。背中に冷やした汗が流れ、背骨が涼しくなり、不気味になった。それは..私が知っていたお父さんではありません。
「来て。いいじゃない?」
「詩、嫌だ…本物…嫌い……」
「嫌い?」
「 !!!... 」
とても笑いながら転がしたら嫌だと言うと、突然冷たい彼の表情に、本当に厚いチェーンにも縛られたように体が固まった。ピシク - 笑ってはゆっくりと近づくその印影に気をつけてもう一度後ろに押しようと手を伸ばしたのか、手先に触れる硬い触感が本当に彼女を狂わせた。
はい。もう本当に窮地に追い込まれたネズミだった。もう逃げる空間なんてなかった。もう何の部屋もなかった。続く反抗ではない反抗に既に芽生えた表情が、過去を連想させた。まあそうしたらわずか3日前だった。記憶の中では毎日同じレパートリーが再生された。
パパが書いた能力が速いスピードで飛んできたら、それを防いでくれるイグノアル。それではまた怒って何でも拾うことを投げるだろう。じっとしているが、横からうっとりとした花が上がってきたお父さんの手にとられたガラスカップが、山々の彫刻や真っ白な中身を掘って入ると、その傷でピジルピジル抜けてきたピットドロップが服に吸収される。
ああ!耳元を掘る鋭い叫び声に印象を付けたお父さんがそのまま足を伸ばすと、血管の中でも薄い毛細血管があちこちに飛び出して不快なぼやけを作り出す。その後、リカバリー能力がその一人で突き出て急速に傷を治す。そのようにしばらく殴られ、パパが疲れていくと、願いもなく書かれた能力にガイディングだけ抜け出してしばらく喘ぐ女主だ。すぐに暴走前兆症状が現れるだろうが、したければまた反政府でガイドを送る。いくらでもエグノエルにリカバリすれば、暴走が飛び出したときに困ることに。
ふとふと思い出す生活に身体がつまんでいる。私も知らずにすっきり気づいて震えていた。そして、そんな私が嫌だった。パパはティーが出るようにしないように少しずつ浮かぶ女主を調べたように口尾を上げてピシク-笑った。きれいにすっきり笑うのではなく、口尾だけさっとキラキラとした明白な笑いだった。
「怖すぎないで。きっとあなたも好きだろう」
「あ、いや…」
「なぜどんなに被害?気持ちよくしてくれるの?」
「詩、嫌。」
「あ、始発。ジョンナ高価だね。お前もいざやってやればいいってもっとやってもらうんじゃない?」
「そうではありません。」
「それをどうやって知ってるの?
「嫌い…本当に。。」
「それでも他人よりもお父さんに学ぶ方がいいじゃない? これはどうするのか、どんな気持ちだ。
「詩、嫌いです!..来ないでください!!」
「なぜ以来~初めてだから殺してあげるよ~」
「ハ、しないㅁ…꺅!!」
ちょっと黙って。見てくれるのはここまでだ。 お父さんがあっという間に女主の髪を曲げながら言った。頭皮が剥がれるようだった。少しブースだったが、結構良く整理されていた髪は、すぐに厚手に編みこまれてしまった。自然に腰が曲がり、自由奔放だった両手は自然に頭を向いた。
「ああああ!ああ、痛い!お願いします、お願い!!」
「黙れ!あなたはただガイディングするだけだ。
「詩、嫌い…」
ラフに当たってくる唇に裏口が一緒に飲み込まれた。 ...汚い、本当.. 吐き気が出るようだった。唇が届いた瞬間から自分が汚れていると感じた。いつブートンが私の存在であることを悲しみ切っていた。目には涙が流れて、一生懸命足を振ってみたが、13歳の少女が成人男性に勝つことはできなかった。

目から涙が流れ落ちた。怖かった。それでもこのように涙だけ震えているしかないという現実にさらに崩れ落ちた。私の最初の経験をひどくても嫌なお父さんに捨てたくなかった。やっと13歳の少女は、早すぎる年齢で自分自身で無力さを感じた。
唇が落ち、汚れた手触りが感じられた。成長期が過ぎて思春期がやってきて、少しボリューム感ができた胸の上に進得した手のひらが通り過ぎ、虐殺一つない船の上に安着した。重い大人の男性の手が感じられると、恐怖は成し遂げられないほど集まってきた。
スウィック-パパの片手がスカートをつかんで上に上げた。恐怖に罰して震えていたその時、ピビッグと言ってお父さんのウォッチが鳴った。現場投入名だった。彼が小さく貪欲で頭を振りながら出て行った。

お父さんが家を出るとすぐに席を迫って出てボスを訪れたヨジュ。最初から最後まで解き明かしたが、ボスは決して聞く心がなかった。それはただそれぞれの事情であり、その個人の事情のためにかなり役に立つ彼女の父をエクスポートできなかった。
女主は裏切り感に震えて家に入って、自分の荷物を簡単に飾って食べることを少し手に入れて反政府を抜け出した。だからランダム走った。走ってまた走った。お父さんがどこにいるのか、バレたらどうなるかは見られず、考えも嫌だった。
しばらく走ってみると、前を見られない人とぶつかってしまった。相手は大人の男性だったが、自分とぶつかって跳ね返っていく小さくて外訴した柄の女主の腕をつかんでくれた。それで優しい声で聞いた。 若く見えますが、ここまではどうしたのですか?もしかしたら迷子になったの? 優しい声にならないことを知りながらも、クセなく彼のズボンの裾をつかんで懇願してしまった。その時はそれだけ緊急だった。
反政府ではないだろうか?する疑いはそもそもしなかったし、する必要もなかった。他人を苦しめる反政府でも同じ仲間として、サロールに頼って仲良く過ごしてきたので、反政府だったら調べたはずだった。反政府の姿はセンターとは相反した。センターが小さい国なら、反政府は大きな村だった。会議もしていろいろなこともする大小の本社、副社を中心に邸宅と様々な設備が設けられていた。そして反政府はそんなに大きくなかったので、お互いの名前、顔、事情まで模造知っていた。 -大体史劇から出てくる朝鮮時代の隣人関係程度と考えればいいと思う。 - 普段隣のおばあちゃんや前の家のおじいちゃんがお母さんを失い、精神が出たお父さんを安らかに見て、彼に被害を受けた女主を可愛く考えてたくさん持ってくれたら話したと思う。
だから自分が知らず、自分を知らないその男に従うことができた。そのように到着したところが…まさにこの場所。センターだった。その日女主を収めてくれたのもセンター長だった。事実上、反政府軍は文明がそれほど大きく発展できず、このように高い建物がなかった。だから認知されるように不思議でぎこちなかった。
センター長に沿って入ったセンタールーム。そこで女主はすべてを言うしかなく、女主の話を聞いたセンター長がそのような女主を可愛く見せて収めてくれた。もう少し正直に言うと、女主の能力があまりにも独歩的だから、ほとんど放置したいと思っておくしかなかった。しかし女主はそれだけでも感謝して良かった。
その後、時には悪夢に苦しんでいた女主だったが、そのたびに家族のような石津の心配と銀人や変わらないセンター長の配慮を考えて一日一日頑張った。それから結局このチームに入ってくるようになって会ったのが前よりはっきりとなった耳目構えだが、確かに分かる石津に会うことになったのだった。
「…ここまでが私の話です」

「キム・ヨジュ、あなた…」
「……」
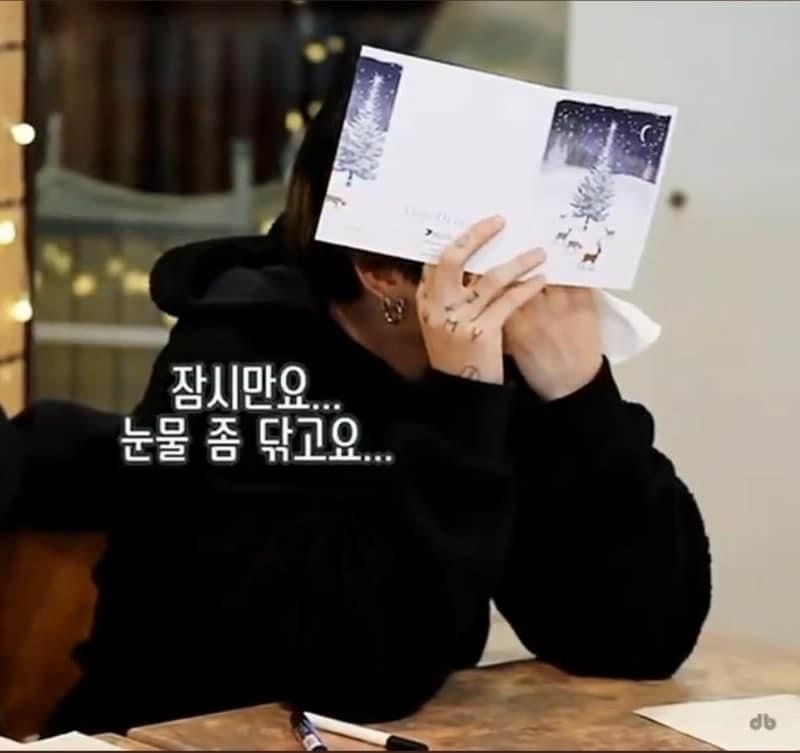
「私、私は…それも知らない…」
いっぱい正色をしてヨジュを見るソクジンと、もうまったくティッシュまで抜いて泣くジョングクをはじめみんなぼんやりしていた表情をほぐして少しずつ真剣になっていった。何か病気は予想したがこの程度一行は知らなかった。テヒョンも大体一見した内容であった、こうして詳細な内幕は初めてだった。

「これまであの痛みを君だけで抱いていたの?」

「13歳…あまりにも愚かな…」

「狂った子じゃない?」

「..今も子供じゃないか」
「あ、それが…」
女主が慌てたが、彼らはそれなりに盛り上がる怒りを落ち着かせるのに苦労していた。自分たちも今すぐにも拍車して、私がこの小さくて余った子供に傷を与えた彼を見つけて引き裂きたいと思ったのか、ちょっと参考にしていたが、その仕事の当事者であり、彼らより小さくて余った新しいメンバーである女主がもう何もないようにシクドンと淡々と話した。そんな中でもヒヨンはスポットライトが自分ではなく女主に向かうようで怒っていた。

「じゃあ、もしグレードはどうなりますか?」
こうしてすべてが明らかになった以上、これ以上隠せない事実だった。こういう状況にムードない、どうやってこんな言葉ができるのか?しかし、誰かは取り出さなければならない問題だった。それがリーダーのナムジュンの役割だった。彼はチームのために爽やかな感情に吊るしてはいけなかった。
「ああ、それはまだ…」
「それでは再会に行きましょう。」
ヒヨンは不安になった。彼女が自分よりも優れていたら、自分はこのチームにいない人になることもできた。しかし、そうでなければ、とにかく評価を見なければならなかった。これまでベールに巻き込まれていた事実が一つ二つずつ水面上に浮かぶ瞬間だった。
今日は本当に長いですね! 大変でした…
文句早く来た?
これは事実、前編を上げるとすぐに書き始める
三日?で完成したのですが…
