永遠だと思った。初めて種を土に埋め、毎日一緒に水を与えた。一日、二日…一週間、一ヶ月…芽はすぐに姿を持ち上げ、さらには上がらせた。あまりにも水をたくさん与えたせいだろうか。あまりにも過度の愛も彼らにとって毒になった。私は四季を通してそのような水を与えました。
。
。
。
冬
。
。
。
雪がスーツが降った朝騒々しく鳴るアラームを消し、眠い目をこすりながらベッドで起きた。窓の外には白でいっぱいの道路が広がっており、一つ二つの朝を準備する人々がいっぱいだった。
ヨジュ
「もう少し寝るか…」
隣にはまだ起きていないツヤが内側に回したまま軽い息を吐いて寝ている。私はできるだけ静かにベッドから歩いてトイレに向かった。
ほっぺ

「起きたら俺先に目覚めよ、俺も歯ブラシくれ」
トイレのドアが開かれたときに目を覚まし、私が目を覚ます。頭は整理もできておらず、すぐ寝て起きてツントンブウン姿が私にはただ可愛いだけだった。
ヨジュ
「なぜ壊れて、今日年次出したんじゃないの?」
ツヤ
「私は寒いです。
ヨジュ
「年齢がいくつかあった。
ツヤ
「一緒に寝ると、君なしでは寒いから」
私たちの最初の冬は非常に寒い寒波速報の連続だったが、一緒にした日常は誰よりも暖かくて優しい。そのように冬を装った優しい季節を過ごした。
。
。
。
春
。
。
。
漢江の周りに数多くの恋人たちが漂う。街路樹はいつのまにかピンクの服を着て漢江に溢れる。お互いに写真を撮る恋人たち、マットを広げる恋人たち、犬と一緒に散歩をする人々。 全世界がこの季節を愛した。
ツヤ
「まだ寒くて、ショールよくしゃべるよ、来て来て」
長く伸びた手は、私の首につながったショールをつかんで殴った。散る桜の花びらとツヤの手で、私は香りはまだ優しく、温かみを抱くように暖かいテキスタイルの香りが混ざって安定していた。すぐに取り出した乾燥機の中のタオルのように、彼の手はふわふわだった。
ヨジュ
「ユンギ、
優しくしてほしい、永遠だと思う。これらの瞬間が

「いつもいつも君にだけ優しくしてあげるよ、永遠に」
時間が止まってほしい。という言葉はここから始まったのだ。永遠という言葉は時間から始まります。私の時間はツヤで、ツヤは私の永遠だった。そう永遠の春を送ってくれた。
。
。
。
夏
。
。
。
「夏だった…」という言葉がある。青春と愛を描くように懐かしさの夏を埋めて思い出にだけ置く言葉、私にとって夏は一番長く怠惰な季節に思い出された。じっとしていても熱い温度に私たちはぴったりついてより暑い夏だった。
ヨジュ
「ユン・ギヤ今日はエアコンパンパンを置いて家にいるのか?」
ツヤ
「電気税を余裕があれば」
ヨジュ
「………暑いですよ、エアコンは違うんですか?」
ツヤ
「ダメ」
そんなに初めて犬もかからないという夏風邪にかかってしまった。ユンギは自分のせいだとし、一晩中私の隣を守ってくれた。
ヨジュ
「私はアイスクリームを食べたい…」
ツヤ
「買うよ」
ヨジュ
「私お腹がすいた」
ツヤ
「作ってあげよう」
ヨジュ
「私はあなたとこんなに横になっているだけです、一日中」
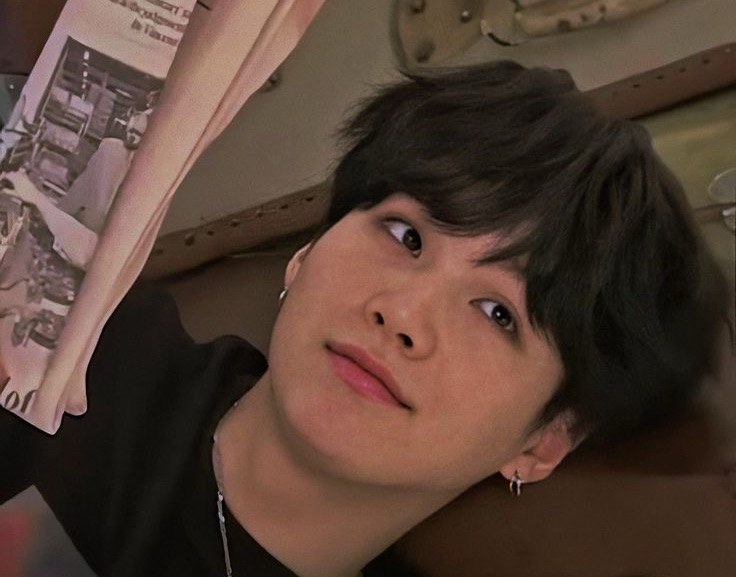
「怠惰な王女の言葉に従ってください」
最も怠惰な夏だった。
。
。
。
秋
。
。
。
黄色がいっぱいの季節がやってきた。そろそろパンパントラックが姿を見せ、路上には厄介なにおいでいっぱいだった。一度その匂いを踏んで一週間のにおいが抜けて大きな苦労をした。
ヨジュ
「悪-! 私は銀行を踏んだ。
ツヤ
「チョーディングですね、まだ子供です」
ヨジュ
「フウイング…匂い…」
私が泣くと、ユンギは後ろも振り返って行っていた道だけ歩いた。内心 涼しい心を隠して家に帰り、惜しい日差しに昼寝をして起きた。家の中に広がったしっかりした臭いとほのかな石鹸の臭いはまだ忘れられていません。
ヨジュ
「ツヤは何してるの?」

疲れて眠ったようなツヤの姿の後ろに水気が突き落ちる白いスニーカーが洗濯物に一足ずつかかっていた。ツヤの懐かしさで私は石鹸の臭いが私をもう一度申し訳ありませんでした。
。
。
。
紹介ティンナム
「一番好きな季節ありますか?」
そのように四季が過ぎて永遠になると思った彼の葉が一つ二つ落ち、結局私一人の時間が流れ始めた。時間は私が追いつかないほど速く過ぎ、彼との四季はそのように思い出に埋めた。
ヨジュ
「四季すべて好きです」
