「え?ミン・ヨジュ、今タバコ吸ってるの?ハハハ。」
イェナは周囲を見回し、誰もいないことを確認してからヨジュを冷笑した。
彼女の鋭い口調はちょっとイライラさせられましたが...まあ、それでも十分かわいいです。
ヨジュはイェナを冷たい目で見下ろしながら答えた。
「あら?タバコは似合わないの?」
ヨジュの予想外の反応にイェナの瞳孔は波に打たれたかのように震えた。
もちろん、それは当然のことだ。ヨジュはイェナの挑発に一度も反応しなかったことはなかった。
でも私はウ・ジェヒです。
君みたいな人がいても私は動揺しないよ、ちびっ子。
ヨジュとイェナの間に緊張が走ったちょうどその時、階段を上る足音が響き渡った。
それを聞いたイェナは、目を大きく見開いて叫び声をあげ、自分の頬を叩いた。
「きゃあああ!」
バン!
ちょうどいいタイミングで、ヨジュが頬を抱えて倒れそうになったとき、ドアが勢いよく開いた。
急いでいる足音から判断すると、その人はかなり驚いたに違いありません。
"彼…!"
そこにはキム・イェナが倒れており、私、ミン・ヨジュが彼女の前に立っていました。
その光景は、深刻な誤解を生むには十分すぎるほどだった。
つまり…まさにそれを狙っていたんですね。

「ミン・ヨジュ、何をしているつもりだ?」
しゃがみ込んだイェナの様子を見ていたソクジンは、心配そうに赤くなった頬を優しく包み、それから顔を上げてヨジュを睨みつけた。
しかし、ヨジュは動じることなくニヤニヤと笑っただけだった。
「イェナ、あなたの光り輝く鎧の騎士が到着しました!この侵入者はそろそろ退くべきでしょう。」
「あなたのしたことは見たわ。捕まらないことを祈るわ。」
ヨジュの冷たい視線と不気味な口調にイェナはたじろぎ、ソクジンはヨジュに怒鳴りつけ、説明を求めた。
ヨジュは彼らを無視して立ち去ろうとした。
イェナが優しい声でソクジンに大丈夫だと言い、ヨジュを許すと、ヨジュは屋上のドアの前で立ち止まった。彼女はシンプルな黒いケースだけの、無地の携帯電話を取り出し、それを振りかざした。
「イェナ、今日は本当に楽しかったよ。」
"何?!"
ソクジンが激怒して飛び上がると、イェナの体は硬直した。ソクジンが驪州に突進しようとしたその時、イェナは素早く彼の腕を掴み、弱々しく繊細なふりをした。
ヨジュはその光景を見てくすくす笑い、携帯電話の画面を彼らの方に向けた。

[録音中]
「あらまあ、話すことたくさんありそうね。ふふ。」
イェナの顔が恐怖で歪むと、ヨジュは口を覆って笑った。
ああ、キム・イェナ。
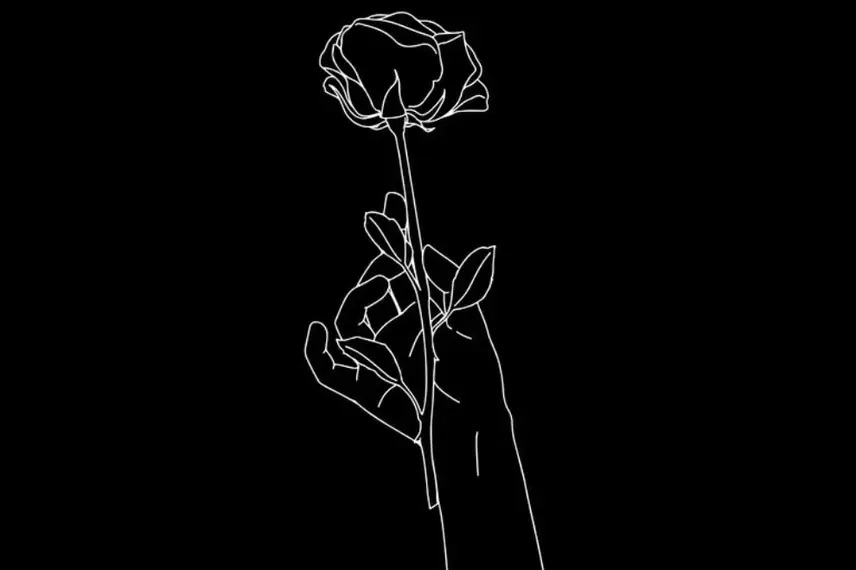
もう一度あなたを壊したい気分になっている。
カリカリ、カリカリ。
イェナは神経質に爪を噛んでいると、デスクの同僚のテヒョンがそれに気づき、心配そうに彼女の手を握った。

「イェナ、どうしたの?ずっと爪を噛んでるよ」
「え?あ、何でもないよ……ふふ」
イェナは無理やり笑顔を作ったが、テヒョンの心配はさらに深まるばかりだった。
すると、気づいたかのように、彼の表情は硬くなった。

「…ミン・ヨジュのせいか?」
"はぁ…?"
「ミン・ヨジュのせいでこんなことしてるの?」
「あ、それは違う――」
イェナはそれを否定しようとしたが、その時、ある考えが彼女の頭に浮かんだ。
テヒョンがヨジュと対峙すれば、彼女はそのチャンスを利用して携帯電話を盗むかもしれない。
そこで彼女はすぐに言葉を変え、涙目で頭を下げました。
「はい、テヒョン…僕はとても苦労しています。」
一筋の涙がイェナの頬を伝った。
必要なのはそれだけです。
テヒョンはすぐに席から立ち上がり、ミン・ヨジュに向かって突進した。
彼が去るのを見ながら、イェナはニヤリと笑った。
誰かが自分を見ていることに全く気づいていない。

「……面白くなってきたな。」
バン!
テヒョンはガラス窓が割れるほどの力で教室のドアを勢いよく開けた。
そして、ヨジュが静かに本を整理していた瞬間、彼はためらうことなく彼女の襟首を掴んだ。
「イェナに一体何て言ったの?」
「……何を馬鹿なことを言っているんだ?」
ヨジュは襟首を掴まれてもじっとしたまま、ただ話した。
テヒョンは嘲笑した。
「はあ――」
「これもまた、注目を集めるための哀れな方法ですか?陰で誰かを苦しめておきながら、人前では無関心を装うなんて?」
「何を馬鹿なことを言っているんだ?」
テヒョンは彼女の反応を無視して続けた。

「そんなに私たちのことが好きなら、黙っていろよ。イェナに手を出すなよ?」
"…何?"
「うわあ……本当に恥知らずだね。本当に最後まで否定するつもりなのか、君は――」
"黙れ。"
「僕が君を…好きだって本気で思ってるの?」
"…何?"
「学期初めに、迷子の子犬みたいに私たちの後をついて回っていたじゃない。忘れたの?」
「……何言ってるの? あんたらのこと、嫌いよ」
感情を欠いた社会病質者にとって、愛とはまったく異質な概念だった。
ヨジュにとって、いや、ジェヒにとって、愛とは無意味な感情に過ぎなかった。
彼女のような人間にとって、自分が密かに彼らに恋をしているという考えは、馬鹿げているだけでなく不快なものだった。
しかし、テヒョンはそれを知らず、ヨジュがただ自分の過ちを認めようとしないだけだと考えていた。
「このガキめ!」
怒りに目がくらんだテヒョンは、ヨジュを殴るために手を上げた。
彼の掌が彼女の頬に触れる直前――
しっかりとした握りが彼の手首を捕らえた。

「キム・テヒョン、何をしてるつもり?」
「…何?パク・ジミン?」
ジミンが止めたのを見て、テヒョンはため息をつき、表情を緩めた。
「おい、絶好のタイミングだ。ミン・ヨジュがまたやってるぞ。えっと、君もそのために来たのか…」
「キム・テヒョン、何をしてるつもり?」

ジミンは無表情でテヒョンを見つめながら、不気味なほど落ち着いた口調を保っていた。
「…パク・ジミンは何を言いたいんですか?」
「ああ、大したことない。ただ疑問に思ったんだけど、ミン・ヨジュはキム・イェナがずっと私と一緒にいたのに、どうして彼女に嫌がらせをできたんだろう?」
"…何?"
テヒョンはヨジュの方を向くと、顔に衝撃の表情を浮かべた。
「…本当ですか、ミン・ヨジュ?」
私も彼と同じくらい驚きました。
しかし、誰かが私を支援してくれるのなら、なぜ断らなければならないのでしょうか?

「うん。パク・ジミンと一緒にいたよ。」
ジミンは私の答えを聞いて、妙に満足そうな顔でニヤリと笑った。
ヨジュは初めて心の中で思った。
たぶん…彼は私よりも狂っている。
