
別れの式
W. マンガ蒸し餅
お互い 抱きしめてどれだけ泣いたのか、どちらも目がマカロンになってしまっては前がよく見えなかった。結局、目のマッサージをすることを持って来ると、家の中に入ってしまった女主の後ろに、私は壁を支えにして座り込んで頭を包んだ。どんなに悲しくて泣いていてもそうです、前後に隠して抱きしめて泣いたと思うので、遅れて恥ずかしがりになってきた。

「…クレイジーだ」
そのようにしばらくを自責して恥ずかしさが足を動かしたのだろうか。使い捨てビニールに氷を盛り込んできたヨジュの玄関口が開かれた。透明ビニールに入った氷。昔の考えや瞬間プッフル。と笑いを放った。本当に何もなかった時代、熱が出たら薬を買うお金がなく、あんなに熱を下した時が思い出した笑いだった。もう少し都合が良くなってこんなにしなくてもいいのに、相変わらずこのように使う姿を見ると、ぜひ昔に戻ったようだった。
「…なんだ、なぜ笑う?」
「昔考えてから」
渡された封筒を目にもたらし、笑った。最初は自分をからかうのかと思って太った女主義の顔も盛り上がった。そうです、私たちはそうでした。すでに通り過ぎてしまった思い出を再び振り返り、並んでしゃがんで封筒を目に持っていって言った。
思い出は絶えず出てきた。高校時代、放課後をしたくてこっそり塀に乗って出たことと、修能が終わった1月1日に巨大に遊んで知覚したこと。だから、一緒に遅くまで残って反省文を書いたこと。思うだけでも笑いが出てきた。今考えてみると勉強も勉強するが、遊ぶのも本当に濃く遊んだようだ。
「先生がそうだったじゃない。そんなに遊びながら性的維持する私たちが不思議だ」
 「そうでしたねwwww」
「そうでしたねwwww」実は先生の言葉は間違っていた。遊ぶのをかき混ぜ、私たちは勉強したから。お互いの状況をとてもよく知っていたので、解決策が勉強だと思っていた私たちは教科書で遊んだ。一人が問題を抱えたら、他の人が合うことに。間違えたら一晩。面白かったのか――と聞かれたらまあ。面白かったようだ。勉強が?、いや二人が一緒にいるの。
「事実、私たちはそれしかできなかったよ。
「そうだ。そういうわけで遊ぶから仕方なく勉強になるんだー。私たちに最高の遊びはそれだったから」
環境が人を作る。大学合格発表が私の当時に骨が折れて感じたのだった。お金がなくてそんなにしか遊べなかったのがたまには不便でもあったが、結論的に大学を一緒につけることができて「幸いだった」と思っていた。
「ただ…私の考えには状況そのものが最悪だったようだ」
頭を震わせて言う女主に私は、その「状況」がいつを意味するのか一気に知ることができた。私たちが別れたその年。私たちはとても疲れていました。お互いを気にするつもりもなく、現実に疲れてしまって出かけていたその時。苦々しく笑った。どうしようか、早く鉄が聞こえたからといって大変じゃないんじゃないから。
「…わたしだ。これまで私が一番不幸だと思ったんだ?」
「……」
「それで銀年中は大丈夫だと思ったんだ。
「……」
「だから君にもそう行動したし、君は絶対に去らないと思って…押し出して、また押し出して。確認されたかった。
そうですね。首を回してヨジュを眺めた私の顔が瞳に照らして鏡をなした。何度も傷つけて、床にすり抜けても結局は俺はまた君の隣を退けたはずだった。叶うのも大変で、忘れるのはもっと大変な初恋。それがお茶だったから。
「…だから、お前だけ大丈夫なら…」
「……」
「私たち、また高校時代に戻るか?」
緊張したのか、細かい膝の上にコムジラク距離は女主の指が見えた。また帰ろうか?…それから?青い木の下にあるだけで私の心を震わせた車女主…私は答えの代わりにただ微笑んだ。ある時は百言葉の言葉より、表情一つが確実な答えを与えたりもした。
私の人生、第二十七だった。
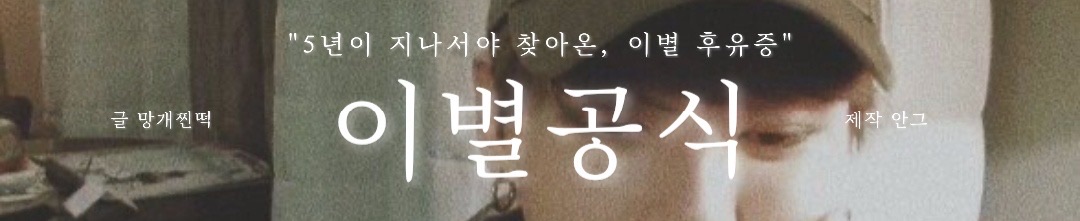
「ヨジュさん、ジョングクさんにファイルをちょっと渡してもらえますか?」
「はい!」
その日以来、私たちの間には付き合ったり、また会いましょう。別の言葉が来なかった。ただし、確実なのは…私たちの間に進捗が生じ始めたということ。
「ジョングクさん、しばらくタンビシルに来ますか?」
「はい、射手様」
私たちは時間に任せることにした。こんなに自然に会うことになったら、それも運命だろうな。
タンビシルに入ったジョングクに私は微笑んで一ヶ月に駆けつけて、ドアが閉まるのが恐ろしく手を挟んでつかんだ。私たちも私たちが何の間なのかは分からないが、少なくとも今は押し出さないということ。そして、あるカップル羨ましくないように愛情が突っ込んでいくことが-変わった私たちの間だ。
 「でもイ・ドヒョン、そもそもお前にそんなによくしてくれ?」
「でもイ・ドヒョン、そもそもお前にそんなによくしてくれ?」「なんだ。嫉妬してる?」
「いや、そうじゃなくて…買、社内なのに―ちょっと距離を維持しなければならないのではないかと思って…」
慌てたというのが顔にはっきりと入るのではないふりは。私はそのまま刈り取った手を持ち上げて尋ねた。 「じゃあ、私もこれを引いたかな?」タンビシルも社内なのだ。そしていつのまにか赤くなった二つの耳元でさり気ないふりを掻きながら言った。
「…私たちは例外高」
「なぜ、例外なのに?」
「…そ、私たち…」
「私たちは?」
「う、私たち…」
唇がびっくりした。とにかく、可愛くなって。ピーシック - 笑った私はそのままジョングクの額を痛くないように人差し指で押した。何を言いたいのか分かりそうだった。いつも同じだったら長団合わせてあげただろうが、今回は可愛くてからかいたかった。
「まずそれはできた。私たちのワークショップの準備はよくやっている?」
「ワークショップ?…」
ワイルドカンパニーの誇り。ワークショップが鼻の前までやってきた。ひたすら職員の福祉のために始めたこのワークショップは、周辺会社でも羨望を生きるほどだった。食べ物も最上級、宿舎も最上級、そしてスタッフの楽しみのためのゲームも最上級!だから従業員が一つのようにワークショップを待っていたのだが、このような事情を知らないジョングクはコーヒーを下す私の後ろに近づいて腰に腕を巻きつけて首に顔を掘って埋葬された。
 「…ただのワークショップじゃない?
「…ただのワークショップじゃない?ワークショップをするにはちょうど休暇を与えるでしょう。そうしたら、休みの日にはヨジュと家デートができるだろうなー。と思ったジョングクは心痛だった。全社で行ったワークショップはまさに最悪だったから。業務の延長線と考えてあまり良く考えなかったからだ。
「ただのワークショップだな。一年に一度だけある祭りなのに」
「お祭り?」
うん。スタッフと遊ぶ人は遊んで、宿で休む人は休んで。しかも、ワークショップ期間中は専用リゾート施設を全部利用できるのか。と言って暖かいコーヒーを一口飲みながら言った。しかし、ジョングクも好きだと思った私の予想とは違って、彼は何か気に入らないようだった。
「なぜ、その日どこ??」
「いや、まぁ…そんなわけじゃないけど。ちょっと…」
「ちょっと?…」
ワークショップで期待をたくさんしている人にどのようにあまりと言うか。深くため息を吐いたジョングクは別れないと言った。 「そう?」と言い、またコーヒーと共にハハホ号。笑っておしゃべりをした二人。しばらくタンビシルに入って政局を訪れる職員に二人の愛情行為はそこでやめたが…。従業員に従うジョングクの顔には不安がいっぱいだった。

「…女主が旅行が好きだったのか?」
二人で旅行に行かなければならなかったが、心から悩んだジョングクだった。。
【蒸し餅のサダム】
ロマンススタートだ…
コメント20個アップ。
