
さようなら、私の世界
:こんにちは、私の世界
世界で最も無駄なことが人間関係に何かを注ぐことだ。それがお金でも、体でも心でも。私が見ている世界はすべてその無駄なことをしている。それもとても切実に。理解できなかった。そんな関係がなんだってそんなに切なくて捨てられた犬だけ落ちるのか。風が抜けた笑い声が漏れていった。彼らに伝える明白な笑いだった。人々は貧しいようだった。どちらかを置くとすぐに切れる間をクンギョンギョン維持しようとする姿が必ずギリギリの綱渡りをしているようだったので。 数平らではない灰色の光コンテナの中で、ヘジンマットレスの上の窓辺に映った私に面した。何も込められていない空虚な二つの目、チャマ拭き取れなかった涙が跡を残した頬、あまりにも痩せて傷ついた唇。あまりにも大きく落ちる白い半袖の上に首にかかった銀色の指輪が輝くと、私はそれだけで気づく。だから、
「…悪い子。」
無駄な綱渡りをしたのも、これによって哀れになった人も全部私だった。一対だった指輪はどこに行ってしまったのか分からず、私は残った指輪一つだけ両手で必ず握っただけだ。
さようなら、私の世界
:こんにちは、私の世界
呼びたくても呼べず、見たくてももうもう見られなかった。彼を失ったとき、私は幼い親に捨てられ、保護施設に入った日よりも悲しかった。実は幼い頃の私は何も知らなかったので、両親の手をつないで施設に入りながら放ち笑った。それが彼らとの最後になるとは知らない。彼らが私に言った時間はちょうど7日、一週間だった。一週間後に迎えに来るので、よく過ごしているという言葉を最後に、私は両親のいかなる痕跡でもニュースを聞くことができませんでした。乞食のような格好をしている今もそうだ。私の記憶の中で、彼らは消えています。今両親は何も必要ありません。もし私の首にかかっているリングの他のペアだけが見つかったら、彼の名前をもう一度呼ぶことができれば、一度でも彼の頬をスワイプすることができれば。私はもっと望むことはないでしょう。
メトリスの上にふわふわ体を掴んだ。全身に力が抜けて倒れるように膨れたという言葉がより似合った。渦中にも絶対に置かなかったリングには彼の名前が刻まれている。 指輪を眺めながら刻印された部分を親指で何度か使うと、ほんのりした臭いがほのかに浮かぶ。私は刻まれた名前を呼んで傷ついた唇をつかみました。
「ジュナ、」
しばらく躊躇している吐き出す名前の終わりの文字がコンテナ全体に鳴る。
「チェ・ヨンジュン、また来ると…」
結局また崩れてしまう。私が彼の名前をむやみに呼べない理由だった。涙が一滴、二滴の顔に沿って流れるといつのまにかメトリスには大きくて小さな涙跡がいっぱいだ。また来るという言葉一つでお前を待ってからもう2年。 2年間あなただけを待って壊れたような体が細く震える。
この頃からみんな気になるのではないか。チェ・ヨンジュンは一体どんな人で、私とはどんな関係を持った人なのか。簡単に言えば、チェ・ヨンジュンは私と同じ日に保護施設に入ってきた人だ。私が来た日、チェ・ヨンジュンも親であるか分からないどんな大人の手を握って施設に入った。多く、多くの子供たちのうち、私の目にチェ・ヨンジュンが入ってきた理由はただ一つ、私と同じ笑いを持っていたためだった。両親が自分を捨てたとは絶対に想像できないその年晴れで純粋な笑いを言う。初めてだった。そんなに恥ずかしかった私が同年代の誰かに先に話しかけ、チェ・ヨンジュンはそんな私を本人特有の人良い笑いに当たっただけだった。もう来て言うのに、私が保護施設で耐えられたのは、チェ・ヨンジュンが隣にあった。もともと寂しいアイラの周りに誰かがいないと気が狂って落ち込んでいました。最初の両親が私を捨てたことに気づいた日、私の隣には唯一のチェ・ヨンジュンがいました。とはいえ、今の私より小さかった手で私などを使って、今後は自分が私の世界になってくれるというそのような話をした。その時がした… 10歳くらいでしたか?あまりにも生きて年齢などは薄れているがチェ・ヨンジュンに対する記憶だけは鮮明なのがその理由だ。私たちはその日、お互いがお互いの世界になってくれると約束した。
実は幼かったから、泣く子をなだめるようにそういう話をしたかもしれない。私もそんな疑いをこれまで一度もしなかったわけではなかったし。私たちが体も心もどんどん大きくなっている頃に、私は流れるように横から空を見物していた彼に聞いたことがある。あなたは以前私に言ったことを覚えていますか?その…私の世界はどうしたのか。私は何の理由から、チェ・ヨンジュンは当然その言葉を覚えていないと思った。それからすでに数年が過ぎた後であり、しばらくの間すぐに保護施設でも出なければならない年齢だったから。まあ、彼が覚えていないとしても、私は一生その言葉を胸に抱いて生きるつもりだった。私が崩れた日ごとにその言葉一つにまた起きたのは事実だったから。瞬間的に星の考えがすべて聞いたようだ。覚えていなければ、なんだかがっかりしそうだったし、覚えていればそれはまたそのまま問題だろうみたいで。私の問いにしばらく空だけを眺めていた彼は、被食の笑いを爆発させてきっとそう言った。
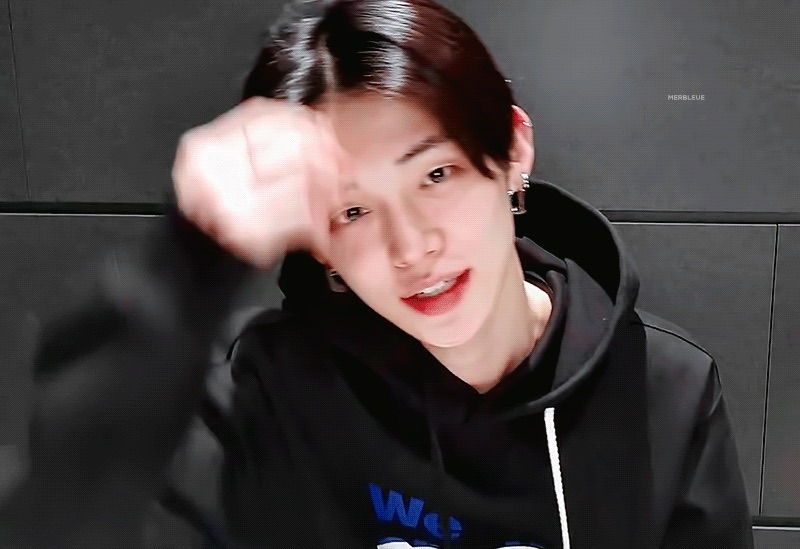
「それを忘れたら私がお前とこうしているのか、バカだ。私はまだあなたの世界であり、あなたはまだ私の世界です。
チェ・ヨンジュンの笑いに直面した瞬間、私はその言葉を信じるしかなかった。もう一度私の世界だった人たちに捨てられたことがあったにもかかわらず、二度と誰かを信じないと誓っていたのが無色に私は私の世界を信じた。
保護施設から出る頃、私は外の世界がパック怖かった。一度も出て行ったことのない世の中にどのように生きていかなければならないのか幕末するだけだった。チェ・ヨンジュンとの約束施設を出る瞬間、終わりが飛ぶと予想したので、施設での最後の夜、私はチェ・ヨンジュンを訪ねた。これまで私の世界になってくれてありがとう。おかげで崩れないことができたと。最後の挨拶をするためだった。星一つなしで非常に黒くなった夜空の下、私は思ったよりもおもしろかった。最初は笑い、途中は惜しい心に視線をつま先に置いたが、最後には結局涙を流した。悲しいことではなかった。最後の挨拶を渡す私を世界になってくれると約束したその日のようにしっかり抱いて、ここで一緒に私が外でももう一度私の世界になってくれる約束して。心臓がぽんと鳴るようなバックチャームに涙が出たのだ。チェ・ヨンジュンはその後、本当に私と一緒に施設を出た。それも私の手をしっかりと握って。
さようなら、私の世界
:こんにちは、私の世界
考えてみると、私たちは本当に乞食よりもできない生活を送った。後進工事場のコンテナ一つに二人が入って生きながら、アルバもいくつか走って体が痛くなるほど働いたが、私は思ったより悪くないという考えをした。環境は私よりはるかに劣っていますが、まだ私の隣に彼がいました。わずか2年前までチェ・ヨンジュンの存在一つだけで私の世界は十分によく戻っていたというのがとても笑う。ある夜、自分が初めて稼いだお金で銀の指輪にお互いの名前を刻んで来た。手に挟んでいると抜けるかもしれないとチェーンで首にかけてくれるまで。夜明けにいつものようにすぐに再び来るとし、2年目のニュースがない悪い奴がチェ・ヨンジュンだった。それは私たちが何の間だったのではありません。私たちが積み重ねたのはやっと幼い頃の思い出とこれまで一緒にした情だけだったのに。チェ・ヨンジュンも2年前その日私を一人置いていきながら疑問だったはずだ。私たちが一体どんな関係だったのか。愛だと言うにはあまりにもクソクジルして、友達と言うにはあまりにも多くを共有したから。空笑いが出続ける。ピーシックが出てくる笑い声とは異なり、泣き声を我慢するために顔はいっぱいになって見えない。
「…こんなことだったらそんな嘘は言うのはなぜだ」
いよいよ何かを決心したようにマットレスの上で起きた。ザグマチ2年をチェヨンジュン一つに壊れていた私が壊れた体を洗い出し始める。突然長いです。私は私が一生をこのように生きると思った。考えを直して食べたのは、2年は懐かしく泣いていっぱい壊れたので、今後2年はとてもよく生きれば、もしかしたらまた会えるかもしれないという愚かな理由からだった。以前チェ・ヨンジュンが働いていた場所を私が満たして働き、チェ・ヨンジュンがよく歩いていた道を私が歩いてチェ・ヨンジュンと住んでいたコンテナでずっと過ごしてみると、いつかチェ・ヨンジュンが再び訪れるのではないかと思った。人間はもともと自分がよく通っていたところを一度は考えて足を運ぶことになるから。正直に来る。一人で過ごす方法を教えてくれなかったあなたが少しずっと憎いですが、もしあなたが再び現れたとき、私があなたよりもよく住んでいれば、少なくとも悔しいでしょう。しかし、
「私はあなたが私よりも仲良くしてほしい、」
全身を水と石鹸で洗い流し、タオルで大体水気を拭き取った髪から水が落ちる。ハピルに乗って降りたところが目で私が流れるのか髪から落ちるのか分からなかった。
「そうすれば私が呼吸できると思う…」
もう一度この乞食のような世界に捨てられたことに対する恨みはない。血が混ざった彼らに捨てられたのは恨みだったのか、いつも彼に捨てられたのは決して恨めなかった。愚かな心だろうが、私の最も大切な青春を一緒にしたあなたを憎むこともできなかった。ああ、もうやっと定義した私たちの関係は、あなたに対する私の感情は、
友情よりは少し深くて愛情だと少し曖昧な。何もないただそのようなものだった。そんな感情とは別に、あなたは私の世界がはっきりしたが。奇妙な感情がいっぱいだった灰色のコンテナを出て、最後に眺める私の口元が苦い。いつかまた会うなら、その時はあなたが私を先に覚えておくことを祈り、私の世界に挨拶を交わした。こんにちは、私の素晴らしい世界。おかげで寂しくなかった。おかげで多くのことを学び、もう一人で起こる方法も学んだ。私たちはお互いの顔は覚えていない台もお互いの名前だけはこれからもはっきり覚えているだろう。誰かが嘲笑を何もしない関係が、いつかは確かに仕上げられることができるように、それまで誰よりもよく過ごしてほしい。だから私の時間は悔しくないでしょう。私もアジバなど生きてみましょう。あなたが私の世界になってくれた時間が無駄にならないように本当によく過ごすよ。ありがとうございました。まだありがとうございました、今後ともよろしくお願いします。ああ、だから私になるように口質に見えるね。それは本当に嫌だったのに…
「…こんにちは、私の世界」
私の世にこんにちはを伝える勇気ができた時は大人になった後だった。だから私はすぐに崩壊してもまったく奇妙ではない錆びた容器を背にした。きっと完璧なさよならではなかったことを知っている。彼の名前が刺さった銀色の指輪は、まだ首にかかってきらめいていたから。おそらく私の名前を付けられたリングも彼から輝いています。これは後でさえお互いを調べるための何かの約束のようなものだと私はそう信じた。
