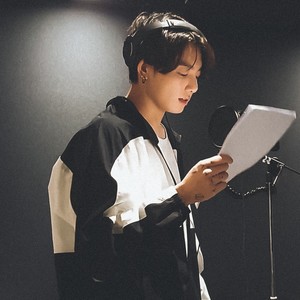悪役
:奇妙な悪役
W. うれしい
- 警告! 作家は主人公をかなり非道徳的な人物として考え・表現しています。
「その実験にあなたも参加しますか?実験体として?」
「はい!」
「まあ、まだ実験体が決まっていないんだけど…、支援が君は異能開花実験も終わったばかりだ。この能が安定するまでは無理しないのが好き」
「それですが……」
ソン博士、だからソンヒョンジは私の前の少女を愛情のこもった目で眺めた。異能開花実験の最初の成功。今17人になった少女が手を挙げて話を選ぶ姿は毒という危険な異能を持ったとは見えないほど愛らしくない。それで…と言って末尾を増やす少女の続く言葉を辛抱強く待ちながら、聖博士は少女知らず小さく笑った。
「博士がそうだったでしょう、私は他の子供よりも少し丈夫な体を持っていると、」
「うん、そうだった」
「だから、新しい実験も上手くできます。そして所長がそうだったんですよ」
「所長が?何と言ったの?」
「私が特別だよ。理能を開花し、私のように素早く適応した子供はいないと言われました。」
「それは…、それだ。サポートがあなたのようによく適応した子供たちはいません。」
「だからね、新しい実験も上手くできますよ、私!」
揃えて手を集めては、目をキラキラして見上げる少女を誰が勝てるのだろうか、聖博士が結局笑いを放ちながら首をうなずいた。ええ、そうです。とりあえず候補に入れておくと、という言葉が終わる恐ろしく少女、支援は嬉しそうに笑いをかけて見せた。ありがとうございます!と言って腰を折りながら挨拶した挨拶した支援が立ち上がった一歩でどこかに走っていくのを見て性博士は乾かないように首を振った。その言葉の間笑いを持つ少女がどこに向かうかはあまりにも明らかだった。実験が成功した後、小腸の目に入ってきれいというというきれいはみな受けていたので、今回の実験に私が参加することになったという事実を誇ろうとすることだった。まだ確定ではないが――、そんな考えをして性博士は握っていた書類を裏付けた。
「…うーん」
新しい実験に必要な実験体は二つであった。一座には既に定められた実験体があるので、空席は残り一桁だけだった。書類を読んでいた城博士の表情が暗くなった。サポートは特別だった。異能開花実験の失敗で死んだ数多くの子供たちとは違って、実験の最初の生存者であり成功体という事実だけでも支援は研究所で特別な存在になることができたが、それだけでなく、常に痛みを伴う実験に遭う実験体の間で唯一言葉笑いをしている子供だった。素敵な子供。それは絹の博士だけが感じる感情ではなかった。この研究所の研究員はもちろん、研究所長にセンターの局長にまで綺麗に受け取る少女が支援だった。
だからもっと探偵しなかった。聖博士はこのプロジェクトの担当者であるだけに、実験体の二つの役割についてよく知っているしかなかった。前庭、すでに確定された最初の実験体。その子が誰なのか知っている人なら、さらに、他の一つの実験体の座がどんな意味なのか分かるしかないのだった。実験体の実験体。ジョングクを完成させるために経る段階で使われる実験体の席に私が惜しむ少女を入れると、実験に失敗した時の状況があまりにも鮮明に目に描かれるのだった。
「それでもあんなに欲しいのに…」
研究所では、実験体の資源は珍しいものでした。その少女を除けば、この実験に資源したい実験体はたった一人もいないだろう。それだけこの研究所で起こる実験は実験体に大きな苦痛を与えた。もちろん、その結果が異能の開花という、とても爽やかな才能で咲くこともあるだろうが、失敗という結果も存在するだけに、そのひどい苦痛の中に私の足に入りたくなる人はいないのだった。だから支援は特別だった。結果だけを考慮するという点が特にそうだった。
…仕方ない。悩みを終えたソン博士は私が持っていたファイルを裏付けて紙一枚を抜いた。 S730928、キム・ジウォン。少女のプロフィールが書かれた紙を別に取り出したソン博士は私の研究室に歩みを移した。あまりできない。どうせこの実験が成功すれば、支援は誰とも比較できないほどの価値を持つことになるだろうから、そのほうが少女にももっと満足しそうだ。城博士は誓った。少女のためにもこのプロジェクトは必ず成功しなければならなかった。必ず。
⚒
「気分はどうですか?疲れませんか?」
「いいね!昨日たくさん食べて、たくさん寝てきて大丈夫!」
「うまくいった、異能開花実験覚えていない?今回の実験もその時と似ているよ。代わりに、注射は一度だけ当たるだろうし、薬物反応安定化すれば前回のようにビーズを与えるから飲み込めばいい。わかるだろ?」
「はいー、」
「うん、いいよ」
サポートは性博士が注射器および静的な知らない薬物を引き出すことを静かに見てみた。慎重な表情で複数の薬を配合するその姿を見て支援が聞かれた。博士、
「ジョングクですか?一緒に受ける実験ではありませんでしたか?」
「うーん…、ジョングクは支援が君の実験が終わればすぐに続いて実験を受けるだろう。同時に進行するにはどうしても無理があって」
「ああ、そうだな…」
「ちょっと数日、ジョングクとそんなに親しくなったら、ちょっと見ないのに見たい?」
「へへ、他の子供たちはみんな私よりずっと幼いじゃないですか。
城博士の顔に笑顔が広がった。今後受け取る実験に対する恐れはないのか、支援はずっとしっかりと騒いだ。ジョングクと庭園を散歩する雨が降り注ぐ風に警護員おじさんが研究所までアップして走ってくれた話、チョコレートがとても食べたくてチョンククと所長に訪れてスナックを変えて群れを使った話、チョンククが教えてくれた空気遊びということをやるやむを得ない話を聞いていたソン博士が配合した薬物を注射器に詰め込んで語った。
「チョコレートがそんなに食べたかったら私に来て、キャンディーもいっぱい買いましたが、私には来ませんか?」
「…博士様は一日に1つずつだけいただきますよ!」
「ええ?
「…秘密ですか? 二十犬受けてジョングクと半分分け食べましたー、」
「生きていない、羊歯はきちんとしたの?」
へへ、笑いながら頭をうなずく少女の愛らしさにもっと混ぜることもできない。聖博士が乾かないように首を振りながら支援の袖を歩いた。すぐに注射を受けるということに気づいた支援の体が緊張で固まった。ソン博士は、苦手な表情で硬く固まった支援の腕を優しく撫でた。
「あまり苦しくないよ今回は」
「…本当ですか?」
「うん、ちょっとだけ参加しよう。実験終わり、ジョングクと遊びに来たら美味しいものをあげる」
「本当でしょうか?
「えっ?5本ずつ減らせる、できたの?」
「おお!!」
幸せになる支援を見て、ソン博士が笑いを放った。緊張で固まった支援の腕がある程度恥ずかしくなった。城博士は躊躇せず、注射針を支援の腕に持っていった。太い注射針が支援の腕を突き抜けて入った。すでに凶悪なマークがいっぱいの支援の腕に別のマークができた。
天井を見ている支援の反応を確認し、ソン博士はゆっくり薬を押し込んだ。反論、異常なし。それなら半分。少し待っていましたが、これ以上の症状はありません。最後の一滴まで罪多支援の腕に投与した性博士がアルコールに濡れた綿で注射針が突き刺された位置を押し下げた。太い針が抜け出した。その鮮やかな感じに支援の目元が細かく震えた。
腕から痙攣が起こった。先日と同じ反応に支援の瞳に恐れがあった。聖博士が支援の手を握った。大丈夫、サポートああ。大丈夫です。延伸大丈夫だという言葉だけを繰り返したが、結局支援の目から涙滴がジュリュルジュリュク流れ落ちた。痛みで顔が歪んで、体が震えてくる。薬の副作用のようなものでした。薬がサポートの体に完全に安定化するまで、聖博士はサポートの手を握ったまま延伸大丈夫という言葉だけを繰り返すだけだった。大丈夫、サポートああ。大丈夫… 。
「ふぅ…、ふ…、うっ、」
「…大丈夫、お疲れ様でした。たくさん痛い?」
「うぅ…、先生…、」
「…お疲れ様、応援あ…」
震えが止まった。冷たい汗に濡れた支援の前髪を撫でてくれたソン博士が支援が息をしっかり休むことができるように助けた。ゆっくりと息を吐いて、そうそう、する性博士の煩わしい声に支援が安定を取り戻した。ふわふわしていた呼吸がきちんと戻ってきた。もう大丈夫ですが、病気になるのにも言葉の笑いを立てて見える支援に聖博士の目が赤くなった。ここで終わりならいいのですが、まだ実験が終わるまで数段階がさらに残っていたという事実が、聖博士の罪悪感を刺激した。
引き出しの中で先日のような円形の艦を取り出した聖博士がそれを支援に押し出した。前回やったことを覚えてる?する城博士の言葉に支援が首をうなずいたことを開いた。黄金色のビーズだった。異能開花実験の時とは違ってきれいな色のビーズに支援の表情が一層快適になった。支援は躊躇せずにビーズを口に入れた。
異能開花実験のような副作用はなかった。ビーズを飲み込んだ後は中がやや熱くなる感じを除いて何もなかった。サポートに接続されたマシンは、彼の状態が完全に安定していることを知らせました。幸いです。聖博士は安心して支援を立てて立てた。思ったよりも実験が早く終わるかもしれないが、思考に性博士の表情が明るくなった。苦労した、という言葉を聞いてヘヘー、というティーなしで澄んだ笑いをする少女を見る性博士の目に愛情が込められた。
「さぁ、もう本当の最後!実験ではなく、結果確認用に異能数値だけちょっと見直すよー」
「はいー、でも博士、今回私が飲み込んだのはどういう異能ですか?」
支援の問いに性博士が困惑した気配を帯びた。サポートが飲み込んだ黄金色のビーズ。先日飲み込んだ緑色のビーズとは違って、それは異能ではなかった。
それは、ガイドの力を込めたビーズだった。
聖博士は悩んだ。私の目の前にいる子供に事実を教えなければならないのか。エスパーの異能とガイドのガイディングを同時に持つことができる人はいなかった。自然にも、人為的にも。もし支援が飲み込んだガイディングを完全に私の能力で受け入れることになったら、2つの相反する能力を同時に持つようになった最初のエスパーになるのだった。しかし、聖博士はその事実を支援に知らせることが躊躇した。最初、それは支援の前に広がるものが全く未知のものであるという言葉と一脈上痛だった。副作用がある限り、その副作用が何であるかわからない。スタートを切ったのがサポートだから。
しかし、成功すれば、副作用ごろは軽く治ることができるほど強力な影響力を持つエスパーになることができる。聖博士は悩みを終えて口を開いた。あなたが飲み込んだ力は異能ではありません。
「それはガイドだ」
「…ガイディングですか?博士、でも私はエスパーなんですか?」
「ええ、あなたはエスパーです。しかし、これはガイディング能力を持つようになったエスパーになりました。」
「…はい?」
「支援ああ、考えてみよう。エスパーの能力は、ガイディングがなければいつ爆発するかわからない時限爆弾のようなものだ。恐ろしい束縛がかかっているわけだ」
でも、ガイディングを自分で埋めるだけなら?ガイドというネックラインから抜け出すことができるエスパーなら?聖博士の言葉に支援の目に異彩が回った。その姿に内心安心したソン博士が支援の頭を撫でた。
「お前は何にもつまらない完璧なエスパーになるんだ。どうしたらいいんじゃない?」
「…カッコイイ、いいよ!」
「そうなんですか?では、サポートがあなたのガイドがどれくらいか、一度確認してみようか?」
「はい!」
支援は深呼吸を一度して手を差し出した。ガイディング数値を測定するために作られた機械に手を上げると、異能に似た何かが機械の中に吸い込まれることが感じられた。手を離さないでください。なじみのない感覚にすぐにも手を離したいという支援を知っているように、ソン博士が断固として言った。その言葉では、サポートはグッドリファレンスマシンから手を離さなかった。 [検査が完了しました。] という通知ウィンドウが灸と同時にサポートは機械から手を離した。なんか手のひらが凍りついたようだった。
「世の中、A級だな!」
聖博士が画面を確認したら、声が出て声を上げた。 B級だけになっても成功だと思ったが、なんとA級ガイディング能力だった。やはり、支援は誰よりも完璧な実験体だった。ソン博士が顔に一杯の笑顔を帯びて支援に語った。
「おめでとう、応援ああ。A級だよ。今回の実験も本当に素敵にやったよ!」
「…成功ですか?」
「じゃあ、まあ、もし知らないからガイディングを一度練習してみたらどうだろうが、今気持ちはどう? もしかして疲れてるの?」
「あ、いいえ。大丈夫だと思います!」
「ええ、じゃあガイディングを自分でやってみて……」
聖博士が嬉しい顔で支援を連れて行った所は研究所長の研究室だった。所長にガイディングを一度やってみるという言葉に支援の目が振り回されていたが、引き続き促す性博士と何気なく手を差し出している所長に結局その手をつかむしかなかった。サポートはゆっくりとガイドを吹き込んだ。異能とは違う感じの能力が私の手に乗って所長に渡るのが感じられた。そして、
「クウク、コップ、」
「…所蔵様?所蔵様!!」
小腸の顔が真っ白になり、やがて吐き気をし始めたとき、聖博士は何かが間違っていたことを強く感じた。支援も同様だった。所長に渡った能力の流れを断った支援が当惑に濡れた顔で性博士を眺めた。床に崩れたまま無駄な悪質な小腸を見る城博士の顔が白く飽きた。
支援のガイディングはガイディングだがガイディングではなかった。その事実を悟った聖博士は急いで研究所長の研究室で飛び出した。いや、言い続けて呟く性博士の顔が切迫した。
失敗だ、失敗した。
少女の実験は凄く失敗した。
⚒