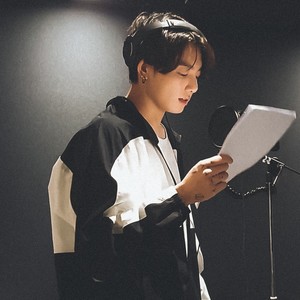悪役
:奇妙な悪役
W. はい
- 警告! 作家は主人公をかなり非道徳的な人物として考え・表現しています。
支援は堤防ベッドに横たわって両手を見つめた。ガイド。今日私が受けた力は明らかに異能ではなくガイディングだった。ガイディングが何なのか、エスパーイン支援が分からない。エスパーの理能を使えるエネルギーになってくれる力。しかし先ほど支援の目の前で繰り広げられた場面は、私が知っていたガイディングの姿とはあまりにも違った。ガイディングを吹き込むと倒れた研究所長の姿、顔を白く染めたままどこかに駆けつけた城博士の姿、部屋に帰るよう指示を受けた自分。失敗した、聖博士の呟きが耳に残っている気分だった。
「…まあ、気にしないの?」
サポートがベッドで体を引き起こした。部屋の隅を占めている引き出しは、絵を描くのが好きな支援のために紙や絵の具のようなものを入れておいて、聖博士が直接置いてくれたものだった。他の実験体の部屋にはこんなことはない。いいえ、引き出しは苦労し、彼らは一人部屋が与えられません。サポートはゆっくり引き出しの最下部の部屋を開けた。細かく保管されているガラス箱を取り出せば、サポートは箱の中に入った赤いビーズの数を数えた。
「三つ?まあ…、十分だろう」
しばらく何かを悩んでいた支援は、今まで横たわっていたベッドのマットレスを持ち上げた。その下に赤いビーズの一つを置いたサポートが、マットレスを元々あったように下ろした。残りの2つのビーズは私の服のポケットに入れた。箱ごとに持ち歩くことはできない法だった。引き出しの一番下のカーンで何かをもう1つ手に入れたサポートは堤防の扉を開いた。ロックされていない訪問が研究所で支援の位置を知らせるようだった。
特別待遇、それは研究所内での権力を意味するものでもあった。一人室も、引き出し場も、ロックされていない訪問も、監視されないのも、すべて権力の一部だった。サポートはおなじみに廊下の端に位置する非常口のドアを開けた。
他の実験体が集まっているところに行かなければならなかった。支援の部屋は一人室で研究所の3階に位置していたが、他の実験体は2階の大講堂のような場所でみんなで生活した。退屈するたびに支援が他の実験体の部屋に行くことは、今や研究所の人々にはなじみがあったので、2階の非常口のドアを開けて入る人が支援であることに気づくと、2階廊下にあった警護員の表情がやさしく解けた。
「スンファンおじさん!」
「サポートですか?なぜ部屋にいないのですか?疲れませんか?」
今日の実験もしたと、心配がたっぷり詰まった声に応援がへへー、笑った。おなじみの支援の名前を呼んで安否を問う2階担当警護員、スンファンは支援を可愛くする数多くの人々の一つだった。
「友達と遊んでもいいですか?」
「ここだけ、今日は庭に出るのはダメだ」
「はい!ここで!少し遊ぶつもりです!」
支援の言葉に、スンファンはそう、はい、とすっきりドアを開けてくれた。絶対逃げられないように三重ロックで固く閉まっていたドアが支援の言葉一言に簡単に開かれた。出て行きたい時はいつでも教えてください。はい!ありがとうございます!日当たりの良い支援の笑いにスンファンの口尾が崩れた。
ガラガラと、厚い鉄扉が閉まる音に支援は顔に掛けていた17人の少女の晴れた笑顔を消した。支援を除いた実験体をただ「実験体」だけで見る研究所の職員であり、支援が彼らを探すたびに本当にハッハホホで遊ぶことだけで分かるが、支援は一度もこの「実験体」たちと話を交わしたことがなかった。これまでこの恐ろしい空間に着実に出入りした理由は、ただ、今日起こる事に対する対策に過ぎなかった。
私には数十個の視線があるにもかかわらず、支援は不便な気配一つなしで大講堂のように広いだけの部屋をぐるぐる回りました。ポケットに入れた赤いビーズに触れながら。どこがいいの?という支援の一言が広い部屋に盛り上がるように響き渡った。
「実はどこでも構いませんが、」
支援は板ばかりの部屋の真ん中に割れた。躊躇せずに床を素手で引き出す支援の姿に、いくつかの実験体が驚いた。支援は彼らに目を引かずに引き出した底に赤いビーズを一つ落とした。そして、まるで何も起こらなかったことだけ、再び床を元の状態に戻した。誰が見ても無理やり外れたような痕跡が残っていたが、構わないだろう。やっと実験体が集まっている空間に研究者たちが大きな関心を注ぐつもりもなく、どうせ今日なら消える建物だった。
ビーズ一つを処理した支援は、迷うことなく部屋の右壁に向かった。壁面に期待していた実験体が支援が近づくと同時にウルル-、彼を避けて動いた。彼らに一言の視線も与えなかった支援は、右の壁を拳で叩きながら動いた。ふっくら、ふっくら、鳴った音がガタガタ、する音に変わるまで。音が変わった壁付近に止まって、サポートが躊躇せずに壁を蹴った。タング!する鈍い音を立てた壁はサポートの足を踏み出す数回で容易に壊れた。暗い空間につながる通路が現れた。子供たちの目が大きく浮かんだ。
「秘密の通路だ」
「……。」
「すぐに研究所が爆発するよ」
生きたければ非常警報音が鳴るとすぐにこの道に沿って脱出してください。支援は私を見つめている実験体に言った。
「それほど前に出ないでください。
警告を残した支援が躊躇せずに歩き回った。ここでのボール日は終わった。生きたければ教えてくれた通りだろう。まあ、信じないと仕方ない。そんな考えをして支援は厚い鉄門をすごい、叩いた。扉に出た槍殺でスンファンが顔を出した。私に行きます… 。その間、シムルクな少女の表情を覆した支援が語った。スンファンの眉毛が目を覚ました。彼はすぐにドアのロックを解除しました。キイイク、という声を出してドアが開かれた。
「子供たちが疲れているのを見て、見たふりをしないでください」
「君は無視したの?
スンファンの言葉に一瞬支援の目つきが鋭く変わった。扉を見て貪りを吐き出したスンファンが再び支援に首を向けたとき、ズムエンはそんな気配を芽生えたサポートが冷たく死ぬかのように眉を伸ばした表情をして見せたのでスンファンがこれを知らせなかっただろうが。むしろ、ジョングクに行って遊んでもらうのか、というスンファンの言葉に支援の顔が明るく開いた。そうだ、こんにちは、おじさん!手を振って非常口のドアを開く支援にスンファンが笑って手を振ってくれた。
「実験体の主題とは」
その実験体が指を一度弾くだけで、私のような一般人はしっかりと死ぬことを知っているだろうか?は、わかったら「実験体のテーマに」のような愚かな発言はしなかっただろう。階段を登って支援は考えた。とにかく支援は、スンファンの言葉や政局を訪ねるつもりだった。スンファンが思うように小子同士で遊ぶための目的ではなかったが。
特別扱いされる実験体、それは支援だけを指すものではなかった。前庭、この研究所で唯一サポートよりも良い扱いを受ける子供。その子供の部屋は4階だったので支援は一層上がった階段の非常口を押して入る代わりに階段をさらに上がり始めた。 4階の非常口の扉が挟み、という声を出して開かれた。経費などあるはずがなかった。
暗い廊下にある数多くの部屋の中でおなじみの部屋の前に立った支援が訪問を叩いた。いや、前政局-、という支援の言葉に訪問越しに声が聞こえた。 …キム・ジウォン?それと同時に開いた扉に支援がその隙間ですっぽり、体を押し込んだ。
「なんだよ、今回?」
もう15人になった男の子は、ちょうど眠りから潰されたように、ふくらんだ髪をして目を飛び散っていた。ジョングクの部屋は支援のものよりはるかに大きかった。支援の部屋にはない机やワードローブもあったから言っていた。まあ、それは重要なことではなかったが。今とジョングクと自身の差別待遇に西雲海するには遅い感があると支援は考えた。彼はただジョングクの部屋をゆっくり見回しているだけだった。まだ正しい場所は見えなかった。サポートはため息をついて休んで、ジョングクのベッドマットレスを持ち上げた。 …何してるの?するジョングクの言葉に何の答えもせず、支援は私の部屋でそうしたようにマットレスの下に最後の赤いビーズを入れておくだけだった。終わった。サポートは遠く離れて立っているジョングクの腕をつかまえた。
「お前、実験された?」
「どんな実験?」
「ガイディング能力開花させる実験、黄金色のビーズを与えること、」
「あ、うん。途中で聖博士が入ってきて、しばらく中断されたのに…それでも最後まで受けた、実験。なぜ?」
「いや、終わったらいいのに。散歩に行きますか?」
支援の姿がいつもとはどこか違うということをジョングクはどんどん感じたが彼は何も問わず首をうなずいて上着を拾って着た。研究所で実験体に支給される服とは質の異なる服だった。支援はジョングクが服を着る姿を遠くから見つめるよりベッドに何気なく広がっていたショールを拾ってジョングクの首に囲んだ。
「外寒い」
「…あなたは?」
「私は大丈夫です。元の寒さはうまくいきません。」
支援はジョングクのアウタージッパーを丁寧に満たした後、彼の手を握って訪問を開いた。おなじみの非常口に向かって歩いていく支援の後ろをジョングクが追い出した。階段を盛り上がり下がる支援を追いかけて倒れるような気持ちで、ジョングクがゆっくり、ゆっくり!と急いで言ったが、支援は政局の言葉が聞こえない人のように転がった。今日のサポートは何か奇妙だった。
1階の入口にはいつも経費が建てられていた。もし知らない実験体の脱走や研究所の機密文書の流出を防ぐために研究所長がきちんと立てたせいだった。もちろん支援と政局には特別な障害にはならなかった。非常口で首を突き抜ける彼らの姿に支援か。どこの店?と親しみやすい言葉をつけてくる経費の姿だけ見てもそうだった。サポートは明るく笑い、ジョングクと散歩です!そうだった。気をつけて行ったという言葉以外にそれらを捕まえることはなかった。研究所の建物の外に出るのは、今息づくほど簡単なことだった。ジョングクの手をしっかりと握った支援がゆっくりと足を運んだ。普段、彼らが散歩する道ではなく反対側に向かう支援に、ジョングクが恥ずかしい表情で尋ねた。
「どこへ行くの? こちらは正門に行く道なのに…」
「うーん…、新しい遊歩道発見中かな?」
支援は政局の手を握って黙々と歩いた。ゆっくりとした足は正門に近づくにつれてますます速くなった。いつもとは違う支援の姿に恐れたジョングクは、彼が率いるように卒卒追いかけていくだけだった。正門との距離が100mも残っていなかったとき、支援が突然方向を変えた。近くの草の森にジョングクを押し込んだせいで、ジョングクは橋に力が解け落ちてしまった。
ジョングクは今日、奇妙な支援の姿がよく理解されていない。さっきからなぜそうなの?するジョングクの姿に迷惑をかけるという表情を立てて唇に人差し指をつけて、シ-、する時だけすることもそうだった。なんだかちょっと凄まじい感情があったジョングクだったが、ここでピジンティーを出してみたところ、以前のように支援の驚き感になるだけだという考えに口をそろえた。しかし、続いた支援の行動には、政局も驚いて目を大きく開けるしかなかった。サポートはポケットから小さなイヤリングを一つ取り出した。いつ耳を開けたのか、彼はおなじみに私の耳に青い宝石が詰まったイヤリングをかけた。実験体は個人所持品を研究所に持ち込めなかった。あんな宝石が詰まった高価な装身具は言うまでもなかった。そんなことをどこで救ったの?ジョングクが目を大きく開いて支援を見つめたが、サポートはジョングクに何かを説明してくれる代わりにイヤリングを何度も触った。そしてサポートが口を開けた。
「うん、私よ」
ジョングクはさらに驚くしかなかった。普通のイヤリングではなく通信機器だったという事実に、ジョングクの目が細かく震えた。 …サポートああ?ジョングクは朝幕だけの声で支援を呼んだが、支援は彼に視線を一度与えては告げない声で話すことだった。
「全部捨ててください」
支援の言葉が終わるやいなや研究所の緊急警報音が騒々しく鳴った。びっくりして耳を挟むジョングクの頭頂をしっかり押して草の森に体をより深く隠した支援がふんわり、する音を出すジョングクの口を引き締めた。怖くて涙が出そうだった。支援を愛処として見つめるのに支援は政局に視線した裾も与えなかった。ただ平気な表情で数字だけ呟くことだった。十、球、腕、塗り、… 、しながら言葉だ。
サム、これ、仕事… 、そして轟音が聞こえた。何かがぽんと鳴る音だった。一度ではなかった。正門を守っていた警備員が飛び散らない爆発に驚き、研究所に向かって飛び込むことが聞こえた。ああ、それで死ぬでしょう。支援が呟いた。もう一度聞こえた爆発音にジョングクが目を閉じた。これが一体どうしたのか、ジョングクは理解できなかった。大きな暴音のために爆発した鼓膜に耳たぶから血が流れ落ちた。ジョングクは私の前にいる、今日のように大きく見える私の友人を見つめた。私と同じように耳元で血を流し、飛び散る灰とほこりを覆し、格好よく髪の上に葉を付けている支援を言う。彼は笑っていた。研究所を掴んだ真っ赤な炎を見ながらこう言いながら―、
「あ~、中涼しい!」
ジョングクは考えた。たぶん私の前にいるこの女の子は、私の友達のようなものではないかもしれません。たぶんこの女の子は友達ではなく、
-悪役かもしれません。十五の政局はそう思った。
⚒