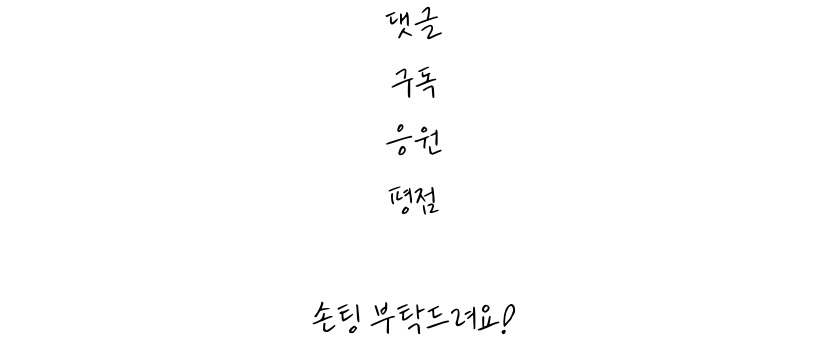記憶を歩く時間
アルバを辞めて一週間ごろ、開学が近づいてきた。開学日の前日、私はワードローブに刺さっていた制服を取り出し、本から本、筆記具の様々なものをバッグに入れた。学校に行く準備を完璧に終えたと思ったとき、手が少し震え始めた。
「またなぜ…!」
学校はもはや私が笑って幸せな空間ではなかった。イ・ジュンがいる時やそんな空間だったし、イ・ジュンが消えた学校は息を止めるだけだった。
その時からだった。制作年冬11月、写真部でイ・ジュンの最後にイ・ジュンに会った時。そしてその日以来イ・ジュンを一度もまた見られなかった今まで。時々学校に行こうとするたびに手が震える。 まるで学校という空間が私にトラウマになったことだけ。
また、イ・ジュンの最後の姿が浮かぶ。
「ジュナ…私はまだあなたの時間に住んでいると思う……」
ベッドサイドの引き出しには唯一のイ・ジュンの写真が位置していた。すでに季節は何度も過ぎましたが…あなたと私だけがまだその冬に止まっているようだった。

きっとアラームを合わせておいたようなのになぜなのか鳴らなかった。朝から灰水がないと思った私はミン・ユンギの電話でやっと起きて制服を着て家を出た。家の前には下服を着たミン・ユンギがフォンを触って作っていた。
「遅れた」
「ごめん、開学初日から遅刻してしまった」
「早く寝てしまったり、昨日何をしたの?」
「ただ…」
昨夜イ・ジュンの写真を抱きしめながら泣いたということをミン・ユンギが知れば氷場のように冷えるかもしれない。だからただという言葉一つで話をぼかした。しかし、ミン・ユンギはそれほど長い友人ではないということをしばらく忘れていたか。
「泣いた?」
「いや…?」
ミン・ユンギの目は決してだまされない。私はミン・ユンギと目にできるだけ遭遇しないように目玉をあちこち転がした。

「そうだね、そうだ。泣かないもの」
「ティーたくさん私?」
「え」
軽い栗と一緒に飛んでくるため息の混ざった言葉だった。私は無心なミン・ユンギの言葉が心配だということをよく知っていたので、ベシシは笑った。もちろんミン・ユンギは何が上手だったと笑うかとなって何と言ったが…
どうせ遅刻確定なのか、あえて汗出して走らないことにした。ミン・ユンギと私はもともと効率的ではなかったことには力を注ぎません。学校までゆっくり歩いて、私たちは様々な話を交わした。それで自然に昨日泣いたことについても話すことになったし。 ああ、ただ走ろうとすることだった。後悔が注がれた。
「まさかまたやる?」
「…突然手が震えたと。仕方がなかった」
ミン・ユンギの表情が瞬間的に固まる。猫がイ・ジュンというのは感情的に分かった。言い訳を余儀なくされた私は率直にすべて打ち明けるしかなかった。
「なった。何と言わない。後で病院に行く」
「うん!」
イ・ジュンに関連する私の仕事にミンユンギが何の話をしないのは手に挙げるほどのことだ。両目が丸く大きくなった私は、私はずっと笑った。
視界に入り始めた学校にどんな混乱したことが生じたのか分からないまま。