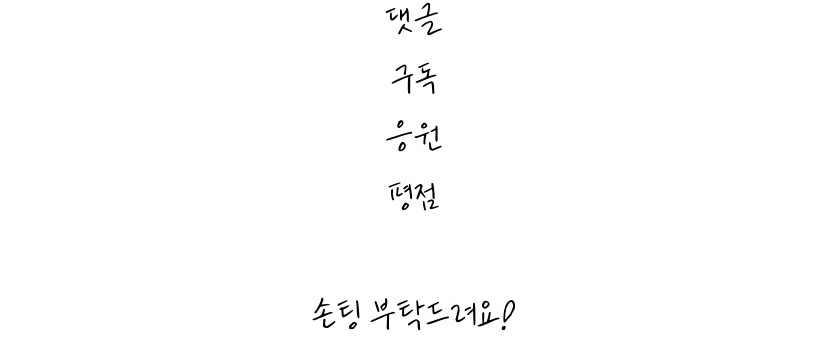記憶を歩く時間
教室に入るとすぐに足が所定の位置に縛られたかのようにきつくできなかった私の代わりに叫んだのはまさにミンユンギだった。ミン・ユンギは彼らにかなり怒っているような顔に近づいて脅威的に振り返った。
「あなたは私が口を閉じたと言った」
「私、私が何! 私、私はただ前政局が気になってくれて教えてくれただけだ!」

「もう一度やり過ぎれば、その時は警告で終わらないだろう。少なくとも残された人々に対する礼儀は守らなければならない。
ミン・ユンギが爽やかな目で警告すると、泣き叫んだああ、近くにいたみんなが口を閉じた。もちろん前政局もそうだった。ここで前政局は間違っていない。前政局は今日、私たちの学校に転校を来ただけで、学生の半分以上がイ・ジュンを覚えていたので、このようなことができたのだ。
耳から耳鳴りが聞こえ始めた。臓器がねじれているように腹が痛くなり、しっとりとした目の前に広がるその日の場面に精神が混迷した。大丈夫だと思った。いや、実は大丈夫ではないことを知っている。結局、私は心を失って席に倒れてしまった。

ここがどこか分からない。全体的に白色だった背景がある瞬間形を整えて作られた。驚くほど大きくなった目で、ちょっと周りを見回した。ここでは…学校だった。しかし、どこか変だった。私を除いた学生は誰もいなかったし、窓の外には暗闇が置かれていた。
「なんだ…ここは一体どこだ……」
混乱がいっぱいになった頭の中を整理するのに忙しい今、教室の中に位置しているカレンダーが見えた。私は廊下に止まっていた足を教室に移し、カレンダーの前に立った。 このカレンダーもどこか奇妙だった。きっと今は2022年8月末頃なのに…。もしかしたら夢ですか?
「2020年11月18日…」
2020年11月18日。私が絶対に忘れられない日だった。 2020年の11月の冬は私にとってとても冷たくて孤独な季節だったから。 11月18日、まさにイ・ジュンの誕生日であり期日だった。
今こそこの場所がどこなのか分かるようだった。この場所は学校、だから正確には2020年11月18日、イ・ジュンが死んだまさにその日の学校だ。後ろに戻って教室の後ろに付いている時計の時間を確認しました。夕方9時46分。私が死んだイ・ジュンを発見する15分前の時間でした。
「たぶん…たぶん私が…!」
瞳が赤くなり、涙がソンゴルソンゴル結び始める。だが私には時間がいくらない。私が死んだイ・ジュンを発見した場所は写真不良、そして時間は15分後だ。 15分前に来て夢を見るのは明らかな理由があるだろう。夢でも私にイ・ジュンを生かす機会が与えられたこともある。
心の中に希望が咲いた。私は一滴ずつ落ちる涙を後にしたまま、すぐに写真不良に走った。息が切れるように荒れたが、呼吸とともに写真不良のドアを開けた。
「イ・ジュン…」
写真不良を開くとすぐに心臓が止まると思った。写真不良の扉を開くと、片手に白い薬筒を持っているイ・ジュンが見えた。涙に濡れた顔で名前を呼ぶと、イ・ジュンは淡い笑顔を見せて名前を呼んだ。
「キム・ヨジュ、私は今日の誕生日ですか?」
「わかりました…私がすべて知って……おめでとう。生まれてくれて、こんなに私の前にいてくれてありがとう。」
「私のお母さんのお父さんも知らない誕生日をあなたが知ってくれています。ありがとう」
「これからも私が知ってあげるよ、私が…私が君を捕まえるよ。だから、出よう。私と一緒に外に逃げよう、ジュナ。お願い……」
涙が顔を覆い、写真不良の床に突っ込んだ。あまりにも多く落ちる涙のため、私の前に立っているイ・ジュンの姿がよく見えなかった。消えた写真不良、泣いている俺。きっと笑っていました。よく見えなくても上がったイ・ジュンの口尾だけは明らかに見えた。
「…それ知ってる?私があなたの笑顔を一番好きだったんだ」
「……」
「中がいっぱい詰まったように苦しくて、すぐにでも涙が飛び出すように悲しく、世の中に一人で残されたように孤独なとき、君を見れば大丈夫だった」
イ・ジュンのすべての言葉が私を鳴らした。すべて知っていた。私はあなたについて知らないものがほとんどないほどあなたをすべて縫っていました。あなたが私の笑顔を好んだということも、あなたの人生が熱かった理由も。今の私はすべて知っている。
それでもっと涙が出ました。イ・ジュンが私に伝える最後の挨拶のようなので、その日の私を心配する君が今からやって来てくれたのではないかと思って。

「もう一度だけ笑ってあげなさい、女主よ。私のために」
息がこぼれるように泣いていた私は泣き声を堪能しようと努力した。目では依然として涙がいっぱい流れており、イ・ジュンのお願いで見上げた口尾は少し震えた。
腕で目元を照らして涙を拭いた。イ・ジュンは今どんな表情をしているのか見たかった。目元をしっかり拭いた私の前に見えるイ・ジュンは私と似た表情をしていた。彼はきっと笑っていたが、目からは涙が一滴落ちていた。
震える彼の手を握ろうとした足跡近づいた時、すべてが壊れて消えた。しばらくして私を呼んでいる声が耳を掘って聞いたので、私は目を開いた。死んでも壊したくなかった夢で結局目覚めただけだった。